| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第10回締約国会議 |
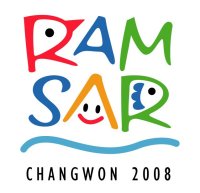
ラムサール条約第10回締約国会議(2008年10月28日−11月4日)決議案22「水鳥のフライウェイの保全のための国際協力の促進」に添付されるため,かつて国際湿地保全連合ウェブに掲載されていた日本語版(http://www.wetlands.org/GFC/docs/Declaration_Japanese.pdf)より、了解を得てこのページに再録. [ COP10決議案22 ] に戻る.

国際会議「世界の水鳥」
世界の主要なフライウェイの保全,管理,調査研究の地球規模での検討
2004年4月3−8日,英国エジンバラ
2004年4月3日から8日にかけて、英国スコットランドのエジンバラにて、水鳥の保全とその持続可能な利用に関する国際会議が開かれた。90か国から 456名の参加者があった。
水鳥のフライウェイとは、渡りの経路という生物学的システムであり、異なる国々や異なる大陸にある生息地ならびに生態系を直接結ぶものであることを意識し、
水鳥の保全とワイズユース[賢明な利用]は、関係する国々とその人々が責任を負うものであり、人類共通の課題であることを想起し、
100年以上にわたってこれまで培われてきた水鳥を保全するための国際協力の長い歴史、たとえば1916年の米国及びカナダ(英国が代行)間で結ばれた渡り鳥に関する条約といった条約/協定、また40年余り前の1963年、ガンカモ類の保全に関する欧州会議の初回会合がスコットランドのセント・アンドリュースにて開催され、これが1971年にイランのラムサールで締結される湿地条約[ラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)]を築き上げる過程のスタートとなったことも想起し、
オランダのノードウェイク・アーン・ゼー(1966年)、ソビエト連邦レニングラード(1968年)、イランのラムサール(1971年)、ソビエト連邦アストラハン(1989年)、米国フロリダ州セント・ピータースバーグ・ビーチ(1992年)、日本の釧路とフランスのストラスブルグ(1994年)で開催された、主要な国際会議が水鳥保全に関する技術的な国際交流をよりいっそう発展させてきたことを特筆し、
更なる条約や協定、方策並びにプログラムの構築とその実践を通して各国政府間の協力関係が一層発展してきたこと、また、水鳥の保全活動やモニタリング活動において非政府の国内的並びに国際的な協力が一層発展してきたことを認識し、
2002年に南アフリカのヨハネスブルグで開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)において、2010年までに『現状の生物多様性の喪失速度を有意に低下させること』を達成するという念願を、世界のリーダーたちが表明したこと、この目標が2004年2月の生物多様性条約第7回締約国会議において更に発展させられたこと、これらを意識するとともに、この目標を達成するには全ての大陸において多大な資金投入と焦点を絞った協調的保全活動が必要とされていることを認識し、かつ広報・教育・普及啓発活動並びに研修活動がこの目標を達成するために重要な役割を果たすであろうことを認め、
政府・政府間機関・非政府機関・地元社会・民間セクターの間の国際協力とパートナーシップを強化することが急務であることを更に意識し、
陸上生態系並びに海洋生態系のいずれにおいても多くの水鳥個体群が危機的な状況におかれていること、そして世界の湿地が質的にも量的にも減少を続けていることに危機感を抱き、
本会議での多数の技術的分科会並びに発表が導き出した結論や優先行動に着目し、直ちにこの宣言文に記録し、
世界の水鳥の現状を再評価するためにエジンバラでこの国際会議を開催することに対し、国際湿地保全連合と英国並びにオランダの両国政府当局が共同でイニシアティブを執ったこと、オーストラリアやデンマーク、米国、日本、ドイツ、スウェーデン、アイルランド、ベルギー、スイスの各国からの支援、ボン条約[移動性野生動物種の保全に関する条約]やアフリカ−ユーラシア渡り性水鳥保全協定、欧州連合狩猟保全団体連盟、狩猟野生生物保全評議会からの支援、並びにその他多くの団体・個人から寄せられた情報を歓迎し、
エジンバラに参集した会議参加者一同は、
水鳥とその生息湿地環境を保全する取組みは有意な進展を見せ、いくつもの主要な成功を導いているにもかかわらず、全体としては重要な課題が残っており、将来的な変化による影響の流動性を考え合わせながらさらなる努力と集中的な行動が必要とされていることを考慮する。
ラムサール条約が言う『水鳥はその季節的な渡りにおいて国境を超え、このために国際的な資源であるとみなされ』また『先見性のある各国の政策と協調的な国際行動によって湿地とその動植物相を保全することができる』ということを再確認する。それゆえに、水鳥が人類の生存維持に有用であるだけでなく水鳥そのもののためにも、水鳥個体群とその生息湿地環境を保全する国家間の努力が拡大されるよう促す。
フライウェイレベルでの保全の取組みは、種に基づいたアプローチと生態系に基づいたアプローチの両方を兼ね備え、渡りの範囲全体で国際的に協調されるべきであることを考慮する。
水鳥と湿地資源の保全と持続可能な利用には、市民や民間セクター、それに依存する地元社会、並びにその他の利害関係者による協調的な行動が必要とされることを認める。
次のような緊急行動を、特に求める:
水鳥と湿地のワイズユースが持続可能な開発と貧困の根絶のために重要であることを伝え、施設や資源が限られた国や地域において、フライウェイレベルの保全に役立つ能力の開発を特に優先させるよう促す。
各国が関係する条約や協定を批准してより一層の国際協力に取り組むこと、そして地球環境ファシリティなど可能な資金源を利用してこの宣言に盛り込まれた行動に資金をあてることを強く奨励する。
協調的かつ国際的な状況評価の長い歴史とともに、2002年に世界レベルのリーダーたちにより採択された2010年目標の達成に向けた進展を評価するために、水鳥が優れた指標となることを考慮する。そして、この目的達成には、ボン条約や生物多様性条約、ラムサール条約、その他の国際協定が共働し、かつこのような状況評価に関係する他のパートナーとも共働すること、特に国際湿地保全連合とともに、3年ごとに編さんされる「水鳥の個体群推定」の分析的な開発をさらにすすめ、それを活用することを求める。
この宣言と本会議の技術的成果[原注1]を世界中に広める必要性を重視する。
今後の進展を評価するために10年後に再び会議で再会することに合意する。
エジンバラ
2004年4月7日
[会議の結論]
上記の勧告を支持し、会議は次のように結論した:
[ PDF (459kb zip)] [ Top ] [ Back ] [ DR22 ]
| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部●主要な決議等 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop10/gfc2004dcj.htm
Last update: 2009/08/11, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).