| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第10回締約国会議 |
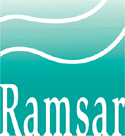
日本語抄訳:琵琶湖ラムサール研究会,2008年4月.
条約事務局に掲載の英語原典:常設委員会第37回会合文書11は,①条約事務局から会合出席者への注記,②決議本文の案,③決議付属書の同プログラム案から構成されていますが,この抄訳ページでは③のプログラム案のみを全文(プログラム案の添付文書を含む)訳出しています.
このページの案文は常設委員会第37回会合の議論を受けて決議案Ⅹ.8に改版されたのち,第10回締約国会議により採択されましたので,もはやこのページは参照せずにそちらをお読みください ☞ 決議Ⅹ.8.
[原文:常設委員会第37回会合(2008年6月)文書11(DOC. SC37-11)の決議案の付属書]
もくじ
1.第三次のCEPAプログラムを以下のとおり示す。これは、第10回締約国会議において採択される[採択された]条約の第三次戦略計画とともに2009年から2014年の6年間に実施されるものである。このプログラムの構造は条約の戦略計画や作業計画と一致するように組み立てられている。決議Ⅶ.9と決議Ⅷ.31の付属書に採択された過去のプログラムに置き換わるものである。「対話」、「教育」、「参加」、「啓発」といった用語の説明が下の添付文書1に述べられている。
2.湿地に関するCEPAが引き続き条約にとって重要であり、ますますその責任を増していることを示す証拠が相当にある。
a)CEPAは、2003年2月の常設委員会第29回会合において公式に、優占順位が高い分野横断的作業領域と認められた。2005年の決議Ⅸ.11では、CEPA専門家が条約の科学技術検討委員会の委員に任命され、同委員会が湿地にかかる新たな手引きを策定する作業においてすべての段階でその専門技術を組み入れる役割を担うこととなった。このCEPA専門家は、特にCEPAに関する条約のネットワークや国際団体パートナー(IOP)のネットワークを活かすことになる。
[訳注.条約のCEPAネットワークとは、締約国が任命した各国のCEPA担当窓口のネットワークのことを指す。]
b)自国の全国的CEPA行動計画をこれまでに条約事務局に送付した締約国はわずか4か国(オーストラリア、ドイツ、ハンガリー、スペイン)であるが、ほかにも多くの締約国が全国的な行動計画の策定に向けて、あるいは他の規模での行動計画の実施に取り組んでいる。各湿地規模あるいは流域規模の保全管理計画策定において、CEPAはその必須部分であると締約国に認められ、それらの計画に適切なCEPA活動が組み入れられているという例証も増えつつある。
c)条約事務局においてもCEPAのための運営上の支援策等を実施している。2006年から2008年にかけては、条約の中核予算の一部にCEPAプログラムを支える費用が控えめながら計上されていた。
d)湿地の管理計画策定に地域社会の参加や教育を含めるというアプローチは条約が発展させてきたものである。また、参加を得るための専門技術やその基礎となるCEPA技術に関する知識も条約のすべてのレベルにおいて急成長しているという証拠も相当にある。
e)条約と、水鳥湿地トラスト(WWT)による湿地リンクインターナショナル(WLI)プログラムとの関係が、2005年11月に結ばれた協力の覚書を通じて強化された。WLIネットワークは成長を続けており、地球規模でのネットワークのもとに、国レベルや地域レベルでのネットワークも発展してきている。
3.ラムサール条約のCEPAプログラムのビジョン(抱負)は次のとおり。
「人々が湿地の賢明な利用のために行動すること」
4.ラムサール条約のCEPAプログラムの基礎となる指導原則は以下のとおりである。
a)人々が湿地の保全と賢明な利用への支持を動機づけられて、関連する政策形成や、計画策定、保全管理に対して自ら参加しようと行動するために必要となる、湿地の価値の理解を助けるためのツールを人々に提供すること。下の添付文書4にこのCEPAプログラムの主要な対象グループや利害関係者を特定している。
b)湿地の賢明な利用に主要な関係者の参加を得る効果や、賢明な利用原則を社会に普及させるために適切なメッセージを伝達してゆく効果のあるCEPAツールやCEPA技能の構築を促進すること。
c)CEPAは各締約国が条約を実施する上でその中心部分をなすべきものであり、湿地問題にかかり十分な理解を持った上での主張や行動をとる人やそのような人々のネットワークを増やし、そのような理解に基づく意思決定とそれを支持する人々を構築するための投資である。
5.このプログラムでは、達成が必要なこと(最終目標)と、それら最終目標を実現する方法(戦略)、達成されるべき成果(主要成果領域)を以下のとおり特定する。ボックス1に最終目標と戦略をまとめた。
ボックス1.対話・教育・参加・啓発(CEPA)プログラムの最終目標と戦略のまとめ
ここでは、湿地の価値についての意識を高めるためにCEPAを用いること、役立つ過程となるようにCEPAを促進すること、地球規模から全国規模、流域から各湿地までの多段階で、それぞれの政策や計画策定にCEPAを組み入れることなどが推奨される。
この最終目標の焦点は、CEPA活動が効果的に実施できる環境を確立することである。ここには、そのための枠組みや行動計画を策定すること、CEPA担当窓口を設置すること、個人や団体、センターなどを巻き込むこと、情報交換や資金、専門家、研修の機会などへのアクセスを得るためのネットワークを確立することなどの、仕組みが含まれる。
この最終目標の焦点は、CEPAの枠組み、そのツールや資料を、湿地の賢明な利用に対して新たに活動的になる動機を人々に与えてそれを可能にするように用いることである。
6.本プログラムは、その効果を発揮するために、条約に関して責任を有する以下の機関や協力団体が実施するものである。
7.段落6に示した組織や団体が、本プログラムを実施する任にある、または実施を手伝うことが要請されている主役であるが、これは例示にすぎず、本プログラムの期間にも変わる可能性がある。条約の成果の達成に関わる全ての団体が、それが一時であろうとも、このプログラムになんらかの形で参加することが必要なのは明らかである。下の添付文書3に、以下の達成されるべき成果(主要成果領域)ごとにその活動の中心になる可能性のある主役を表にまとめてあるので、各国が本プログラムの実施をモニタリングするための手段のひとつとされたい。
主要成果領域:
主要成果領域:
主要成果領域:
主要成果領域:
主要成果領域:
[参照]
主要成果領域:
[参照]
主要成果領域:
[参照]
主要成果領域:
[参照]
主要成果領域:
[文献]
1.本CEPAプログラムを用いる際に重要なことは、締約国をはじめとする関係者が、対話、教育、参加、啓発、能力育成、研修という用語の意味を、共通して理解しておくことである。以下に示す助言は、「生物多様性の主流化 Mainstreaming Biological Diversity」(ユネスコ・生物多様性条約・IUCN作成)に基づいており、この分野で実践にあたる人々が用いているこれら用語の共通した意味と、本プログラムを組み立てるにあたって用いられた考え方を示そうとするものである。
2.対話(Communication)とは、相互に理解を高めうる情報を双方向に交換することである。対話によって、活動に参加しようとする人や利害関係者の参加を得ることができる。まず始めに彼らに耳を傾けて意思決定の理由と方法を明確にする。こうして対話を用いて社会のさまざまなグループの協力を得ることができる。手段的アプローチにおいて、対話が、湿地保全を支えるための手段や、経済的制約に対処する手段、行動する動機を与える手段などとともに用いられる。
3.啓発(Awareness)は、成果に影響を及ぼす力を持つ個人や主なグループに、湿地に関連する問題へと目を向けさせる。啓発は、重要な問題や望まれる目標が何であり、それはなぜなのか、その達成のために何がなされているか、またなしうるかを、人々が理解するのを助けるための課題設定や主張の呼びかけである。
4.教育(Education)は、人々が湿地保全を支えるよう、情報を提供し、動機や力を与えることができるプロセスである。それは、個人や、制度、企業、政府の運営の方法に変化を起こすことだけではなく、ライフスタイルの変化を誘導することによって可能となる。広い意味で、教育は一生涯続くプロセスである。
5.研修(Training)は、仕事場へ持ち帰るべき特定の知識や技能、態度、行動などを増強する過程である。公的に提供される研修の機会などを利用することも、日々自己研鑽することも可能である。
6.能力育成(Capacity-building)には、個人から団体、組織にいたるまで、湿地の賢明な利用を効果的に実施する能力を高めるための一連の過程が含まれる。その能力には、設備や財源、資源、インフラストラクチャー、実施環境条件なども含まれる。
7.参加(Participation)は、利害関係者が湿地を賢明に利用するための戦略や行動の策定から実施、評価にいたるまでの共同過程に積極的に加わることである。どの程度参加するか、どのように参加するかは、その過程に特有の状況とその過程をリードする個人・組織の決め方しだいで、さまざまに異なる。考えられる参加のレベルと種類の幅はボックス2のように示される。
[文献]
ボックス2.参加のレベル
1.決議Ⅸ.18(2005年)で締約国は常設委員会に対して、同委員会第34回会合においてCEPA監督小委員会を設立し、締約国各国が任命する政府と非政府のCEPA担当窓口二者の幅広い役割を明確にすることを同小委員会の主要任務のひとつにするよう指図した。(CEPA監督小委員会の任務の全てについては http://ramsar.org/outreach_oversight_panel.htm を参照のこと。)
2.CEPA担当窓口の役割と責任について、同小委員会は2006年5月のその第1回会合において議論を交わして会合報告(前項のウェブに掲載)に記録した。同報告は、常設委員会第35回会合で承認された。以下の記述は、各締約国が自国のCEPA担当窓口の担当者やその役割と責任を決定するのを導くために、同小委員会が熟考したものであり、締約国はこれを用いる。
3.CEPA担当窓口を任命する理論的根拠、ならびに考慮すべき主要因は次のとおり。
4.最終的に、自国のCEPA担当窓口の的確な役割と責任を承認するのは各締約国である。彼らの役割と彼らに期待されることが、さまざまなレベルで取り組みを進める彼らの能力とその人材選択に反映されなければならない。そのときの候補の人材には担当窓口の役割と責任の条件を満たすために必要な情報を提供すること。
5.CEPA担当窓口の主要な役割と責任として、湿地CEPAを計画し実施する人々がその取り組みを発展させることを支える環境条件を提供するには、CEPA担当窓口が次のような役割を果たすことが提案される。
本プログラム段落6に示された実施主体を下に再録し、締約国が実施主体を特定したり実施状況をモニタリングする際の一助として、主要成果領域の各項目と組み合わせた表にまとめた。表内に○印を付したものが期待される実施主体である。空白列を残してあるので、追加の主体を書き入れることができる。また、主体ごとに2列を与えてあるが、右側の空白列はたとえば実施状況の追跡に用いることができる。全国規模[国]/集水域[流]/個々の湿地[個]といった実施レベルをわけて表に記入することもできる。
| 主要成果領域 | AA | N RC | CE PA | ST RP | IO P | R RC | 他 団体 | 事務 局 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 意識を高め、地域社会の支援を構築し、「自然の管理人」アプローチ(スチュワードシップ)と湿地と向き合う姿勢を促進するためのキャンペーンや、プログラム、プロジェクトなどが、主要なパートナーと協働して実施されていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 湿地の価値や機能についての意識を高めるため、国や地方のレベルで適切なイベントやプロモーションを用いて世界湿地の日を祝ったり、参考資料の配布が行われていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | メディアと協力することが、意思決定者や湿地を利用する主要な人々に対して、また広く社会の人々に対して、湿地の価値や恩恵について知らせることに役立っていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 条約の賢明な利用の原則を実証するものとして適切な条約湿地が活用されており、それら湿地には能力や、条約湿地であることの標識、解説資料などが適切に備えられていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 湿地の賢明な利用を推進する際、特に湿地資源をじかに利用する人々の関与を促すには、いかなるCEPA活動を適用するか、それを明らかにするためのパイロットプロジェクトが企画され、その結果が一連の方法で査定されていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 既存のCEPA計画やCEPA活動の事例が総括され、それらの経験から得られる効果的な取り組み方に関する教訓が文書にまとめられていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 前二項から得られた所見や結論が、適切な仕組みを通じて、締約国や広く社会の人々が利用できるようになっていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 他の条約や組織との共同作業計画を含めた条約のすべての作業計画にCEPAが組み入れられ、締約国のための条約の手引きのさらなる策定においても科学技術検討委員会のCEPA専門家を通じて同様にCEPAが含められていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 適宜、湿地に関するCEPAが、湿地、生物多様性、林業、農業、灌漑、発電、鉱業、旅行業、漁業などに関して、国や地方において、それらの政策や計画を策定する各種委員会の活動に組み入れられていること。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 他の国際的な条約やプログラムのもとで取り組まれるCEPA活動との相乗作用が、地球規模や各国での協働を通じて、促進されていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 主要な利害関係者が協働して、湿地に関するCEPAが、地域から、国、集水域、地方までの関連するすべてのレベルで、湿地部門や、たとえば、生物多様性保全、水管理、漁業、貧困削減など他の適切な部門において、その政策や、戦略、計画、プログラムに組み入れられていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 個々の湿地の管理活動に役立つCEPAの役割や、それら管理活動への人々の参加を得るために決定的なCEPAツールやCEPA技能の役割を示す事例研究が文書にまとめられ、締約国や他関連団体に配布するために条約事務局に提出されること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 集水域・河川流域や地方において、湿地に関する計画策定や管理を導き十分な情報を組み入れるための各種利害関係者からなる組織が設置されており、またそこには適切なCEPA技術が備えられていること。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | 集水域・河川流域の計画策定や管理に関する文書に、対話、教育、参加、啓発、および能力育成が、水や湿地の管理目標の全体を達成するためのプロセスの中心に、含められていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 個々の湿地の管理計画に、CEPAのための適切な戦略や行動が導入されていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | 締約国が、政府とNGOそれぞれの湿地に関するCEPA担当窓口に、その役割を果たすのに適格な人物を任命し、条約事務局にその担当者と連絡先を報告していること。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | 国レベルの湿地CEPA委員会がCEPA担当窓口と主な利害関係者やNGOの参加のもとに設立されており、湿地CEPAのニーズや、技能、専門的技術、選択肢の見直しが行われ、その作業計画を共同策定し実施するための優先事項が定められていること。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | CEPA担当窓口と湿地センターなどの環境教育センターとの協働が進められ、湿地CEPA委員会や他の計画策定組織にそれらセンターからの代表が適宜含められていること。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | 国レベルで(国に準ずるレベル、集水域レベル、地方レベルでも適宜)湿地に関するCEPA行動計画が作成されていること。行動計画には、そのために条約が準備したCEPAツールキットや、参加型管理に関する条約の指針(決議Ⅶ.8)、前項2.1.2から得られる結論が活かされていること。また、その行動計画の写しが条約事務局に提供され、他の締約国や関心のある団体・個人が利用できるようになっていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 政府の教育、国土・水管理、農業などの関連省庁の間の対話と情報共有が効果的に行われているかどうかに注意が払われており、必要に応じてその欠点を補う仕組みを展開していること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | 条約のウェブサイトが、利用しやすいCEPA関連ページなど適切な資料で定常的に更新されており、確実にこれらが地球規模でCEPA活動の情報源であり続けていること。 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | 条約の国際団体パートナー、特にIUCN教育コミュニケーション委員会、ならびに協力の協定を結んでいる他の組織が、世界規模のCEPAプログラムの助けとなる参考資料や効果的なCEPAアプローチに関する情報を一般に利用可能なものとなるように進めていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | 湿地に関するCEPA活動を支援するための参考資料が、引き続き、作成、配布、共有されていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 2.2.5 | 各国の条約担当政府機関や、CEPA担当窓口、CEPA専門家、条約湿地の管理者や利害関係者、環境教育や普及啓発を専門とする施設などが含まれるように、条約の世界規模のメーリングリストが維持され、いっそうの拡大が図られていること。同様のメーリングリストが、世界規模のものと連係しつつ、各国内でも設立され、支えられていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 2.2.6 | CEPAにおける専門的技術の一覧とCEPA担当窓口の連絡先一覧が、各国ならびに国際レベルでのCEPA活動に役立つように、オンライン検索可能なものとして設置され、維持されており、CEPAの計画や活動に活かされていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 2.2.7 | 湿地資源や、それらを賢明に利用する方法についての意識を啓発し、それらの大切さの認識を高めようとする、地球規模から各国、各湿地までの取り組みを支援するための、条約の電子的フォトライブラリーが財政が許すならば設置されていること。 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 教育センターが、条約湿地や他の湿地に設置され、地方規模から全国規模までのCEPA活動への窓口となっていること。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | 既存のセンターの能力を高めたり、新たなセンターを設置することによって、質の高いCEPA活動が進められていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | 湿地教育センターが存在している場合、それらが提供している情報の見直しがなされて、その情報がラムサール条約とその賢明な利用の原則を推進するのに適切に役立っていること。それらのセンターが、湿地管理に携わる地元の人々や利害関係者のあいだの対話や適切な参加の助長に役立っていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 2.3.4 | 世界や各国内のCEPA専門的技術にアクセスしたり経験を共有するための仕組みとして設立されている湿地リンクインターナショナルへの、各地の湿地教育センターの参加が進められていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 2.3.5 | 先進国にある湿地教育センターと、途上国や市場経済移行国にある湿地教育センターとの間で、情報と専門的技術の交換や移転を進めるために、湿地教育センターの姉妹提携を促しそのための財源調達を図る努力が進められていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 湿地教育センターの設立と運営にかかる場合を含め、湿地CEPAの分野における現在の国内のニーズと能力の見直しが実施され、その結果が全国湿地CEPA行動計画における研修と能力育成にかかる優先実施事項の決定に用いられていること。優先事項には自国のCEPA担当窓口の研修が含められること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | ラムサール条約のための能力育成諮問委員会や条約の国際団体パートナーとの協力のもとに、地方レベルから、国、地域、世界レベルで専門的技術と知識の共有を促進するため、専門家や研修の機会の情報源が特定されていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 3.1.3 | 前二項の取り組みによって優先事項と特定された研修と能力育成を支援するための財源が、適切なメカニズムを通じて求められていること。それら研修と能力育成においては確実に、女性や先住民社会・農村社会などの主要グループが見過ごされていないこと。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 3.2.1 | 能動的な参加が湿地管理技能を築くために有効な過程であるということが、全国的に認識されていること。 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 文化的あるいは経済的に湿地との結びつきをもつ利害関係者グループや、その生計を湿地に依存している社会の人々の参加に、高い優先順位が与えられ促進されていること。それら参加にあたっては、条約の住民参加指針(決議Ⅶ.8)が利用されていること。 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | 各湿地の先住民や社会が保持する湿地の知識が尊重されており、その湿地の管理計画の中に統合されていること。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
1.一般社会または市民社会という最も広い範疇で、数多くのグループが本CEPAプログラムの対象となりうる。自らの取り組みを決めようと本プログラムを用いる締約国ほかの一助として、この添付文書では、湿地の状態や長期的な持続可能性に対して違いを顕著にじかにもたらすことができると特定される27のグループについて記述する。
2.締約国ほかは、本CEPAプログラムに基づく行動を国または地方で計画する際に、本添付文書の内容をそれぞれの状況に照らして考慮し、優先順位が最も高い対象グループを決めることが強く要請される。
3.本CEPAプログラムに対応してとられる行動は条約自体や条約が奨励しようとする諸原則を実施する人、伝える人、支える人の数の増加に結びつくということが、本プログラムの根本的な前提である。そうなれば、本プログラムへの支援は、意思決定者を助け、湿地の保全と賢明な利用の達成にむけた行動を各湿地で結集することをねらった投資と見られる。
| 対象グループ/個人 | 理論的根拠 |
|---|---|
| 地主(特に、湿地の管理に責任を持つ者) | 地主は湿地に直接影響する決定を下す。締約国とラムサール条約は、彼らに情報を与えるとともに、彼らが専門的情報と専門的技術を利用できるようにしなければならない。 |
| 全国規模のNGO、地方のNGO | 多くの国で地方のNGOは行動の達成になくてはならない存在である。彼らは、利用できる専門的情報や専門的技術を獲得する必要がある。 |
| 先住民及び地域社会 | 湿地に関係のある多くの先住民や地域社会は、こうした生態系を持続可能な方法で管理する偉大な知識をもち、また現在も湿地と文化的につながっている場合もある。そのような湿地の経験を他の湿地の管理者と共有することを奨励し、先住民の湿地の管理者としての立場(スチュワードシップ)を認めることを、ラムサール条約は志すべきである。 |
| 女性 | 多くの文化では、女性は、家族という単位の中で一番実行力に富み、生活習慣の変更を受け入れやすい傾向があるので、湿地管理に携わる女性を増やすことは優先事項である。女性はまた、家族の中で一番多くこどもと言葉を交わすものである。 |
| 子ども | 子どもは次の世代の環境管理者ないし環境の世話人であり、子どもたちには、ラムサール条約が湿地の重要性とその賢明な利用法を確実に伝えなければならない。子どもたちは自分たちが受けた教育を通じてその親たちの教師となることもできる。 |
| 電子メディア、活字メディアに携わる人々 | 電子メディアや活字メディアでのニュースやその他の記事を通じて、一般社会への湿地に対して肯定的な参考情報の伝達を促進できる。 |
| 社会的リーダー、著名人(スポーツ選手、宗教の指導者、芸術家、王族、教師、オピニオンリーダー等) | 社会的リーダーは、知名度を活かして問題に対して、人々の注意を引くことができる。なかでも湿地保全に共感する人々は、ラムサール条約のメッセージを普及する理想的な大使となることができる。 |
| 対象グループ/個人 | 理論的根拠 |
|---|---|
| 地方自治体や国の政府のなかの環境政策決定者及び計画策定者 | 左記の当局者は、地方から国までの規模で主な意思決定者である。彼らの行動は、湿地に対して、個々の湿地規模あるいは集水域・河川流域規模で、直接に、プラスにもマイナスにも影響しうる。 |
| 地方自治体や国の政府、集水域・河川流域管理当局のなかの湿地管理者(監視人、レンジャー等) | こうした人々は、湿地生態系を管理する最善の実践方法の助言や、彼らの仕事に対して市民の支持と参加を得るための助言を受けるという特別な必要がある。条約湿地の管理を担当する場合には特にそうである。彼らが有する直の湿地管理経験は貴重であり、これらの経験を管理者どうしの間や他の対象グループの人々と共有するための方法を見つけることが優先事項である。 |
| ラムサール条約担当政府機関 | 彼らは、効率的な適用と普及に足る最善の情報を持つべきである。 |
| 他の環境関連条約担当政府機関とその担当窓口 | 国土・水資源の管理に湿地を含めてより統合的なアプローチが採ろうとするならば、他の条約を実施する関係者にラムサール条約へのいっそうの理解と共感を呼び起こす必要がある。 |
| ラムサール条約や他の環境関連条約に関する国内諮問委員会(国内ラムサール委員会等) | 同じく、ラムサール条約や他の条約の実施に関して政府に助言する人々にも、ラムサール条約へのいっそうの理解と共感を呼び起こす必要がある。 |
| 持続可能な開発と教育関連のすべての職務及び環境関連条約を担当する大臣ならびに国会議員、地方議会議員 | 彼らは政策の設定や予算配分等に直接介入するため、ラムサール条約はこうした大臣やあらゆる政府閣僚から支持を得る必要がある。野党の国会議員らは、将来こうした地位につく可能性がある。 |
| 各国の援助機関、二国間援助機関 | ラムサール条約は、持続可能な開発にかかる一連の問題で各国政府を援助しているこれら機関において、条約の活動内容全般が十分に理解されているよう確保する必要がある。ラムサール条約は、関係する援助機関職員が、締約国内の現地プロジェクトを通じてラムサール条約の原則を支えるように十分な指示を受け、それを可能にするように確保しなければならない。 |
| 大使、及び海外任務につく職員 | 本国政府がより良く情報に精通できるように、こうした職員がラムサール条約とその運用方法について全面的に理解していることが重要である。 |
| 対象グループ/個人 | 理論的根拠 |
|---|---|
| 世界的な組織:世界銀行、地球環境ファシリティー、国連開発計画、国連環境計画、地球水パートナーシップ等 | ラムサール条約は、持続可能な開発にかかる一連の問題で各国政府を援助しているこれら機関において、条約の活動内容全般が十分に理解されているよう確保する必要がある。当該機関に資金供与計画がある場合には、ラムサール条約は、関係する援助機関職員が、締約国内の現地プロジェクトを通じてラムサール条約の原則を支えるように十分な指示を受け、それを可能にするように確保しなければならない。 |
| 地域的組織:南太平洋地域環境プログラム、欧州委員会、南部アフリカ開発共同体、地域的な開発銀行、アセアン環境プログラム等 | 上に同じ。 |
| 世界的なNGOパートナー、その他国際NGO、地域NGO | ラムサール条約の5つの正式なNGOパートナー(バードライフ、国際水管理研究所、IUCN、国際湿地保全連合、WWF)は、いずれも条約の推進に活発に効果を発揮している。さらに多くの国際NGOや地域NGOをラムサール条約のメッセージ伝達に巻き込む必要がある。 |
| 他の環境関連条約等の事務局(生物多様性条約、砂漠化対処条約、ボン条約、気候変動枠組み条約、ワシントン条約、世界遺産条約、人と生物圏プログラム) | 地球規模ならびに各国において、条約どうしの相乗効果を高めるために欠かせない。 |
| 対象グループ/個人 | 理論的根拠 |
|---|---|
| 潜在的な後援者、支援者 | ラムサール条約は、湿地の持続可能な利用を推進しているのであるから、企業による活動が条約の目標に反する作用を及ぼさないように企業に働きかけなければならない。 |
| 主要な産業各部門 ・水・衛生 ・潅漑・水供給 ・農業 ・鉱業 ・林業 ・漁業 ・環境管理者 ・観光 ・廃棄物処理 ・エネルギー | これらの産業部門等は、湿地にマイナスの影響を大きく及ぼす可能性がある。ラムサール条約は、これら産業部門において湿地の減少を招かない活動を助長しなければならない。 |
| 職業団体 | ラムサール条約は、条約の賢明な利用法の適用をこれら職業団体を通じて奨励すべきである。 |
| 対象グループ/個人 | 理論的根拠 |
|---|---|
| 教育大臣、教育課程作成当局、試験委員会・大学、現職教官等 | 左記はすべて、湿地の保全と賢明な利用という問題を、学校等の公的教育課程に含めるように働きかけることができる。 |
| 全国教職員協会、国際教職員協会 | 教育課程や学習プログラムにラムサール条約の原則を盛り込むことは、一般的に、教職員協会と協働することによって促進できる。 |
| 環境教育に関する、全国ネットワーク、国際ネットワーク、協会、評議会 | 左記の組織が作成する教育課程等の資料に、湿地と水の問題を盛り込むことができる。 |
| 湿地センター、環境センター、動物園、水族館、植物園等 | 左記は、ラムサール条約のメッセージを広める理想の場であり、利用可能な情報・資料や学習プログラムが適切に備えられているよう努力が傾注されるべきである。 |
| 図書館の全国ネットワーク、国際的ネットワーク | 図書館ネットワークは、ラムサール条約と湿地に関する情報を一般市民に利用しやすいものにできるすばらしい場を提供する。 |
[ Word (50kb zip)] [ PDF (104kb zip)] [ Top ] [ Back ] [ Res X.8 ]
| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部●主要な決議等 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop10/sc37_doc11j.htm
Last update: 2009/09/05, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).