
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
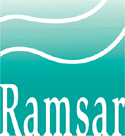
日本語訳:環境庁,2000年[了解を得て再録].
英語 フランス語 スペイン語 (以上,条約事務局) PDF (環境省のインデックスページ)

[決議Ⅶ.27において採択]
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動1.1.1.特に締約国の少ない地域の国々や、重要な湿地資源及び二つ以上の国にまたがる湿地資源(共有される種を含む)、またはそのいずれかを持つ国々に、条約への加盟を募る。[締約国、常設委員会地域代表、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動1.1.2.地域会合とその活動、そして国際団体パートナーの地域事務所を通し、条約への加盟を促進する。[常設委員会地域代表、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動2.1.1.法制度と実施状況の見直しを行い、COPへの国別報告書で賢明な利用ガイドラインがどのように適用されているかを示す。[締約国] |
|
| 行動2.1.2.国家環境行動計画や国家生物多様性戦略、国家自然保護戦略といった他の国家的な保全計画策定の明確な構成要素の一つとして、または独立した政策として、国家湿地政策を策定するよう、いっそうの努力を促す。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動2.2.1.湿地、その中でも特に集水域と沿岸域の利用計画策定の情報を収集し、締約国が利用できるようにする。[条約事務局] |
|
| 行動2.2.2.国家、都道府県、地方の土地利用計画策定に関わる文書や活動において、またすべての関連部門及び予算配分に関する条項に、湿地を含めることを促す。[締約国] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動2.3.1.賢明な利用の追加手引きの適用を、他の機関と協力して、油流出防止や除去作業、農業による水質汚染、都市廃棄物や産業廃棄物といった特定の問題にまで拡大する。[締約国、科学技術検討委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.3.2.既存のガイドラインと追加手引きが効果的に適用された例を公表する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動2.4.1.湿地の恩恵と機能の経済評価を示す文書と方法論を開発し、広い範囲への普及と適用を促進する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.4.2.IUCNや他の協力機関の支援を受けて、COP6で発表された湿地の経済評価に関する情報を出版する。[条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.4.3.行動2.4.2に基づいて出版される経済評価に関する知見を実施するような具体的活動を始める。[締約国] |
|
| 行動2.4.4.湿地の経済評価の分野で推奨しうる具体的な実践例の内容と実施状況を、COP7(1999年)の分科会で検討する。[科学技術検討委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
技術の発達、汚染その他の人為的干渉の結果、変化するおそれがある(ラムサール条約第3条2)ものについては、環境影響評価を実施する。
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動2.5.1.COP7(1999年)の分科会に向け、「環境影響評価のためのガイドライン」の検討結果と、現在行われている環境影響評価の最良の実践例を準備し、賢明な利用の追加手引きの内容を拡大する。[常設委員会、科学技術検討委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.5.2.湿地に影響を及ぼす可能性を持つ開発案件や、土地利用・水資源利用変更の結果、生態学的特徴に変化が起こる恐れのある登録湿地では、(湿地の恩恵と機能の経済評価を十分に考慮しながら)確実に環境影響評価を実施するようにし、またその結果をラムサール条約事務局に通知し、関係当局がその結果を十分に考慮するように図る。[締約国] |
|
| 行動2.5.3.開発案件や土地利用・水資源利用の変更のために、特に湿地資源への悪影響が起こる恐れのあるその他の重要な地域においても、環境影響評価を実施する。[締約国] |
|
| 行動2.5.4.開発案件あるいは土地利用・水資源利用の変更による影響を評価する時には、(都道府県や地方レベル、並びに集水域あるいは沿岸域のレベルでの)「統合的環境管理」や「戦略的環境影響評価」を考慮する。[締約国] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動2.6.1.復元あるいは機能回復の必要がある湿地を特定するため、地域あるいは国の科学的な湿地目録(勧告4.6)を用いるか、モニタリングを実施する。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.6.2.失われた湿地または機能が劣化した湿地を、復元そして機能回復するための方法論を提供し実施する。[締約国、科学技術検討委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.6.3.破壊された湿地または機能が劣化した湿地、特に主要な河川系または高い自然保護上の価値を有する地域(モントルー会議の勧告4.1)において、湿地の復元・機能回復プログラムを確立する。[締約国] |
|
| 行動2.6.4.COP7(1999年)で湿地の復元と機能回復に関する分科会を催し、都道府県や地方レベルそして集水域レベルにおける最良の実践例10例を特定する。[科学技術検討委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動2.7.1.湿地の管理に地域住民そして先住民の参加を得るという、勧告6.3を実施する。[締約国、条約事務局] |
|
| 行動2.7.2.湿地の生態学的特徴をモニターするため、湿地の管理者そして地域住民がすべてのレベルで協力して仕事を進めることを奨励する。こうすることで、管理ニーズや湿地に対する人間の影響への理解が深まる。[締約国] |
|
| 行動2.7.3.特に登録湿地において、湿地管理委員会を設立し、湿地管理に地域社会の参画を求める。委員会には、地域の利害関係者や土地所有者、管理者、デベロッパーそしてその他の利益団体、特に女性グループの代表者を入れる。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.7.4.湿地の保全と賢明な利用について、先住民や地域社会が持つ伝統的な知見そして管理のやり方を認識し、適用する。[締約国] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動2.8.1.民間企業が湿地に影響を与える事業を展開する際に、湿地の属性や機能そして価値をより深く認識することを促す。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.8.2.民間企業が湿地に影響を与える開発事業を展開する際に、賢明な利用ガイドラインを適用するように奨励する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動2.8.3.民間企業に湿地管理者とパートナーシップを結び、湿地の生態学的特徴をモニタリングするよう奨励する。[締約国] |
|
| 行動2.8.4.湿地管理委員会への参加を通じ、湿地管理に民間企業を参画させる。[締約国] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動3.1.1.地球規模の協調で、湿地の「教育・普及啓発」プログラムを開発し、実施するための調整の仕組みと機構を特定し、設立することを支援する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動3.1.2.地域の教育・普及啓発活動のニーズの特定と、実現のための資源を開発するための優先事項の確認に参加する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動3.1.3.各国の教育・普及啓発プログラムを支援するための国際的な参考資料の開発を支援する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動3.1.4.湿地教育センターや教育者の間で、情報、知識、技術の交換を促進する国際的プログラムを支援する。例えば、国際湿地保全連合の教育普及啓発作業部会(EPA Working Group)、地球河川環境教育ネットワーク、湿地リンクインターナショナルなどである。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動3.1.6.COP7と併せて、湿地に関する国際的な教育・普及啓発活動の見直しを行う。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動3.2.1.政府機関やNGO、そして国内向けの教育・普及啓発プログラムを開発できるようなその他の機関とのパートナーシップを奨励する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動3.2.2.特定されたニーズや対象とするグループに基づいて、湿地を肯定的に捉えるようなビジョンを創り出し、湿地の価値と機能に対する関心をすべてのレベルで喚起するための、国内事業やキャンペーンを支援する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動3.2.3.湿地の現場に教育センターを設置するよう奨励する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動3.2.4.博物館、動物園、植物園、水族館、そして環境教育センターとともに、学校教育外で湿地についての教育・普及啓発を支えるような展示やプログラムの開発を奨励する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動3.2.5.高等教育そして専門的な研修コースを含め、教育のすべてのレベルの教育課程に湿地に関連した単元を組み込むよう奨励する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動3.3.1.条約事務局の広報活動、特に地域そして国内広報ネットワークの創出とその機能に関する活動を見直し、新しい資料と技術の利用を開発し、既存の資料を改訂する。[条約事務局] |
|
| 行動3.3.3.各地域の持つ個別の問題、そして未加盟国に対しては条約加盟に伴う利点を強調した資料を準備して、既存の「ラムサール条約情報セット」を補完する。[常設委員会地域代表、条約事務局、締約国] |
|
| 行動3.3.4.締約国、常設委員会委員、科学技術検討委員会、条約事務局、協力機関を結び付ける、電子メールネットワークと電子掲示板/メーリングリストを作成し維持するために、電子通信業者の支援を求める。[すべての関係者] |
|
| 行動3.3.5.1997−1999年の3年間における経験に基づき、COP7に向けて「条約広報戦略」を準備する。[常設委員会、条約事務局、締約国] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動4.1.1.湿地の保全と賢明な利用に責任を持つ、国内の既存の担当機関を見直す。[締約国] |
|
| 行動4.1.2. |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動4.2.1.「賢明な利用のガイドライン」を実施する際に必要な研修とその対象者を、国、都道府県、そして地方レベルで特定する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動4.2.2.湿地の保全と賢明な利用のために不可欠な分野で、現在行われている研修機会を特定する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動4.2.3.「賢明な利用ガイドライン」の実施に関連し、あらゆる地域において適用できるよう、… の分野の専門的な単元を含んだ、新しい研修活動と一般的な研修用単元を開発する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動4.2.4.以下のことを通して、管理者研修の機会を提供する:実地研修のための職員の交流、特定の登録湿地における試験的な研修講座の開講、登録湿地に湿地管理者研修用の施設を設置、世界各国にある湿地管理者向け研修講座についての情報を入手し広める。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動4.2.5.「小規模助成基金」の「実施ガイドライン」において、研修活動に対する支援に高い優先度を与える。[締約国、常設委員会] |
|
| 行動4.2.6.湿地の保全と賢明な利用について、また、南・南間の協力(途上国間の協力)についての、情報、技術的援助や助言、専門知識の交流を図る。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動5.1.1.COP6(1996年)で採択された「生態学的特徴の実用上の定義」に照らし合わせた、登録湿地の生態学的特徴を維持するために必要な、的確な方策を見極めて実行に移す。[締約国] |
|
| 行動5.1.2.変化する可能性のある生態学的特徴を特定するために、地域社会及びその他の利害関係者から意見を聞き、関係者による湿地の定期的な内部検討を実施する。そして、対応措置をとり、必要な場合にはその湿地のモントルーレコード登録を申請する。[締約国] |
|
| 行動5.1.3.モントルーレコードを見直し定期的に改訂する。(釧路会議決議5.4、5.5、及び決議Ⅵ.1)[締約国、科学技術検討委員会、条約事務局] |
|
| 行動5.1.4.ラムサール登録湿地の将来の管理についての助言を提供するため「管理ガイダンス手順」(モントルー会議勧告4.7)の適用を増やす。[締約国、常設委員会、条約事務局] |
|
| 行動5.1.5.「管理ガイダンス手順」派遣調査団の報告書にある勧告の実施を促進する。[締約国] |
|
| 行動5.1.6.有毒化学物質(勧告6.14)、気候変動、海水面の変化を含む地球規模の危機が、ラムサール登録湿地の生態学的特徴に与える可能性がある影響を特定する。[科学技術検討委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動5.2.1.現場での経験及び勧告6.13に照らし合わせて、「管理計画策定ガイドライン」の見直しを行う。[締約国] |
|
| 行動5.2.2.締約国の参考になるように、1999年のCOP7以前に、地方、地域レベル、または集水域や沿岸域レベルで、登録湿地の管理計画の好例と考えられる10例の事例研究を出版する。[科学技術検討委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動5.2.3.地域住民や他の利害関係者から意見を聞いた上で、いくつかの湿地において試験的にプログラムを始め、COP8(2002年)までに各締約国の登録湿地の少なくとも半数で確実に、管理計画かそれに代わる機構が準備中あるいは実施に移されているようにする。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動5.2.4.広い面積を持つ登録湿地、湿地保護区、その他の湿地について、ゾーニング(利用目的による区域分け)のための手段を確立し、実施に移すことを促す(釧路会議勧告5.3)。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動5.2.5.登録湿地はその他の湿地の中でも、特に環境変化の影響を受けやすく、また面積も小さなもの、あるいはそのいずれかのものは、厳正な保護措置の確立、そしてその実施を促進する(勧告5.3)。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動5.2.6.「小規模助成基金」の運用ガイドラインにおいて、登録湿地の管理計画策定への支援に高い優先度を与える。[締約国、常設委員会] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動5.3.1.湿地登録の指定が完了した際に、標準書式として承認された「ラムサール登録湿地情報票」に従うかたちで、ラムサールのデータベースに対し、締約国は登録湿地の完全な地図と記載を提出する。また、管理計画策定と生態的特徴のモニタリングに用いられるのに十分な詳細情報を提供する。[締約国、条約事務局、国際湿地保全連合] |
|
| 行動5.3.2.データベースの有用性と使い勝手を向上させるために、登録湿地の情報票や地図の抜け部分や不完全な部分を速やかに提出することを最優先事項とする。[締約国] |
|
| 行動5.3.3.「登録湿地情報票」は、締約国会議が2回開催される間に少なくとも1回の頻度で定期的に更新されるようにする。このことは、条約の達成度合いの評価、将来の戦略計画作成、広報活動に役立つほか、登録湿地・地域・テーマごとの分析ができるようになる(決議Ⅵ.13)。[締約国、科学技術検討委員会、条約事務局、国際湿地保全連合] |
|
| 行動5.3.4.COP7(1999年)までにラムサール条約登録湿地一覧を見直して改訂出版することとし、COP8(2002年)までにCOP7とCOP8の間に登録された湿地の要旨を作成する。[条約事務局、国際湿地保全連合] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動5.4.1.現在データベース中にあるデータを評価し、締約国によって提供されたデータとの間に違いがあればそれを特定する。[締約国、科学技術検討委員会、条約事務局、国際湿地保全連合] |
|
| 行動5.4.2.GIS(地理情報システム)を構築する可能性を含め、見込まれる要求に対応できるようデータベースを最新のものにして更新を行い、それらに応じて構造を改良する。[条約事務局、国際湿地保全連合] |
|
| 行動5.4.3.電子通信ネットワーク(インターネット)や、フロッピーディスクやCD−ROMのランタイム版を通じて、また特別報告書やその他の成果品で、データベースを多くの人が利用(読みとり専用)できるようにする。[条約事務局、国際湿地保全連合] |
|
| 行動5.4.4.ラムサールデータベースと互換性のある国内湿地データベースの各国での構築を支援し、情報交換と相互交流ができるよう共通の規格を開発する。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動6.1.1.登録湿地候補地を特定した地域の湿地目録を作成、定期的に改訂(特にアフリカの場合)、そして広く配布する。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動6.1.2.各締約国の領土内において、登録湿地の候補となる国際的に重要な湿地、そして都道府県や地方レベルで重要な湿地を特定した、国内科学的湿地目録を作成、改訂し、配布を行う。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動6.1.3.湿地の保全または消失の世界的な傾向を考慮するベースラインとなる、地球規模の湿地資源の定量化に着手するために、地域や国内の科学的湿地目録や、その他の情報源を活用する。[条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動6.1.4.水鳥と他の分類群の個体群の大きさに関する情報を国際湿地保全連合とIUCNが更新する際にこれを支援し、これらの情報を登録湿地候補地を特定するために用いる。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動6.2.1.ラムサール条約の下での各地域及び各締約国内において、代表的な湿地タイプがすべて湿地登録されているようにするため、新たに締約国となった国家による湿地登録、そして既に締約国となっている国家、特に途上国による追加登録を促進して、登録湿地の面積が増えるようはからう。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動6.2.2.登録を考慮される湿地が登録湿地選定基準を満たすことを確認する作業において、締約国を支援し助言を与える(釧路会議決議5.3)。[条約事務局] |
|
| 行動6.2.3.適切な場合には、特にサンゴ礁、マングローブ、藻場、泥炭地といった、これまであまり登録湿地として指定されていない湿地タイプが新規登録されるよう優先的に注意を払う。[締約国] |
|
| 行動6.2.4.現状では国内法で特別な保護指定を受けていない湿地を保全し賢明に利用するための措置を講じる第一歩として、それらの湿地の新規登録に特に目を向ける。[締約国] |
|
| 行動6.2.5.国境をまたぐ湿地の登録を、優先事項として検討する。[締約国] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動6.3.1.地球規模の湿地保全の優先事項及び価値を確実に反映するよう、一般的選定基準を継続的に見直す。[締約国、科学技術検討委員会、条約事務局] |
|
| 行動6.3.3.既存の登録湿地選定基準を様々な地域で適用する際のさらなる手引きを提供する。[締約国、科学技術検討委員会] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動7.1.1.国境をまたぐ国際的に重要な湿地(複数の国家に共有される集水域や河川流域を含む)を特定し、「集水域アプローチ」(釧路会議勧告5.3)を用いて、これらの地域の共同計画を準備し実施するよう促す。[締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動7.1.2.国境をまたぐ湿地、あるいは似かよった特性を持つ湿地の姉妹湿地提携を促進し、成功例を国際協力の利点を具体的に提示するために用いる。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動7.2.1.情報交換や協力を促進するために、関係する条約との協議に参加し、あるいは新たな協議を提唱し、共同行動をとれる分野を開発する。[常設委員会、条約事務局] |
|
| 行動7.2.2.他の条約及び国際団体パートナーと一緒にプロジェクト案を準備し、支援を得られるかもしれない援助機関に共同で提出する。[締約国、常設委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動7.2.3.生物多様性条約との協力と協働を強化する。特に、国家生物多様性戦略に湿地への配慮を盛り込むこと、湿地に影響を与える作業計画の策定と実施に関して強化する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動7.2.4.ラムサール登録湿地、世界遺産指定地、生物圏保護区のすべてに、あるいはそのいずれかに指定されている湿地について、「世界遺産条約」及びユネスコの「人と生物圏(MAB)プログラム」と協力する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動7.2.5.主として移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約)、フライウェイ(渡り鳥の渡りルート)に関する協定やネットワーク、そして移動性の種を取り扱うその他の機構等との協力体制を通じて、複数の国家で共有される湿地生物種のための国際協力に対し、ラムサール条約の貢献度を高める(勧告6.4)。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動7.2.6.「ワシントン条約」との相互関係を強化することによって、湿地に影響を与える野生生物の取引に関する問題にラムサール条約はさらに貢献する。[条約事務局] |
|
| 行動7.2.7.気候変動が湿地に影響を与える恐れがあるという観点から、「気候変動に関する国際連合枠組み条約」との連携をはかる。[締約国、条約事務局] |
|
| 行動7.2.8.地域レベルで湿地の保全と賢明な利用に関わる条約及び機関との協力を拡大する。特に、「ヨーロッパ共同体」とは、生息地指令の湿地への適用、ヨーロッパ連合外の国々の湿地に対して生息地指令のような方策を採択し適用する件に関して協力を促進する。また、ヨーロッパ評議会の「ヨーロッパの野生生物及び自然生息地に関する条約(ベルン条約)」とは、汎ヨーロッパ生物景観多様性戦略に関して、バルセロナ条約と地中海行動計画とは「地中海湿地フォーラム」の活動に関して協力を進める。西半球条約との協力、特に「地域海条約(Regional Seas Conventions)」に関して国連環境計画、そして「南太平洋地域環境プログラム(SPREP)」との協力も促進する。[締約国、条約事務局] |
|
| 行動7.2.9.例えば「国際サンゴ礁イニシアチブ」と「世界水協議会」等、湿地に関連する事項を扱う他の専門機関との協力を発展させる(決議Ⅵ.23)。[条約事務局] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動7.3.1.開発援助機関に支援された、あるいは多国籍企業が始めた湿地プロジェクトの中で、代表的な模範例を特定する。[条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動7.3.2.多国間及び二国間開発機関、さらに多国籍企業と共に、湿地の価値と機能を十分に認識するための活動において協力し(モントルー会議勧告4.13)、OECDの開発援助委員会により出版された「熱帯と亜熱帯の湿地保全と持続的な利用を改善するための援助機関用ガイドライン」を考慮に入れて、湿地保全と賢明な利用が促進されるように、それら機関と企業の活動を改善することを支援する(勧告6.16)。[条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動7.3.3.途上国がラムサール条約の下での責務を果たせるようにするため、二国間の開発プログラムを通じて、また多国間開発援助機関との相互協力によって支援を行い、実施された活動及びその結果を報告する(釧路会議勧告5.5)。[締約国] |
|
| 行動7.3.4.特に途上国の湿地に影響を与える可能性のある援助を行う、各国の援助機関の責務について、締約国が国際協力の分野の責務をどのように果たせばよいかという点に関するガイドラインを、COP7(1999年)の分科会での検討に向けて作成する。[常設委員会、条約事務局] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動7.4.1.各締約国は湿地の保全と賢明な利用のために予算を割り当てる。[締約国] |
|
| 行動7.4.2.開発援助機関が資金提供する開発計画の中に、湿地の保全と賢明な利用のためのプロジェクトを含め、それら援助機関が各締約国のラムサール担当省庁との協議を確実に行うようにする。[締約国] |
|
| 行動7.4.3.開発援助を行う多国間機関と、特にプロジェクト案件の選択、開発、評価に関して緊密な関係を保つ。[条約事務局] |
|
| 行動7.4.4.湿地の保全と賢明な利用、そして「戦略計画」を実施する上で、途上国と市場経済移行国を支援するため、多国間及び二国間開発援助機関から直接援助を得るよう取り組む。[締約国、条約事務局] |
|
| 行動7.4.5.他の機関からの資金援助を受けて湿地プロジェクトを展開するために、途上国と市場経済移行国を支援する。[条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動7.4.6.湿地プロジェクトの案件選択、開発と評価にあたり、二国間開発援助機関を支援する。[科学技術検討委員会、条約事務局] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動8.1.1.COP7(1999年)から会議の再編成を行い、管理運営上の議題を扱う運営会議と、湿地保全と賢明な利用における優先事項を扱う分科会に分け、必要に応じ小規模な作業部会を加えた形にする。[常設委員会、条約事務局] |
|
| 行動8.1.2.締約国数の増加に伴い、常設委員会における地域区分及び代表者数の継続的な見直しを行う。[締約国会議、常設委員会] |
|
| 行動8.1.3.COP7(1999年)までに、常設委員会の役割、責務、必要とされる財政措置を見直し、必要があれば変更を加える。[締約国会議、常設委員会] |
|
| 行動8.1.4.毎回の締約国会議において、科学技術検討委員会の業務の優先順位を見直す。[締約国会議、常設委員会] |
|
| 行動8.1.5.作業計画の決定に従って、必要となる条約事務局の職制と人数を見直し、条約事務局と他条約の事務局や国際団体パートナーとの関係を見直す。[締約国会議、常設委員会] |
|
| 行動8.1.6.締約国会議で毎回「戦略計画」の実施状況についての評価を報告し、2回ごとの締約国会議で次期6年間(締約国会議2回分)の「戦略計画」の草案を準備する。[締約国会議、常設委員会、条約事務局] |
|
| 行動8.1.7.常設委員会で検討し承認を得るため、締約国会議で採択された「戦略計画」と3年間の作業計画に基づき、条約事務局の年間作業計画を作成する。[常設委員会、条約事務局] |
|
| 行動8.1.8.条約事務局との調整を行いながら各地域での条約の施行状況を向上させるため、締約国または国際団体パートナーにおける連絡調整機構を開発する。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動8.1.9.政府機関、NGO、主要利害関係者、先住民、民間企業、利益団体、土地利用計画策定及び管理担当当局からの意見を取り入れたり、それぞれの代表が参加する機会を提供するため、国内ラムサール委員会の設立を促進する(釧路会議勧告5.13)。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動8.1.10.湿地の保全と賢明な利用に関係するすべての政府機関が条約の活動により活発に参画するようにするため、各締約国のラムサール担当省庁の見直しを行う。[締約国] |
|
| 行動8.1.11.締約国会議用の国別報告書の見直し(決議Ⅵ.21)を含んだ、ラムサール条約のすべての制度、機構、事業の効果と効率を評価するための手続きを確立し、それが定期的に実施されるようにする。それによって発生する勧告を実行に移し、その結果を締約国会議及び常設委員会に報告する。[締約国会議、常設委員会、条約事務局] | この3年の間に、常設委員会は条約事務局の支援を受けて、下記を見直した。
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動8.2.1.条約の基本予算に対する拠出金が請求された際には、これを全額各年の始まりに速やかに支払うものとする。[締約国] |
|
| 行動8.2.2.途上国と市場経済移行国からの常設委員会代表が、それぞれの地域全体において条約の活動と情報の伝達を調整する際に、効果的に機能できるようにするため、財政面及び人材協力の面で十分な支援を提供する。[締約国会議、常設委員会] |
|
| 行動8.2.3.資金提供の見込みのある者にプロジェクトを説明する際、触媒的な役割を果たすのに十分な職員が条約事務局に確実に配置される。[締約国会議] |
|
| 行動8.2.4.研修計画、教育・普及啓発活動、ラムサールのデータベースの開発、条約の広報戦略への資金手当を優先して行う。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動8.3.1.国際団体パートナーと共同で計画する仕組みを強化し、職員の出向を含め連絡と情報交換を向上させる。[締約国、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動8.3.2.資源の効果的利用を最大化し、取組の重複が起こらないようにするため、また特に賢明な利用ガイドラインについて新たな協力関係を結ぶため、国際団体パートナーとの正式な協約を見直し更新する。[条約事務局、国際団体パートナー] |
|
| 行動 | 進捗状況、優先項目、目標 |
|---|---|
| 行動8.4.1.COP6(1996年)後の最初の正式な常設委員会で承認し、すぐ実行に移すことができるよう、ラムサール小規模助成基金のため最低年間100万米ドルを確保するための戦略を策定する。[条約事務局、常設委員会、締約国、国際団体パートナー] |
|
| 行動8.4.2.COP7(1999年)で、小規模助成基金の実績を批判的に評価する。[締約国会議、常設委員会、条約事務局] |
|
| 行動8.4.3.小規模助成基金を高い水準で適用することを奨励し支援する。[常設委員会、条約事務局、国際団体パートナー] |
|
訳注1 COPは締約国会議のこと。COP7は第7回締約国会議(COPに続く数字は、何回目の締約国会議かを表す)。
訳注2 渡り鳥ルート(ネットワーク)の開発。
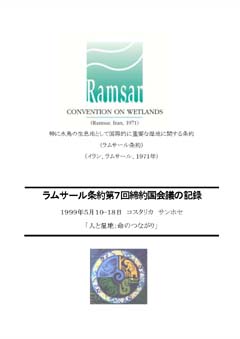
[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.27 Annex "Ramsar Convention Work Plan 2000-2002", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/key_workplan_2000.htm.]
[和訳:「ラムサール条約第7回締約国会議の記録」(環境庁 2000)より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2001年6月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_workplan_2000_j.htm
Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).