| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日
1.ラムサール条約の『2003−2008年戦略計画』(行動1.2.3)は、科学技術検討委員会(STRP)、条約事務局および生物多様性条約(CBD)に対し、「第9回締約国会議(COP9)での検討に向け、湿地の生物多様性と機能を迅速に評価し、また生態学的特徴の変化をモニタリングするため、内陸、沿岸及び海洋生態系における指標などの使用も含めたガイドラインを策定する」ことを要請している。
2.このことは、内陸水に関するCBDのプログラム(ラムサール条約はこの実施のための主要パートナーとされている)についてのCBDの決定Ⅳ.4が、各種の内陸水生態系に適した内陸水生物多様性の迅速評価のための地域別ガイドラインの策定および配布を要請していることに呼応する。同様に、CBDで科学技術助言補助機関(SBSTTA)による勧告Ⅵ.5は「沿岸海洋域の生物多様性に関連するものを含んだ、科学的評価のための ﹍ 方法論の開発」を要請している。
3.内陸水に関するCBDの手引きは、コンサベーション・インターナショナルが起草したものであるが、各国のラムサール及びCBDの担当窓口の指名による両分野の専門家が加わった、両条約事務局の共同開催による専門家会議によって一層の発展をみた。この手引きは、CBD及びラムサール条約第3次共同作業計画に基づき、両条約双方の必要性を満たすことを特に意図している。沿岸海洋域の手引きは、電子的手段を活用した作業部会を通じて策定されたもので、内陸水用手引きをもとにしており、アプローチ及び全般的構造は内陸水の手引きと合致する。
4.CBDガイドラインの原本は、CBDのSBSTTAの第8回会議に向けて準備され、現在はCBDのウェブサイト[http://www.biodiv.org/convention/sbstta.asp]からダウンロードできる。ファイルは、CBD/SBSTTA/8/INF/5(内陸水)、および CBD/SBSTTA/8/INF/13(沿岸海洋域)、並びに、沿岸海洋域に関する短い補足文書(CBD/SBSTTA/9/INF/25)である。
5.内陸水ガイドラインに関して、2004年CBDのCOP7(決定Ⅶ.4)では、当該ガイドラインを歓迎し、各種陸水生態系の基準もしくは比較対照データセットをつくり上げるために、また淡水系の種の分類学、分布および保全状況に関する知識の深刻な不足に対処するために本ガイドラインが役立つことを認識し、またCBD締約国その他の政府および関連機関に対して、特に小島嶼開発途上国および生態学的に災害を受けた内陸水生態系を持つ諸国領域内において、この手引きの適用を促進するよう奨励している。
6.2004年、ラムサール条約のSTRPは、目録、評価およびモニタリングに関するラムサール条約の手引きに、CBDの迅速評価ガイドラインの多様な要素をどう盛り込むのが最善かを検討した。STRPはラムサール条約における「湿地」の定義が内陸水と沿岸海洋域の両方を含むことを考慮し、このような手引きのラムサール条約締約国による適用として最も適切なのは、内陸水、沿岸、海洋という3つ全てのCBD関連文書を統合したひとつの手引きを作成し、利用に供することであるとした。したがって、本ガイドラインは、CBDのものをひとつに編纂したものであり、条約事務局およびSTRPが、CBD事務局と協力して作成したものである。ラムサール条約版の本ガイドラインでは、「内陸水」および「沿岸及び海洋生態系」というCBDの用語は、ラムサール条約における意味での「湿地」という語に適宜置き換えられている。
7.CBDによる迅速評価ガイドライン文書には、迅速評価についての一般的な手引きの実施の助けとなる、詳細な方法論の一覧そして事例もたくさん含まれている。本ガイドラインには、これらの詳細な一覧の全ては含まれてはいない。これらのCBD添付文書、一覧および事例一式は、さらにとりまとめを進めて、『ラムサール技術報告書』としてラムサール条約締約国およびその他の利用に供する計画である。
8.本ガイドラインは、種及び群集レベルでの生物多様性評価を主眼としている。とはいえ、湿地生態系の評価の助けとなるツールについても言及されている。加えて、自然災害発生後の沿岸生態系の変化を評価するための、迅速評価の方法論についての情報もガイドラインに盛り込まれている。これらの方法論は、2004年12月のインド洋津波による沿岸生態系への影響の評価の助けとなるよう開発された。
9.本ガイドラインは、湿地生態系の生物多様性が持つ社会経済的、文化的価値の全体を迅速に評価するための方法論的手引きを提供するものではない。CBDのCOP7(決定Ⅶ.4)はこの点を認識し、CBD、ラムサール条約および他の関連機関との間でさらに共同作業を進めて、内陸水生態系の機能と健全さ並びに内陸水生物多様性の社会経済的、文化的価値を評価するための補足ツール一式を開発するよう要請している。加えて、STRPは現在、『ラムサール技術報告書』として、湿地の経済評価に関する手引きを作成中であり、その手引きには「迅速」とみなしうる経済評価方法に関する情報が盛り込まれるので、この観点で貢献するものである。
10.現行の迅速評価のためのガイドラインは、ラムサール条約の「湿地目録の枠組み」(COP8決議Ⅷ.6)における、適切な湿地目録を選択する方法についてのガイドラインに強く依拠し、またそれとの整合が図られている。この中で述べられているように、迅速評価の方法は、様々な種類および目的の湿地目録および評価に適用することができる。したがって、この手引きは、ラムサール条約の「湿地目録、評価及びモニタリングのための統合的枠組み」(決議Ⅸ.1付属書E)の多くの面についての実施に活用できる。
11.本ガイドラインは、ラムサール条約締約国と生物多様性条約締約国の双方の必要性に応えるよう設計されている。迅速評価の方法は、より包括的な目録、評価、モニタリングのプログラムとのつながりで位置づけられており、迅速評価方法の設計および実施のための概念的枠組みが盛り込まれている。ガイドラインは、地理的な大きさ、湿地タイプ、制度面での能力など、状況の異なる広範囲の締約国にとって役立つ助言および技術的手引きを提供することを意図している。
12.本ガイドラインは、評価の設計と実施の基礎として、評価の目的をそれぞれの場合に応じてはっきりと確立することの重要性を強調している。ガイドラインはまた、迅速評価方法による現地調査が新たに必要かどうかを決める前に、まず、地域社会が保有する情報など既存の知見と情報について検討すべきことを強調している。
13.次に、評価の目的に合致する適切な方法がスムーズに選択できるよう、その後のステップが「決定樹」の形で示されている。また、それぞれの迅速評価方法を通じて入手できる情報の種類が示されている。さらに、迅速評価のそれぞれの目的にふさわしい、利用可能なもののうち適切な方法の概略、および各種データ分析ツールについての情報が盛り込まれている。
14.本手引きは、迅速評価を次のように定義する。すなわち、「定められた目的に向け、信頼のおける適用可能な結果を最短期間でもたらすために、しばしば緊急事項として行われる、概観的な評価」。
15.湿地を迅速に評価する方法が、一般的に、生態系に生じる季節性などの時期的な分散を考慮するようには設計されていないことを留意しておくことは重要であろう。しかし、迅速評価方法の中には、統合的モニタリングプログラムの一環として、反復調査の中でこのような時期的分散を検討するために使用できるものもある。
16.迅速評価のための技法は、種レベルの生物多様性に特に関連しており、現在の手引きはそのレベルでの評価を主眼とする。その他にも、リモートセンシング技法などの迅速評価の方法には、特に迅速に目録評価をする目的で生態系/湿地の生息地レベルで利用できるものがあるが、生態系レベルで迅速に評価するための方法に関しては手引きをさらに開発することが適切だろう。一方で、遺伝子レベルでの生物多様性評価は、一般に、「迅速な」アプローチに向いていない。
17.湿地生態系が持つ複雑な性質や変動性が意味しているのは、幅広い湿地タイプに対して、また様々な目的の全てに適用できる単一の迅速評価方法というものはないということである。さらに、個別の場合において何が可能となるかは、利用できる資源と能力によって異なる。
18.後述する詳細な手引きにおいては、迅速に評価を行う目的を、具体的な5つの目的に分類している。すなわち、「基準情報目録」(CBD版のガイドラインでは「目録評価」とされている)、「特定の種の評価」、「変化の評価」、「指標の評価」、および「経済資源の評価」である。
19.下記の9つの課題は、迅速評価を設計する場合には常に考慮すべきことである。
ラムサール条約COP8は決議Ⅷ.6において、以下の湿地目録、評価およびモニタリングの定義を採択している。
注:この定義の下で「目録」は、基準情報目録を含んでいるが、多くの場合、具体的な目的、優先順位およびニーズによっては、核となる生物物理学データのみならず「評価」に使える情報を与える管理特性データも含むことがある。ただし、そのためにはより広範なデータ収集および分析が必要となる場合もある。
20.迅速評価は、締約国が湿地を評価するために使うことができる一連のツールおよび対応方法のひとつである。完全な湿地目録および評価のために必要なデータや全ての種類の情報が、迅速評価の方法を通じて収集できるわけではない。しかしながら、通常、目録および評価で一般的に使用される主要データフィールド全部について、何らかの最初の情報を収集することは可能である。ただし、場合によっては、迅速評価によって信頼性の低い予備的な結果しか得られないこともある。しかしそのような種類のデータ及び情報も、詳しいフォローアップ評価が必要だと思われる部分を特定することに使用できる。
21.ラムサール条約決議Ⅷ.6ら導かれた、湿地の生物物理的特徴と管理特性の評価および目録のための主要データフィールドの概要、ならびに、迅速評価を通じて収集できる各データフィールド情報の一般的な質を表1に示す。
| 生物物理的特徴 | 「迅速評価」を通じて収集されるデータの質の十分さ |
|---|---|
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| (✔) |
| ✔ |
| (✔) |
| ✔ |
| ✔ |
| 管理特性 | |
| (✔) |
| (✔) |
| (✔) |
| (✔) |
| (✔) |
| (✔) |
22.生物多様性の社会経済的および文化的特徴を検討する。本手引きは、主に生物多様性の生物要素の評価を扱っている。通常、完全な経済評価は、迅速評価の範囲から大きく外れるものの、評価目的の多くにおいては、生物多様性の社会経済的および文化的特徴に関する情報の収集もまた重要である。ともあれ、迅速な目録評価またはリスク評価の一環として、どの社会経済的および文化的特徴が調査湿地に関連するのかの初期見通しをとりまとめることに役に立つであろう。これによって自然資源基盤の変化の兆候を見極めることができるし、また、どの特徴をより詳細なフォローアップ評価の対象にすべきかを示すものとしても役立つだろう。
23.生物多様性に由来する、内陸水の社会経済的恩恵/サービスに関する例については、UNEP/CBD/SBSTTA/8/8/Add. 3 の付属書Ⅱを参照、生態系の恩恵/サービスについての詳しい情報は、ミレニアム生態系評価の「生態系と人類の福利」(Island Press,2003年)も参照のこと。
24.内陸水の文化的機能及び価値(ラムサール条約COP8文書15「湿地の文化的側面」に基づく)で考慮すべきものは、下記の通りである。
a)古生物学的及び考古学的記録、
b)歴史的建造物及び人工遺物、
c)文化的景観、
d)伝統的な生産および農業生態系、例えば水田、塩田、河口の利用、
e)水・土地の集団管理手法、
f)慣習上の権利及び所有形態を含む、自主的管理手法、
g)湿地資源を利用する伝統技法、
h)口頭伝承、
i)伝統的な知識、
j)宗教的側面や信条及び神話、
k)「芸術」−音楽、歌、踊り、絵画、文学および映画。
25.湿地の生物多様性に対する脅威の評価 多くの迅速評価においては、生物多様性に対する脅威もしくは圧力を完全に評価することはできない。しかしながら、社会経済的、文化的特徴に関しては、脅威類型についての暫定評価を行うことで、その後のさらなる評価の主眼をどこにおく必要があるのかを特定するのに役立つであろう。この目的のためには、国際自然保護連合(IUCN)の種の保存委員会(SSC)が生物種情報サービス(SIS)の一部として開発中のもの等の、脅威類型チェックリストが役立つだろう(http://www.iucn.org/themes/ssc/sis/authority.htm 参照)。
26.システム管理のためのモニタリングを目的とした仮説に基づく研究には、迅速評価よりもさらに総合的なツール及び方法論が必要になる場合がある。しかしながら、迅速な方法の中には、もともとはモニタリングのために開発されたが、迅速評価目的のために同じように適用できるものもある。同様に、迅速評価のツール・方法論の中にも反復調査によって、仮説に基づき行うより長期のモニタリングに適用できるものもある。これは、季節性の問題に取組む際には特に有用な技法ともなる。
27.迅速評価および生物多様性の傾向 生物多様性の傾向を評価するように設計された迅速評価では、2回以上の反復調査が必要である。このような情報を集めるために、定期的な時系列データが必要になる場合があり、そのような状況では、調査の結果全体的な評価が明確になるまでに通例より長い期間がかかるが、各調査を迅速に評価するための方法を用いて行う場合、これを迅速評価とみなすことができる。
28.季節性 ほとんどの迅速評価で、調査地点の「スナップショット」調査を一度だけ行う。しかしながら、多くの湿地および湿地に依存する生物相(例えば渡り性の種)には季節性があることから、異なる分類群の調査は、一年のうちの異なる時に行うことも必要であろう。季節性に関係する迅速評価のタイミングは、評価によって信頼しうる結果を生もうとするならば、きわめて重要で考慮すべき問題である。
29.内陸湿地における他のタイプの時間的な変化、特に異なるタイプの内陸水生態系における水の流れの変化についてもまた、考慮する必要があろう。これには下記が含まれると考えられる。
a)一年中地表流となっていて干ばつの間も流れが絶えない、枯れることのない水系;
b)例年の雨期の間は予想通り水流があるが、1年に数ヶ月間枯れている場合のある、季節性の水系;
c)長期間水流があるが予想がつかず季節的でもない、不規則な(周期的または断続的な)水系。これらの水系は一般に、降雨のほかに地下水も加わって水流を形成する。時に、ある部分だけに地表流が生じ、他の部分では地表下の流れになっている場合がある。流れる期間、様々な種の定着遷移、他の水源への近さ、および前回流れが生じていた期間により、動物相が著しく異なることがある;
d)稀につかの間水流があり水流がなくなると乾燥状態に戻るような、一時的にしか水流のない(短命の)水系。水源は通常、降雨のみ。大変素早く(2、3のうちに)生活環を終えることができる水生生物のみが、このような流れの条件を利用できる。
30.小島嶼国において優先される迅速評価の種類 小島嶼国における限られた内陸湿地の重要性、沿岸海洋域の重要性、生物多様性に関する情報の全般的な不足、および組織的対応力の限定性に鑑みれば、迅速評価の方法は小島嶼国において特に役立つものとなる。優先順位の高い評価目的は、下記の通り。
a)水質および水量といった定性的及び定量的側面、
b)生物多様性喪失および水質汚染の原因、例えば、森林伐採、殺虫剤の流出およびそ他の持続可能ではない利用等、
c)持続可能ではない土地利用の圧力(例:観光、農業、漁業、産業)。
31.国連食糧農業機関(FAO)は、小島嶼開発途上国の漁業および養殖の重要性の高い問題について詳細な情報(http://www.fao.org/figis/servlet/static?dom=root&xml=index.xml 参照)を提供するとともに、「世界漁業情報システム Fisheries Global Information System」(http://www.fao.org/fi/default.asp)を運営している。「小島嶼開発途上国農業行動計画 Plan of Action on Agriculture in Small Island Developing States」もまた、小島嶼開発途上国特有の漁業の必要性を認識し、内陸水およびその他の自然資源の持続的管理に関する手引きを提供している。
32.この概念的枠組みは、ラムサール条約湿地目録の枠組み(決議Ⅷ.6)を基にしており、また相互に整合の図られたものとなっている。時間尺度の最短化という迅速評価に固有の要素を考慮して、ステップの順番とタイトルに若干の修正を加えてある。
33.概念的枠組みの適用プロセスを図1にまとめた。概念的枠組みのステップ、および各ステップ適用の手引きは、表2に記載した。
34.この枠組みは、初めて湿地の迅速評価を行う際の計画策定及び実施の手引きとして設計されている。フォローアップ評価、ならびに実用性の証明された手順及び方法を使って新たな区域について行う評価については、全部のプロセスを経る必要はない。ただし、湿地生態系の種類の違いなど、地域的な条件の違いに関係した方法論の見直しは行われるべきである。
35.例えば自然災害または人為的災害などの緊急事態に対処するために評価を行う場合、できる限り概念的枠組みのステップに従うべきある。しかしながら、このような状況の下で、非常に素早い対処が必要であるとき、枠組み適用の簡略化が不可欠な場合がありうるだろう(本手引き第53節も参照)。
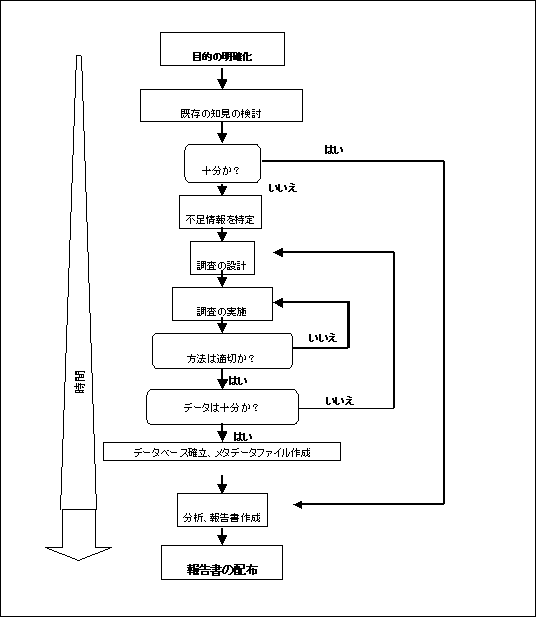
図1.迅速評価の概念的枠組み適用における重要ステップの概要
(詳細については表2を参照のこと)
| ステップ | 手引き |
|---|---|
|
迅速評価を実施する理由を明言する。なぜ情報が必要なのか、誰が情報を必要としているのか。 |
|
目的と目標を達成するのに必要な、地理的規模とデータ精度を決定する。 |
|
陸水の位置、大きさ、及び特徴を示すのに十分な、核となる、あるいは最小限のデータセットを特定する。必要な場合にはこのデータに、湿地の生態学的特徴に影響する要因に関する追加情報、及びその他の管理問題に関する追加情報を補うこともできる。 |
|
利用可能な情報源および人々(科学者、利害関係者、地域住民及び先住民を含む)の知見を、机上研究、ワークショップなどにより検討し、評価の対象となる地域の内陸水生物多様性について、どの程度既存の知見と情報が利用できるかを決定する。利用可能な全てのデータ源を含めること[表下注]1、および、調査場所に優先順位をつけること[表下注]2。 |
|
|
|
必要な情報を得る方法を選択するために、利用可能な方法を検討し、必要に応じて専門家に技術的助言を求める。表3(目的の違いに応じた迅速評価の種類)を適用したうえで、適切な現地調査方法を選択する。 |
|
地球規模で承認されている分類はないので、評価の目的に合った生息地分類を選択する。 |
|
次の事項に関する時間的スケジュールを確定する、a)評価の計画策定、b)データの収集、収集したデータの処理と分析、c)結果の報告 |
|
評価に使える資源の範囲と信頼度を確定する。必要ならば、資源不足が原因でデータが失われることのないように、緊急時対応計画も策定する。 制度、財政、職員面での現行条件のなかで、結果の報告も含め、計画を実施できるかどうかを評価する。 データ取得と分析の費用が予算内かどうか、計画を完遂するための予算が得られるかどうかを判断する。[適宜、計画の定期的見直しの計画を策定。] |
|
電子形式または印刷形式で保管することを含め、データの収集、記録、収納についての明確な実施要綱を定める。 標本の保管検索(キュレーティング)が適切に行われるようにする。これにより、後のユーザーがデータ源、その精度、信頼性を判断し、参照収集物にアクセスできるようになる。 この段階で、適切なデータ分析方法を特定することも必要である。すべてのデータ分析は試験済みの厳格な手法によって行い、情報はすべて文書化する。データ管理システムはデータ分析を制約するのではなく、その助けとなるものでなければならない。 メタデータベースは、a)目録のデータセットに関する情報を記録するため、b)データの保管責務及び他のユーザーの利用権の詳細をまとめるために使用する。既存の国際標準を使用すること(ラムサール条約湿地目録の枠組み:決議Ⅷ.6参照)。 |
|
時宜にかない、かつ高い費用効果が得られるように、すべての結果を解釈し報告する手順を確立する。 この報告は、目標が達せられたかどうかを記載し、さらなるデータや情報が必要かどうかを含めて、管理行動に関する勧告を盛り込んだ簡潔なものとする。 |
|
公的な開かれた検討プロセスを確立する。これは報告を含めたすべての手順の有効性を確保するため、また必要ならば、評価プロセスを調整するための情報を提供するためである。 |
|
調査を開始する。使用する手法と専門機器を試験・調整し、作業に携わる職員に研修が必要かどうかを評価し、データの照合、収集、入力、分析、解釈の手段を確認する。特に、適切な「現場確認(グランド・トルース)」作業によってリモートセンシングを確実にバックアップできるようにする。 |
|
公的な開かれた検討プロセスを実施する。これは報告を含めたすべての手順の有効性を確保するため、また必要ならば、計画を調整したり終了するための情報を提供するためである。 結果は、適切な様式および詳細さで提供されなければならない。特に提供の対象となるのは、地方自治体、地域社会、その他の利害関係者、地方および国の意志決定者、援助機関そして科学者達である。 |
36.本手引きの主な目的は、湿地生態系を迅速に評価する適切な方法を決定する際の実践的な参考とすることである。表3に、湿地生態系の迅速評価に利用できる多くの方法を図式で示す。これにより、選定基準の体系的枠組みに基づいて適切な評価方法を選択することができる。最も重要な湿地評価要素が順にまとめられている。迅速評価のためのデータ収集および分析方法についてのさらなる情報を、添付文書1および2に示す。また、迅速評価方法の選択に関する、様々な資源的制約(特に時間的、資金的、専門知識的制約)及び評価の範囲に関係したさらなる統合的湿地情報が、これから出版される「ラムサール技術報告書」として提供される予定である(CBD資料には陸水の手引きと沿岸海洋系の手引きに分かれた詳細な手引きもある。(それぞれ、CBD/SBSTTA/8/INF/5 及び CBD/SBSTTA/8/INF/13))。
37.迅速評価の目的にかなう適切な方法を選ぶ作業は、まず最も基本的で大まかな評価要素から始めて、次第により選択性の高い基準に進むべきである。必要な評価の全体的枠組みが、目的、必要とされる情報、利用できる資源、および範囲によって決まる融合形態として最終的に浮き上がってくる。考え方としては、実際的な評価モデルを提示し、その実施のために利用できる方法を決定するために、アウトプットや目的といった情報を限定する要素を、時間枠、利用できる資金、および地理的範囲などの運営体制を限定する要素と結びつけることである。
38.目的を明確化することが、評価の第一ステップである。表3は、評価の種類を決める5つの具体的目的に対応する3つの一般的目的を示す。決定樹に使用されている5つの具体的な評価の種類は下記の通り。すなわち、「基準情報目録」、「特定の種の評価」、「変化の評価」、「指標の評価」、「資源の評価」。評価の種類を、以下に詳しく説明する。
39.目的および評価の種類が一旦決まれば、より具体的な評価の構成要素を通じて段階的アプローチをとるべきである。より具体的な評価の構成要素とは、資源的制約および評価の各種要素の範囲である。本項ではまず始めに、評価のために利用できる資源の査定を扱う。時間、資金および専門知識が決定樹において考慮される重要な資源的構成要素である。つまり、これら資源が得られるのか制約されるのかによって、すべての迅速評価の範囲と能力が決まる。次に、さらに具体的な6つの限定要素(分類群、地理、対象湿地の選定、方法、データ収集、分析)を考慮し、評価の資源的制約に関係するそれぞれの範囲を決める。資源的制約および範囲基準の様々な組み合わせにより、評価プロジェクトが具体化する。
40.アプローチはまず、いかなる迅速湿地評価も保全および賢明な利用という全てに優先する目標に留意して実施すべきという想定から始める。そして、湿地の生物多様性に関する基準を確立して、湿地生態系の変化や健全さを評価し、湿地資源の持続的利用を支えるための知識や理解を増大させる方法を用いる。この考え方に基づいて、湿地を迅速に評価する5つの具体的理由がある。これらの中には迅速な評価をする理由となる幅広い事柄が含まれている。
a)目録作成のために全般的な生物多様性データを収集し、湿地に生息する生物種、群集および生態系について優先順位をつける。対象地について基準となる生物多様性情報を入手する。
b)焦点となる種または標的種(絶滅危惧種等)の状況について情報を集める。特定の種の保全に関係するデータを収集する。
c)特定の対象地または対象種に対して、人為的または自然の攪乱(変化)が及ぼす影響に関する情報を入手する。
d)特定の湿地生態系の全般的な健全さまたは状態を示す情報を集める。
e)特定の湿地生態系における生物資源の持続的利用の可能性を明らかにする。
41.5つの目的は、対応する評価の種類の順に従う。表3の列は、生物多様性条約の3つの目標に関連する。第1列および第2列(目録の評価及び種の評価)は、生物多様性の保全に関係する。第3列から第5列(変化、指標及び資源の評価)は持続的利用に関わり、第5列(資源の評価)はまた、遺伝資源の利用から生じる恩恵の公平な配分に関連する。
| 一般的目的 | 生物多様性に関する基準 | 攪乱及び生態系の健全さ | 資源の持続可能性と経済学 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 具体的目的 | 基準情報目録、優先順位設定、保全、同定 | 特定の種の保全、外来種の状況 | 変化の探知 | 生態系全体の健全さまたは状態 | 生物資源の持続的利用 |
| 評価の種類 | 基準情報目録 | 特定種の評価 | 変化の評価 | 指標評価 | 資源評価 |
| データの種類と可能な分析 |
|
|
|
|
|
| 他に依拠しうるもの | 目録評価 | 目録評価(望ましい) | 特定種の評価 | ||
42.湿地の生物多様性を評価する適切な方法を選ぶにあたり、湿地に用いる迅速評価は5種類あると認識されている。これら評価の種類は、特定の評価プロジェクトの目的および要求されるアウトプットにより異なる。評価の種類にはそれぞれに固有のアウトプットがあり、それぞれ固有の目的に適合する。したがって、多様性、保全及び管理に関係するあらゆる評価について、その目標及び全体の目的を決めることが重要である。評価プロジェクトは、その目的とアウトプットの目標が確定すれば、どれもこれら5つの評価の種類の一つ以上にあてはまるはずである。評価の種類を以下に簡潔に述べる。
43.基準情報目録は、具体的な分類群や生息地についての広範なまたは詳細な情報ではなく、むしろ全体的な生物多様性に焦点をおく。目標は、生物学的構成要素及び関連する特徴についての、広範かつできるかぎり包括的なサンプリングを通じて、湿地生態系についてできるだけたくさんの情報を集めることである(ラムサール賢明な利用ハンドブック第10巻「湿地目録」も参照)。最も重要なデータ形式は、種および生息環境タイプのリストであることが多いが、関連する他の基準データとして、下記のものが含まれうる。すなわち、生息種数、豊富さ、相対的な個体群の大きさ、分布および範囲、生物多様性の重要性に加えて文化的重要性、およびその他の生物学的関連情報で水質(例えば、DePauw & Vanhooren 1983 および米国地質調査局(USGS)の全国水質評価事業 http://water.usgs.gov を参照)、水文学及び生態系の健全さに関係するもの。地理、地質、気候、生息地に関するデータもまた重要である。地域社会は、生息地の種数についての貴重な情報源となりうる。例えば、地域社会および消費の調査を通じて、短期間で情報を集めうる。
44.完全な種の基準情報目録を作成するには、区域内に存在する種の一覧を造るというたいへんなサンプリング努力を要する。そうして作成された目録は、区域の保全価値を生物多様性の面から明らかにするのに利用できる。目標は、できるだけ多くの場所でサンプリングを行い、かつ評価のために与えられた短い時間の中でできる限り多くの種をリストアップすることである。種のリストは、調査区域内の特定のサンプリングの場所に対応するように作成するのが理想である。各サンプリング場所で観察または収集した生物分類群ごとに分けて種のリストを作成すれば、調査区域内の異なる生息地および調査地点の識別に役立つ。分類データは、魚類、プランクトン、着生および底生無脊椎動物、水生および陸生植物、ならびに藻類のサンプルを含むことが多い。
45.湿地生息環境タイプの目録作成は、現地調査または地理情報システム(GIS)およびリモートセンシングデータの分析を通じて行うことができる(ラムサール条約「湿地目録の枠組み」(決議Ⅷ.6)の添付文書ⅡおよびⅢ、ならびに発行予定の「ラムサール技術報告書:湿地目録、評価およびモニタリングへのGIS適用の手引き」も参照のこと)。現地にある生息環境タイプの目録を作成するにあたり、区域内のさまざまな生息環境タイプおよびその内部での生態的漸次変化を理解するために、何カ所かでサンプリングを行う必要がある。GISが利用できる場合、湿地生息環境タイプの分類に、標高、自然地理学、および植被率などの空間データを使用することができる。評価の際に集める、湿地に生息する生物種および生態系についての情報には地理情報を付加しておくことが望ましい。
46.基準情報目録は、明確にされた対象についての最初の情報を提供するものである。それから提供される情報は、特に保全上懸念が生じている種または区域の優先順位設定を行う際、新しい種を同定する際、および区域の生物多様性全体についての広い見方を確立する際に役立ちうる。保全と管理において、この情報は特に種及び区域の優先順位設定と関係する。この後、優先順位の高い種について、特定の種を評価するための方法で評価を行う。調査地点または生息地に特定の人的負荷がかかっておりそのために優先順位が高い場合は、変化の評価法による評価の対象とすることを検討する。
47.目録評価からのアウトプットとして可能なものは下記を含む。
データ:
適用:
48.特定種の評価は、湿地に生息する特定の生物種または分類群について、対象地における状況を迅速に査定するものである。評価によって、保護、利用または根絶(例:侵入種の場合)という文脈の中で、焦点生物種についてのより詳細な生物学的情報が示される。ゆえに、この評価の種類は一般的に、生態学的にまたは経済的に重要な種に関係するものであり、かつ、その状況が不明であるか特に重大な区域内の重要な種について素早く情報を提供できるものである。同様にこの評価は、(評価が2回以上繰り返される場合)特定の区域における種の状況、絶滅のおそれがある、絶滅が危惧される、または安定している、といった事項を確認するために利用することができる。
49.特定種の評価からのアウトプットとして考えられるものは下記のとおり。すなわち、
データ:
適用:
50.人為的活動(環境汚染、物理的改変など)または自然の攪乱(嵐、異常な干ばつなど)が湿地域の生態学的健全性にもたらす影響を特定するために、しばしば評価が必要となる。この種類の評価で収集した情報は、事実上過去を振り返るかまたは予測的なもののどちらかである。かかる予測的評価は、プロジェクトの環境影響評価において着手されることが多い(ラムサール賢明な利用ハンドブック第11巻「影響評価」も参照)。
51.過去の状況を推定するアプローチは、各種プロジェクトや管理法による攪乱や改変がどの程度実際に生物多様性や生物学的健全性に影響を及ぼしているかを評価しようとするものである。生物多様性の見地からすれば、この取組は比較するために攪乱を受ける前の(基準となる)データがなければ困難なはずで、そのような場合は傾向を分析したり、対照調査地または環境基準(EQS)を使用したりすることが必要となる。対照にできる湿地は、同じ地域にあり、影響を受けた場所の攪乱以前の状態に等しくて、比較分析のためのデータを提供できるところである。
52.変化を迅速に評価するための4つのアプローチは、下記の通りに区別できる。
a)2カ所以上の異なる湿地を同時に比較する。
b)同じ湿地をさまざまな時期に比較する(傾向)。
c)影響を受けた湿地を対照調査地と比較する。
d)観察した状況を環境基準と比較する。既存の迅速評価方法は、ほとんどがこの目的のために設計されている。そのいくつかは(生物学的、物理化学的あるいは生態毒性学的であれ)「早期警戒指標」としても利用することができる(ラムサール条約のリスク評価の手引き:決議Ⅶ.10付属書およびラムサール賢明な利用ハンドブック第8巻E節、ならびに脆弱性評価の手引き[ラムサール技術報告書]も参照)。
53.変化を迅速に評価するための方法は、洪水、高潮、および津波などの自然(およびその他の)災害の影響を評価する際に特に役立つ。災害後に沿岸域湿地系を迅速に評価するための方法が、特に2004年12月のインド洋津波に対応するツールとして開発された。これらには下記のものが含まれている。
ⅰ)「自然災害後に沿岸生態系を迅速に評価するための現地実施要綱」(データ入手先:国際湿地保全連合 http://www.wetland.org/Tsunami/data/Assessment%20v3.doc)。これは沿岸横断調査区(トランセクト)アプローチを使用し、特定の種類の湿地(マングローブ、サンゴ礁、干潟、塩生湿地を含む)が、人々や社会基盤に損害を与えるような津波の影響をある程度弱めたかどうかを評価し、湿地の恩恵/サービスおよび生態学的再生が、失われた生計手段の回復をいかに助けられるかを明らかにするためのものである。
ⅱ)「サンゴ礁の津波被害に関する迅速評価及びモニタリングのガイドライン」(データ入手先:http://www.unep-wcmc.org/latenews/emergency/tsunami_2004/coral_ass.htm;http://www.icriforum.org/ および、http://www.ReefBase.org/)。国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)および国際サンゴ礁学会(ISRS)作成。
54.予測的アプローチは、ダムや開発など特定のプロジェクトの影響見込みを評価し、また、生物多様性の変化を長期的にモニタリングするにあたってその基準となるデータを確立する。このアプローチによって、「前後の」評価データや、差し迫る変化の影響を受けそうな種や生息地域の特定が可能になる。影響の見込みの予測には、既に変化が起きている区域の比較分析を用いることができる。このアプローチを使う分野は、環境影響評価(EIA)(ラムサール条約決議Ⅷ.9及びラムサール賢明な利用ハンドブック第11巻も参照のこと)、傾向分析およびシナリオ分析、ならびに(予測という意味での)モデリングである。この予測的アプローチは、過去の状況を推定するアプローチ、特に早期警戒指標、の結果に大きく依存する。予測的アプローチと政策反応の間には直接的なつながりがある。しかし、これらの方法の多くは、一般的にあまり「迅速」なものとはなっていない。
55.生態学的群集レベルでの変化は、生息地の条件が変わらなくても起きる場合があり、特別な注意を払わなければならない。生態学的群集レベルの変化が起きるケースとしては、攪乱を受けた後の生態学的条件に適応して、先駆種(パイオニア種)が急速に広まるという場合があり、こうした先駆種は、自然に存在する種にとってかわる。これによって生態系の状態に関する難しい問題が生じる、つまり、生態学的には過去よりも種が豊富になる場合があるのだ。状況が特に複雑なのは、新たな種がもとの生態系を形成する種よりも望ましいと考えられる場合である。変化の評価からのアウトプットは、関係する変化が既存のものなのかあるいは潜在的なものなのかにより、次のように分類される。
56.変化の評価からのアウトプットとして考えられるものは、下記の通り。すなわち、
データ:
適用:
57.指標評価が想定するのは、生物多様性は、種および群集の多様性という面からみた場合、特定の生態系の水質、水文学および総合的な健全さについて多くを語るはずだということである。バイオモニタリングが、しばしばこの種類の評価と結びついている−これは、伝統的には、毒性レベルおよび含有化学物質のモニタリングに生物指標を用いることを指すが、最近ではこの種の取組は、物理的および化学的パラメータだけのモニタリングよりもむしろ、生態系の総合的健全さをモニタリングするためにより広く適用されている(Nixon et al. 1996 参照)。特定の化学的または生物指標の存在の有無は、環境的な条件の反映でありうる。生物分類群、個々の種、種グループあるいは群集全体を指標として利用することができる。一般的には、底生大型無脊椎動物、魚類及び藻類を、生物指標として使用することができる(Rosenberg & Resh 1993;Troychak 1997 参照)。したがって、湿地生態系の状態を評価するにあたり、種の存在の有無、ならびに場合によっては豊富さや生息環境特性を使うことが可能である。
58.指標評価からのアウトプットとして考えられるものは下記を含む。
データ:
適用:
59.資源評価は、対象とする区域または水系における生物資源の持続的な利用の見込みを明らかにすることを目的とする。データは、経済的に重要な種、人々の生計を支える種、あるいは市場価値の見込みがある種についての、存在、状況及び状態に関係する。資源評価が、破壊的もしくは持続不可能な活動に代わる、生態学的に持続可能な開発の進展を促進することが望ましい。
60.したがって、資源評価の主たる目標は、豊かな生物資源をもつ区域での実行可能な経済の選択肢としての持続的利用方法を、開発しまたは特定することにある。このため、資源評価の重要要素は、ニューサウスウエールズ州の地域社会による生物多様性調査の例のように、地域社会および政府が全面的に参加することである(NSW National Parks and Wildlife Service 2002 参照)。このことは、すべての参加者のニーズ、能力および期待との関連で特に重要である。この統合的アプローチは、あらゆる持続的な資源収穫システムの実施を成功させるために重要である。資源評価の範囲としてはこの他に、使用した基準情報を、漁業およびその他の資源の健全性のモニタリングに提供することが考えられる。
61.湿地を経済的に評価するための方法の使用は、資源評価との関連性が高く、また、このような方法のうち多くが「迅速」だとみなすことができる(利用可能な湿地の経済評価方法についてのさらなる情報は、近刊の「ラムサール技術報告書」、およびラムサール条約出版物である『湿地の経済評価:湿地にはどのような価値があるのか』(1997)にて入手可能)。
62.資源評価からのアウトプットとして考えられるものは下記の通り。
データ:
適用:
63.湿地の生物多様性を迅速に評価するために利用可能な方法は、具体的なプロジェクトの目的およびアウトプット次第で決まる。これと同じく重要なのは、利用できる資源および制約の考慮であり、これは特に評価の範囲についてあてはまる。「時間」、「資金」および「専門知識」は資源的制約であり、これによって特定の評価プロジェクトに利用できる方法論が決まる。さらにそれらによって、以下の分野でのプロジェクトの範囲が決まる。すなわち、「分類群」、「地理」、「対象湿地の選定」、「分析」、「データ」、および「サンプリング方法」。これらは湿地生物多様性評価の重要な構成要素であり、それぞれの範囲または能力は、プロジェクトのニーズおよび資源的制約により異なる。
64.時間、資金および専門知識は、湿地の生物多様性を迅速に評価する際に考慮すべき主たる要素である。これらの資源が豊富ならばかなり柔軟な対応ができる一方、不足する場合は、ほぼ全ての面で評価プロジェクトの潜在力が制約される。しかしながら、場合によってはある領域での豊富さが他の領域での制約を埋め合わせできることもある。これら資源の利用可能性によって、かなりの程度、評価の範囲と能力が決定される。
65.時間は、あらゆる迅速な評価の根本に関わる考慮すべき事柄である。
66.科学的には、長期のモニタリングおよび研究は、迅速評価よりも統計上の優位性が高い。長期のモニタリング及び研究を行えば、より詳細でかつ完全なサンプリングが可能であり、それによって経時的変化を測定できるし、統計手法により厳密な結果を生むことができる。一方、迅速評価に内在する期間の短さが、この種類の調査の魅力である。つまり、迅速評価は、区域の状態についてすばやい判断を可能にするスナップショットあるいは概要把握を可能にする。従って、迅速評価は、緊急に決定を下さなければならない際に情報を提供できる。迅速評価はまた、さらなる研究が認められた場合にその基準として用いるデータを確保する良い方法となる。評価に使える時間の長さは重要な資源であり、だからこそ十分に計画策定を行って時間をどのように使うか決めるべきである。迅速評価は、長期のモニタリング及び研究の代わりには絶対になりえない。
67.「迅速な」の定義には幅があるが、この言葉は時間こそが本質であることを含んでいる。迅速に評価するための時間は、概して迅速評価の典型的な長さが基準となり、それは次のように、「短」(1−7日)、「中」(8−30日)、および「長」(31日以上)に分けられる。これは、移動、データ収集、および予備分析を含み、プロジェクト全体を最初から最後まで終えるための時間を指す。最終分析及び結果にはもっと時間がかかる場合があるが、予備的結論が重要であり、かつ早く入手する必要がある。そうでなければ、迅速評価の目的が失われる。
68.評価のために利用できる資金額は、時間とならび、湿地を迅速に評価するための能力および範囲を決める。金額は相対的なものであって、広義の類型では通貨価値の流動性を十分に反映できないため、単純な類型化を用いる。これは、実際の金銭価値を基準とするものではなく、むしろ、評価を実施するために利用できる資金の相対額を基準とする。したがって、ある評価のために使える資金は、不足、つまり制限的又はプロジェクトの目標を実行するために望まれる金額よりも少ないと考えられるか、あるいは豊富、つまり評価の全要素を科学的に正しくかつ適切な方法で実行するに十分な資金があるかのどちらかとなる。
69.専門家は、例えば生物分類群の標本を種のレベルまで同定できる、現在のサンプリングおよび収集方法に通じている、データの分析ができる、そして、より広い生物学的生態学的視点において生物分類群に通じている人を指す。この言葉は、その分野における一般的理解又は基礎的知識を持つ人を指すのではない。地域レベル及び国際レベルで専門家の利用ができるかどうかを明らかにすることは重要である。地域における専門知識は、利用できる場合には優れた資源である。地域の専門家はしばしば、地域の地理、生態学、地域社会の問題について優れた理解をもっている。しかしながら、地域に専門家がいない場合、地域以外の専門家に参加してもらう必要があるだろう。極めて専門性の高いケースでは、その調査分野で専門家とみなされる人の数がごく少数、またはたった1人という場合もありうる。
70.施設支援とは、分析、データ保管、およびその他の形の支援のために技術センターを利用することを指す。専門知識が利用可能かどうかを判断する際には、施設支援が利用可能かどうかについても考慮すべきである。というのも、これがあらゆるプロジェクトの能力と範囲の制約となる場合があるからである。どの形の迅速評価が実現可能かを判断する際に、その調査分野の専門家である個人(地域の専門家も含む)を評価プロジェクトが利用可能かどうかを明らかにすることは重要である。
71.範囲を知るためには、評価の多様な要素の規模について考慮する必要がある。評価がどれほどの区域を対象とするのか? いくつの種をサンプリングするのか? どれほどの量のデータを収集するのか? いくつの場所でサンプリングをするのか?
72.一般的に、迅速評価の範囲は、評価の目的と資源次第で決まる。豊富な資源があれば、評価の様々な部分の範囲をそれに合わせて増やすことが可能になる。予算が厳しければ2日間の評価で広い地理的範囲を対象にすることは難しい。この点において、範囲のある面は範囲の別の面と互いに関連しあってもいる。たとえば、もし対象湿地の選定およびデータ収集の範囲を非常に小さくするならば、2日間で広い地理的範囲を調査することが可能なこともありうる。一般に、評価の資源が豊かならば、範囲の決定は、プロジェクトの目的と目標のみによって決まる。
73.評価の範囲は、以下の領域、すなわち、「分類群」、「地理」、「対象湿地の選定」、「サンプリング」、及び「データ分析」ごとに異なる場合がある。これらのひとつひとつは分けて考慮すべきである。たとえば、対象とする地理的範囲が広く、広大な面積をカバーしなければならない一方、対象とする分類群の範囲は絞込んで限られた数の分類グループに集中するといった評価プロジェクトの場合もある。
74.分類学的範囲は、どれだけ多くの、またどの生物分類群が調査に組み込まれているかで決まる。調査によって、水生無脊椎動物だけに焦点をあてる場合もあれば、いくつかの生物分類群を含む場合もある。概して、調査に適合するのはどの分類群なのかは評価の目的によって決まる。なぜなら、ひとつの評価の種類に対する有用性は個々の生物分類群によって高かったり低かったりするからである。例えば、水条件に敏感でかつ比較的サンプル調査しやすいという理由で、河川および渓流の影響評価には、しばしば底生大型無脊椎動物が用いられる。水生哺乳類または鳥種の中にも水条件の変化によって影響をうけるものもあるが、サンプル調査が比較的難しいうえ、反応がよりとらえにくくより長く時間がかかることから、これらの変化の優れた指標ではない。
75.いかなる評価の場合も、他と比べてサンプル調査しやすい種または生物分類群があるということを考慮することが重要である。調査が特に難しい生物分類群を含めるコスト(時間と資金という意味での)と、それを含めた場合に得られる利益とをはかりにかけなければならない。時間と資金の有効利用の観点から、ある分類群はあきらめて別の分類群をとった方が良い場合もあろう。これに関係するのが、必要になる生物分類群の相対的な大きさである。対象地によって、たとえば、トビケラ(毛翅目)調査の分類学的範囲は、水生の哺乳類、鳥類及び魚類の種に特化した調査よりも大きい場合がある。
76.評価の地理的範囲は、関係する生物分類群やプロジェクトに関係する区域の大きさによって決まる。地理的範囲は、特定の種の分布域、特定の生態系または生息地の面積、あるいは影響を受けている区域によって異なることがある。すなわち、特定の種類の堆積物等の生息地の一部分となる場合もあれば、集水域全体、湖沼系、流域または沿岸域など比較的大きな地理的区域におよぶ場合もある。
77.地理的範囲はまた、統計的に正しいデータを得るために調査しなければならない区域の大きさによっても異なる。したがって、調査区域の範囲や面積、また調査すべき生息地の数の見地から地理的範囲を決めることが重要である。どれほどの地理的範囲を評価する能力があるかは、プロジェクトに利用できる資源により決まる。
78.対象湿地の選定とは、評価のために必要となる湿地の数および種類を指す。地理的範囲同様に、対象湿地の選定は評価の他の面に大きく依存する。基準情報目録の場合は、さまざまな生息地をもつ湿地のいくつかにおいて比較的幅広く生物多様性を評価することが必要である。特定の種の評価の場合、標的種が利用する生息地に特化し、サンプリングの場所のいくつかはあきらめて、湿地の数を絞ってさらに掘り下げた調査を行う場合がある。影響評価のための対象湿地の選定の場合、問題になっている影響と関係のある湿地に特化する。資源の評価を行う湿地については、利用の対象となりうる区域に焦点をあてる。指標評価の場合、なくてはならないデータを作成するために、必要なだけ多くの数の湿地を含める。
79.選択する湿地の種類を考慮する際に有り得る1つの質問は、それが特徴的であるという理由で湿地を選ぶべきか、または他とは異なるという理由で選ぶべきかということである。特徴的な湿地とは、対象区域に典型的な生息地を代表するものである。しかし、ほとんどの区域では、生息地は連続的でないうえ、生息地の場所場所で少しずつの変化があるため、関連しているが他とは異なる群集が徐々に移り変わりモザイクを形成する。他とは異なる湿地を選ぶことで、これらの特有なおよび特殊化した生息地を調査することができる。
80.他とは異なる生息地を選ぶか典型的な生息地を選ぶかは、しばしば、評価の資源及び目的によって決まる。時間が短ければ、より独特な湿地を評価しようとする前に状況の全体像を正しく捉えるために典型的な区域を手早く調査するのが最善だろう。もう少し時間があり、かつ、できるだけ多くの種を調査する、または生息環境タイプを説明することが目的ならば、他とは異なる生息地がより注目をうけるべきだろう。
81.さらに検討すべきなのは、遠さ、土地利用による制限(例、武装地帯)、土地所有形態、洪水・火事の起こりやすさ、および季節・気象条件などを考慮した現場へのアクセスである。
82.使用するサンプリング方法の種類は、評価の目標に応じて決まり、小島嶼国を含む全ての国についてほぼ同じでなければならない。使用するサンプリング方法は、標準化の必要性、専門的なものになりうるかどうか、時間的制約および利用できる機器の種類により異なる。最も重要なのは、そのサンプリング方法が、洞察にあふれ統計学上正しく、評価の目的に適用できるデータを提供しようとするものであることである。
83.ほとんどの調査において、さまざまな水質変数が計測される。水質変数に含まれうるものとしては、温度、電気伝導度(EC、完全に溶けた塩の測定)、㏗(水の酸度またはアルカリ度の測定)、クロロフィルa、全リン、全窒素、溶存酸素、および水透明度(セッキー板深度)。これらの変数は個別の機器かまたは何種類かの測定部位がついた一台の複合機器で計測できる。
84.大型植物の場合、水面の上からまたは下から(スキューバ)目視で或いは特殊なサンプラーを用いて探索できる。魚類は、適用される法律に留意しつつさまざまな方法でサンプリングできる(添付文書2参照)。地域の漁師に質問することやその漁獲物を調べることも有用な方法となることがある。水生無脊椎動物は、水中から(プランクトンが)、抽水・浮葉・沈水植物から(着生動物相が)、および、底質から(底生無脊椎動物が)、適切なサンプリング技法によってサンプリングできる。爬虫類および両生類は一般的に、網、トラップを用いてか、あるいは日中および夜間の目視探索によりサンプリングする。
85.添付文書2に、迅速評価で利用しうる、湿地の特徴および分類群の違いに対応した幅広い様々なサンプリング方法を記載した。サンプリング方法についてのその他有用な一般的参考情報源には、次のようなものがある。すなわち、Merritt et al. (1996);James & Edison (1979);Platts et al. (1983);Nielsen & Johnston (1996);および Sutherland (2000) 。有用な参照用ウェブサイトには、次のようなものがある。すなわち、米国環境保護庁(www.epa.gov/owow/monitoring)、世界自然保護モニタリングセンター(www.unep-wcmc.org)、国際分類同定専門家センター(ETI)が提供する「世界生物多様性データベース World Biodiversity Database」(www.eti.uva.nl)、およびカナダの「生態学的モニタリング評価ネットワーク」(http://www.eman-rese.ca/eman/intro.html)。
86.迅速評価において使用するデータは、使用目的に対して適切な種類及び質のものでなければならない。時間、資金及び専門知識の面でより多くの資源が利用できる場合は、信頼しうるデータ及び信頼できる統計結果を得る可能性は高くなる。さらに、評価に必要なデータ、サンプリング設計及び分析のタイプについてよりよい見識を得るために、対象地、種、生息地についての既存の情報を集めることは重要である。
87.データ収集にあたって、下記の7つの質問を検討すべきである。
a)データの種類は何か? 評価の目的から、関心をよせるべき変数が特定される。その変数とは、例えば目録及び生態の記述に用いるリスト、集合または階級のような定性的なものであることもあり、また例えば生息密度、豊富さなどに用いるカウント及び測定のような数値化された定量的なものであることもある。具体的な測定基準を計算するために集める必要のある変数については、良い文書情報がある(例えば、Barbour et al. 1999 を参照)。
b)データ収集はどう行うのか? サンプリング設計に2種類ある。すなわち、無作為性に基づく等確率抽出法、および対象となる湿地に特有の問題に焦点をあてる標的設計である。等確率抽出法の設計によれば、抽出された場所での推定に基づき地域全体について推測を行える。単純無作為抽出法は、まず個体群を定義し、その全体から無作為に選択する。グループや生息環境による変異性が考えられる場合、層別無作為抽出法によって、個体数推定に関わる誤差を下げることができる。クラスター抽出法は、極めて大きな個体群向けに設計されている。まず抽出単位を、多くの場合その地理的近接度に基づいて、クラスター(群)にグループ分けする。次に、クラスターを無作為に選んで、このクラスター内の抽出単位だけからデータを収集する。GISを利用すれば評価対象の湿地を無作為に選ぶ手間暇が減る。最後に、魚類や大型無脊椎動物、付着生物等で既に確立された各実施要綱に従ってサンプリングを実施する。カナダ環境省が主催する「生態学的モニタリング評価ネットワーク」が、様々な分類群のモニタリング実施要綱について詳しい情報を提供している(http://eqb-dqe.cciw.ca/eman/ecotools/protocols/freshwater)。
c)どれだけの量のデータを集めるのか? サンプル数は、利用できる資源、評価の地理的・時期的範囲、信頼性レベルなどの要素によって決まる。サンプリング場所の数及び種類は、定量または定性分析のための十分なサンプリングを提供するものであるべきである。概して、サンプリングの場所の数が多いほど、対象区域のカバー率が大きくなる。サンプリング場所の数を絞るという選択をすることで、各場所においてさらに詳細な調査を行うことが可能になる。評価によって、サンプリング場所の数が多い方が有益な場合もあれば、より内容の濃いサンプリングを行うためひとつひとつの場所でより長い時間をかけたほうがいい場合もある。これらのどちらかを選ぶのではなく、カバー率と内容の濃さの間で最善のバランスがとれるよう考慮すべきである。評価の際の計測誤差に関わる分散を説明するには反復が必要となる。
d)データ入力はどう行うのか? 生物情報学(ソフトウエア、データベースアプリケーションなど)を用いたデータ管理は、非常に信頼性が高くかつ有用である。評価の具体的な必要性にあわせてアプリケーションを開発できる。フィールドデータシートまたは用紙は、プリントアウトして現場で記入できる。生物多様性情報学によって、より効率的な結果の分析、配布、および他のデータベースへの統合が可能になる。内陸湿地用フィールドデータシートの見本が、米国環境保護庁の河川における迅速生物評価実施要綱のプログラムにより提供されている(http://www.epa.gov/OWOW/monitoring/techmon.html)。
e)データ分析はどう行うのか? 収集したデータおよび評価の目的により、分析に使用する方法は、単純記述、一変量、探索的データ解析(EDA)、もしくは多変量解析(クラスタリング、類似度分析、序列法、多変量分散分析(MANOVA))となりうる。これまで使われてきたのは2つのアプローチで、米国のほとんどの水資源機関が利用している複数の測定基準による解析、あるいはヨーロッパとオーストラリアのいくつかの水資源機関が使用する多変量解析となっている(生態学的多様性の計測についてさらに詳しい情報は、Magurran (1988) を参照)。
f)どのようにデータを統合し、報告をするのか? 評価をより大きな空間的および時期的規模で完全なものにするために、そして生物多様性についてのより完成した評価を提供するために、あるデータセットから別のデータセットへデータを統合することが重要である。評価報告には、当局や科学者を導くための科学的な情報、結果やさらなる行動のための勧告が含まれなくてはならないが、それだけでなく、科学者以外のより広範な聴衆の関心をとらえるために、グラフ表示、およびマルチメディアツールでの発表を加える。最後に、情報の所有権次第では、データベースおよび結果は、インターネットおよび関連する生物情報のネットワークを通じて配布し、さまざまなユーザグループの必要性に供するべきである。
本添付文書は、湿地迅速評価の様々な面に関係する分析方法および指標、ならびに詳しい情報の得られる総説や主要論文といった情報源の、非網羅的かつ例示的なリストとなっている。
| 評価方法 | 適用 | 参考文献 |
|---|---|---|
| 生息環境評価方法 | ||
| 生息地の分類 | ||
| 河川生息環境調査(RHS) | 内陸湿地 | Raven et al. (1998) |
| CORINE ビオトープ分類 | 陸生、水生 | Nixon et al. (1996) |
| 生態系分類 | 水生、陸生 | Groves et al. (2002) |
| Huet の魚類ゾーン | 内陸湿地 | Nixon et al. (1996) |
| Davidson の水棲群集 | 河口 | Nixon et al. (1996) |
| EUNIS(欧州大学情報システム)の生息地分類 | 沿岸海洋域湿地 | http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/EUNIS/home.html [編注]2008年現在のアドレス: http://eunis.eea.europa.eu/ |
| 米国大気海洋局による生息地分類 | 沿岸海洋域湿地:太平洋およびカリブ海 | http://biogeo.nos.noaa.gov/benthicmap/ |
| 予測システム | ||
| RIVPACS(河川無脊椎動物予測分類システム)、英国生態学水文学センター | 河川、底生大型無脊椎動物 | Nixon et al. (1996) |
| AUSRIVAS(豪州河川評価システム) | 内陸湿地:大型無脊椎動物 | http://www.deh.gov.au/water/rivers/monitoring.html http://ausrivas.canberra.edu.au/main.html Schofield & Davis (1996) |
| HABSCORE (生息地状況スコア体系) | 河川、サケ科 | Nixon et al. (1996) |
| エコシム付エコパス | 漁業の生態系への影響、管理アプリケーション | http://www.ecopath.org/ |
| 物理化学的評価方法 | ||
| AUSRIVAS の地質評価 | 内陸湿地 | http://www.deh.gov.au/water/rivers/monitoring.html Parsons et al. (2002) |
| Prati 指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Prati et al. (1971) |
| 生物学的評価方法 | ||
| 基礎データ | ||
| 所定の分類群の個体の豊富さ | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| 合計個体数(同定なし) | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| 生息種数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| 多様性指数 | ||
| シンプソン指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984), Hellawell (1986) |
| Kothé の種の欠損 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| Odum の「種の千分率」 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| グリーソン指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| Margalef 指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984), Hellawell (1986) |
| Menhinick 指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984), Hellawell (1986) |
| 元村の等比級数の法則 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| フィッシャーの「α」(=ウィリアムのα) | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984), Hellawell (1986) |
| Yules の「特質」 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| プレストンの対数正規則 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| Brillouins 指数H | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| Shannon-Wiener 指数 H' | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984), Hellawell (1986) |
| Pielou の一様度指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| 冗長度 R | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| Hurlbert 等確率種間遭遇多様性指数H | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| McIntosh 指数M | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984), Hellawell (1986) |
| Cairns 逐次比較指数(SCI) | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984), Persoone & De Pauw (1979), Hellawell (1986) |
| Keefe 指数 TU | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| 生物指数、スコアおよび複数の測定基準 | ||
| 汚水生物系列 | ||
| Kolkwitz & Marsson の汚水生物系列 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地:バクテリア、原生動物 | Washington (1984) |
| Liebmann | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Persoone & De Pauw (1979) |
| Fjerdingstad | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Persoone & De Pauw (1979) |
| Sladecek | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Persoone & De Pauw (1979) |
| Caspers & Karbe | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Persoone & De Pauw (1979) |
| Pantle & Buck | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Persoone & De Pauw (1979) |
| Zelinka & Marvan | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Persoone & De Pauw (1979) |
| Knöpp | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Persoone & De Pauw (1979) |
| 藻類 | ||
| Palmer の指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地:藻類 | Washington (1984) |
| 植物 | ||
| Haslam & Wolsley の渓流被害評価および汚濁指数 | 内陸湿地 | Nixon et al. (1996) |
| 植物スコア | 内陸湿地 | Nixon et al. (1996) |
| Newbold & Holmes の栄養指数 | 内陸湿地 | Nixon et al. (1996) |
| Fabienne 他の大型植物栄養指数 | 内陸湿地 | Nixon et al. (1996) |
| 大型無脊椎動物系 | ||
| Wright & Tidd の「貧毛類指標」 | 貧毛類 | Washington (1984) |
| Beck 指数 | 大型無脊椎動物 | Washington (1984) |
| Beak 他の「湖」指数 | 内陸湿地:湖沼 | Washington (1984) |
| Beak の「河川」指数 | 内陸湿地:大型無脊椎動物 | Washington (1984) |
| Woodiwiss のトレント川生物指数(TBI) | 大型無脊椎動物 | Washington (1984) |
| Chandler の生物スコア | 大型無脊椎動物 | Washington (1984) |
| BMWP 法(生物モニタリング作業部会のスコア) | 大型無脊椎動物 | Metcalfe (1989) |
| ASPT 値(分類群ごとの平均スコア) | 大型無脊椎動物 | Metcalfe (1989) |
| Tuffery & Verneaux の生物一般質指数 | 大型無脊椎動物 | Persoone & De Pauw (1979), Metcalfe (1989) |
| 地球規模生物指数(IBG) | 大型無脊椎動物 | Metcalfe (1989), AFNOR T90-350 (http://www.afnor.fr/portail.asp?Lang=English). Standard available for purchase from: http://www.boutique.afnor.fr/Boutique.asp?lang=English&aff=1533&url=NRM%5Fn%5Fhome%2Easp |
| ベルギー生物指数(BBI) | 大型無脊椎動物 | De Pauw & Vanhooren (1984) |
| Goodnights & Whitleys 「貧毛類」 | 貧毛類 | Washington (1984) |
| Kings & Ball 指数 | イトミミズ科、水棲昆虫 | Washington (1984) |
| Graham 指数 | 大型無脊椎動物 | Washington (1984) |
| Brinkhurst 指数 | イトミミズ科、ユリミミズ属 | Washington (1984) |
| Raffaeli & Mason 指数 | 線虫、カイアシ | Washington (1984) |
| Sander 浄化法 | 多毛類、二枚貝(海洋性) | Washington (1984) |
| Heister による修正 Beck 指数 | 大型無脊椎動物 | Washington (1984) |
| Hilsenhoff 指数 | 大型無脊椎動物 | Washington (1984) |
| EPT 指数 | カゲロウ目、カワゲラ目、毛翅目 | |
| Rafaelli & Mason 指数 | Washington (1984) | |
| K135 品質指数(オランダ) | 大型無脊椎動物 | Nixon et al. (1996) |
| デンマーク動物相指数 | 大型無脊椎動物 | Nixon et al. (1996) |
| Wiederholm のベントス質指数(BQI) | 内陸湿地:ユスリカ、貧毛類(湖沼) | Nixon et al. (1996) |
| トレンド除去一致分析(DCA) | 内陸湿地:湖沼 | Nixon et al. (1996) |
| Jeffrey の生物学的質指数(BQI) | 大形底生生物(河口、沿岸水域) | Nixon et al. (1996) |
| 生物堆積物インデックス(BSI) | 大型無脊椎動物(堆積物) | De Pauw & Heylen (2001) |
| 魚類 | ||
| Karr の生物保全指数(IBI)(魚類指数) | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地:魚類 | Karr (1981) |
| 鳥類 | ||
| 越冬水鳥のための国際水鳥センサス(IWC) | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地:鳥類 | Nixon et al. (1996) |
| 「包括的」システム | ||
| Patrick ヒストグラム | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地:藻類から魚類;バクテリアを除く | Washington (1984) |
| Chutter 指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地:全部;ただし、ミジンコやカイアシ類を除く | Washington (1984) |
| 類似度指数/比較指数 | ||
| Jaccard 指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984), Hellawell (1986) |
| 百分類似度 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| Bray-Curtis 指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| Pinkham & Pearson 指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| ユークリッド距離/「生態学的」距離 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Washington (1984) |
| Sorensen 類似度指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| Mountfort 類似度指数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| Raabe の比較測定 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| Kulezynski の類似度係数 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| Czekanowski の比較測定 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| Sokal の距離測定 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Hellawell (1986) |
| 生態系の健全さ | ||
| AMOEBA(生態系記述評価法) | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Nixon et al. (1996), Ten Brink et al. (1991) |
| 統合または複合評価システム | ||
| 三連構造(堆積物)品質評価 | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地:生物堆積物インデックス(BSI)、生態毒性学、物理化学(堆積物) | http://www8.nos.noaa.gov/nccos/ccma/publications.aspx?au=Chapman http://www.ingentaconnect.com/content/klu/ectx/2002/00000011/00000005/05096179 |
| 米国環境保護庁の迅速評価要綱(RBP) | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地 | Barbour et al. (1999) |
| SERCON(河川保全評価システム) | 内陸湿地、沿岸海洋域湿地:物理的多様性、自然性、代表性、希小性、生息種数 | Boon et al. (2002)(Parsons et al. (2002) も参照) |
注:費用見積は機器などの費用であり、報酬または給与の費用を含まない。機器入手先の記載は、供給業者や機器を保証宣伝するものではない。
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理的プローブ | 陸水、沿岸海洋域 | ㏗、O2、電気伝導度、温度、BOD、流量 | 短:10−30分 | 100−3000米ドル。プローブ数及び質による。 | 湖沼、河川、湿地、全ての水域 | なし | 無 | ㏗プローブ、温度プローブ、DO(溶存酸素)プローブ、導電率系、流量計、BOD測定機器、滴定機器 | http://www.geocities.com/RainForest/Vines/4301/tests.html http://www.hannainst.com/index.cfm | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| セッキー板 | 陸水、沿岸海洋域 | 水透明度 | 短:5−10分 | 10米ドル | 主にたまり水または緩流河川;浅い沿岸水域 | なし | 無 | セッキー板 | http://www.nationalfishingsupply.com/ | Wetzel & Likens (1991); English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 採水と実験室での分析 | 陸水、沿岸海洋域 | 全リン、全窒素、クロロフィルa | サンプルあたり、現場で10分、実験室で3時間 | 高:実験室の設備 | 全ての水域 | 実験室の設備を使う訓練 | 水試料 | 分光測光器、ろ過装置びん、水試料、反応する植物プランクトン用ネット | http://www.hannainst.com/index.cfm | Wetzel & Likens (1991); Downing & Rigler 1984; Strickland & Parsons 1972 |
| 目視による水の色の評価 | 陸水 | 水の色及びタイプ(黒、白、澄んでいる等)、濁度 | 速:1−5分 | 無し | 全ての水域 | なし | 無 | 深いところの水用の採水器(動物プランクトンのサンプリング用のものでも可) | ||
| 目視による堆積物の評価 | 陸水、沿岸海洋域 | 堆積物の色及びタイプ(有機、砂質、粘土質など) | 速:1−5分 | 無し | 全ての水域 | なし | 堆積物試料 | グラブサンプラー(底生無脊椎動物サンプリングと同時に行うことも可) | http://www.elcee-inst.com.my/aboutus.htm | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地現地評価 | 陸水、沿岸海洋域 | 河川地形、河岸特性、水量、速度、堆積作用、攪乱の証拠、微小生息地の構造(早瀬など)、水辺の属性、水深 | 1−3時間 | 低 | 一切の内陸または沿岸域の湿地環境 | 実地手法の訓練 | 無 | 流量計、巻尺、カメラ、基質採取装置 | www.usgs.gov/nawqa [編注]2008年現在のアドレス: http://water.usgs.gov/nawqa/ | |
| 空間データ分析 | 土地利用、植生の種類および分布、河畔域特性、渓谷の地形,水域の大きさと形、河道勾配、水の色、水文状態、スロープ | 不定:データ解像度および入手可能性による | 不定:データ解像度および入手可能性による | 全ての湿地タイプ | データおよびGISを読み取る知識 | 無 | 衛星画像、航空写真、数値標高モデル、土地被覆、水路測量、地質 | www.freshwaters.org www.usgs.gov | ||
| マンタ法調査 | 海岸地形、地形および土地利用の同時マッピングを補完する、湖岸の生息地のマッピング | 4−5人のチームで1日あたり汀線15km | ボート、燃料 | 濁りのない水域すべて、水中の視界により一般的に水深3−10m | 1−2日で習得可能 | 無 | マンタ法用のボード;スノーケリング用具;膨らませることのできるボートおよび船外機付きボート;地図;水中ノートと鉛筆、GPS | マンタ法用のボードは、マリン用合板で容易に作成可能。 | www.ltbp.org/PDD1.HTM Allison et al. (2000); Darwall & Tierney (1998); English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目視探索 | 陸水、沿岸海洋域 | 例えば河川の増水の跡、最高水位線など、一定区域内の、目に見える植物に留意する定性分析用 | 不定:探索する区域による | 無し | 河川、湖沼、沼、湿地;あらゆる沿岸海洋域生息地 | 種の同定 | 有 | 基本的な機器 | 随所 | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 無作為抽出 | 陸水、沿岸海洋域 | 定性、目視探索に比べ偏りがない | 1−5時間 | 無し | 河川、湖沼、沼、湿地、あらゆる沿岸海洋域生息地 | 種の同定と無作為抽出を行う知識 | 有 | 基本的な機器 | 随所 | Downing & Rigler (1984), Moss et al. 2003 in press; NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| プロット | 沿岸海洋域 | 全ての海岸植生(プロットの大きさは不定。植生の種類による) | 不定:通常約1時間/プロット | 低 | 沿岸生息地全部、マングローブを含む | 種の同定と調査設計 | 有 | 基本的な機器 | 随所 | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| グラブ | 陸水、沿岸海洋域 | 優れた、定量的方法 | 1−5時間 | 350−1100米ドル | 河川、湖沼、沼、湿地、軟底の沿岸海洋域植生 | グラブを使う技術;無作為抽出によるトランセクト法についての知識 | 有 | グラブサンプラー、ブイ、GPS、ボート | http://www.elcee-inst.com.my/aboutus.htm | Downing & Rigler (1984) |
| ダイビング・スノーケリング | 陸水、沿岸海洋域 | 深い水中での植物調査が可能 | 通常約1時間、繰り返しにより異なる | 低(スノーケリング)から、高(スキューバ) | 河川、湖沼、沼、湿地、濁りのない沿岸水域・海域 | ダイビング認定証 | 有 | ダイビング用具、標本収集用はさみ;水中用シート、水中スレート、鉛筆 | http://www.mares.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボックスサンプラー | 陸水、沿岸海洋域 | プランクトン、甲殻類および輪虫用 | 1−3時間 | 100米ドル | 河川、湖沼、沼;全ての沿岸水域・海域 | サンプラーを使う技術 | 有 | プランクトン(ボックス)サンプラー | http://www.mclanelabs.com | Downing & Rigler (1984) |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各種サンプラー、植生の種類による | 陸水、沿岸海洋域 | あらゆる内陸湿地、沿岸域 | 1−4時間 | 100−200米ドル/サンプラー | 河川、湖沼、沼、貯水池、海草および海藻底 | サンプリング技術 | 有 | チューブまたはボックスサンプラー、ふるい | Downing & Rigler (1984); Kornijów & Kairesalo (1994); Kornijów (1997) |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目視探索・スノーケリング・ダイビング(コドラート、インターセプト及びベルトトランセクト) | 陸水、沿岸海洋域 | 大型動物を探すのに良い(例:甲殻類動物)、濁りのない水域および中型・大型動物の調査に適する | 通常約1時間、ただし、繰り返しの程度による | 低(スノーケリング)から高(スキューバダイビング) | 河川、湖沼、濁りのない沿岸水域すべて | ダイビング認定証 | 有 | スノーケル・スキューバ用具、たも、水中用シート、スレートおよび鉛筆、収集用具 | http://www.nationalfishingsupply.com/seinenets1.html http://www.mares.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| グラブ、チューブサンプラー | 陸水、沿岸海洋域 | 柔らかいまたは砂質の堆積物に生息する無脊椎動物全て | 不定:一般的におよそ1時間/場所 | 350−1100米ドル | 柔らかいおよび砂質の堆積物のサンプリングに適する | グラブ装置を使う技術 | 有 | グラブサンプラー、金網ふるい、ローズベンガル染色、ブイ、ボート、整理箱, 容器および防腐剤 | http://www.elcee-inst.com.my/limnology.htm http://www.elcee-inst.com.my/aboutus.htm | Downing & Rigler (1984); English, Wilkinson & Baker (1997) |
| キックネット | 陸水、沿岸海洋域 | 硬い基質に生息する無脊椎動物全て | 1−5時間 | 55米ドル | 小レキ又は石礫の河床で歩いて渡れる渓流に適する | キックネットの技術 | 有 | キックネット | http://www.acornnaturalists.com/p14008.htm http://www.greatoutdoorprovision.com/ | Downing & Rigler (1984); http://www.wavcc.org/wvc/cadre/WaterQWuality/kicknets.htm |
| たも | 陸水、沿岸海洋域 | 浅水域の遊泳動物のサンプリングに適する(例:甲虫、ミズダニ) | 1−2時間 | 5−20米ドル/たも | 湖沼、河川、湿地(沿岸域湿地を含む) | たもを使う技術 | 有 | たも | http://www.sterlingnets.com/dip_nets.html http://www.seamar.com | Downing & Rigler (1984) |
| 引き網 | 陸水 | 強い流のない浅水域での大型無脊椎動物(甲殻類動物)のサンプリングに適する | 1−4時間 | 10−20米ドル/網 | 小さな河川、ボートを使えば湖沼でも可能 | 引き網の技術 | 有 | 引き網 | http://www.nationalfishingsupply.com/seinenets1.html | Downing & Rigler (1984) |
| ソリ | 沿岸海洋域 | 半定量、エピファウナ(表在動物)サンプリング | 約1時間/場所 | データなし | 軟底の生息地 | ソリの技術 | 有 | ソリ、ふるい、整理箱、ブイ、GPS | English, Wilkinson & Baker (1997) | |
| 桁網 | 沿岸海洋域 | よくても半定量、広域調査および目録作成に有用 | 約1時間/場所 | 桁網当たり500−600米ドル | 軟底:基質の深い部分からの試料 | 桁網の技術 | 有 | 桁網、ふるい、ボート、整理箱、ロープ、GPS | http://wildco.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| トロール網 | 沿岸海洋域 | 定性:比較的大型のエピファウナおよび底生遊泳生物(他の方法の補足) | 2−3時間/場所 | 網代1000米ドル、レンタルボート、および現場アシスタント | 軟底基質 | トローリング技術 | 有 | トロール網、ふるい、ボート、整理箱、ロープ、GPS | http://www.seamar.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| サーバーサンプラー | 陸水、沿岸海洋域 | 石礫または小レキの基質に生息する無脊椎動物全て | 1−3時間 | 200米ドル | 砂礫又は石礫の河床をもつ 河川及び渓流、よどんだ水域 | サーバーを使う知識と、データ定量化の要件についての知識 | 有 | サーバーサンプラー、バケツ | http://www.kc-denmark.dk/public_html/surber.htm http://www.kc-denmark.dk | Downing & Rigler (1984) |
| 空中ネット | 成長した無脊椎動物の捕獲 | 1−5時間 | 35−50米ドル | 陸地 | 空中ネットを使う技術 | 有 | 昆虫ネット | http://www.rth.org/entomol/insect_collecting_supplies.html http://bioquip.com/ | Downing & Rigler (1984) |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引き網 | 主に比較的小さい魚類 | 1−4時間 | サイズにより、10−250米ドル/網 | 強い流のない浅水域、小さな河川、ボートを使えば湖沼でも可能(大きな網を使う場合、網の仕掛けと引き上げにボートが必要な可能性あり) | 引き網の技術 | 有、網は魚類を殺さない | 引き網 ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.nationalfishingsupply.com/seinenets1.html http://www.seamar.com | Bagenal (1978); English, Wilkinson & Baker (1997) | |
| 刺し網 | 陸水 | すべてのサイズおよび種類の魚類 | 24 時間:一晩放置 | 150−200米ドル/網 | 浅水域から中程度の深さの水域、よどんだ水域または緩流河川 | なし | 有、網は魚類を殺す | 刺し網 | http://www.nationalfishingsupply.com/seinenets1.html [表下原注1] | Bagenal (1978) |
| キル・ネット | 沿岸海洋域 | メッシュの大きさにより、すべてのサイズおよび種類の魚類 | 12−24時間:一晩放置 | 50−500米ドル/網 | 浅水域から中程度の深さの水域 | 網を仕掛ける技術 | 有 | 流し網、かすみ網、ブロック、巻き網、刺し網、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.seamar.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| フィッシュトラップ(袋網) | 陸水、沿岸海洋域 | すべてのサイズおよび種類の魚類、主に底生魚 | 24時間:一晩放置 | 50−100米ドル/トラップ | 主に 浅水域(より深い水域の場合、モーターウィンチが必要) | トラップを正しい場所に仕掛ける技術。漁師の助けが望ましい | 有、トラップは 魚類を殺さない | フィッシュトラップ、(モーターウィンチが必要な場合あり)、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.seamar.com | Bagenal (1978); English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 定置網 | 沿岸海洋域 | 主に浅水域の、殆どのサイズおよび種類の魚類 | 12−24時間:潮汐による(垣網および箱網)えりの仕掛け時間はこれより長く、24時間程度おきに集める | 50−500米ドル/網、サイズにより、えり | 浅水域 | 網を仕掛ける技術。えりの仕掛けには専門家(漁師)が必要 | 有 | 垣網、箱網、えり、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.seamar.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| トロール網(各種。例:ビームトロール網、オッタートロール網) | 陸水、沿岸海洋域 | 深海の遠海魚、群泳魚、および底生魚に対してのみ使用、きわめて環境破壊的となることもある | 1−4時間 | 網代 1000米ドル、レンタルボートおよび現場アシスタント | 大きな比較的深い水域で、水底に障害物がなく水面に破片などない場合のみ | トローリング技術 | 有、ネットは魚類を殺す | トロール網、ボート、最低2−3人の手伝い 計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.fao.org/fiservlet/org.fao.fi.common.FiRefServlet?ds=geartype&fid=103 http://www.seamar.com | Bagenal (1978); English, Wilkinson & Baker (1997) |
| スクープ・アンド・トレイ・ネット | 沿岸海洋域 | 水面近くの小魚に適する。河岸方向にのみ使用のこと | 1−5時間 | 5−20米ドル/網 | マングローブなど近づけない区域で使用 | 網を使う技術、ただし習得しやすい | 有 | スクープ・アンド・トレイ・ネット、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.seamar.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| プッシュネット | 沿岸海洋域 | 小型生物のみの捕獲 | 1−2時間 | 5−20米ドル/網 | 殆どの浅水域 | 網を使う技術、ただし習得しやすい | 有 | プッシュネット、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.seamar.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 投網 | 沿岸海洋域 | 小型の魚類やクルマエビ類に適する | 1−2時間 | 50−200米ドル/網 | 密閉区域および浅水域に良い | 投網の技術。やる人により効率が異なる | 有 | 投網、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.nationalfishingsupply.com/ | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| ドロップネット | 沿岸海洋域 | 小型生物 | 1−2時間 | 50−100米ドル/網 | 小さくかつ浅い水域に良い | 仕掛けを作りおよび使う技術。労働集約的 | 有 | ドロップネット、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.seamar.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 敷網 | 沿岸海洋域 | 一カ所に集まっているはずの小型、希少種 | 1−2時間 | 50−100米ドル/網 | 小さく浅い水域に適する | 網を使う技術 | 有 | 敷網、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.seamar.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 水中銃(各種) | 沿岸海洋域 | 全ての種に適するが、主に大型で選んだ(他の方法では捕獲しにくい)種 | 1−6時間 | 50−200米ドル/水中銃 | 濁りのない水域すべて;難しい区域 | 技術を練習により習得する | 有 | 水中銃および用具一式、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://divebooty.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| 浮延縄または底延縄 | 沿岸海洋域 | 選んだ魚類、使用する餌に応じる | 12−24時間:一晩放置 | 100−300米ドル/延縄、釣り針の数次第 | あらゆる水域、ただし、高い起伏のある硬い水底を除く | 延縄の技術 | 有 | 釣り針、釣り糸、餌、ブイ、おもり、ボート、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.seamar.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| たも | 陸水、沿岸海洋域 | 水面近くの小魚に適する | 1−5時間 | 5−20米ドル/たも | 河川、湖沼、その他の湿地内の、限られた区域 | たもを使う技術 | 有 | たも | http://www.sterlingnets.com/dip_nets.html | Bagenal 1978 |
| 釣り道具 | 陸水、沿岸海洋域 | 使用する餌次第で、どの魚種にもどの水域にも適する | 繰り返し次第で不定 | 繰り返し次第で不定 | 河川、湖沼、その他の湿地 | 手釣りの技術 | 有 | 釣り針、釣り糸、餌、(ボート)、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://www.nationalfishingsupply.com/ | |
| ロテノン(薬剤の一種) | 沿岸海洋域 | 囲いの中の区域の魚全部。全ての魚を殺す。許可が必要な可能性あり | 一か所あたり数分 | 350米ドル/20リットル | 浅い開放水域において、区域をネットで囲む。深い水域の場合、洞窟および,岩の裂け目で用いる | 網を仕掛ける技術 | 有 | ロテノン、網、スクープ・ネット、計測板、はかり、シート、鉛筆、スレート、ポリ袋、プラスチックラベル、防腐剤、GPS | http://southernaquaculturesupply.com/index.php | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| ソナー | 陸水、沿岸海洋域 | 群泳魚、遠海魚に適する、データはあまり正確ではない | 水域の大きさによる | 100−1000米ドル | 深い湖沼および深く大きな河川;全ての沿岸水域、ただし主に深水域 | ソナーの操作技術 | 無 | ソナー、ボート | ||
| 電気漁法 | 陸水 | 中型から大型の魚類のサンプリングに最適、いくらか塩分のある比較的冷たい水域により適する | 1−5時間、繰り返し回数および生息環境タイプにより異なる | 500−2000米ドル | 主に浅水域 | 電気漁法の訓練および免許 | 有、魚類を気絶させるが殺さない | 電気ショッカー一式;収集機器 | http://www.fisheriesmanagement.co.uk/electrofishing.htm | Bagenal 1978 |
| ダイビング・スノーケリング(トランセクト、定置、自由移動) | 陸水、沿岸海洋域 | 場所を突き止める或いは行くのが難しい個別の生態系の調査に適する;澄んだ水域 | 通常約1時間。ただし、繰り返し回数により異なる | 低(スノーケリング)から高(スキューバ)、機器の費用 | 湖沼、河川、全ての澄んだ沿岸水域 | スノーケリング:なし;ダイビングには認定証が必要。種の同定および調査設計 | 無 | スノーケル・スキューバ用具、たも、水中用のシート、鉛筆およびスレート | http://www.mares.com | English, Wilkinson & Baker (1997) |
| アンケート | 陸水、沿岸海洋域 | 地域の漁師に、観察したことのある、および利用している魚類を訊ねる | 2−4時間 | 低 | 全ての水域 | 適用しやすい。但し、アンケート作成のための知識が必要 | 無 | 紙、ペン、地域の人への差し入れも考えられる |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たも(両生類) | 陸水、沿岸海洋域 | オタマジャクシの捕獲に適する | 通常およそ1時間、ただし繰り返し回数による | 5−20米ドル/たも | 河川、湖沼、その他の 内陸湿地、種の生息するあらゆる沿岸水域 | たもを使う技術 | 有 | たも | http://www.sterlingnets.com/dip_nets.html http://www.seamar.com | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 目視探索(両生類・は虫類) | 陸水、沿岸海洋域 | 比較的見やすい生物を探すのに良い | 不定 | 無し | 陸地および地表水 | 微小生息地の知識 | 無 | なし | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) | |
| 鳴き声調査 | 陸水、沿岸海洋域 | 耳を澄ましてカエルの声にを探して時々録音し、かつ、鳴き声から種を同定する | 不定、探索および録音時間により、数 時間 | 低:テープレコーダー | あらゆる水域、水辺環境、陸地 | カエルの声に関する知識、および鳴き声と生息地から種を同定する | 無 | テープレコーダー、録音用テープ、テープ再生装置、懐中電灯 | 信頼できる電子機器店 | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| ドリフトフェンス付きピットホールトラップ(両生類、爬虫類) | 陸水、沿岸海洋域 | 観測が難しい動物の収集に良い;相対的な生息数と種数を推定 | 24−48時間放置 | 古いバケツを再利用すれば出費は無い | 陸地 | ドリフトフェンス付きのピットホールトラップを設置する技術 | 有 | バケツ、ハンドシャベル、フェンス用の金属 | http://www.agric.nsw.gov.au/reader/2730 | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| リター調査(両生類・爬虫類) | 陸水、沿岸海洋域 | 通例、区画法とともにカエルを見つけるのに使う | 不定。繰り返し回数次第で異なる | 無し | 陸地 | 最低必要レベル | 有 | 随所 | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) | |
| トランセクト(両生類・爬虫類) | 陸水、沿岸海洋域 | データを定量化し標準化するための対照調査として用いる | トランセクトの長さ及び数による | 無し | 陸地 | トランセクトを確立する知識 | 有 | マーキングテープ | http://www.npws.nsw.gov.au/wildlife/cbsm.html | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| スノーケリング・ダイビング(爬虫類) | 陸水、沿岸海洋域 | カメを探すために用いられる | 不定。繰り返し回数による | 低(スノーケリング)から高(スキューバ) | 河川、湖沼あらゆる沿岸水域 | ダイビング認定証 | 有 | スノーケル・スキューバ用具、たも、水中用のシート、スレートおよび鉛筆 | http://www.mares.com | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 輪縄(爬虫類) | 陸水、沿岸海洋域 | トカゲに適する | 探索するトカゲの数による | 無し:草で作れる | 陸地 | 輪縄を作る技術およびトカゲを見つける技術 | 有 | しなやかで長く強い雑草、ロープ | http://www.macnstuff.com/mcfl/1/lizard.html | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| カメ用罠/タートルトラップ(爬虫類) | 陸水、沿岸海洋域 | 陸上及び水上でカメを捕らえるために使用 | 最低1日 | 65−150米ドル/トラップ | 湖沼、河川、陸地、その他の内陸および沿岸域湿地 | タートルトラップを仕掛ける知識 | 有 | タートルトラップ、餌 | Limpus et al. (2002); NSW National Parks & Wildlife Service (2002) | |
| アンケート | 陸水、沿岸海洋域 | 漁師を含む地域の人に観察したことのある種、利用している種について訊ねる | 2−4時間 | 低 | 全ての水域 | 適用しやすい。ただし、アンケートの設計に経験を要する | 無 | 紙、ペン、地元の人への差し入れも考えられる | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空機での調査 | 陸水、沿岸海洋域 | 個体数および相対生物量についての粗見積もりができる;特定種に偏る | 1−4時間 | 高:飛行機借上げ費用 | あらゆる開放地;植物が密生している湿地を調査する唯一の方法でもある場合がある | 素早く種を認識する経験 | 無 | 可能ならば、肉眼で同定できる高度で飛行する;双眼鏡、テープレコーダー、地図、GPS装置 | http://www.telescope.com | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 定点観察法 | 陸水、沿岸海洋域 | 陸棲種:データを定量化し標準化するための対照調査となるトランセクト法をともに用いる。乾期なら徒歩で雨期ならカヌーで実施可能 | 1−5時間 | 100米ドル程度 | 陸地、河川、湿地;沿岸生息地全部 | 定点観察法を実施および記録するためのパラメータについての知識 | 無 | 双眼鏡、巻尺、境界用旗 | NSW National Parks & Wildlife Service[ニューサウスウエールズ国立公園・野生生物局](2002) | http://www.npws.nsw.gov.au/wildlife/cbsm.html NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| トランセクト法 | 陸水、沿岸海洋域 | 陸生及水生種:データを定量化し標準化するための対照調査として用いる。徒歩でもボートでも実施可能 | 1−5時間だが、調査区域による | 100米ドル程度 | 開放系のあらゆる生息地 | 種および調査設計の知識 | 双眼鏡、巻尺 | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) | |
| 鳴き声調査 | 陸水、沿岸海洋域 | 耳を澄まして鳥の鳴き声を探して時々録音し、かつ、鳴き声から種を同定する | 不定、探索および録音時間次第で数時間 | 低:テープレコーダー(必要ならば) | あらゆる水域、水辺環境、陸地;沿岸生息地 | 鳴き声、生息地から鳥の種を同定する知識 | 無 | テープレコーダー、録音用テープ、テープ再生装置(必要ならば) | 信頼できる電子機器店 | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 営巣地の探査 | 陸水、沿岸海洋域 | 水上または水際で営巣をする鳥の種 | 1−5時間 | 100米ドル程度 | あらゆる水域 | 営巣環境や営巣生態の知識(攪乱を避けるため) | 無 | 双眼鏡、地図 | http://www.telescope.com | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 方法 | 適用環境 | 適用 | 現地調査所要時間 | 費用 | 湿地タイプ | 必要となる専門知識 | 収集の可能性は? | 必要な機器 | 機器入手先の例 | 方法についての参考情報源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目視調査 | 陸水、沿岸海洋域 | 哺乳類が水面に浮上するのを探す | 不定 | 無し | 河川、湖沼、湿地;沿岸海洋域生息地全て | 最低必要レベル | 無 | 必要ならば双眼鏡 | http://www.telescope.com | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 繁殖地の特定 | 陸水、沿岸海洋域 | 陸上にも住む水生哺乳類に適する | 1−5時間 | 無し | 陸地 | 繁殖環境の知識 | 有 | なし | ||
| トラップ | 陸水、沿岸海洋域 | 小型および中型の哺乳類(例:カワウソ、ミンク) | 12時間:一晩放置 | 20−50米ドル/トラップ | 陸地、水辺、浅水域;全ての沿岸生息地 | トラップを仕掛けるおよび場所を探す技術 | 有、トラップは動物を殺さない | トマホークトラップ、シャーマントラップ | http://www.thecatnetwork.org/trapping.html | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| 足跡調査 | 陸水、沿岸海洋域 | 陸地、水辺における哺乳類の存在を探知する | 1−4時間:探索時間による | 無し | 陸地および水辺の区域 | 足跡を見つけ、足跡から種の同定ができる | 無 | 最低必要レベル−写真撮影または石膏標本作り | カメラのサプライヤ | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
| トランセクト | 陸水、沿岸海洋域 | 多くの目撃がある場合、データを定量化する | 1−5時間 | 無し | 河川、湖沼、湿地;開けた沿岸生息地 | トランセクトを確立する知識 | 無 | 必要に応じ、双眼鏡 | http://www.telescope.com | http://www.npws.nsw.gov.au/wildlife/cbsm.html |
| 航空機での調査 | 沿岸海洋域 | 個体数についての粗い推定および特定の種に対する相対的な生物量 | 1−2時間、ただし調査区域の大きさによる | 高:飛行機借上げ費用 | 全ての開放地 | 素早く種を同定する経験 | 無 | 双眼鏡 | http://www.telescope.com | NSW National Parks & Wildlife Service (2002) |
[ PDF(637㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]
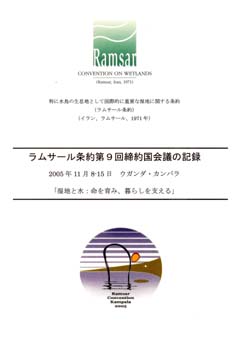 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_Ei.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_Ei.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_01_annexei_j.htm
Last update: 2008/06/25, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).