| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日
1.締約国会議が第8回締約国会議において「特に干ばつ等の自然災害が湿地の生態系に及ぼす影響」に関する決議Ⅷ.35を採択したことを想起し、しかし続けて発生する異常気象やその他の災害、特に2004年12月26日のインド洋における破壊的な津波が証明したように、自然災害の範囲は、同文書が扱ったよりはるかに広範であることを認識し、
2.国連環境計画/国連人道問題調整部(UNEP/OCHA)の共同環境ユニットが、環境上の非常事態及び環境への影響を伴う自然災害時における国際的援助の動員を担当する国連の調整機関であることを意識し、
3.国連防災世界会議(2005年 神戸)が、自然に由来する災害(ハザード[訳注1])とそれに関連する環境的技術的なハザードとリスクによる災害を包含する視野を持ち,それによって災害危機管理に対する、また社会・経済・文化・環境の体系に顕著な影響を与えうるさまざまな災害の相互関係に対する全体論的な多重災害手法を反映する『兵庫行動枠組』を採択したことを想起し、
4.災害の回避、影響緩和に、また災害後の再生に対する一つの国際的な活動の主体としてラムサール条約が重要な役割を果たし得ることを認識し、
5.生態系が機能し、それが社会へもたらす恩恵/サービスの提供を確かなものにする上で、洪水は重要な役割を果たす自然現象であることを再び認識し、
6.マングローブなど自然の湿地生態系の保全は、それら沿岸域湿地の賢明な利用とともに自然の洪水と高潮の影響緩和に寄与すること、ならびに泥炭地その他集水域もしくは氾濫原の湿地の保護と回復は、自然洪水の防止に寄与することを確認し、
7.世界の多くの地方が湿地、特に泥炭地の激しい火災による深刻な影響を受けてきていること、そしてこの火災に伴う煙の害が数百万の人々の生活に影響し、大きな環境、社会、経済問題の原因となることを意識し、自然現象に伴う悪影響は、湿地からの排水といった別の人間活動によって拡大する可能性があるということも再び認識し、
8.締約国が、決議Ⅷ.1を通じて、湿地の恩恵/サービスの多く、特に水の保持と浄化、地下水の涵養、人間のためならびに地球規模での生物多様性の維持のための水や食料及び繊維の提供などを、湿地が確実に提供し続けられるためには湿地への水の配分を維持することが決定的に重要であること、そして災害後の局面で特にこの必要性が高まることを強調していることを想起し、
9.自然災害の影響を重点的に扱う他の多国間環境協定や機関、特に国連環境計画/国連人道問題調整部(UNEP/OCHA)の共同環境ユニット、また国連国際防災戦略(ISDR)、世界保健機関(WHO)、世界気象機関(WMO)、陸上の活動から海洋環境を守るための地球行動計画(UNEP)、自然災害影響緩和計画(世界銀行)、国連砂漠化対処条約、国連気候変動枠組条約、ユネスコ国際海洋地理委員会などとの相乗作用の重要性を認識し、政府、非政府団体(NGO)、市民団体、また特に国際水管理研究所(IWMI)とともに条約国際団体パートナーが構成する「ラムサール津波グループ」、及び地球環境センター(GEC)などが自然災害直後に果たし得る重要な役割も再び認識し、
10.ラテンアメリカ及びカリブ海諸国環境大臣フォーラム(ベネズエラのカラカスで2005年10月31日−11月4日開催)の決定17の重要性を念頭におき、「広域カリブ海地域」諸国において続発する異常気象と、その他の地域におけるこの現象の影響が湿地に及ぼす影響の重要性を、防災、早期警戒、回復、モニタリングその他、湿地が十分な生態学的機能を果たし続けるようにする活動のための資金の必要性とともに認識し、
締約国会議は、
11.自然災害が生態系の恩恵/サービスの提供に及ぼす破壊的な影響と、それが災害を受けた国々の国際的に重要な湿地その他の湿地の生態学的特徴の維持に与える影響を強調する。
12.締約国に対して、条約湿地や他の湿地ならびに関連する生態系が人々や生物多様性にその生態系の恩恵/サービスを全面的かつ継続的に提供できることが確実となるように、決議Ⅷ.1の求めにそって、自然の水文環境に従い、自然災害の影響を受けた生態系の再生を援助する条約の手引きを念頭に置きながら、条約湿地や他の湿地ならびに関連する生態系を、自然災害に対する脆弱さを減らすように、維持または再生することを強く要請する。
13.火災のリスクを低減し、干ばつ時の水の供給を図るために、世界のさまざまな地域で実施されている泥炭地の保護と回復のための対策の拡張を支持する。
14.締約国と河川流域当局に対して、洪水のような自然現象の影響を緩和し、乾燥地域や半乾燥地域においては干ばつに対する回復力を与え、また気候変動や砂漠化の影響を緩和するための広範な戦略に貢献するように、またそれによって、それら変動によって誘発されあるいは増大される自然現象が及ぶ範囲やその規模を減らすことができるように、防災計画の一部として、確実に湿地生態系を管理し再生するよう奨励する。
15.条約事務局に対して、締約国と他のパートナー団体と協働して、洪水や高潮、干ばつ、侵入的外来種などをはじめとする自然災害を防止し、影響緩和し、それらに適応するよう統合され社会的に公平な湿地生態系管理を確実にするために、影響を受けたすべての生態学的区域に対する意思決定を支援するツールを策定し、それに基づいて行動するよう要請する。
16.影響を受けた締約国に対して、自然災害の条約湿地や他の湿地の生態学的特徴への影響、ならびにそれら湿地に依存し被害を受けた人々の暮らしへの影響をモニタリングし評価するように、また条約湿地については、決議Ⅷ.8の要請に従って、次の締約国会議に向けた条約の科学技術検討委員会(STRP)による条約湿地の生態学的特徴の現状と傾向に関する報告の助けとして利用できるように、それらの情報を条約事務局に報告するよう要請する。
17.締約国に対して、開発に適した区域を定める多重災害分析と、湿地の賢明な管理を含む、災害による被害を防止したり、最少限に抑えるための事前手段を意識した防災計画とを確立することを奨励する。
18.締約国ほかに対して、緊急に、2004年12月のインド洋津波災害の被害を受けた国々の沿岸域湿地及び関連地元社会の暮らしの回復、ならびに沿岸域の地元社会や湿地の脆弱性の削減を促進し活発に支援するために協働するよう求める。それらは以下のような取り組みを通じて進める:
19.条約事務局と国際援助機関に対して、湿地がもたらす生態学的な恩恵/サービスを維持するという観点で、これらの異常気象の広域カリブ海諸国の湿地への影響ならびに同様な災害の影響を受けたその他地域の湿地への影響を緩和し、再生し、回復し、モニタリングすることを目的とした行動を実施することから生じる必要を満たすのに、それらの政府とともに、寄与できるように、それぞれの国との間で設けられる協定の文脈の中で、資金調達、資源の動員、国際協力を探すにあたって優先順位をつける必要性を認識するよう要請する。
20.STRPに対して、国際団体パートナーや関係他機関と協働し、生態系の回復と脆弱性に対する対応を実施する際の統合的沿岸域管理(ICZM)の中での湿地の役割に関連する、既存や新規の手引きに書き加えることや、適切ならば、自然災害の影響緩和における湿地生態系の役割を強調する既存のガイドラインを更新することなど、自然災害全般の後に実施すべき湿地再生活動のための一連のガイドラインを、締約国のために策定するよう指示する。
21.条約事務局に対して、条約の広報・教育・普及啓発(CEPA)プログラムを通じて、資金の許す範囲で、賢明な湿地管理を組み入れた防災計画を通じて災害の影響を防止し最小化する適切な事前の方策に関して世界中から得られる教訓を中心とする資料を策定するよう指示する。それら資料は災害の影響を弱めることに成功した取組の例示となり、また緩衝帯としての湿地の役割について社会の意識や能力を向上させる役に立つはずである。
22.条約事務局に対して、関連の国際的な団体機関、特に国連環境計画/国連人道問題調整部(UNEP/OCHA)の共同環境ユニットや、国連国際防災戦略(ISDR)、世界気象機関(WMO)ならびに国連環境計画(UNEP)と、また適宜条約の国際団体パートナーと協働して、湿地、特に条約湿地に影響を及ぼす、あるいは及ぼしかねない自然災害の発生に対して政府等が直ちに開始すべき一連の対応に関する手引きを策定するよう指示する。
[ PDF(194㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]
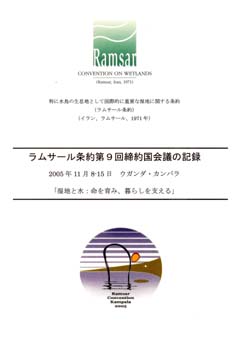 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.09.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.09.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_09_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).