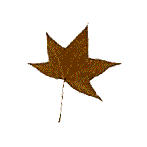|
| 津城三十二万石余の大名となった誠意の人 |
| 藤堂高虎(1555〜1630) |
| ● |
誕生 |
|
天文二十四年(1555)、近江国藤堂村(在土)に生まれる。父藤堂虎高は京極家の後、浅井家に仕えた犬上郡数村の領主。藤堂家は、中原氏(平安時代以来の朝廷に仕えた大臣)の家柄であるが、高虎時代は状勢より藤僚氏系と名のった。 |
| ● |
徳川時代 |
|
慶長五年(1600)四十五歳・関ケ原戦で家康に従軍し、功績をたて今治二十万石の城主となる。以後、丹波篠山城・亀山城の普請奉行に任ぜられる。慶長十九年(1614)五十九歳・江戸城普請奉行となる。元和三年(1617)六十二歳・東照宮の縄張りを賞せられ、三十二万二千九百余石の大大名となる。寛永七年(1630)七十五歳・十月五日没す。寒松院(津市)に葬る。 |
|
 |
| ● |
十五歳にして191Cmの体格 |
|
生まれたときから乳母の一人の乳だけではたらず、家来の女房から乳をもらった。三歳には餅を食い、六歳で大人の食事をし、七歳で40Kgの荷物を持ち、元服の十五歳には191Cmの筋骨たくましい怪童であった。 |

高虎公園内(高虎像) |
● |
誠意ある人柄 |
|
生涯を通じて誠意を冬くす人に対して必ず誠意を冬くす人であった。若武者時代は父に従って湖北の雄「浅井家」に仕え織田信長軍(姉川合戦)とよく戦った。浅井家滅亡後、秀吉の弟「秀長」に仕え、彼の実力が認められるようになる。主君秀長が死んだ時は、高野山で出家(僧になる)までする。徳川家康に武家屋敷を建てた時、自費を払って裏門を造営する。秀吉亡きあと、後見人石田三成の高慢なところに嫌気がさしていたところ、徳川家康の誠意に共感し、家康こそが私の主君と決断し、関ケ原戦で徳川軍として善戦する。家康は高虎の仕事に対する気構えと忠臣精神を認め、遺言状の後見人としての扱いをたまわり、伊勢国三十二万石余の大名となる。 |
| ● |
築地土木の天才 |
|
高虎の体は巨人であったが、指がなく全身は刀傷で切り刻まれていた。彼の武勇を語る証である。そればかりではない、高虎には築城工事に優れ名築城家としての才能があった。秀吉時代は伊予大洲城、宇和島城、家康時代は普請奉行としてヨーロッパ築城技術を取り入れた今治城、二条城、穴太衆(滋賀)の石垣技術をフルに利用した再建の大阪城、日本一高い石垣の伊賀上野城、伏見城の補修、そして城主となった津城、また、江戸城の修築などと日光東照宮である。家康の命によって日光東照宮の大棟梁となった甲良豊後守宗廣は、高虎と同郷である。ときに高虎四十五歳、宗廣二十八歳であった。 |
|
|