
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
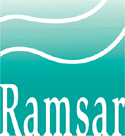
日本語訳:琵琶湖ラムサール研究会,2001年.
英語 フランス語 スペイン語 (以上,条約事務局) PDF (192㎅)

条約第5条の実施のための
[決議Ⅶ.19(1999)の付属書として採択]
§1.はじめに
§1.1.条約第5条の解釈
§1.2.過去の締約国会議の決議と勧告が与える手引き
§1.3.ラムサール条約の「1997−2002年戦略計画」総合目標7
§2.国際協力のためのガイドライン
§2.1.複数国にまたがる湿地、河川流域の管理
2.1.1.境界をまたぐ(国際的な)湿地
2.1.2.境界をまたぐ(国際的な)河川流域
§2.2.複数国にまたがる湿地に依存する種の管理
2.2.1.渡り性水鳥
2.2.2.他の渡り性の種
§2.3.地域的・国際的な環境条約や機関とのパートナーシップ
2.3.1.他の地球的環境条約
2.3.2.地域的環境条約,協定,団体
2.3.3.国際的プログラムや団体
§2.4.専門知識と情報の共有
2.4.1.知識の共有
2.4.2.研修
2.4.3.湿地姉妹提携や湿地ネットワーク
§2.5.湿地の保全と賢明な利用を支援する国際的な補助
2.5.1.湿地に対する環境基金の増進
2.5.2.各分野の戦略や開発計画において湿地を適切に考慮することの確保
2.5.3.国家的計画の枠組みにおける湿地関連事項の統合を支援すること
2.5.4.開発援助機関の能力の改善
2.5.5.援助を受ける政府の能力の向上
2.5.6.開発援助機関とラムサール条約担当政府機関の協力の向上
§2.6.湿地に由来する動植物産品の持続可能な収穫と国際取引
2.6.1.収穫の制御と監視
2.6.2.ワシントン条約(CITES)
§2.7.湿地の保全と賢明な利用を確保するための海外投資活動の規制
2.7.1.影響評価
2.7.2.行動規範
1.条約第5条は次のとおり.締約国は,特に二以上の締約国の領土に湿地が渡っている場合又は二以上の締約国に水系が及んでいる場合には、この条約に基づく義務の実施につき、相互に協議する。また、締約国は、湿地及びその動植物の保全に関する現在及び将来の施策及び規則について調整し及びこれを支援するよう努める
.
2.第6回締約国会議において条約の「戦略計画」が採択された.「戦略計画」の行動7.3.4は特に途上国の湿地に影響を与える可能性のある援助を行う,各国の援助機関の責務について,締約国が国際協力の分野の責務をどのように果たせばよいかという点に関するガイドラインを,第7回締約国会議(1999年)の分科会での検討に向けて作成する
よう常設委員会とラムサール条約事務局に指示した.
3.第5条条文の解釈に関して,このガイドラインは以下の前提に立つ.
a)締約国は … この条約に基づく義務の履行につき、相互に協議する
.この条文は,第2条6(渡り性水鳥の保護,管理,賢明な利用),第3条1(賢明な利用の計画策定と実施),第4条3(調査とデータや出版物の交換の奨励)ならびに第4条5(研修,管理,管理者の設置の促進)を含み,これらに限らない,条約のすべての義務にあてはまるものと考えられている.
b)特に二以上の締約国の領土に湿地が渡っている場合又は二以上の締約国に水系が及んでいる場合
.この条文は,(第3条1に一致して)国際的に重要であろうともそうでなかろうとも国際的な境界をまたいでいる湿地,ならびに国際的に重要な湿地を包含していようといまいと国際的な境界をまたいでいる河川流域にあてはまると考えられている.
c)また、締約国は、湿地及びその動植物の保全に関する現在及び将来の施策及び規則について調整し及びこれを支援するよう努める
.この条文は,複数国にまたがる湿地に依存する種や,二か国・多国間の補助,湿地に由来する動植物産品の取引,海外投資活動といった分野における締約国間の協力にあてはまると考えられている.
4.これまでの6回の締約国会議において,条約のもとでの国際協力の側面の助言を提供する決議や勧告が多数ある.それらは,次のようなものである:
決議
勧告
5.第6回締約国会議において採択された条約の「戦略計画」には国際協力に関する総合目標7が含まれている.この総合目標には4つの実施目標があり,このガイドラインがその第2節で言及しているテーマを識別するために用いられている.
6.締約国は,下記のガイドラインを条約第5条の実施の基礎として考慮し,適切に採用することが求められる.
7.条約は常に,いわゆる複数国にまたがる湿地の管理における協力が第5条に従う締約国の根本的な義務であると認識している.複数国にまたがる湿地はこんにち定常的に国際的な湿地と呼ばれる.その概念は比較的単純なもので,国際的な境界をまたぐ湿地を意味する.過去においては,登録簿に掲げられた複数国にまたがる湿地の管理において締約国が協力することに優先順位が置かれていた.条約の第3条1は,そのような協力が,登録簿に掲げられているか否かにかかわらず,すべての複数国にまたがる湿地に拡張されるべきことを示している.
8.条約は,河川流域の一部として湿地を管理する必要があるということを認識し,それに対応している.その結果,国際協力の解釈も拡張されて,ある締約国の湿地の集水域が他の締約国にまで広がり,集水域側の国における活動がその湿地の生態学的特徴に影響を及ぼすことになるような場合も含まれるようになった.このような条件のその湿地が条約に登録されていても,その締約国の管理の及ばない状況のために条約に基づく義務に従った行動をとることには無理があったためである.上流側の国が下流側で影響してしまった問題を扱うことが困難であることも考慮しなければならない.沿岸性湿地でも同じような状況はおこり,ある締約国の活動あるいはそれをしないことが,他の国の側の湿地に負の影響を及ぼしてしまうことがある.陸域に端を発した海洋汚染がそのひとつの例である.
9.複数国にまたがる河川流域の場合,締約国は,適切ならば,調印当事者となりうる流域に関する協定から生じる義務とラムサール条約第5条の実施とを調和させることを追求すべきである.国際的・地域的な規模でこのような協定は200を越え,協力体制の法的基盤を既に提供している.地域レベルでは,「国際水路および国際湖沼の保護と利用に関する条約(ヘルシンキ,1992年3月17日)」が新たな協定を策定するための包括的な基礎を提供する重要な原則と規則を示している.
10.これらのことからわかるように,複数国にまたがる湿地や河川流域の管理におけるいまひとつの側面は,外来種あるいは侵入種の問題である.国際的な境界をまたぐ湿地では,このような侵入種が負の影響を与えるかぎり,これらを制限するためにできる対策に関与しうるすべての管轄国が明確に責任を負う.これは,複数国にまたがる河川流域にも同様に適用され,侵入種がある締約国から周辺国へ水系を通じて移入することを防ぐことも,条約の国際協力のためのガイドラインのもとに責任を負うものと考えるべきである.
11.この国際協力のためのガイドラインに則り,締約国は,自国にある複数国にまたがる湿地系(沿岸性湿地を含む)を識別し,それらの管理にあたっては周辺の管轄国と協力することが求められる.この協力は,その湿地の管理計画の策定と実施における公式の共同管理作業や共同事業に拡張しうる.包括的な地球レベルでの評価ではないにしろ,世界自然保護モニタリングセンターが準備した報告「世界にある複数国にまたがる湿地と河川流域」がそのような湿地を識別するための予備的な基盤を提供している.この報告では,955のラムサール条約登録湿地を分析対象とし,そのうちの92ヶ所(9.6%)が,周辺管轄国からの影響を受ける対象となっており,従って関係国のあいだにおける管理協力の取り組みがそれらの湿地に有益であることを示している.
12.自国にある複数国にまたがる,あるいは国際的な湿地を識別し,それらの管理にあたって協力することが求められているのと同様に,締約国には,複数国にまたがる,あるいは国際的な河川流域ならびに沿岸系における同様の協力が期待されている.多国間の管理委員会を設立することは,河川流域がまたがる国々が考慮し精力的に追求しうるひとつの重要な概念である.その流域の一部をなしている湿地を含め,水資源の管理の国際協力の促進のために,このような機関が効果的であることは経験から明らかである.前節§2.1.1にも示したように,世界自然保護モニタリングセンターの報告「世界にある複数国にまたがる湿地と河川流域」がそのような河川流域を識別するための予備的な基盤を提供し,締約国がこのガイドラインの要素を実施することを支援している.この報告では,対象とした955のラムサール条約登録湿地のうちの267ヶ所(28%)が国際河川流域内にあることが示されている.
13.複数国にまたがる沿岸性湿地については,締約国は,既存の地域的な海域計画や沿岸帯を包含する大規模海洋生態系の概念の中での協力の枠組みを発展させることが求められる.地域的な海域計画は,条約や議定書を含む,協力のための法的枠組みを提供する.締約国はまた,主要な沿岸性湿地系(例えば,堡礁やマンゴローブ系,暗礁系,海藻系のひろがり)を大規模海洋生態系の概念のもとに管理することが奨励される.このような管理の取り組みのモデルのひとつにオーストラリアのグレートバリアーリーフが挙げられる.そこは複数国にまたがる湿地でも(ラムサール条約登録湿地でも)ないが,賢明な利用を実行しているすばらしい例証であり,複数国にまたがる沿岸性湿地の管理に責任を負う締約国は考慮すべきものである.このモデルは,暗礁系へ影響を及ぼしうる一帯へ水が流れこむ河川系の管理を考え合わし,それらによる潜在的な負の影響を取り除くように確保しようとしており,それはたいへん適切なことである.複数国にまたがる沿岸性湿地系においても重要な考慮である.
14.河川流域管理委員会や沿岸性湿地系のための同等の協力機構の設立には,所要の財源とともに,専門家や公平な支援が必要なこともある.既存の組織より専門的技術が提供されることもありえ,また必要な場合あるいは状況に応じて,ラムサール条約がそれら組織の参加を促すべきであろう.締約国は,自主的な手はずを新たに整えるかわりに,他の目的のために設立された組織あるいは他の国際的・地域的協定のために設立された組織などの既存のものを利用することもできるだろう.援助機関においてもまた,河川流域管理や沿岸管理のための委員会を設立・運営することが,持続可能な発展のためのプログラムにおける優先事項であることを認識する必要がある.
セクションA
複数国にまたがる湿地と河川流域の管理に関するガイドライン
A1.締約国は,隣接する管轄国と自国とにまたがる湿地系の全てを把握し,そのような湿地の二国間あるいは多国間での管理計画を開発し実施することに公式の共同管理の取り決めあるいはに共同作業のような活動を通して,その管理に隣接国と協力することが奨励される.
A2.同様に複数国にまたがるあるいは国際的な河川流域や沿岸系においても,二国間あるいは多国間の管理委員会の設立を通して同様の協力関係が期待される.
A3.締約国は,「地域海域計画」や他の適切な国際的並びに地域的条約と緊密に取組み,また,ラムサール条約の賢明な利用原則を促進し,複数国にまたがる河川流域や沿岸系における公正なそして持続可能な管理制度を確立することが奨励される.
15.ラムサール条約におけるいわゆる複数国のあいだを行き来する種の管理における国際協力は,そのはじまりからの優先事項である.実際,ラムサールのような条約を策定し発効させた国々の動機は,渡り性水鳥の保全のための国際協力を促進しようという願いによるところが大きかった.こんにちでも,条約はこの目的の側面もたいへん協力に推進し続けており,渡り性の種に関する知識が増進するにつれ,複数国の間を行き来する種の管理に対してよりいっそう戦略的な取り組みを進めなければならない.渡り性の種の保全に欠かせない湿地は必ずしも広大なものではなく,小さな湿地でも渡りの経路の必須要素となっているものがたくさんあり,そしてそれらが集合的に生物多様性の保全に重要なものであることを認識しておくことが重要である.また,すべての複数国のあいだを行き来する種が渡り性ではないことも理解しておく必要がある.生息範囲が限られている一方, 複数国にまたがる湿地や隣接している国々の範囲内に見られるものなどで,渡り性ではない種がある.このような種に対しては,前節§2.1を通して奨励されるような,このような湿地の管理における協力が決定的である.
16.ラムサール条約とボン条約(移動性の野生動物種の保全に関する条約)は親密な関係にあることを認め,ふたつの条約の合意書がむすばれている.このもとに,ボン条約がその生息範囲の国々のあいだでむすぶ多国間協定をとおしてその保護を進めようと努力する絶滅のおそれのある渡り性の種にとって重要な生息環境が保護され適切に管理されることを見届けることがラムサール条約の課題となっている.新たに組織化された目標をもって改訂された国際的に重要な湿地選定のためのラムサール基準(決議Ⅶ.11)は,ラムサール条約登録湿地リストに関するビジョンの基本要素のひとつとして,いまやこのことに明確に焦点を当てている.
17.種の分布や生物学の理解が深まるとともに,複数国のあいだを行き来する種は顕著な渡りを示す水鳥だけではないことが認識されるようになってきている.沿岸性湿地環境においては,ウミガメ類やいくつかの魚類群のような多くの移動性の種がある.ボン条約とのパートナーシップのもとに,いまやラムサール条約は,従来からのクライアントである水鳥とともに,これらの種にも注意を振り向けなければならない.
18.ラムサール条約やボン条約の構築を動機づけたまさしくその論理が,「北米ガンカモ類保全計画1986」の構築にまた活躍した.この計画は(1994年改訂時に)カナダ,米国,およびメキシコの3か国政府のあいだで締結された協定である.この計画を通じて,北米全域でガンカモ類が依存する湿地環境を守り,また復元することによって,その個体群を回復させ保護することを3か国が共同で追求している.ラムサール条約と同様に,この計画のはじめから国際協力は優先事項であった.そして,ジョイントベンチャーとよばれる共同事業での国際協力を達成するための保全活動パートナーシップこそ,この計画が他に類を見ない折り紙つきの証しである.保全のための景観レベルの取り組みならびにパートナーシップの取り組みの両方をこれら3か国に奨励することによって,この計画は幅広い範囲の湿地依存性の種に長期的な利益を与えるだけでなく,世界の他の地域で応用されうる国際協力のモデルを提供している.アジア太平洋地域の渡り性水鳥の保全は,「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略:1996−2000」のもとに,シギチドリ類,ツル類,ガンカモ類の重要生息地ネットワークの設立を通して推進されている(勧告6.4参照).また,「西半球シギチドリ類保護区ネットワーク」が,各湿地での地元のパートナーシップを築くことで,アメリカ地域のシギチドリ類の保全の推進に成果をあげている.
19.渡り性水鳥についてラムサール条約は,渡りの経路の一部をなす重要な湿地環境が認識されてとわに適切に管理されるように見届ける責任を,国際協力の一部として担っている.ラムサール条約の国際的に重要な湿地の登録簿は,この最終目標に向かって条約が活用しうるツールとなっている.締約国が,登録簿に掲げる湿地を選定するための基準のうちの水鳥に関するものを満たすすべての湿地を識別し登録することがまず第一であることはもちろんのことである.その湿地の管理計画の策定とその実施をもって,条約はこれらの種の保護に対する地球的な努力に十分に貢献できることになる.重要湿地(生息地)ネットワークの概念(§2.4.3節参照)は条約がより強力に推進すべきもののひとつである.これは,各地の湿地の管理者が情報を共有し,また戦略的な保全の目標の設定を単に個別の湿地レベルにとどめることなく促進できるように,管理者を連携させることができる.
20.複数国にまたがる湿地に依存する種に関する本節の初めに述べたように,いまや,ラムサール条約は水鳥だけでなくより幅広い種の生息環境である湿地の保護と管理に積極的な役割を担うことが当然のことと認識されている.ボン条約のもとに,たとえばウミガメ類のような種群の保全のための多国間協定の構築が進められている.これに対してもやはり,それらにとって重要な生息環境を国際的に重要な湿地に指定したり,その生息地ネットワークを奨励したりすることを通じてラムサール条約が貢献することができる.前述の渡り性水鳥(§2.2.1節参照)に加えて,条約の魚類に関する登録湿地選定基準は,締約国がその移動経路上の重要な生息範囲を登録し適切に管理することによる共同行動のひとつの方法を提供している.
セクションB
複数国にまたがる湿地に依存する種に関するガイドライン
B1.締約国は,まず水鳥に関する登録湿地選定基準を満たすすべての湿地を識別して登録し,そしてそれらの湿地の管理計画の策定とその実施を進める.本ガイドラインの文脈にしたがい,この点は渡りの経路上や複数国にまたがる湿地に対して特に適用される.同様に複数の締約国のあいだを行き来するその他の湿地依存性の種(例えば魚類)に対しても,それらにとって重要な湿地環境を登録し管理することが,国際協力の見地からみたひとつの責務である.
B2.複数国のあいだを行き来する種のための重要湿地(生息地)ネットワークの概念は,情報を共有し必要に応じて技術的ならびに財政的支援を得ることができるようにそれらの湿地の管理者を連携することをめざして,条約がより強力に推進すべきものである.湿地ネットワーク全体にとっての,ならびにその湿地が支えている種の個体群にとっての戦略的な保全目標の設定することが重要である.締約国は,関係する国際的ネットワーク(東アジア−オーストラリア地域シギチドリ類重要生息地ネットワーク,北東アジア地域ツル類重要生息地ネットワーク,東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク,西半球シギチドリ類保護区ネットワーク)への湿地の登録を検討すべきである.
B3.条約はまた,湿地依存性の種についてのボン条約からの助言を求め,これらの種の保全のための多国間協定の構築を奨励するその努力を支援する.
B4.締約国は,湿地依存性の種の保全のための多国間協定を構築する際に,たとえば「北米ガンカモ類保全計画」や「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略:1996−2000」といった地域的モデルを吟味し,適切ならば採択することが求められる.「北米ガンカモ類保全計画」や「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略:1996−2000」が行政機関や非政府機関,民間企業などすべてのレベルを参集しているようなパートナーシップの取り組みを,これらの協定が採用することが理想的である.
21.1996年に採択された「ラムサール条約1997−2002年戦略計画」は,その実施目標7.2において,国際的な或いは地域的な環境に関する条約や機関との国際協力に関する方向性を提供している.これらの条約や機関と共通の目標に向かって進むために互いの協力や共同作業を築き上げることがラムサール条約にとっての優先事項であるということが,この項目によって,本質的に規定されている.ラムサール条約はまた,数々の非政府組織と独得なパートナーシップを結んでいる(バードライフ・インターナショナル,IUCN−国際自然保護連合,世界自然保護基金−WWF,国際湿地保全連合).そして,決議Ⅶ.3によって,それを拡張することを考慮に入れようとしている.このような国際的パートナーとの協力関係は,世界レベルから地元レベルまでのすべてにおいて,条約の実施を引き続き加速させるであろう.
22.「ラムサール条約1997−2002年戦略計画」の実施目標7.2及びは決議Ⅶ.4が,生物多様性条約及び,世界遺産条約,人と生物圏プログラム,ボン条約(上記§2.2節参照),ワシントン条約(下記§2.6.2節参照),気候変動に関する国際連合枠組み条約,並びに砂漠化防止条約との協力関係の発展させることを言及している.ラムサール条約は,生物多様性条約との協力の覚書と共同作業計画を結んでいる.共同作業計画には生物多様性条約における湿地保全にかかる課題においてラムサール条約が先導的パートナーとしての役割を担うこととしている.上に記したようにボン条約とのあいだにも協力の覚書が交わされ,またこれらのガイドライン(上記§2.2節参照)のもとに共同行動を通してこの協定はより強化されるであろう.1998年12月には砂漠化防止条約との協力の覚書が,また1999年5月には世界遺産条約との覚書が締結された.ラムサール条約は他の国際条約とも同様の取り決めを築き,それを通じて共同作業計画をつくりあげてゆく.このガイドラインの§2.6.2節は,ワシントン条約との近い将来の協力体制の基礎を提供するものである.
23.国レベルでは,締約国はこれらの種々の条約の実施を可能な限り調和し統合して進めることを確保することが必要である.国内での行動のほかに,各国は国際協力の見地からの責務を負い,これらの予測に応じてその対応を整合させることをめざすべきであろう.このことは,多かれ少なかれ,ここに提案される行動の全てについて適用される.そのように統合的なアプローチを採用することはより費用効果があるに違いない.
24.国際的な環境条約と同様に,地域的な条約や協定,並びに団体とのパートナーシップを築くこともラムサール条約にとって必要である.条約の「戦略計画」行動7.2.8は,いくつかの地域条約,協定,及び団体とパートナーシップを結ぶ行動が優先事項であることを示している.「南太平洋地域環境プログラム」,「ヨーロッパの野生生物及び自然生息地に関するベルン条約」,「アマゾン川協力条約」がそのなかに含まれる.このような地域的な取組みとのパートナーシップは,湿地の保全と賢明な利用を含む環境にかかる挑戦へのより結束した対応をはぐくむであろう.湿地の保全と賢明な利用のための協力関係を助長することに大きく貢献した例として,地中海沿岸の国々が参加する「地中海湿地フォーラム」が例としてあげられる(決議Ⅶ.22).これは条約が推進すべきもののひとつのモデルである.
25.ラムサール条約がよりいっそう緊密に共働すべき国際的プログラムや団体は多数存在する.国連やその機関(持続可能な発展委員会,UNDP,UNEP,WHOなど)の後援のもとに運営されているものもあり,条約と国連の関係プログラムとのあいだで正式な協力の覚書を結ぶことが追求されるであろう.§2.5節において条約と援助機関とのあいだの関係について詳細に検討する.その他にも,「国際流水域団体ネットワーク」や「地球河川環境教育ネットワーク」といった団体やプログラムは,ラムサール条約の締約国に対して専門的技術を提供できるものであり,これらと共働するパートナーシップを結ぶことが有利であることは明らかであろう.上述のように,条約の国際団体パートナー(決議Ⅶ.3)との協力行動の継続はまた,決定的に重要なものであり,これらの団体とのパートナーシップを高める努力はすべてのレベルで追求されなければならない.ラムサール条約は,(生物多様性条約,ボン条約,砂漠化防止条約及び世界遺産条約と同様に)その他の適切な国際的並びに地域的条約,協定及びプログラムとのパートナーシップを構築し,それを通じて共同作業プログラムを策定し実施し続けるであろう.
セクションC
国際的或いは地域的な環境条約や機関とのパートナーシップに関するガイドライン
C1.国レベルでは,締約国は種々の環境条約の実施を可能な限り調和して進めることを確保する.そうすることによって,各国は国際的並びに地域的な協力関係の責務を果たすことへのより統合的なアプローチをとることができるであろう.
C2.ラムサール条約と国連とのあいだの正式な協力の覚書を結ぶことが追求される.また条約事務局と各国の条約担当政府機関は,条約の国際団体パートナー並びに「国際流水域団体ネットワーク」や「地球河川環境教育ネットワーク」などのその他の関係団体とのパートナーシップを追及するように要請される.
26.湿地管理の知識や専門技術はどこの国にもある.世代を越えて湿地生態系に依存し何世紀にも渡って生活を支えてきた賢明な利用方法を応用してきた先住民にも見られる.湿地とともに暮らす人々が,時を越え同じ生態系の一員として,感情移入してしまうくらい理解し,また湿地の価値を敬うかたちで習得された不文律もある.そして,調査や新たな技術の発展によって得られた最新の理解もある.これは実践的な調査,高性能の設備,あるいは低コストの技術がもしれないし,あるいはこんにち湿地管理者が取り入れなければならないさまざまな分野の新しい科学の適用を通じたより良い管理の実践を促進することかもしれない.
27.ラムサール条約がその地球的な使命を達成するためのかぎは,ひとつにこの知識資源の共有をいかにして増進するか,その方法を見つけることである.ラムサール条約普及啓発プログラム(決議Ⅶ.9)を通じて,湿地の湿地広報教育普及啓発担当窓口が任命され,また同様に,ラムサール条約科学技術検討委員会担当窓口も各国に設置されることとなっている(決議Ⅶ.2).知識の共有をめざして,これらの担当窓口が,専門的技術の地球規模でのネットワークを築き,これらふたつの分野(伝統的な現地での知識や現在進行中の共同研究の成果)における国内の資源を総論することが期待される.これらの担当窓口や条約担当政府機関ならびに条約事務局が,他の条約の実施にかかわる各機関・窓口と,知識の共有を加速できるように共働しうるすべての機会をとらえることも重要である.世界のいくつかの地域では,国家的あるいは地域的な情報収集機関の概念もそのような支援の増加をもたらす.
28.条約の全ての側面の実施ならびに湿地管理にたずさわる人々への研修は,まだまだ優先事項である.地球規模で見てみれば,これらのさまざまな分野の研修を一連の機関が提供している.条約が取り組むべきは,必要とし望んでいる人々へ適切な種類の研修の機会を届けることである.条約事務局は情報収集を開始しており,「湿地管理研修機会目録」として条約のウェブサイトで提供している.しかし,これは研修プログラムに参加する資金も,緊急な必要性がある締約国の湿地で研修プログラムを開く資金を提供しているわけでもない.いまひとつ不十分な点は,国レベル,地方レベル,また現地レベルで必要としている研修の優先順位を決定するような分析を行なっている国がほとんどないことである.このような研修の必要性の吟味をしなければ,たとえ研修の機会があったにしても,その妥当性を欠く危険性がある.
29.アジア太平洋地域において条約のすべての側面にたずさわる人々への研修の共有と提供の必要があり,既存の国際的なしくみができていないことが認められるので,新熱帯区における「未来の湿地イニシアチブ」をもとにした研修の新たな取り組みのモデルをアジア太平洋地域においてもつくりあげるべきである.このような取り組みには,地域的な湿地研修調整センターを設立することが役立つであろう.
30.この「ラムサール条約の国際協力のためのガイドライン」の優先事項のひとつは,研修のための資源を結集することである.湿地の姉妹提携や重要湿地(生息地)ネットワーク(後述の§2.4.3節参照)は,研修資源を結集するひとつの方法となりうる.二国間あるいは多国間で援助国に直接働きかけることももうひとつの方法である(§2.5節参照).ラムサール条約小規模助成基金も研修を優先事項にしており,アメリカ合衆国政府の惜しみない支援によって「未来の湿地イニシアチブ」を実施しており,それは新熱帯区における研修と能力増強プログラムに焦点を当てている.
31.ラムサール条約においては,異なる締約国の登録湿地のあいだで姉妹提携するというコンセプトが,意見交換や情報共有を進める道筋として奨励される.第7回締約国会議に提出された国別報告書によると,それまでに25までの姉妹提携が結ばれていた.それと同時に,移動性の種が利用する湿地を連携する重要生息地ネットワークのコンセプトもラムサール条約のもとに推奨されるものである.
32.現在進められている数多くの姉妹提携のための取組みから示唆されるように,条約下の国際協力の推進のツールとしてこのコンセプトが果たし得る可能性の全てが明らかにはなっているわけではない.このガイドラインを通じてそれを明らかにすることが優先事項である.このような取組みでは,情報や専門技術,資金などを関係湿地間で共有するという目的が伴うように意図された姉妹提携やネットワーク形成を優先して,締約国は追求すべきである.このような機構は,種や湿地管理に関しての知識を共有する機会といった研修目的の人事交流の枠組みを提供し得るものである.
33.姉妹提携並びに重要生息地ネットワークはまた,特に南北の湿地間で,発展のための支援を直接提供するための道筋をつけ得るものである.
セクションD
専門技術や情報の共有に関するガイドライン
D1.知識(伝統的な,先住民の,及び最新の技術や手法など)を締約国のあいだで共有できるように,条約は,湿地広報教育普及啓発担当窓口や科学技術検討委員会担当窓口を通じて,その努力を増大する.担当窓口は,これらの情報を速やかに収集したり広めることができるように,国レベルでの専門家のネットワークを築き上げることが優先事項である.
D2.条約の実施並びに湿地管理の全ての側面でその任務をもつ担当者を研修させることは引き続き条約の最優先事項のひとつである.そのような研修は情報の共有(上記参照)を通して促進され,発展支援機関並びに小規模助成基金や新熱帯区の「未来の湿地イニシアチブ」のような支援プログラムからの資金を結集し,また湿地姉妹提携やネットワーク形成を通じて,促進されるべきである.他の締約国は成果があがっている既存の湿地関係者研修プログラムの例を見習うことが要請される.
D3.研修活動を実施する前に必要なことは,国レベル,地方レベル,地元レベルでの研修の必要性を事前評価し,適切な研修となることを確保することである.
D4.締約国は,湿地管理者のあいだでの情報共有を促進し,研修の機会を提供し,また適切な場合に発展支援を監督するための道筋として,湿地姉妹提携やネットワーク形成を優先事項とするよう要請される.
34.湿地の保全と賢明な利用を援助する国際的な支援を結集することが重要であること,ならびにそれが条約第5条のもとの国際協力の中心的な要素をなすということを,締約国はずっと認識してきた.第1回締約国会議は,勧告1.2において,途上国に対しては援助の要請やプログラムのどのようなものにおいても保全の手段によりいっそうの注意を払うように,いっぽう先進国や国際機関に対しては開発援助政策においてそのような要請に対して相応の注意を払うよう
に求めている.その後の締約国会議は,湿地保全への資金を増強すること,開発援助資金の管理と規制を改善するように求める決議や勧告を全部で9つ採択している(§1.2節参照).
35.条約の「1997−2002年戦略計画」はその実施目標7.2,7.3,7.4において,他の条約や政府機関並びに非政府機関と協力する湿地の保全と賢明な利用の取組みに対して,国際協力活動を増強し資金援助を結集するための更なる方向性を提供している.
36.二国間及び多国間の開発援助機関のいくつもが湿地の保全と賢明な利用に対する援助は過去5年間に着実に増加してきた.これは湿地生態系が提供する機能や価値,恩恵,また食物や水の保障,貧困の軽減,並びに生物多様性の保全に対する湿地生態系の重要性に対する認識が高まってきた結果である.にもかかわらず,同時期にその予算や対象とする地理的範囲や主題範囲を有意に減少させた援助機関も存在することが憂慮される.
37.環境的,経済的,並びに社会的見地から湿地の重要性を認識されれば,この国際協力のガイドラインの下の優先事項のひとつは,締約国並びにその二国間開発援助機関が,既存の環境に関する基金やその他の基金を通して,湿地の保全と賢明な利用のための資金配分を増加させることである.同時に,湿地保全のための活動を長期間に援助できるような画期的な機構,例えば信託基金や利用者負担金制度などを途上国に設立することについても,これらの機関が調査し考慮することが奨励される.
38.多国間の支援に関しては,ラムサール決議Ⅵ.10が,湿地に関する事項が地球環境ファシリティーの主要分野に関連していることを留意し,地球環境ファシリティーとの協力を拡大し深化させることを要請している.続いて1998年の生物多様性条約第4回締約国会議は,決定Ⅳ/4において,内水面生態系の生物多様性の保全と持続可能な利用に対して締約国が地球環境ファシリティーに援助を求めるように要請している.対象となる締約国は,この生物多様性条約の決定を詳細に精査して,地球環境ファシリティーの考慮を求めるべく適当な提案を準備するべきである.
39.締約国並びに開発援助機関はまた,「ラムサール条約湿地保全及び賢明な利用のための小規模助成基金」の業務を援助するために,長期的に資金を委託することも奨励される.小規模助成基金の評価(決議Ⅶ.5)は,その価値と有効性を示し,しかし適切なプロジェクトであるにもかかわらず資金の不足から支援することができないものが毎年いくつもあることを明らかにしている.
40.「1997−2002年戦略計画」の行動7.3.3において,締約国は,途上国並びに市場経済移行国に条約の責務を満たすような支援がどのような水準及びタイプで提供され,それが如何に効果的であるかということを締約国会議に示すことができるように,自国の二国間援助機関に対して,その支出を適切にモニタリングする体制を備えることを確保するべきであるとされている.このために,開発援助機関のプロジェクトモニタリングデータベースに,それが無い場合は,湿地保全にかかる報告部門を盛り込むことが理想的であろう.
41.資金を結集することとは別に,開発援助機関が各々の分野において及びより広範な戦略や政策において湿地に関係するプロジェクトを考慮する責任についても,過去の締約国会議は考慮している.勧告3.4は,開発援助機関に持続可能な利用や賢明な管理,湿地の保全に向けた首尾一貫した政策を定式化して採択すること;そしてこのような政策を自らの活動の全てに対して統合することが確保できるような特別なプログラムをつくること
を要請した.
42.この勧告3.4のいくつかの要素については,例えば環境影響評価など,その実行が有意に進展したことは明らかであるが,まだ充分には実行されていない側面が残されている.開発援助機関の分野別戦略や一般的プログラムにおいて湿地問題を適切に考慮することを確保することは引き続き優先事項である.農業や水産業,水資源,林業,運輸並びに発電の分野での活動は,湿地に影響を与える可能性を潜在的にもっており,これらの分野への資金配分を方向づける戦略や政策は,ラムサール条約の賢明な利用原則並びにこの国際協力のガイドラインと整合させることが欠かせない.
43.特に,締約国は開発援助機関とともに,勧告3.4並びに5.5で要請された行動を確保するべきである.それはすなわちその政策を定期的に評価する適切な手段をとること
(勧告3.4)及び条約が提供する責務と機会に照らして自らの開発協力政策を見直し,途上国が条約の責務を満たすことができるように支援することを目指した国ごとのプロジェクトを援助すること
(勧告5.5)である.この点については,条約が推進する湿地保全と賢明な利用原則が農業や水産業,水資源,林業,運輸,発電の分野にかかる政策にどの程度適切に考慮されているかを見極め,またこれらの政策に対して必要な導入或いは改正を追求するように,締約国は見直しを行うべきである.
44.締約国はまた,このような自国の開発援助機関の分野別戦略や政策の見直しに当たっては,持続可能な林業や水産業,湿地の復元,エコツアリズム,構造物を伴わない洪水調節などのように環境的に安全な開発行為を通じて条約の賢明な利用原則を適用したプロジェクトを優先的に考慮するように奨励することを追求すべきである.
45.条約の第3条は,湿地の保全を促進するため計画を作成し、実施する
ことを求めている.「賢明な利用の概念実施のためのガイドライン」並びに関連する締約国会議の決議を通じて,国家湿地政策或いは戦略の策定が国家の保全と開発との調整に湿地を統合させるためのおよそ最良の方法であると認識されている(「国家湿地政策の策定と実施のためのガイドライン」に関する決議Ⅶ.6).
46.同様に勧告3.4は,開発援助機関が借手或いは受手の政府が湿地の保全と賢明な利用のための国家政策を策定し採択するように影響を行使する
ことを求めており,このことは依然として優先事項である.湿地政策の策定はまた,より広範囲な社会問題並びに経済発展にかかる国家的計画の統合的な一部分であって然るべきであり,締約国はそのような取組みを推進することが奨励される.このためには,能力増強の方法によって支援される必要があるかもしれないし,あるいは各国の分野別開発政策や全体的な経済発展計画に湿地保全と賢明な利用の考慮を盛り込むための直接的な支援が必要かもしれない.
47.開発援助機関が援助する湿地関連プロジェクトの数を増加させるための機構のひとつは,湿地が提供する数多くの機能と恩恵について,これら機関の計画立案者や政策決定者の認識を高めることである.条約の「普及啓発プログラム」(決議Ⅶ.9)はこれらの担当者をその優先的対象と識別しており,締約国は自国の開発援助機関の重要な意思決定者に対する適切な研修と参考資料を提供する努力を確保するよう求められている.
48.例えばOECD援助と環境に関する指針第9号:「熱帯及び亜熱帯の湿地保全と持続的な利用を改善するための開発機関用ガイドライン」のようにこの分野における支援策が準備されつつあるが,以前の締約国会議の決定に考慮されている数々の行動を通してこれらの機関における一般的な認識と理解の向上をはかることは引き続き必要である.奨励される行動には,湿地に影響を及ぼすプロジェクトを策定し実施する全ての部門における生態学的知識を強化するための
内部的及び外部の研修プログラム(勧告3.4),各国の条約担当政府機関との連携の強化(「戦略計画」行動7.4.2),並びに締約国の会合に出席する代表団の中に、開発援助の授受に責任を負う各省庁の代表を含めること
(勧告5.5)が含まれる.
49.プロジェクトの策定と実施の見地からみた被援助国の能力,並びに開発援助を求める際に湿地プロジェクトにどれだけ優先順位を与えようとする意思次第で,湿地関連のプロジェクトに対する開発援助の流れを結集できるかどうかがある程度は決まる.能力の問題は複合的であるのでケース・バイ・ケースで考慮しなければならない.それを制約するのは,人的資源の欠如,或いはプロジェクトを策定する際や援助機関に対応する際の経験の欠如のような要因によって決まるかもしれない.各国の政府内部において湿地関連プロジェクトに対して優先順位を与えることができないこともまた複合的な問題であり,意思決定者が湿地の真の価値を充分に認識していないこと,或いは国家湿地政策や国内ラムサール委員会などの統合された計画策定過程のような手段を通じて政府の業務の主流に湿地を位置づけるということができていないということが,それに関係しているかもしれない.
50.過去の締約国会議は,政策を実施するために国レベルで,またプロジェクトの対象地方の開発担当機関において,制度上の取組み及び生態学的技術を強化すること;及び,プロジェクトを実施するレベルでの担当者を研修教育すること
を開発援助機関が追求すべきである(勧告3.4)ということに合意している.受給資格のある国は,必要な技術的な並びにプロジェクト策定技能を自国の担当者に提供できるような研修の機会を追求すべきである.この点については本ガイドラインの§2.4節が関係している.被援助国はまた,国家湿地政策(或いは同等のもの)を策定するための資金,また条約の「普及啓発プログラム」(決議Ⅶ.9)に一致させて国内において湿地に関する広報教育普及啓発プログラムを実施するための資金を援助機関に求めることが更に要請される.これらふたつの方策はともに,湿地関連プロジェクトに資金援助の優先順位を与えることに役立つに違いない.
51.湿地保全とその賢明な利用は多くの途上国において引き続きその重要性を高めつつあるため,開発機関は個々の活動が結びついて湿地に負の影響を与えてしまうことがないことを確保するようにそのプログラムを国際的レベルにおいて調整する
べきであり(勧告3.4),また他の開発機関とも経験を共有し,被援助国における活動が重複することを避けるように協力関係を高めるべきである.
52.開発援助機関とその国の条約の担当政府機関との協力関係を増強することは,上記§2.5.4節において開発援助機関の能力向上の重要な側面として認識され,また「1997−2002年戦略計画」行動7.4.2においても奨励されている.締約国は,開発援助機関と条約の担当政府機関とのあいだで協議するための公式の機構を開発すること,並びに国内ラムサール委員会が存在する場合は委員会に開発援助機関の代表が参加するように確保することが奨励される.締約国会議に出席する代表団の中に開発援助機関の代表を含めることもまた要請されている(勧告5.5).
セクションE
湿地の保全と賢明な利用を援助する国際的支援に関するガイドライン
E1.締約国,並びに特にその国の二国間開発援助機関が,湿地の保全と賢明な利用への資金配分を増加させることが引き続き条約の最優先事項である.
E2.二国間開発援助機関は,湿地の保全と賢明な利用のためのその他の奨励措置とともに,信託基金や利用者負担金制度などの画期的な機構を途上国に設立するための援助について,調査し考慮することが要請される.
E3.ラムサール条約と生物多様性条約の両方の締約国となっている国は,生物多様性条約の決定Ⅳ/4を精査し,適切な場合は内水面生態系の生物多様性の保全と持続可能な利用に関する適切な提案に対する地球環境ファシリティーの資金援助を追求するということに関するその指示に対応することが要請される.
E4.締約国並びに開発援助機関は,「ラムサール条約湿地保全及び賢明な利用のための小規模助成基金」(決議Ⅶ.5)の業務に援助するように長期的に資金を委託することが求められる.
E5.締約国はまた,途上国に条約の責務を満たすような支援がどのような水準及びタイプで提供され,それが如何に効果的であるかということを第8回締約国会議に示すことができるように,自国の二国間援助機関に対してその支出を適切にモニタリングする体制を備えることを確保するべきである.
E6.湿地問題が自国の開発援助機関の分野別戦略や一般的プログラムに適切に考慮されることを確保するために,ラムサール条約の賢明な利用原則が農業や水産業,水資源,林業,運輸,発電の分野にかかる政策にどの程度適切に考慮されているかを見極め,またこれらの政策に対して必要な追加或いは改正を追求するように,締約国は見直しを行うことが奨励される.
E7.自国の二国間支援プログラムを通して,並びに多国間のプログラムに参加することを通じて,締約国はまた,湿地における環境的に安全な開発行為を通じて条約の賢明な利用原則を適用したプロジェクトを援助すべきである.
E8.「賢明な利用の概念実施のためのガイドライン」に認識されているように,締約国は条約を実施するための適切な国家政策の枠組みを準備することが重要である.また,このことは資金援助を追求する国々にとって引き続き優先事項である.湿地政策の策定はまた,より広範囲な社会問題並びに経済発展にかかる国家的計画の統合的な一部分であって然るべきである(決議Ⅶ.6).
E9.条約の「普及啓発プログラム」(決議Ⅶ.9)は開発援助機関の重要な意思決定者をその優先的対象グループと識別しており,締約国はこれら担当者に対する適切な研修と参考資料を提供する努力を確保するよう要請される.
E10.開発援助機関の職員における湿地の機能と価値に対する一般的な認識と理解の向上をはかることは引き続き必要である.奨励される行動には,内部的及び外部の研修プログラム,各国の条約担当政府機関との連携の強化,並びに締約国の会合に出席する代表団の中に開発援助機関の代表を含めることが含まれる.
E11.締約国は政策を実施するために国レベルで,またプロジェクトの対象地方の開発担当機関において,制度上の取組み及び生態学的技術を強化すること;及び,プロジェクトを実施するレベルでの担当者を研修教育すること
を開発援助機関が追求すべきであるということに合意した勧告3.4を継続して実施すべきである.
E12.湿地関連のプロジェクトへの資金の流れの水準を高めるために,受給資格のある国は適切ならば,必要な技術的な並びにプロジェクト策定技能を自国の担当者に提供できるような研修の機会を追求することが奨励される.
E13.被援助国は,国家湿地政策(或いは同等のもの)を策定するための資金,また条約の「普及啓発プログラム」(決議Ⅶ.9)に一致させて国内において湿地に関する広報教育普及啓発プログラムを実施するための資金を援助機関に求めることが要請される.これらふたつの方策はともに,湿地関連プロジェクトに資金援助の優先順位を与えることに役立つに違いない.
E14.開発援助機関は個々の活動が結びついて湿地に負の影響を与えてしまうことがないことを確保するようにそのプログラムを国際的レベルにおいて調整する
べきであり(勧告3.4),また他の開発機関とも経験を共有し,被援助国における活動が重複することを避けるように協力関係を高めるべきである.
E15.締約国は,開発援助機関と条約の担当政府機関とのあいだで協議するための公式の機構を開発すること,並びに国内ラムサール委員会が存在する場合は委員会に開発援助機関の代表が参加するように確保することが奨励される.
53.ラムサール条約は湿地の保全と賢明な(持続可能な)利用を推進しており,これには湿地から得られる動植物産品の収穫も含まれる.登録湿地個々の規模では,このような収穫は利害関係者と緊密に協議して策定された管理計画によって規制されるべきものである(勧告6.13).条約第3条1はまたその領域内の湿地をできる限り適正に利用することを促進する
ことを締約国に要請している.
54.条約のもとでの国際協力の見地から,湿地由来の動植物産品の国境を越える取引は従ってまた,その収穫が持続可能な方法で行われるということを確保するように規制されるべきである.このように登録湿地で収穫する場合は,締約国はその収穫が当該湿地の生態学的特徴をなんら脅かさず或いは変化させないということを確保するという明確な責務がある.このことは二国あるいはそれ以上の締約国の境界をまたぐ登録湿地について特に適用される.
55.湿地は生産性の高い生態系であるがゆえに常にその自然生産物が利用されてきた.その賢明な利用原則を通して条約は,そのような収穫が今後も継続されるものであると認識し,その湿地資源が将来の世代を養うことができるような方法で収穫が行われることを確保することを求めている.湿地由来の動植物産品の収穫が持続可能であることを締約国が確保するためにはいくつもの方法がある.保護種あるいは絶滅危惧種の取引のような特別な場合について下に考慮するが,その他の種について締約国は国際取引を監視し,また湿地由来の種が含まれる場合には当該の収穫が生物学的に持続可能であることを要求する所要の法的及び機構的,行政的手法を実施することが奨励される.これらの生産物の取引から得られた資金を湿地の保全と賢明な利用に向けるといった機構を築くことが望ましい場合もあろう.これらの生産物が得られる湿地の管理計画は,科学的な種の管理計画とともに,強く奨励されるものでもある.
56.ラムサール条約の締約国はまた,湿地由来の動植物産品が他の締約国から自らの領域に輸入される場合に,絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引に関する条約(ワシントン条約,CITES;下記参照)にリストアップされているものの場合は特に,それが持続可能に収穫されたものであることを確かめる責任を有す.ある締約国の国民が他の締約国の領域内で密猟を行うことは,条約第5条に逆行するものである.
57.この分野に関しては数々の複合的な問題がありここでは詳しくは扱わない.例えば,遺伝資源の利用や所有,生物学的予測などである.これらの問題について締約国は,湿地に由来する産品の国際取引の問題に対する適切な国家的対応を策定する際に関連する自国内の担当窓口と協議することが要請される.
58.ラムサール条約の締約国がワシントン条約の締約国でもある場合,当該国は絶滅のおそれのある或いは潜在的に絶滅のおそれのある動植物ならびにそれらからの派生物の国際取引を規制し監視することを確保する責任を有す.このことを湿地に由来する種に適用する場合は,両者に加盟する締約国は,当該の収穫が持続可能であることとワシントン条約の規則に従っていることとを保証する必要な行動をとるという二重の責務を負う.ラムサール条約の湿地の定義のもとに,ワニ類,(なんびとも商業取引はできないが)淡水亀類とウミガメ類,魚類,サンゴ類などの動物種,及び薬用に供する多数の湿地由来の植物種や泥炭地森林の材木のいくつかがこの対象となる.
59.ワシントン条約附属書Ⅰの掲載種については一切の国際取引が認められず,附属書Ⅱのものについて締約国は科学的な種の管理計画の準備とそれらの産品の取引について法的並びに行政的手段を通じて規制し監視することが必要である.
セクションF
湿地に由来する産品の取引に関するガイドライン
F1.締約国は,湿地由来の動植物産品の国際取引の全ての輸出入を見直し,収穫が持続可能であることを要求しまたワシントン条約並びに関係する地元の規則と国際協定に従う必要な法的並びに機構的,行政的手法を適切に実施することが要請される.
F2.ワシントン条約の締約国でもあるラムサール条約の締約国は,湿地に由来する産品の国際取引を見直し,必要に応じてワシントン条約附属書へのこれらの種の掲載を追求する.
F3.ワシントン条約の附属書に既に掲載されている湿地由来の種については,締約国は,当該種にかかるワシントン条約の責務を満たすように油断なく監視し,違反行為についてはラムサール条約事務局へも報告するべきである.
F4.このような種がラムサール登録湿地及びその他の湿地で収穫される場合には,締約国は,可能ならばワシントン条約が奨励する種の管理計画にそれを統合するかたちで,それらの湿地の管理計画の策定にそのような活動を考慮することが奨励される.
F5.ラムサール条約の担当政府機関は,自国の(科学的な担当と管理担当の両方の)ワシントン条約の担当政府機関と協力的業務の取組みを確立し,上記の行動を協力して実施することを追求すべきである.
F6.湿地に由来する産品の国際取引の問題に対する適切な国家的対応を策定する際には,ワシントン条約の担当政府機関との協議に加えて,ラムサール条約の担当政府機関は,関係する生物多様性条約の担当窓口,並びに特に生物取引,遺伝資源の持続可能な利用及び生物学的予測などの問題に関係する担当者と協議することが要請される.
F7.「国家湿地政策の策定と実施のためのガイドライン」(決議Ⅶ.6)並びに「湿地の保全と賢明な利用を促進するための法制度の見直しに関するガイドライン」(決議Ⅶ.7)の採択に留意し,締約国はこれらの過程を通じて湿地に由来する産品の国際取引の問題を考慮することを確保するように要請される.
60.海外投資の規制は明らかに各国の主権であり,条約が尊重すべき自己決定権である.条約は,この国際協力のガイドラインを通じて投資を抑制したり経済発展を阻害したりしようとするものではない.ただ,支援しようとする締約国が,その条約の下の責務に逆行してしまうような海外投資による援助活動を避けることができるように助言を提供しようとするものである.また,利用する湿地資源の長期的な持続可能性に対してプラスの貢献を確保できるような方法で締約国が海外投資を規制する可能性について留意することも重要である(後述の§2.7.2節参照).
61.その他の場合もあるが,多くの国々において海外投資は法律によって密接に規制されている.湿地に影響を与える可能性のある行動を海外投資が援助する場合,締約国は明らかに,その行動が及ぼす潜在的な(環境的,経済的及び社会的)影響の厳格な事前評価を,国内における活動と同様に,要求する明確な責務を負う.
62.ラムサール条約のもとで,締約国は,開発提案による湿地の破壊或いは劣化を防ぐために機能し得るような適切な影響評価の実施が奨励される.このような措置がない場合には,その導入が最優先事項である.たとえ開発提案の全額が国内資金で賄われる場合,部分的に国内資金で賄われる場合,或いは全額海外投資による場合のどの場合でも,その開発提案を影響評価の対象とすることが,行政上また欠かせない.
63.いくつかの国々では,産業界の構成員がその海外投資活動にも適用する自主的行動規範を採択しているものもある.それは持続可能な発展のための世界産業協議会のような団体が推進しているものであり,過去に湿地を破壊するという評判を受けた分野によるこの責任ある姿勢を条約は強く是認し推進すべきである.締約国は,海外投資活動のこのような側面を大いに強調する必要があり,また投資者はこのような行動規範を持って生態学的に持続可能な開発活動を提唱することが信任されるうるものであると考える必要がある.すべての締約国が考慮できるように,このような行動規範のモデルを集めて広報することが条約事務局に求められる.
64.前述のように,海外投資者(および場合によっては国内の投資者)に,資源を長期的に持続可能な形で利用できるように計る活動を支援する環境債券や同様な他の寄付の支払を必要としている国々も現在ある.例えば,海外投資者による湿地関連の開発を承認するにあたっては,湿地管理者の研修や湿地の価値の普及啓発のためのセンターとして活用でき,またコミュニティにツアリズムなどによる地域経済効果を生むような教育施設を設立しその維持を補助することをその条件の一部とすることが考えられる.ただし,このような計画においては,海外投資者の現地代理人によってこのような条件をすり抜けてしまわないようにする適切な措置が必要である.
セクションG
海外投資にかかるガイドライン
G1.締約国は,開発提案による湿地の破壊や劣化を避けることができるように機能しうる適切な影響評価の実施を確保することが求められる.施行にあたっては,開発提案を,全分野の環境的,経済的,社会的に可能性のある影響(決議Ⅶ.16)を考慮する厳格な影響評価の対象とすることが欠かせない.
G2.海外投資者に対して,締約国は,それらの会社の開発行為が生態学的に持続可能であることを確保できるように設計された行動規範を促進し奨励することに努めるべきである.これを支援するために,条約事務局は行動規範の適切なモデルを集めて広報することが要求される.
G3.締約国はまた,開発の承認過程を点検し,湿地の長期的な持続可能性を確保して後世に伝えられるような湿地管理などの活動に使う資金が開発活動から得られるような機構の導入を考慮すべきである.
[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.19 Annex "Guidelines for international cooperation under the Ramsar Convention", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/key_guide_cooperate.htm.]
[和訳:宮林 泰彦,雁を保護する会,2001年7月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部●「渡り性水鳥」 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_guide_cooperate_j.htm
Last update: 2007/05/16, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).