
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
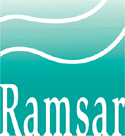
日本語訳:日本弁護士連合会,2002年[許可を得て再録].
英語 フランス語 スペイン語 (以上,条約事務局) PDF (536㎅)

(ラムサール条約決議Ⅶ.6にて採択)
主編者:Clayton Rubec、寄稿者:David Pritchard, Paul Mafabi, Nadra Nathai-Gyan, Bill Phillips, Maryse Mahy, Pauline Lynch-Stewart, Roberta Chew, Gilberto Cintron, Joseph Larson, Sundari Ramakrishna
Ⅰ.「湿地政策」への道をひらく
Ⅱ.国家湿地政策の策定
Ⅲ.政策文書の構成
Ⅳ.「政策」の実施
Ⅴ.文献
付属文書1:湿地政策策定のための優先事項
付属文書2:勧告6.9「国家湿地政策策定及び実施のための枠組み」
付属文書3:ラムサール条約締約国および地域による国家湿地政策と行動計画/戦略の要約
ラムサール条約 国家湿地政策指針
1.国家湿地政策はラムサール条約のワイズユース概念を実施する際に期待される行動の中でも、鍵となる要素である。しかしながら、湿地の保全と管理を推進するための国家政策の枠組みを定め、具体的に策定し、実施することは、この(イランのラムサールにおいて1971年に採択された)「湿地条約」の多くの締約国にとってはいまだに容易ではない目標である。こういった現状を打破するために、著者らは1996年3月オーストラリアのブリスベン市における第6回締約国会議で採択された勧告6.9に答えようとしてきた。この勧告は、締約国とラムサール事務局、その他の協力によって、国家湿地政策についての『枠組みとなる報告書』を準備することを求めたものである。
2.以下に提供する「国家湿地政策を策定し実施するためのガイドライン」は、湿地政策の策定に関する経験や専門知識をもつ政府あるいはNGO関係者から報告者を募り、共同作業によって準備されたである。執筆陣は、オーストラリア、カナダ、トリニダード=トバゴ、ウガンダ、米国のラムサール条約担当政府部局、そして非政府の組織(NGO)としてバードライフ・インターナショナル、米国マサチューセッツ大学、国際湿地保全連合よりなる。
3.主たる寄稿者として Clayton Rubec 氏(今回のプロジェクトの調整員であり主著者ともなっている)、Nadra Nathai-Gyan 女史、Paul Mafabi 氏、David Pritchard 氏、Bill Phillips 氏が参加しており、また、Roberta Chew 氏、Gilberto Cintron 氏、Joseph Larson 氏は米国での経験に基づいて事例を報告しており、Sundari Ramakrishna 女史はマレーシアにおける国家湿地政策策定当初の動きに基づいて報告をしている。条約事務局の Maryse Mahy 女史は特にヨーロッパにおける国家政策資料の多くを提供してくれた。カナダの Pauline Lynch-Stewart 女史は有益な提案と多くの章の草案を提供してくれた。条約の事務局長 Delmar Blasco 氏、Michael Smart 氏(前事務局次長)、北米湿地保全協議会(カナダ)の Ken Cox 氏、IUCN(国際自然保護連合)環境法センターの Lyle Glowka 氏その他の方々もまた、有益な助言及び当報告の推敲に協力してくれた。
4.著者らは、当報告において用いられているいくつかの用語や語法が、主として英連邦の行政システムから派生したものであること、そしてまた何人かの著者らの国レベルでの経験に基づいたものであることを認識している。読むにあたって他の行政システムに携わってきた方々には、意味を汲んで必要な場合には用語を置き換えるなどして適宜代用させていただきたい。
5.当報告は国家湿地政策の草案を書くためのモデルとなっているわけではないことを強調しておきたい。むしろ、著者達が直接経験してきた内容から観察出来た事柄をまとめたものである。著者らが最も有用だと感じた経験に基づいて、全体の概要をまとめあげることから着手した。いくつかの草案が1998年に作成され、南北アメリカ地域合同会議、アフリカ大陸、オセアニア、アジア地域といった締約国の地域会合の際に参加者からコメントをもらった。これらの会合は1999年5月に中米コスタリカの首都サンホセで開催された第7回締約国会議の準備会議としての役割をもち、締約国会議の専門会議Ⅱの中でガイドライン案は議論され、いくつかの改訂をされた上で最終的に採択された。
6.ガイドラインは湿地に関する国家政策や戦略を新たに策定しようとすでにしている、あるいは新たな策定を考慮中の国々にとって最も有用なものとなるだろう。各章は段階ごとになっており、それぞれで問題となる事項を扱っている。すなわち、取組の目標を定めることから始まり、適切な過程を組織立てて考え、政策文書の内容をどのように発表するか、実施のため、そして実施後のモニタリングのための戦略作りといった事柄があげられている。内容的には、すでにこれらの問題への取組がかなり進展していると思われる国々にとっても興味深いものであろう。当報告の中で検討されているトピックの中のいくつかは、そういった取組のなかにまだ取り入れられていないこともあろうし、これまでの国際的な視野での経験の分析によって、各国の個別の努力が、より広い視点からはどう見えるかといった新しい光を投げかけてくれることもあるだろう。
7.すでに示唆されているように、当報告は次のような7つの事例研究によって補完されている。すなわち、米国マサチューセッツ大学の Joseph Larson 氏による「国家湿地保全戦略におけるNGOの役割」、トリニダード=トバゴの Nadra Nathai-Gyan 女史による「国家湿地政策における利害関係者とは」、カナダの Clayton Rubec 氏による「湿地政策策定のための協議」、オーストラリアの Bill Phillips 氏による「連邦国家における湿地政策」、ウガンダの Paul Mafabi 氏による「湿地に関する分野別政策及び法律の総括」、米国 Roberta Chew & Gilberto Cintron による「合意形成の戦略」、マレーシアの国際湿地保全連合アジア太平洋支部の Sundari Ramakrishna 女史による「マレーシアの湿地政策―策定と調整のプロセス」である。
8.当ガイドラインによって、ラムサール条約締約国が各国における国家レベルの政策や戦略の再検討が促され、またその際には有用な参考文献となることを望んでいる。またさらに、ラムサール条約がこれまで培ってきた、有益な知見や体験を分かち合うという伝統がさらに高められることを期待する。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
9.湿地はこの地球上で、農地や森林とともに、主要な生命維持システムのひとつとして認識されてきている。これはラムサール条約の『1997−2002年戦略計画』、『世界保全戦略』、『新世界保全戦略(かけがえのない地球)』、『ブルントラント委員会』報告、そして『アジェンダ21』の中で明確に述べられ全世界的に展開しつつある、持続的開発と環境保全に対する支持と政治的言明の中でも中心的なテーマとなってきている。湿地の役割は「生物多様性条約」においては、内陸の淡水そして沿岸の生態系保全の実施において鍵となる要素とされている。我らが湿地の重要性は、多くの絶滅の危機に瀕している動植物種の生息地であるというレベルを越えたものである。湿地は国内そして全世界的な生態系であり、そして経済活動のかけがえのない要素である。
10.湿地が今日でも引き続き喪失していることの深刻さのため、湿地管理に新しい取組が求められている。居住地域の湿地の大部分は、自然状態から、農業、都市化、産業、そしてリクリエーション利用の追求などといった他の土地利用を支えるよう改変されている。湿地はまた、植生破壊、栄養や毒物の負荷、砂泥堆積、混濁化、水流の改変といった結果を招く土地利用方法によって劣化している。浚渫、集約的な魚介類養殖、伐採そして酸性雨もまた、湿地の本来のバランスに影響を与えている。
11.湿地の持つ機能の崩壊は経済的にも、社会的にも、そして生態学的にも高いコストを伴うものとなっている。湿地の自然バランスを崩すことは、医学的そして農業上の目的のために必要とされる危機的状況の遺伝子プールをさらに破壊しかねないし、水質を改善する自然の能力に影響を与え、教育目的やリクリエーション目的での利用を妨げてしまう。価値ある湿地の破壊は止めなくてはならないし、残された湿地の多様性は保持されなくてはならない。そして可能な場合には、湿地機能の回復、湿地の復元、再創造が試みられなければならない。以下に湿地の量的そして質的喪失という課題に対する障害といくつかの可能な解決法を概略する。
12.湿地とその保全が、国民の健康や福祉のために極めて重要であることを例証することが必要である。湿地保全は、国際協定とそれらに関連した国際的責務として述べられている生物多様性保全の目的を達成するために不可欠である。湿地は『世界保全戦略』の例で説明されているように、これらの目的を達成するために重要な役割を果たしている。
13.国際的に、そして国内的に重要な湿地を保全するという挑戦に成功するためには、国内での活動の基盤、そして国際的及び国内での協力のための枠組みとなる、総合的な国家政策が求められる。そのような湿地政策は、野生生物と他の生物学的資源のため、そして現在と将来世代の人類の必要性のために、国家が管理上や生息地としての要求事項に対処しようとするものであり、価値のあるものである。
14.1971年に採択されたラムサール条約条文の中で、第3条1は締約国は(国際的に重要な湿地の)リストに掲げられている湿地の保全を促進し及びその領域内の湿地をできる限り賢明に利用することを促進するため、計画を作成し、実施する
としている。
15.ラムサール条約に対応するために締約国が考慮すべき行動として勧告がなされているもののひとつに、湿地保全を促進する国家政策の形成がある。これまでにそのような国家政策を完成させた多くの国々の例では、時に長期間で複雑な過程を伴うものであることが知られている。政策の過程が進行している間にも湿地喪失を引き続き起こしてしまう社会経済的要因に加えて、政治的な、また管轄権の間の、組織上の、法的な、財政的な制約が、そのような政策の形成に影響を与える。
16.国家レベルで湿地政策を確立し実施する過程は、財源が十分でないことや、政府機関やその他の所でも業務のやり方に変化をもたらすことに組織として躊躇すること、といった障壁を乗り越えるためには、時間がかかるかも知れないし、適切な協議が必要だということを認識しておくことが重要である。広範に効果を発揮できるために、「国家湿地政策」は広い守備範囲をもたなければならず、単に野生生物保護の政策であってはならないし、またそのように受け止められてはいけない。「国家湿地政策」の野生生物側面のみに焦点をあてることは、社会や国家にとってのその価値に限界を与えることにしかならない。「国家湿地政策」の策定は実際、多くのレベルにおいて、協力と行動を促進する『黄金の機会』なのである。「政策」は不確実性に直面しつつも策定することができる。行動を起こす前に、総合的な目録や科学的情報が求められるわけではない。
17.課題を解決し、湿地保全を達成するための数多くの機会を以下に確認する。
18.連邦、州、領土の政府や市町村といった自治体では、それらの政策やプログラムにおいて湿地保全の価値を認識していることはまれである。政府に方向性が欠如すると次のような結果を生み出す。
19.「国家湿地政策」は、湿地生態系の利益のために、こういった政府機関がそれらの行動の説明責任(アカウンタビリティ)を確立し、その部門の政策に変更を加える際に助けとなる。
20.大部分の国々において湿地に関わる管轄権は、連邦、州、領土、市町村のレベルの政府の間で、そしてレベルの異なる省庁や部局の間にまたがっている。どのレベルにおいても、これら無数の部局や機関のひとつだけで、湿地管理、保全、持続的利用のすべての側面について責任を持つことはとうていできそうにない。何らかの努力が行われてきてはいるが、政府内のそして政府間の調整や連絡は不適切なままになっている。必要なのはどれかひとつの機関が湿地の面倒を見ることではなく、よりよい連絡網と、すべての政府機関が守らねばならない首尾一貫した、義務づけられた政策を強調することである。「国家湿地政策」はこういった機関間での効果的な調整、そして連絡を高め促進するメカニズムとなりうる。
21.多くの国々で、湿地保全プログラムにおいてリーダーシップを提供できる政府機関は、しばしば人員や資金の点からは資源が限られており、支持が十分には得られていない状況である。また、政府内での階層構造における政治的立場も、上位のひとつかそれ以上の他の省へ連絡を行わねばならないような、影響力のより小さい低いランクのものであるかも知れない。国の水資源、農業や開発の優先事項と比較すると、湿地のためになるプログラムの機会を調整するといったような、効果的であるべき結びつきを、政府が考慮することが難しいことがしばしばである。
22.(政府や他機関による)これまでの奨励策プログラムは、湿地保全のための努力と利害が衝突する場合がしばしばある。いくつかの国では、収入税及び資産税に関わる奨励策、排水や堤防のための補助金、農業生産物の割り当てなどがしばしば農家が湿地を耕作地に変更してしまう強い財政的誘因となっている。このような誘因がなければ、経済要因がこのような改変を通常押しとどめる働きをする。これとは逆に、土地所有者に湿地を自然状態で維持させるような奨励策は少ない。一般の人々は湿地から何らかの恩恵を得ており、政府が拠出あるいは支援する奨励策によって、保全のための努力を正当に支えることができる。「国家湿地政策」は、新しい、より良い経済的かつ部門別の奨励策の実施を促し、湿地の減少に通じる要因や障害となるような奨励策を廃止するツールとなりうる。
23.NGO、地域社会、私有地所有者、政府機関はしばしば保全目的のために土地を獲得したり保持したり湿地を管理するのに苦労している。資産税やスタッフの費用は高いことがしばしばであり、管理する者たちは生態学的に配慮したやり方で湿地を利用し歳入を得る方法を熟知していない。歳入の創出が補助となってくれる場合もあるが、長期的管理は湿地保全に関わるすべての機関にとって大きな関心を呼びつつある。「国家湿地政策」はこれらの要因に対処し、解決策を見つける機会である。
24.湿地の状況、生態学的機能、そして価値(水文学的もしくは経済的価値)についての情報は限られている。多くの国々で湿地を分類し目録を作成するのに進展が見られているが、全世界的に見れば、まだまだ完璧とはとうてい言えない状況である。必要な湿地の数や種類に関して目標を立てるため、さらに多くの努力が払われなければならない。「国家湿地政策」は情報の優先事項を確立し、湿地管理のために必要な、より良い情報を獲得し利用するための戦略を立てる役に立ってくれるだろう。
25.湿地が改変される速度や、湿地の経済的価値は適切に定量化されてはいない。湿地改変に伴う経済的、社会的そして生態学的な費用と便益は未だ十分には理解されていない。しかしながら、湿地が経済学的にも、そして生態学的、社会的にも、重要であるという証拠が積み重なってきている。湿地についての現存する知識が十分に行き渡っているとは言えないし、土地利用に関する決定に影響を与えるように効果的にも利用されていない。湿地に関する知識におけるギャップは重要な障害ではあるが、保全のための行動は、展開中の調査活動による結果を待つことなく前進させなくてはならない。
26.経済的発展が困難なままとなっている多くの国々で、あるいは経済が移行状態にある国々で、環境プログラムに対する現存の社会的政治的障壁は著しいものがある。経済的な福利厚生や、持続的な水及び自然資源の利用との結びつきがはっきりしないので、湿地保全は優先順位の高くないものと位置づけられ続けることになる。自然災害や内戦あるいは国境紛争によって引き裂かれた国においては、理解できることではあるが、環境上の重要課題も政府の行動においては優先順位の低いままとなる。
27.湿地に関する教育プログラムは強く支持されておらず、首尾一貫していないし、自然資源のワイズユースや自主管理(スチュワードシップ)の重要性を強調してもいない。国家レベルあるいはそれに準じたレベルの多くの例で、湿地について情報をより良く提供されていれば、一般の人々は保全プログラムをより支持することが示されている。これは、湿地の価値、機能、恩恵、そして継続的な湿地の損失による結果について、より良い理解を深めるような一般向け啓発事業を通じて発展していく。
28.土地所有者は、持続的な経済的便益を生み出すよう、更新可能な自然資源の管理を改善する方法を知る必要がある。政策決定に関わる人々は、湿地問題の重要性、保全と持続的な経済発展との間の密接な関係、そして資源の計画作りや管理に生態学的理解を応用するやり方について学ぶ必要がある。教育は相互作用を持った過程である:政治的指導者、政府職員、科学者、土地利用者、そして湿地利用者は皆すべて、湿地とその保全についてお互いから学ぶことができる。全く同様に、例えば建設や観光開発といった活動も、潜在的には湿地かかる圧力を増大させる一方で、持続的管理を促進させる取組に、重要な役割を持つ利害関係者を参加させる機会となるだろう。
29.「国家湿地政策」は国家における湿地資源についての認識を高めるための、メカニズムと優先事項を共同で確立する意義深い機会となる。
30.政府は、NGOや地域社会の資金調達や保全に関する能力や努力について、あるいはこれらのグループが湿地保全や政策策定について助けとなる潜在能力について、十分認識しているとは言い難い。これらNGOや地域社会は、しばしば関心を持つ人々による資金を集めるのに適しており、湿地保全に結びつく費用を現物による貢献を通して負担する。彼らは、地域においても全国的にも湿地保全プロジェクトの実施において、特にモニタリングや監視において、政府の効果的なパートナーとなりうる。これらNGOや地域社会の場合の、管理諸経費は政府のものより小さくてすむ傾向にある。信頼できるNGOや地域に根ざしたグループは、政治的また官僚機構の『障害』を打ち破るために必要な、一般的な支持を短期間に獲得することができる。[事例研究1 ☟]
31.ワイズユース(賢明な利用)概念はラムサール条約のきわだった特徴となった。ワイズユースは条文第3条1に述べられており、締約国は....その領域内の湿地のできる限り賢明な利用を促進するため、計画を作成し、実施する
ことが期待されている。ワイズユースは、条約の実施すべき概念の中でも最も努力を必要とする要素のひとつである。その結果として、締約国によるワイズユース概念の実施を支援するために、条約では「指針」そして「追加手引き」を作成している。
32.『ワイズユース』はラムサール登録湿地のみに適用されるのではなく、締約国の領域内にあるすべての湿地に適用される。『湿地のワイズユースに関する指針』は1987年にカナダで開催された第3回締約国会議において採択された。勧告3.3では締約国が、勧告文に含まれるワイズユースの定義と、付属文書として組み込まれた指針を利用することを求めている。
33.条約によって作られた「指針」は、いくつかの締約国が国家湿地政策を策定する助けとなった。この「指針」は、「国家湿地政策」の要素として、体制や組織上の改善、法的政策的必要性への対処、湿地の価値についての知識や認識を高めること、目録作成と湿地の状況のモニタリング、優先されるプログラムの確認と個別の湿地における行動計画を策定すること、といった事項が必要であることを概略している。
34.1990年にスイスで開催された第4回締約国会議において、締約国は(勧告3.3に取って代わる)勧告4.10として『ワイズユース概念実施のための指針』を採択し、「ワイズユース概念」が湿地保全のすべての側面に適用されるべきことを再確認した。この勧告は、国家湿地政策が国内の湿地に関する可能な限り広範囲の問題や活動に対処すべきであることを指摘した。国家レベルにおいて、次のような5つのカテゴリーの行動(付属文書1 ☟ として詳細なリストが提供されている)が提案された。
35.「国家湿地政策」が準備されているか否かにかかわらず、「指針」は国家レベルで直ちに注意が払われるべきいくつかの行動を求めている。これらの行動は、国家湿地政策の準備を促し、湿地保全とそのワイズユースの現実的な実践が遅れてしまうことを回避させる。予想されるように、締約国はその国の優先事項に従って、行動を選択している。いくつかの国では組織的、法的、あるいは教育的手法を実施しているし、同時に湿地目録作りや科学的作業に着手している。同様に、国家湿地政策が策定されるのを待たずに湿地のワイズユースを促進しようと望んでいる締約国は、次のような行動をとるべきである。
36.こうしてラムサール条約は、1971年の誕生以来、そして特にこの12年間において、湿地資源のワイズユースを促進し、各国における持続的開発の目的に貢献してきた。ワイズユースの概念は、全般的な湿地政策の作成と実施、そして個別の湿地におけるワイズユースの両方を求めている。これらの行動は、持続的発展の不可欠の要素である。
37.しかしながら、第3回締約国会議の『ワイズユース・ワークショップ報告書』で認識されているように、国家湿地政策の考案は長期的なプロセスとなりうる。政治的そして国内での制限がそのような政策の作成を妨げる重要な要因であることに鑑み、第4回締約国会議では、すべての締約国が、総合的な「国家湿地政策」の作成に向けて長期的な努力を行うこと、そしてそのような政策を国家の体制や組織の実情に合わせた適切な形で策定するよう勧告している。
38.1993年、日本の釧路で開催された第5回締約国会議において、なぜ加盟国が国家湿地政策を採択できずにいるのか、そして湿地政策をどのようにして「国家環境政策」あるいは「国家自然保護戦略」との統合を図るのかが問われた。さらに、釧路会議では、社会経済的要因が湿地喪失の中心的な理由であることが注目され、「国家湿地政策」の準備過程において考慮を払うことが求められた。
39.オーストラリアのブリスベンで1996年に開催された第6回締約国会議では、『1997−2002年戦略計画』が採択された。過去の締約国会議における決定と合わせる形で、『戦略計画』作業目標2.1は締約国に、「ワイズユース指針」の適用を確実にするため、国家あるいは超国家的な法律、組織や運営方法を検討し修正することを求めた。またこの目標を実施するために、各締約国にその領域内の法律や運用の仕方を検討し、次回締約国会議の「国別報告書」の中で、どのように「指針」が適用されたかを記載することを求めた。
40.さらに1996年に各締約国は、個別の政策として、あるいは「国家環境行動計画」、「国家生物多様性戦略」、「国家自然環境保全戦略」といった自然保護上の他の国家計画策定における取組において、明確に区別できる構成要素として国家湿地政策を策定するために、これまで以上に多くの努力を促すことを求められた。第6回締約国会議の勧告6.9(付属文書2を参照)は、この種の政策を持っていない締約国が利用するために、「国家湿地政策」を策定し実施するための枠組みが必要だと述べている。また、このような政策の例や概略をまとめることも求められた。同勧告はラムサール事務局に、「国家湿地政策」策定及び実施のためのガイドライン作りのための作業を企画するよう指示した。
41.湿地が国家レベルで、水、森林、土地、農業やその他の分野における既存の自然資源管理政策において明確に扱われていることはまれである。独自の、『単独で成り立つ』湿地に関する政策綱領もしくは戦略、あるいはその両方を策定することは、湿地の様々な問題と、それらに対処するための目標を絞った行動を認識するための重要なステップとなる。独自の湿地政策を通して、湿地がその管理や保全のためには異なった取組が求められる生態系であること、そして他分野の管理目標の陰に隠れてしまうようなものではないことを明確に認識する機会が与えられる。
42.しかしながらこれまで多くの場合、湿地政策もしくは戦略は、国家の持続的発展、水資源、あるいは他の分野の環境政策の中の構成要素となってしまいがちであった。このような場合、湿地に関するメッセージは、政府のより広範囲の目標設定の中で薄められてしまい、圧倒されてしまいかねない。多くの国々で資源管理の担当機関のスタッフが少人数であり、日々多くの要求と新しい問題や期待と対峙しており、湿地に関する誓約や目標を実施するために費やされるスタッフの時間は、より広範囲の問題に対応しなければならないというプレッシャーの下でつぶされてしまうこともあるだろう。このことは、湿地の保全目標にとって不利に働く。
43.単独で成り立つ独自の湿地政策は、特に議員達や一般の人々の湿地問題に対する大きな関心をひきつける。湿地生態系のための明確なゴールと目標を明文化することは、政府が持つ責任を明らかにし、政府がそういった約束を実際に果たしてくれるだろうという期待を生み出すことになる。
44.何が『政策』であるのかについて明らかにしておくことは重要である。そしておそらくより重要なのは、どんなものは『政策』とは言えないかだろう。「政策」は、『組織または政府が意図するか受け入れが可能な、行動もしくは方向性を示す原則をまとめたもの』と定義されている。政策はまた、『ゾウのように、それを見た時には認識できるが定義することは難しい』ものと述べられたりもする。確かなこととして政策とは、理性的な決定や行動を導くような、考慮事項についての表明とされるべきである。ラムサール条約の下で「国家湿地政策」の策定及び実施のための以下のガイドラインはこのような政策についての定義に沿って、提案されている。
45.『国家湿地政策』という言葉は、他の場所においては『国家湿地計画』あるいは『国家湿地戦略』と同じ意味において用いられている。これらの用語について、標準的な英語、仏語、スペイン語やその他の言語での使用の際にも、こういった言葉が明確に使い分けられるように区別することは不可能である。そうではあっても、本報告の著者らは『政策』の考え方について、共通の概念を提供することができると考えている。本報告において一般的に『政策』とは、中央政府やそれに準じた政府によって明確にされ出版された声明を意味し、多くの場合、具体的な数値目標、スケジュール、態度表明、そして行動のための予算を備えたものである。『計画』や『戦略』は考えられる行動やパートナーシップのリストをあげて、政府が向かう所はどこなのかといった将来像を明文化したものであるために、このベンチマークには達していないことがあり、さらに特定のスケジュール、予算や数値目標を持った誓約を規定することが必要である。いずれにせよ、「国家湿地政策」、「計画」、「戦略」はすべて、きわめて重要だと認識されるものであり、ここでは、実際にそれらのうちのどれかを達成しようという努力を抑制することは意図していないし、どの用語あるいは特定の定義が最も適切であるかを示そうというつもりもない。
46.著者達は、湿地『政策』、『計画』、『戦略』という用語の正確な使用や標準的な定義が欠如したままであることを認識している。「国家湿地政策」に関する世界的な状況の調査段階で、著者達は実際多くの機関や政府がこれらの用語を相互に交換可能な形で使用していることに気づいた。
47.これらの用語のうち、政策は文書としておそらく最も一般的に考えられるものである。そして、確かにこのように利用しやすい形で、これらの用語をひとまとめにして考えておくことが便利だろう。また、政策作成を、合意形成、考え方や態度表明の集約、実施、説明責任と再検討をというプロセスとして考えることは有用だろう。政策は階層構造の頂点に立つものと見なすのがよいだろう。それは行政側にとって、一般の人々の意志あるいは要求・指令(mandate)を把握し、それ自身の展望の上に改善を加えるためのメカニズムである。次の国家の立法機関あるいは政府がどのようにしてこれを扱うのかという段階は、政策の域を超え、法律によるものとなろう。実施に責任を持つ機関もまた、戦略や行動プログラムによって「政策」と取り組むことになるだろう。
48.政策がその効果や正当性を獲得する源泉となるものは数多くある。いくつかの政策は、政府全体としてか、あるいは個々の大臣によってか、いずれかの方法で承認される。ある政策が政治的に承認されたからといって、そのまま『実践における』成功を保証するものではないことは覚えておくべきである。多くの場合、そして広範囲にわたる課題や様々な分野の利害を扱う場合には特に、「政策」を策定するために用いられたプロセスそのものが、政策の強さの最大の源となる。
49.「政策」は、物事に対する態度を反映し、望ましい原則を表し、意図を述べ(例えば、よく使われる表現ではゴール/目標/目的)、戦略の方向性に関しどのような選択肢が作られたかを示し、態度表明をし、合意のための焦点を提供し、懸念を表明し助言を提供し、役割と責任を明確にする。
50.「国家湿地政策」は、全国レベルの視点を持つと理解されているが、政府のさまざまなレベルにおいて同時にあるいは連続的に、策定されることもありうる。例えばオーストラリアやカナダでは、連邦政府と州政府の両方が湿地保全政策を策定している。このことは両国の、(湿地管理を含む)自然資源管理の法政上の担当者が政府レベル間で分割されているという、連邦制の性質を反映している。
51.いくつかの国々では、政策は、中央政府の中で実施にあたって関連組織すべてに命令を下しうるレベル(例えば内閣)による適切な手続きを通して正式に採択される。憲法上の管轄権を共有する連邦制の国家では、これが当てはまらない場合もある。連邦政府は、連邦政策を通じて湿地保全に対するその関わり方を表すことになるだろう。しかしながらその政策は、連邦政府機関と連邦管理下にある地域にのみ適用される。しかしながら適用の範囲は、国家の下に位置する管轄(例えば、州や町村政府)への法的拘束力のないガイダンス、あるいは良い例を示すといったこととにとどまらず、各国の状況によって異なるだろう。
52.「国家湿地政策」は、どのような行動が求められるか(政策自体の中に行動に関する詳細な処方箋が設定されてはいないが)、そしてどのような結果が期待されているのかについて、明確な結論を導き出させる枠組みの機能をもつ。もし政策がなかったら何が違ってくるのかが、明らかでなければならない−したがって、それ自体の付加価値を示す必要がある。もしその趣旨が湿地についての国家政策を明確に規定することであれば、ただ『枠組み』としての性質を持った短いものとなる。深く掘り下げることは重要ではないが、湿地に影響を及ぼす主要な政策課題をカバーする点においては完全でなければならない。そのいくつかが、最初に担当となった政府機関の管轄の外にあったとしても同様である(したがって幅広さが重要だ)。ここには水資源、開発計画作成、汚染制御、教育及び外交関係など、自然資源管理に関わる行政当局が含まれる。
53.ラムサール条約締約国における湿地政策の状況に関する報告書が、第6回締約国会議に提出された(Rubec, 1996)。報告書はラムサール条約の下での7つの地域ごとに構成されており、92国家を対象としていた。
54.Rubec の報告書は、ラムサール条約締約国による国別報告書で用いられている用語に基づいて、「湿地戦略及び計画」と、単独に策定された「湿地政策」の策定を分けて報告している。Rubec(1996)は、この区別は彼の国の経験に基づいた重要な区別であり、個別の「政策」は多くの場合、明確に定義された目標、スケジュール、予算、そして実施を前進させるための構造を備えた、政府の約束の表明であるとしている。
55.個々の組織や国家政府によってこれらの用語がどのように用いられているかについては、かなりの重複があり得ることが認識されている。それゆえ分析(表1参照 ☟)の中で、湿地に対する国家のどのような取組が、「政策」とされ、または「戦略/計画」となっているかは、集計に用いられた情報源によるため、部分的には不正確となっている可能性もあり得ることを考慮に入れておかねばならない。著者達はそれらの国家的取組のどれかが、他の例と比べても良いとか劣っているとか、あるいは適切であるとかを示唆しようとするものではない。
56.Rubec の報告は、1995年のラムサール条約常設委員会のために準備された地域別報告、そして1996年3月にオーストラリアで開催された第6回締約国会議のための国別報告書から得られた情報に基づいている。この内容は1999年5月にコスタリカで開催された第7回締約国のために提出された国別報告書の中の情報に基づいて更新され、ラムサール条約HP(Ramsar Bureau 1998c)に掲載されている。
57.1999年4月の時点で114ヶ国あったラムサール条約締約国のうち、計44ヶ国が「国家湿地政策」の策定中、あるいは実施の最中であると報告している。それらの国々のうち大多数(39ヶ国)はまた、「国家湿地政策」に加え、これと並行して他のメカニズムを通じ、または独立した文書として、「国家湿地行動計画」あるいは「戦略」を策定中であると報告している。これらの取組はラムサール条約の7地域すべてにわたっている。12締約国のみがそのような「政策」は、政府によって採択されたものだと報告している。さらに6締約国が「国家湿地政策」は草案の段階にあり、26ヶ国がそのような「政策」の策定を考慮中あるいはすでに提案されたと報告している。カンボジアのように未だ加盟国となっていない、いくつかの国もまた「国家湿地プログラム」を策定中であった[訳注:カンボジアはその後条約に加盟]。約70のラムサール条約締約国が、まだ、いかなる形でも「国家湿地政策」を計画中であるとは示していないとしていた。
58.多くの国々、特にオーストラリア、ベルギー、カナダ、パキスタン、アメリカ合衆国のような英連邦国家または連邦制の国々では、国家に準じたレベルにおいてもまた、湿地政策や戦略を策定あるいは考慮中であることを報告している。これは、これらの国々における国家レベルや準国家レベル(例えば州)の両方において、湿地保全のための制度上の管轄権が分割されていることを反映している。いくつかの例では、湿地は準国家レベルでの管轄の下にあるため、国家的な湿地への取組は期待されていない。これら準国家レベルの政策もしくは戦略のいくつかが、付属文書3 ☟ としてリストされている。
59.第7回締約国会議における検討では、「国家湿地戦略」及び「行動計画」が、「国家湿地政策」と独立して考慮された。1999年5月の時点で、約50の締約国が「国家湿地戦略」あるいは「行動計画」を採択しており、12ヶ国で草案段階であり、39の締約国においてそのような取組が考慮中あるいは提案されていた。これらはラムサールの7つの地域すべてにわたっている。そのような国家戦略あるいは行動計画策定に向けて踏み出したとの報告がないのは13の締約国のみだ。このようにラムサール条約の締約国の大多数は「国家湿地政策」とは別の、あるいはそれに追加する形で、「国家湿地保全プログラム」を実行に移してきている。
60.第6回締約国会議の分析(Rubec, 1996)は、条約の下での湿地政策に関する情報を編纂する最初の試みであった。第3回締約国会議から第6回締約国会議までの議事録と第7回締約国会議のための国別報告書の分析によれば、1971年にラムサール条約が生まれてから1999年までに世界的なレベルで大きな進展があった。この傾向は第7回締約国会議以降も続くことが期待されている。
61.表1は1987年から1999年4月までの期間における、「国家湿地政策」、そして「国家湿地戦略」及び「行動計画」の策定や採択に関する情報の概略を示したものである。この表は、条約履行のすべての側面に対する各国の報告を基にした、国家湿地政策及び戦略について概説した会議文書を検証することによって作られた(Ramsar Bureau 1987,1990,1993,1998a,1998c;Smart 1993;Rubec 1996)。
62.この期間において、「国家湿地政策」を公式に採択した国家の数は0から12となり、さらに23ヶ国がそのような「政策」に取り組み始めているか、現在考慮中となっていた。同期間に、「国家湿地戦略」あるいは「行動計画」を作成し終わったと報告している国の数は4から50となっている。
63.1987年において、「国家湿地政策」、「戦略」あるいは「行動計画」に取り組んでいると示した締約国は5ヶ国のみであった。1999年までにこの数は少なくとも101となった。これらの国々の多くが、1999年4月までに、個別の「国家湿地政策」を策定中あるいは採択中であると報告した44ヶ国となった。このように取り組んでいる締約国の数は、第7回締約国会議の後も増え続けることが期待されている。
| 国家湿地政策、戦略、行動計画の現状 | 1987年レジャイナ会議(第3回締約国会議) | 1990年モントルー会議(第4回締約国会議) | 1993年釧路会議(第5回締約国会議) | 1996年ブリスベン会議(第6回締約国会議) | 1999年サンホセ会議(第7回締約国会議) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家湿地政策 | |||||
| ⒜ 採択済み | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| ⒝ 草案段階 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| ⒞ 提案済みもしくは考慮中 | データなし | 1 | 6 | 13 | 26 |
| ⒟ 今のところ対応なし | 17 | 43 | 36 | 65 | 70 |
| 国家湿地戦略/国家湿地行動計画 | |||||
| ⒜ 採択済み | 4 | 9 | 9 | 35 | 50 |
| ⒝ 草案段階 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 |
| ⒞ 提案済みもしくは考慮中 | データなし | データなし | 5 | 8 | 39 |
| ⒟ 今のところ対応なし | 12 | 35 | 33 | 36 | 13 |
| 提出された国別報告書の数 | 加盟国数35中17 | 60中45 | 76中51 | 92中92 | 114中107 |
64.湿地のワイズユースはすべてのレベルで実施可能な概念である。それゆえワイズユースの原則は、現場における特定の行動についての選択肢、それとともに政策レベルでの戦略的方向性の選択肢を形作るのを助ける指針となる。「国家湿地政策」の主要項目のそれぞれを、ラムサール条約によって確立・採択されたワイズユース定義に対比検討させ、条約のこの主要概念に対して適切であるかをテストすることができるだろう。
65.ラムサール条約を批准する国は原則的に、その領域内の湿地のワイズユースを可能な限り促進するという義務(条文第3条1)を受け入れていることになる。それゆえこの義務は自動的に、国内の湿地に関する政策として最低限持っていなければならないものとなる。「国家湿地政策」はさらに各国独自の状況を反映させつつ、このゴールに向けた国としての考え方をさらに精錬させたものとするができる。もちろん、ラムサール条約の下で採択された世界共通のものよりも、より厳密な基準を用いることができる(条約下の共通な基準が厳密でないということではない)。
66.このように「国家湿地政策」は、条約の「ワイズユース概念実施のための指針」及び「ワイズユース概念実施のための追加手引き」の中で提案された一連の行動の中でのひとつの道具である。ただし「国家湿地政策」が湿地保全のワイズユース・プログラムのために必要な行動のうち、最優先であるとか、現実的な唯一の行動であると限定して考える必要はない。
67.「国家湿地政策」(あるいは準国家レベルでの取組)が採択あるいは承認されるレベルがどのレベルならば、最も効果的あるいは最も望まれるのかを決定づける要因は数多い。理想的には、「政策」は国の内閣によって採択されるものだろう。別の場合には、国の法律の下で、あるいは法制度上の改正を伴って採択することを意味するだろう。そのような動きは、ある政権から次の政権への政府の政策の連続性が標準的な過程となっている国では、常に求められているとは限らない。英国や米国では、実際に、支持的な役割を果たす一連の法的及び政策上の仕組みがセットとして一緒に用いられる。単独の湿地国家法ですべての管轄をカバーしようとしても、機能できないようになっているのである。しかしながら、より小さな国々で法制度がそれほど複雑ではない場合には、単独の国家湿地法がきわめて適切な道具となるだろう。このように、どの分野においてどの時点で法的仕組みが考慮されるかに関しては、柔軟な考え方をもつことが重要である。
68.国によっては、法律として明確に取り扱われていない事がらは、その時の政府によって見過ごされたり無視されたりすることがある。内閣あるいは政府による法令としての「政策」の採択は、このような場合に、政府が問題を認識しているということと、実行に移す意志があることを示す、最低限のレベルと見なすことができる。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
第1段階:政策策定
準備的な最初の取組
草案チームの設立
「国家湿地諮問委員会」の創設
背景資料と国家的課題に関する報告書の準備
背景資料と課題報告書の配布
法律の検討
省庁間の協議
政策草案の策定
的を絞った協議と全国的及び地方におけるワークショップ
異なるレベルの政府間での会議
政策草案の改訂
追加的な省庁間協議
政策の最終案の策定
第2段階:政策の採択と実施
関係部局間での検討
実施計画と予算の準備
内閣文書の準備
中央政府/財務局への提出
内閣/政府の承認
公布
作業計画の実施
実施のための中心機関の創設
「国家湿地委員会」の継続的役割の設定
実施ガイドラインの作成
他の政策との調和を図る
関係する機関の研修プログラムの策定
法的実施あるいは改正
69.以下の本ガイドライン第Ⅱ章の部分および第Ⅳ章の全体は、「国家湿地政策」を策定し実施するために、配慮すべき事項と考えられるステップについて検討する。図1に「国家湿地政策」の採択及び実施に到る2つの主要な段階における、いくつかのステップの概略的なフローチャートを示す。主要な段階は、第1段階−政策の策定、そして第2段階−政策の採択と実施である。
70.政府機関の1つが「国家湿地政策」の策定と実施において中心的役割を果たさなければならない。まず、どのような課題があるかという報告書の策定、会議とワークショップの計画作り、そしてその後における政策もしくは戦略の原案作りには、調整作業と資源的な支援(例えば、スタッフの勤務時間、事務所の提供、旅費など)が必要となる。
71.中央政府機関が地方や地元当局と協力して、政策策定の段階を調整しつつ進めていく必要がある。多くの場合、最初の計画段階からNGOや企業関係者の参加を考慮することが極めて適切である。このプロセスを促進するために「政府」からの契約によって国内もしくは国際的NGOが協力する場合もある。
72.しかしながら、策定段階で中心的役割を果たす機関が、実施段階においても中心的役割を果たすとは限らない。これらの段階においてどの機関が、そして誰が中心的役割を果たすかは、かなりの程度まで全国的な協議の結果と政府の望むところによって決まってくるだろう。
73.「国家湿地委員会」は、ラムサール条約の目標を国家レベルで実施するのに直接的な役割を果たしたり、他の機能を持ったりできるが、条約はさまざまな会議を通じて、そういった委員会を設立するためのガイダンスを提供している。いくつかの国々では、「国家湿地委員会」を創設したことが、「国家湿地政策」の策定において政府を支援する効果的な手段となったことが示された。
74.一つの例が、トリニダード=トバコであり、国家湿地委員会が「国家湿地政策」を提案し、数年間をかけて提案した政策に関する全国的な議論を大きく前進させる役割を果たした。政府が、いくつかの部門ごと(政府、研究者、NGO、産業界)の代表者を文書作成に関わる計画作りと国家政策協議に関する諮問委員会に招いた。この委員会のメンバーは慎重に選択され、それぞれの専門知識を活かすとともに異なる分野間で議論をすることが、政策策定のプロセスで役立つことが分かった(Pritchard 1997)。
75.委員会は、土地利用や土地利用に責任のある、連邦政府や様々な行政レベル(例えば、地方、州、または市町村政府など)からの代表者を全て含むようにするとよいだろう。一人かそれ以上の政府高官を含むことも、政府内において「政策」を前進させるのに効果的な戦略であるかもしれない。
76.「国家湿地委員会」はまた、中央政府によってこの過程の成功のために重要だと思われるような、NGOや産業界のような他の利益代表を含むこともあるだろう。この「委員会」は専門知識と学問範囲の広がりを通してさらに効果的となり、「政策草案チーム」に対して支援することもできるだろう。この「委員会」は、情報交換、プログラム、政策や調査の調整や協力推進により活動的になれば、国家の湿地の課題により直接的な取組ができるだろう。全国的な協議のためのワークショップ(セクション2.7参照 ☟)の結果に基づいて、「国家湿地委員会」は現実的な湿地政策の枠組みを考慮できるようになるだろう。
77.いくつかの例では、「国家湿地委員会」が「国家湿地政策」の採択、あるいは包括的な国家湿地プログラムの実施の結果として設立されている。こういった「委員会」は、助言的役割として、湿地管理、湿地政策や科学的取組の企画や実施において、政府が国内の湿地資源を管理する助けとなることができる。
78.「政策」採択の前後いずれの場合であっても、「国家湿地委員会」の設立によって多くの部門や利害関係者からの支援を促進し確実なものとすることができ、政府にとっては賢い行動と言えよう。「委員会」は湿地保全において、利害対立を避け解決する大きな助けとなる。
79.湿地政策や戦略が必要であるという国家としての合意形成において、提案された政策の全国的な協議を始めるための手がかりとして、国家の簡単な『課題リスト』あるいは『展望に関する声明文』を準備することに価値があることが分かってきた。図2にカナダ(North American Wetlands Conservation Council Canada 1998)における湿地に関する連邦の声明文の例が示す。このような声明文は湿地保全に関する、政府の憂慮、あるいは国家の関心事項を表明する。この声明文は検討会や全国的なワークショップでディスカッションをするための、予備的な『考慮事項のメモ』("think piece")として用いることができる。
80.国家の湿地の状態や全体像に関する詳細な背景資料は、湿地政策あるいは戦略策定に向けての全国的な協議を助けてくれる貴重な道具(ツール)である。そのような資料は以下のような項目を組み込むのが良いだろう。
81.背景資料の中には「国家湿地政策」のための、実施可能な目的、目標、原則や戦略的方向性についての予備的な規定を含むこともよい。背景資料は、一般に公開して、普及教育活動に役立つ資料として広く用いられるよう企画することができる。図表や写真を多く使うことは有効だろう。全国の教育関係者、環境関連機関やNGOの協力のもとに作成することもできるだろう。
展望:国民と野生生物による持続的利用のための、湿地生態系の長期的確保に向けて、政府、NGO及び民間企業は共に協力しあう。この展望を達成するために6つの目標を設定する。
目標1.総合的な湿地保全政策を実施する
目標2.国内及び国際的な協力体制の改善
目標3.湿地に関するデータの管理を確実なものとする
目標4.効果的な湿地科学を促進する
目標5.地方レベルでの湿地保全を達成する
目標6.湿地の価値に関する教育を進める
82.ラムサール条約の定義を利用するか、国内の状況に合わせて、『湿地』という言葉を明確にしなければならない。ラムサール条約条本文では次のように定義される。湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか塩水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地、又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。
、そして水辺及び沿岸の地帯であって湿地に隣接するもの並びに島又は低潮時における水深が6メートルを超える海域であって湿地に囲まれている
地域を含む(条文第1条1と第2条1)。
83.『湿地』は、永続的あるいは一時的な湿った土地、浅い水域、そして水と土地が交わる部分を全体として表すのに用いられる。湿地は、淡水であれ塩水であれ全ての水系に存在し、自然の状態では一般的に湿った条件に適応した動植物相や土壌という特徴をもつ。
84.湿地の定義が国内で採択されており、国内の科学的知見にしっかりと基づいているような場合にはそれを用いるのが適切である。このことは特に、湿地目録や保全プログラムにおいて引用されうる詳細な国内の湿地分類システムと結びつける有益である。ラムサール条約の『湿地の分類システム』は極めて一般的なものとして考案されているが、これより詳細なものが国内にない場合には貴重な情報源となる。
85.米国、ノルウェーやカナダといった国々では、湿地の定義が長い間使われてきており、それはしばしば法律や政策の中でも用いられている。これらの定義は、ラムサール条約で採択されている広い定義(段落82参照)と全般的に似通ったものとなっており、これらの国々の湿地プログラムの基礎となっている。一方でそれらは、特に沿岸や海洋システムにおいて何が湿地として含まれるかという定義の全体像においては、ラムサール条約の定義とは異なっているかも知れない。国ごとにこういった湿地の定義や分類体系が作られていることは、ラムサール条約の柔軟性の重要な要素であり、定義の違いが制限とはなっていない。重要なのはこれら違った定義が存在することを認識し、適切な管理担当機関がこのことをしっかりと意識することである。
86.国によって湿地の定義が異なる例を以下に引用するが、参考のために他の国々やラムサール条約の定義との比較についても触れておく。引用に値する例はこの他にもたくさんある。
87.「国家湿地政策」における重要なステップのひとつは、「政策」の企画、討議、実施によって誰が影響を受けるか、あるいは誰が参加する可能性があるかということをしっかりと見極めることである。政策の最終成果をできるだけ達成可能であり効果的であるようにするためには、利害を持つグループあるいは様々な段階で貢献できる全てのグループを含めて協議すべきであり、そのためにこういった見極めを行うことが重要である。利害関係者には、「国家湿地政策」に興味を持つ、あるいはそれによって影響を受ける機関、組織、グループなどが含まれる。それは政府の関連部局、NGO,地方政府その他多くを含む。この範囲は国ごとに極めて異なったものとなるだろう。[事例研究2 ☟]
88.「国家湿地政策」に先立って、国として協議参加を働きかける範囲は、国によって異なるだろう。利害関係者、時間、移動、手続きの複雑さといった観点から、こういった協議がどの程度まで広く扱われるべきかを、中心的役割を果たす機関が決めなければならない。たとえば連邦制の国家では、実際的な湿地管理の管轄は明らかに中央政府のレベルよりは下位の政府レベルに依存している。また、国土が広大な国家では、中心となる機関は様々な観点からの意見を求めて、広範囲に渉って行動しなければならず、より複雑な任務に立ち向かうことになると言えるだろう。
89.全国の利害関係者が参加するワークショップを主催して、意見を求めることは有効な取組のひとつである(セクション2.7参照 ☟)。そこには、必要に応じて主要な政府機関、企業グループ、NGOや、先住民、地域社会、一般市民の代表が一堂に会することになるだろう。そのような会合は、政策の支持基盤を作り、「政策」やその提案内容について『言葉を広めて』くれるような、よく情報を掌握したパートナーのネットワークを作り出す有効な仕掛けとなるであろう。会議に参加した個人も、特に地域社会レベルにおいて、地域協議の場を組織し、運営することができる。こういった意味合いにおいては、全国的な協議のための会合は、ある程度まで研修ワークショップとして位置づけることもできるであろう。
90.また、直接的協議の手段としては、地方レベルにおける、あるいは特定のグループや組織が参加する、数多くの小さな会合などがあるだろう。いろいろな場面での応用が可能な標準化された視聴覚機材を用いる協議用資料や配布用の印刷物を作ることができるだろう。こういった『面と向かった』会合はしばしば、省庁間や政府間の協議、そしてまた主管の地方政府やNGOとの協議に必要不可欠である。
91.担当者が直接訪問したり地域で開かれる会合をしたりしない間接的な協議には、同様の協議用資料が用いてもよい電話や郵便等をつかって実施するものなどがある。求められる回答を引き出すためには、最初の連絡の後に頻繁に接触をすることが必要となる場合もあるが、基本的には移動やスタッフの勤務時間といった点では費用が少なくてすむ。
92.この段階において、政策の影響を受ける可能性のある、あるいは影響力の強い政府機関との省庁間協議を行うことは極めて重要である。これは大臣の間の適切な連絡や、彼らが所管する政府部局の関与や貢献を促すことから始めるとよい。
93.公開協議には、公共メディアを通じた費用のかかるプログラムが必要こともあるだろう。そのような協議を効果的に行うためには、広範囲にわたる移動や、詳細で緻密な運営計画作り、そして専門知識が必要である。しかしながら、多くの国ではそのような公開協議が法によって定められており、政府による新しい取組を始めるときには避けることはできない。公開協議のためには、多くの種類の印刷資料やデジタル化された会議資料が必要となり、容易ではないかも知れないが公開の会議はたくさん必要であろう。
94.ここで重要なことは、協議の中ででてきた意見を十分に活かすためには、協議の提案ができるだけ初期の段階のもので完結的でないようにして正しいバランスをとることである。政策の選択によってどのような違いが生じてくるのかという点について、十分に考え抜かれた情報を提供した上で、意見を求められる人々や機関が、自分たちの問題だという意識をもち、自分たちの意見が活かされるのだという感覚を作り出すことが重要である(すなわち、既に決定したことを提示するのではない)。
95.全体のプロセスと中心的議題を明らかにするために、基本的なアウトラインを提供することが有益である。このプロセスの中ではフィードバックがあること、例えば草案の改訂が行われる点等を指摘することが適切であろう。プロセスが効率的であり完成されるためには、際限なく時間がかかるのではなく、理にかなった程度に押さえることも必要だ![事例研究3 ☟]
96.利害関係者が参加する「国家湿地政策」ワークショップの開催が合意形成のための効果的なメカニズムであることがいくつかの国々において示された。湿地保全と管理に関する課題に関して共通の理解を得るため、これらの課題を扱う上での障害や問題点を認識するため、そしてそれらの問題点を乗り越えるための解決策や手段を提案するために、これを実施してもよい。こういったワークショップは様々なレベルで実施してよい。小さな地域社会で暮らす人々は、中央の人々が主催する大きな会合では怖じ気づいてしまって、自分達にはとても参加することができないと考えることもあるので、場合によっては、地域単位の非公式な会合が不可欠となる。別の場合には、公式な全国規模の政策ワークショップが極めて妥当だということもあるだろう。
97.ワークショップの目的は、「湿地政策」のための概念及び全般的な取組を草案するための足がかりを作ることにある。二つ目の目的は教育のためのフォーラムとして機能することであり、地方から全国レベルまで、参加している人々の関心や知識に合わせて、そして問題レベルやその複雑さに適するような協議資料が準備できる。こういったワークショップは、政府が、場合によっては異なるレベルの政府がそれぞれの管轄において、効果的な湿地政策を草案し実施する上で役立つように企画される。そのようなワークショップの利点を以下に述べる。
98.ワークショップの主要な原動力となるのは、「国家湿地政策」(あるいはいくつかの国々では州ごとに異なる政策)を策定しようとする、連邦あるいは中央政府の関心や意思の表明である。一連の政策声明を作り出すにはガイダンスが必要である。そのようなガイダンスに対して幅広い政府関係者やNGO、利害グループの参加によるワークショップは、重要な基礎となってくれる。
99.もう一つの側面は、湿地資源に影響する土地利用計画の策定や地域社会に根ざした問題を議論する上での焦点を作り出すことである。国家レベルではそのような議論は中央政府、産業界、全国的なNGOや州レベルの政府の間で行われるだろう。地方レベルでは、地域の組織や国家機関と協力している地方政府を含むものになるだろう。協議は「国家湿地委員会」(上記セクション2.2参照 ☝)によって進めるのがよいだろう。
100.中心的役割を果たすよう任命された機関が、「政策」の起草、そして必要となる協議や説明用資料の準備に責任を負うことになる。報告書作成のために必要な資源が提供できるように豊富な知識を持つスタッフや起草能力のあるスタッフからなるグループをつくらなければならない。このうちの何人か、場合によっては全員が、関係する利害関係者や協議グループと連絡を密に取り合うことになるだろう。「起草チーム」設立を助けるために、他の機関や分野からスタッフを一時的に人選し任命することもありうる。彼らの業務は全国的な協議の結果に基づいたものとなる。一度設立されたら「起草チーム」は「政策」の文書化に必要な全ての事項が達成されるまで、改変されてはならない。何人かのスタッフは各地を転々と移動しなければならないことがあり、チームの他のメンバーとは定期的な打ち合わせの時にだけ会うことになるかも知れない。もっとも、あまりにもたくさんの旅行は費用もかかるし、関係する個人にとっても困難なものとなる。チームのそれぞれのメンバーは「政策」の最初の草案を準備するために、政策、科学、政治についての幅広い知識を持ち込まねばならない。
101.「起草チーム」の少なくとも一人は中央政府での業務経験を持っている必要があり、この取組を動かすことになる個別の政府機関が、『どのように機能するのか』についてはっきりと認識していなければならない。
102.それぞれのステップ(例えば草案の作成)において、進行中の作業行程や最終目標である政策の採択に対して政府からどのような支持を受けているかを示す方法として、政府高官との話し合いや大臣、総理大臣または大統領の各レベルにおける記者発表を用いることができる。大臣や政府首脳(総理大臣等)による重要な政策についての演説や記者発表は、目標となる日が設定された場合にはその日までに「政策」を完成させ、また財政的な支援を行うという政府の公約を伝えるツールである。
103.これらのステップを通じて、「政策」策定に責任のある大臣は、内閣の同僚及び彼らが所管する政府部局と定期的な連絡を取り合う必要がある。スタッフはこれらの部局やその大臣に常に情報を提供し、彼らの支持を得て、内閣レベルまで文書が速やかに到達するようにしなければならない。こういった協議を通じて、大臣たちが指摘する問題点を早い時期に解決することが、その後の「政策」の採択に極めて重要である。
104.上記のように、時間は湿地政策策定において重要な要素である。政策策定過程の全ての段階において、時間に関して合理的な理解及び決断が求められる。最初の段階で、スタッフの業務実施や政策策定過程全体の見渡しのために、十分な時間をとって適切な計画を立てなければならない。文案作成、会合、省庁間協議から、望まれる政府発表までの、詳細なスケジュールを決めたフローチャートを作り、定期的に更新しなければならない。
105.採択された場合には、「政策」自体の中に時間という要素が組み込まれている必要がある。静止したものであったり、時代遅れの文書となってはならない。定期的な検討を行い再認可することを定めた条項を含めることは、「政策」を更新し将来的な追加を行う場面で役に立つはずだ。「政策」の実施もまた明確に数えられる日程に基づいて諸活動や諸結果の日程を定めた行動計画に基づいていなければならない。
106.いくつか可能な草案の選択肢が完成したら、さらに何回かの協議を行うことは価値があるだろうし、場合によっては法的に必要とされるだろう。これらの草案のオプションはこの段階では、一般の人々やNGO機関に公開される場合もあるし、そうでない場合もあるだろう。影響を受ける省庁や政府機関、そして他の部門とは、彼らの憂慮する点に関する反応を聞くため、さらに個別的な協議をしたほうが良いこともあるだろう。継続的な協議、法的アドバイス、政府の方向性や望むところに対する反応を通して、草案はさらに練り上げられるだろう。
107.他省庁との協議がすべて終了した後は、各国の政治システムによって次のステップが決まる。いくつかの国々では、特定の様式に基づいた公式の「内閣覚え書き」、「白書」あるいは他の文書が準備されることとなり、これは関係部局の幹部専門家や管理担当者のアドバイスに基づいて、全ての大臣が承認する必要がある。そのような国家レベルでの承認のやり方としては、議会による採択、新しい法律の制定、あるいは法制度上の改正(場合によっては、憲法改正)等があり、それぞれの国の政府システムに則する。注意深く政治的配慮をすることで、大臣達によるこの最終的な検討段階における内閣内での利害衝突を避け、ときには何年もかかることもある政策採択までの道のりを円滑なものにできる。
108.いったん内閣による承認(場合によっては大統領による承認等)が得られれば、担当機関が「政策」を一般向けに公表するための広報戦略を考慮することになる。市民向けのイベントや政府による発表等を計画することもよい。これには、短期及び長期的配布のために十分な量の印刷物、報道関係用資料、記者会見、発行部数の多い新聞雑誌の記事、そして実施のパートナーとなる特定の機関が参加する会合などが含まれる。簡潔で読みやすく、人目を引きやすい広報用資料が必要である。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
109.「国家湿地政策」には以下の項目のいくつか、またはすべてを含むとよい。
110.「政策」には、国家の他の政策や文化的環境に配慮した、一つまたは限定された数の、平易な目的設定と適切な原則が含まれなければならない。これまでに策定された既存の湿地政策の多くは、平易で手短にゴールを表現している。言い回しは多少異なっているが、主として二つのテーマに沿っている。すなわち、国家の湿地が現在また将来世代の人々のために持続的なやり方で利用されること、そして、湿地保全は国家の環境上・経済上の福利厚生のために必要不可欠であることである。
111.本来、原則とは、「国家湿地政策」を実行するために、政府がその責任をどのように考えるかという責任についての表明であり、これは政府の法制上の管轄や国の文化的慣例と首尾一貫している。8−10程度の原則を簡潔な形で書くことが妥当だろう。これには、「政策」を通じて実施される政府の行動によって、その政府を構成する地方や州政府の権利が侵害されることはないという原則や、実施のための行動が地方や州政府との協力という精神を確実なものとするといった原則を含むとよいだろう。先住民族や地域社会に関する同様の原則を定めることもできる。原則はまた、適切な場合には、持続的発展、環境、あるいは生物多様性保全といった政府の義務と「政策」との結びつきについて言及することができよう。
112.目標というものは、様々なキーワードに焦点を当てる必要がある。それらがしばしば「政策」のイメージとなるからである。目標のリストが求められる(これまで採択されたいくつかの「国家湿地政策」では、5−10の目標が記述されている)が、それらは「政策」発表においては、全てが同じように重要だという意図をもって示される。しかしながら実際的な政策の実施の場面では、一般の人々の注目を最も浴びるのは、それらのうちたったひとつか二つであるという結果になることがあるだろう。例えば、1992年のカナダ連邦湿地政策の発表では、湿地機能の保持、湿地に作用する土地利用計画立案の進展、連邦の土地における湿地機能の「No Net Loss(実質上の消失を生まない)」、湿地機能の向上や回復、国家的重要湿地の確保、国内の湿地における連邦政府の活動すべての影響緩和、そして湿地資源のワイズユース、これらに焦点を当てた7つの目標を持っていた。しかしながら、カナダの「政策」中で最も注目された側面は、「No Net Loss(実質上の消失を生まない)」という目標であった。
113.「国家湿地政策」草案を練る際には、次のような目標の可能性を考慮することが有益である。
114.「国家湿地政策に関する利害関係者ワークショップ」(セクション2.7参照 ☝)は、これらの目標をどう奨励するか、連邦、州、領土、市町村レベルの適切な政府機関が一連の政策実施戦略を通して、どのように目標に対して行動できるかを検証するものとなるだろう。
115.「政策」は何らかの形で評価が可能な特定の実施戦略を含むべきである。政策戦略は政府の優先事項となっている主要な分野を扱わなければならないし、また、異なる利害関係グループからの参加や協力についても望まれるレベルになるよう奨励していかなければならない。戦略に組み入れることが可能ないくつかの分野が、以下で論議される。このリストはすべてを網羅したものではなく、一般的な考え方を提供するにすぎない。
116.これらの戦略と、水、生物多様性、持続的開発に関する国内の他政策に対する取組とのつながりについては、さらに進んだ検討をしなければならない。下に示されているテーマ以外でも、「国家湿地政策」にとって重要となる場合があるだろう。3.5節 ☟ では、いくつかの政府がその「国家湿地政策」の中で採択しているテーマをタイトルから検証している。以下の議論ではもっぱら、政策のために考慮するとよい8つの分野についてのみ焦点を当てており、可能なすべてのテーマを扱っているわけではない。
117.付属文書3 ☟ は世界中の政府あるいはNGOによる、既存のあるいは策定中の湿地保全政策や戦略をリストアップしたものである。これには国家や国家に準ずる取組が含まれている。表2は既存の9例の「湿地保全政策」文書のにおいて挙げられた実施戦略の概略を示したものである。オーストラリア、カナダ、コスタリカ、フランス、ジャマイカ、マレーシア、ペルー、トリニダード=トバゴ、ウガンダにおける、採択済みあるいは草案段階の「国家湿地政策/行動計画」が含まれる。これらの文書は単に『草案』であったりNGOとの『協議』のための文書であったりする場合もあるが、ここでは戦略的な取組を発展させる機会を説明するために採用した。
118.ここで引用された例を見ると、いくつかの戦略の取組でも共通の強調事項があることが明らかである。すなわち、一般の人々の認識や教育を改善すること、中央から地方まで異なる政府レベル間の協力やパートナーシップを発展させること、支持的役割を持つ法律や互いに関連した土地及び水利用に関する政策及びプログラムを策定すること、個別の湿地管理上の責任を果たすこと、科学的調査や専門知識を通して政策のためのしっかりとした基礎を構築すること、政策実施のための事務処理上及び財政的能力を発展させること、国際的公約を果たすこと、といった事項の必要性である。表2で概略された例では、全体的に見て5−13の戦略的項目が作られており、主要テーマに関して明確なビジョンを提供するように書き上げられ、全国的にも受け入れられやすいものとなっている。
|
オーストラリア:
カナダ:
コスタリカ:
フランス:
ジャマイカ:
|
マレーシア:
ペルー:
トリニダード=トバゴ:
ウガンダ:
|
ラムサール条約 国家湿地政策指針
119.国家湿地政策の実施にあたって、誰が中心になるのかという点に関して、協議の過程を通じて明確な合意が得られることが基本である。政府の特定の部局あるいは機関が、関係ある多くの省庁、パートナー、利害関係者と密接に働く、中心的なコーディネーターあるいはファシリティターとしての役割を果たすことになるだろう。また、湿地管理に責任を持つ他の諸機関の役割を定めることも重要となる[事例研究4 ☟]。
120.いくつかの選択肢があるが、いずれもひとつの事実に結びつく。すなわち、実施に関わる機関は、「政策」が言っていることが何で、どういう意味を持つか、誰が担当か、どのような専門知識がどこに存在するか、役割と責任がどう分担されるのか、そしてそれらに関係する多くの質問があり、これらを理解するためには、助力と訓練とを必要とするということである。「政策」の策定自体と並行する形で、『実施のためのガイド』と呼ばれる文書を作成することが出来るだろう。「政策」について数年の経験を積んだ場合には、こういった『ガイド』は、より容易に作成することが出来るだろう。
121.この『ガイド』は利害関係者と湿地資源の利用者にとって役立つものでなければならない。それゆえこれは湿地の管理者を対象に据える。管理者は政府の機関であったり、地域社会であったり、公有あるいは私有地の所有者であったり、その他の利害関係者であったりする。政府機関の場合、「政策」の採択に中心的役割を果たす個別の政府の管轄における、すべての土地管理者や政策決定者を含むものとなろう。『ガイド』は次のような分野で役に立つ:
122.『実施ガイド』があれば、市民啓発のための資料製作等を通じて、「政策」が誰に適用されるのかについて明確に理解することができるようになる。
123.場合によっては、どのような資源が必要とされるかを定めてしまうことは、「国家湿地政策」の構成や目的・目標を十分に議論することの妨げとなってしまうかも知れない。政府機関において資源が十分にはない時には、実施のための新しい資源を管理するために最も適した位置にいるのは誰かという点に関して、重要な点に関して姿勢をはっきりさせる必要性や議論が生じるかも知れない。そのような際には、どのようなことがなされるべきかという議論と、誰がどのようにしてそれを行うかという議論を分けて考えることが有効だろう。このように誰が責任を持つか、そしてどのようにして資金を調達するかという議論から、政策策定を分けることによって、国として合意形成が難しくなるような問題を避けることが出来る場合もあるだろう。
124.国家湿地政策を実施するための予算は、承認のために政策が政府に提出される段階になってから、すなわち何がなされるべきかという点についての協議が終了してから、初めて要求されることになるだろう。こういった国家湿地政策の財政面についての記述は、文書全体に渡って述べるよりは、そのために別個のセクションを設けて提示するのが最善だろう。はじめに設定された『必要財源等の見積もり』は、政策の実施期間の間に改訂が必要となる場合もあるだろう。それゆえ、あまり詳細な費用計算を、政策文書自体の中に組み込むのは適当ではないだろう。
125.『行動計画(アクションプラン)』は有益だろう。典型的行動計画は、実際のスケジュールが付いた、政策の目的・目標を達成するための活動のリストである。さらに、予算配分された担当スタッフの配置や財源に関する記述が加われば、それは『作業計画(ワークプラン)』(後述のセクション4.8参照 ☟)と見なすことができるだろう。作業計画では、採択された実施戦略のタイトルごとに個別の計画が作られるだろう。
126.政策実施のかなりの割合が、様々な省庁にわたってすでに存在する多くの活動を通じて実施されることになる。すなわち、湿地に関係した特定の項目を、独立して切り離すことが困難かまたは不可能な場合もあるわけである。この点に関しては、必要となる資源全体に関して大変な努力を払って定量化しようと試みることよりも、むしろ記載にとどめておくことが重要である。それゆえ、政策を効果的に実施するために「新たに」必要とされる資源の概略を記載することが有益となる。また、政策の効果的実施において、どのような形で資源節約を図ることが期待されるかについても言及すべきである。
127.条約におけるワイズユース概念の要素の一つとして、湿地に悪影響を及ぼしかねない法を再検討し、適切な場合には、湿地のワイズユースと保護とを促進するための新しい法律を制定することを締約国に求めている。これは非常に重要なステップであり、現存する計画、政策、法律等で自然保護の実施を妨げる要素を持っているもの、そして湿地に悪影響を与えるものを見極め、新たな選択肢を提出するためには、一連の複雑な研究が必要となる場合もある。
128.湿地保全を支持する国家の法律を再検討したり新たに策定したりするための一助となるよう、ラムサール条約とIUCN環境法センターは協力して、1999年の5月に開催された第7回締約国会議で採択された決議Ⅶ.7「湿地の保全とワイズユースを促進するための法と制度を再検討するためのガイドライン」とその付属文書を作成した。これらの文書は、1998年7月の「湿地に関連する法と制度を再検討するための方法論の構築」をテーマとした国際ワークショップの結果を基にしたものであり、このワークショップではオーストラリア、カナダ、コスタリカ、インド、ペルー、ウガンダ、そしてワッデン海事務局からの報告がなされた。
129.いくつかの国では、新しい法律が必要とされている、あるいは期待されている。例えばアフリカ諸国の多くは、法律に従わない場合に関して明確な法律の規定や罰則を設けることが望ましい。他の国々では、自主的な取組や、土地の管理者としての自覚を持った取組(スチュワードシップ)のような、規制によらない解決策を推進することに比べると、新しいあるいは追加の法律を作ることは効果的ではないと思われる場合もあるだろう。こういった政策の実行にあたっては、NGOや地域の組織が効果的なパートナーとなるだろう。法律が必要かどうかといった点や法律に関わる取り決めが国によって異なるので、この課題に関する標準的な規則や公式といったものはない[事例研究5 ☟、事例研究6 ☟]。
130.法律や政策における相互互換性、共同作用、利害の衝突といった事項を分析することが(認識された利害の衝突を解決することを目的として)必要となる。既存の法的メカニズムを利用できる場合もあれば、新しい法律を考慮することが必要な場合もある。法的検討はまた、政府の湿地保全目的とは相容れない、あるいは時代遅れになってしまったと考えられる法律や政府政策を改正したり廃止したりすることを意味する。これは政府内部での競合する利害による対立を招いてしまい、困難となる場合もあり得る。
131.法的必要性や機会は国によって異なり、特に途上国と先進国の間で、さらに経済状態や政治的体制が著しく異なる場合にその違いが顕著である。新法の導入と、その実施及び遵守が成功するためには、新法が機能するように図る関係者の忍耐力がテストされることになるだろう。
132.原則的には、法律によってもたらされる強制的な取組よりは、自主的な行動の方が好まれる傾向にあると言えるだろう。しかしながら、最終的には強制的に実行させることも可能だという条項を設けることによって、関係者が自主的に取り組もうとしなくても求められる結果をもたらせるよう基本的な能力は確保しなければならない。
133.湿地政策は、他の政府機関の(おそらく利害的には対立しかねない)優先事項や政策との協議を図り、調和を保つように実施されなければならない。すなわちひとつの機関が、プロセス全体を機能しうるようにするために、十分な影響力あるいは権限を備えて中心的役割を果たさなければならない。こういった場合には、高級幹部が参加(例えば副大臣レベル)し、閣僚に直接報告する義務を持った、省庁間にまたがる湿地政策委員会が効果的となるだろう。
134.政策では「何が優先されるか?」という質問に対して、単純な答えはない。他の省庁の責任、義務、あるいは法的権限が、湿地の保全とワイズユースに関して政府が望む目標と利害が対立することもあるだろう。中央省庁が政策を策定し徹底させる実権を与えられている国家もあれば、より非公式な、助言を提供する立場としてしか機能しない国もある。省庁が主導し実施する程度というのは、中央政府の個々の分野における責任機関の強さや弱さをしばしば反映するものであるし、その組織の憲法上の位置づけにもよる。
135.先に述べたように、「国家湿地政策」の実施において、その策定や協議段階の初めから、影響を受ける省庁が関与することが必要不可欠である。いくつかの例で、「湿地政策省庁連絡委員会」は政策の採択前、そして採択後にも効果的であった。こういった委員会は、様々な課題において意見の一致を生み出し、利害対立を解決し、省庁間の実施に関わる手続きを簡略化するのに役立つ。
136.政策のための多くの戦略が、政府機関(そしてNGO)の既存のプログラムや関連組織の活動を協調させることによって、実施可能である点もまた認識されてよい。そのためには、そういったプログラムを一部手直しする場合もあり得る。こういった取組において重要なのは、既存の予算とスタッフを効果的に用いることによって、「政策」実施のための新しい予算措置において大きな節約となりうる点である。また、このことは、各国にとって、援助を必要とする明確かつ個別の必要性のみに国際的な援助の焦点を絞るにあたって、大きな助けとなる。
137.こういった既存のプログラムを手直しするための技術としては、既存の優先事項の評価、特定のスタッフの業務における方向性の修正、そして職員研修が実施できるよう合理的かつ注意深い態度で新たな取組や技術の統合を図ること、等がある。こういった方法はすべて、官僚として働く人々が業務過剰になることや未知の取組に対して恐れをいだくのではなく、むしろ彼らの支持を生み出すように機能させなければならない。
138.政策や科学的事項に関する専門家をスタッフとして擁するだけの資源を備えて、中央政府の特定機関を政策実施の中心機関として任命しなければならない。この機関は、アドバイスの提供、研修の企画、そして省庁間の相互調整を行うことになるはずである。理想的には、国内の湿地に関する専門能力を有し、組織として湿地や環境保護に関する国内及び国際レベルでの経験を持っている機関であるべきである。多くの場合、ラムサール条約における責務履行の担当機関として任命されている機関と一致することになるだろう[事例研究7 ☟]。
139.『実施計画(作業計画)』にそれぞれの戦略が短期的そして長期的にどのようにして、そして誰によって実施されるかを記してもよい。もし新しい財源が利用できるようであれば、国家にとって計画実施のために適切な期間の展望、例えば5年−10年といった期間に基づいて必要となる予算やスタッフを規定することになる。新たな財源が供給されない場合には、こういった予算に関する段階は必要でないが、個々の政府機関がそれぞれ既存の予算やプログラムを用いて政策を実施するように求める戦略が必要となる。
140.個別の状況に応じて、行動計画やプログラムを提供する最善の方法が決まってくる。例えば、それらが「政策」自体の一部として(付属書として等)提出される場合もあるだろうし、担当省庁の既存手段の中に組み込まれるのが最良の場合もあるだろう。
141.「国家湿地政策」の鍵となるのは、政府が明らかにした公約を確実に実行に移せるようにすることである。ここには、誰がいつまでに、どのような水準まで、何をしなければならないか、そしてこういった情報がどこで入手できるか、といった事項について明確にすることが含まれる。この「確実に実行に移せるようにする機能」に対して責任のある担当者はこの段階で、扱う範囲に見落としがないか、すなわち、「政策」の中で示唆されたすべての行動が実際に「実施計画」の中に見いだされるかをチェックし、そしてギャップが有ればそれを埋めるような手段を講じなければならない。行動を段階的に実行するようにすること、それらを連続的に構成することが、関連する箇所に明確に記されていなければならない。行動計画では、(あるレベルにおいて)行動が計画されたように実施されなかった場合にどうすべきかも示唆しておかねばならない。
142.湿地管理官たちのための環境影響評価に関する研修、あるいは企画担当官のための「政策」全体像に関する研修、そして全般的な湿地についての研修は、湿地政策実施の成功のためには絶対必要である。これは取捨選択可能なオプション、または良識だと考えてはならない。湿地の調査、管理、そして監視についての研修を促進することは、ラムサール条約第4条5項の下での責務である。
143.湿地研修に関しては多くの取組の例がある。これらの中には、様々な機関が実施している、地域を対象にしたものや国家レベルでの研修コースやワークショップが数多く含まれる。例えば日本の海外援助担当機関(JICA)は、第一段階として1994年から5年間、湿地保全と渡り鳥に関する国際研修コースを設立した。オランダの Lelystad の「湿地諮問及び研修センター」が運営する「湿地管理に関する国際研修コース」では、毎年6週間に渡る総合的なプログラムが提供されている。ラムサール事務局は湿地研修コースについての国際的な調査を行った。これは『湿地管理研修の機会目録』(Ramsar Bureau 1998b)として出版され、16ヶ国に及ぶ67以上の研修の取組がリストアップされている。
144.「国家湿地政策」もしくは「国家湿地戦略」を扱うための、特別な実践ガイドそして研修コースを設立した国も若干ある。ひとつの例は、『連邦土地管理者のための実践ガイド』(Lynch-Stewart et al. 1996)である。カナダ政府とその提携機関、「北米湿地保全協議会」(本部カナダ)は、『湿地とともに働く』と銘打った研修コースを実施している。これはカナダにおける連邦政府機関に合わせた形で、いくつかのプログラムで提供されている。研修コースは20名程の管理者達を対象として開催され、講義、事例研究、そして実際の湿地への視察などが含まれている。オーストラリア政府も同様の研修を検討中である。また、ウガンダでは「国家湿地政策実践プログラム」が樹立されている。
145.「国家湿地政策」が採択されればすぐに、国家レベルで湿地研修における『必要項目の評価』を行うことができるだろう。これは中身について細かく記載したものである必要はないが、課題や中心となる研修手法、主要な必要事項と欠点がどこに存在するかといった点について、概要を提供するものとなるべきである。国家レベルで考慮する価値のあるもうひとつの側面は、研修を提供する側の評価である。これには、確認された必要事項に対処するために関係しそうな、資源、コース内容、機関やコンサルタントの目録が含まれる。
146.ラムサール条約の最も興味深い側面のひとつに、各国の経験に基づいた情報を交換する伝統がある。「国家湿地政策」の分野でも、湿地政策の専門家や研究者の世界的な交流が行われてきている。本ガイドラインの著者達のうち何人かは、新たに「国家湿地政策」に取り組もうとしている国々に自分達の経験を提供してきた。例えばカナダは、マレーシア、オーストラリアや他のいくつかのラムサール条約締約国が「国家湿地政策」を策定するために、非公式に助言を提供してきている。同様に、オーストラリアとウガンダは非公式な形で、アドバイスをボツワナに提供しているし、バードライフ・インターナショナルはトリニダード・トバゴに助言のできる専門家を派遣した。
147.こういった交流では、招聘による短期間の訪問やサバティカルの利用といった例もあれば、内々での助言や政府原案の検討等に関わる非公式な文書交換といった場合もある。協議のためのワークショップ、NGOとの共同作業、政府高官との話し合い、財源確保のための仕組みを探る方法、そして草案作成といった事項への提案が含まれている。こういった提案内容は関係者によって、有益であり積極的な取組となったと見なされている。今日までこういった取組はどちらかといえば非公式なものであったが、非公式であるが故に、招聘された専門家が短期コンサルタントかつアドバイザーとして、1国から場合によっては数ヶ国に及んで旅行することもできた。「政策」策定に関してある締約国が得た経験を分かち合うことで、地方レベルでも専門的能力が高められる。どの場合でも、地域の必要性や状況に適合させるために大幅な応用が必要となる。ラムサール事務局は、条約締約国の間のそういった交流を促すよう支援してくれる。
148.「国家湿地政策」とその関連プログラムの実施において、独立してはいるが必要不可欠な要素として、2種類のモニタリングの実施がある、すなわち、⒜湿地の健全性と土地利用に関するモニタリング、そして⒝プログラムの成功に関するモニタリング、である。いずれも、湿地に関する取組を、「政策」の方向性や政策を必要とした課題に対応するよう助けてくれるだろう。
149.湿地モニタリングには、気候変動、汚染その他、長期的影響に対応して変化する湿地の生態学的事項、すなわち、動植物相、水文学あるいは化学についての認識が含まれる。国家や地域レベルでの野生生物生息地/土地利用の研究をとおして、直接的な自然環境保全の取組が成功しているか否かを評価できるようになるだろう−すなわち、湿地の喪失はまだ起きているのか? もしそうならそれはなぜか? といった疑問に対する答えを提示してくれる。
150.「政策」が成功したかどうかについてのモニタリングは、通常プログラムごとあるいは組織レベルで行われる。例えば、スタッフの勤務時間が拡充されるように資源が提供されているならば、それはよく目標に合致したものであるのか? 現在のデータシステムは、プログラムがどこでどのようにして機能しているのかについて、政府に適切な情報を提供しているか? 「政策」の目的は達成されつつあるのか? 「政策」は、それがうまく機能しているかどうかを判断する方法、自己モニタリングの手法、さらに究極的には、必要があれば調整を行うための手法、これらが備わっている必要がある。
151.「政策」の最後の部分は、文書内で引用された文献の目録である。報告書はまた、さらなる研究や、引用文献の内容をさらに深めるために選択された、国内そして国際的に興味深い文献についての総合リストを付属文書として含むこともできるだろう。どの場合でも、一般の人々が参照することができる資料のみを含むようにすることが望ましい。もしいくつかの資料が特定の人々しか利用できない部類のものだったり、絶版のものだったりすれば、そのような文献リストはあまり役に立たない。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
Lynch-Stewart, P., P. Niece, C. Rubec and I. Kessel-Taylor. 1996. The Federal Policy on Wetland Conservation, Implementation Guide for Federal Land Managers. Canadian Wildlife Service, Environment Canada. Ottawa, Canada. 32 p.
North American Wetlands Conservation Council Canada. 1998. A Wetland Conservation Vision for Canada. Booklet. Ottawa, Ontario. 8 p.
Pritchard, D. 1997. Implementation of the Ramsar Convention in Trinidad and Tobago. Royal Society for Protection of Birds and BirdLife International. RSPB Sabbatical Report. Bedfordshire, United Kingdom.
Ramsar Bureau. 1987. Review of National Reports Submitted by Contracting Parties and Review of the Implementation of the Convention Since the Second Meeting of the Conference in Groningen, Netherlands in May 1984. Document C.3.6, Proceedings, Third Meeting of the Conference of the Contracting Parties. Convention on Wetlands. pp. 231-236. Regina, Canada.
Ramsar Bureau. 1990. Review of National Reports Submitted by Contracting Parties and Review of the Implementation of the Convention Since the Third Meeting of the Conference in Regina, Canada in May/June 1987. Document C.4.18, Proceedings, Fourth Meeting of the Conference of the Contracting Parties. Convention on Wetlands. Vol. 3: pp. 351-354. Montreux, Switzerland.
Ramsar Bureau. 1993. Review of National Reports Submitted by Contracting Parties and Review of the Implementation of the Convention Since the Fourth Meeting of the Conference in Montreux, Switzerland in June/July 1990. Document C.5.16, Proceedings, Fifth Meeting of the Conference of the Contracting Parties. Convention on Wetlands. Vol. 3: pp. 469-485. Kushiro, Japan.
Ramsar Bureau. 1998a. Regional Overviews of the Implementation of the Convention since the Sixth Meeting of the Conference in Brisbane, Australia in March 1996. To be published in the Proceedings, Seventh Meeting of the Conference of the Contracting Parties. Convention on Wetlands. San José, Costa Rica.
Ramsar Bureau. 1998b. Directory of Wetland Management Training Opportunities. First Edition. October 1998.
Ramsar Bureau. 1998c. National Reports of Contracting Parties submitted for COP7. Available from Ramsar Web Site http://ramsar.org; also summary papers by Regional Coordinators for Ramsar Standing Committee Meeting, October 1998.
Rubec, C.D.A. 1996. Status of National Wetland Policy Development in Ramsar Nations. Proceedings, Sixth Meeting of the Conference of the Contracting Parties. Convention on Wetlands. Vol. 10/12A: pp. 22-29. Brisbane, Australia.
Smart, M. 1993. Summary of Comments in National Reports: Guidelines for the Establishment of National Wetland Policies. Proceedings, Fifth Meeting of the Conference of the Contracting Parties. Convention on Wetlands. Vol. 2: pp. 152. Kushiro, Japan.
Shine, C. and L. Glowka. 1999. Guidelines for Reviewing Laws and Institutions to Promote the Conservation and Wise Use of Wetlands and Reviewing Laws and Institutions to Promote the Conservation and Wise Use of Wetlands, by Clare Shine. Ramsar Bureau. IUCN Environmental Law Centre Report to COP7 Ramsar Convention. San José, Costa Rica.
ラムサール条約 国家湿地政策指針
ラムサール条約の下で期待されている中心的なこととして、「国家湿地政策」を通じてワイズユースを実施することがある。ワイズユース実施を支持する「国家湿地政策」に関する行動は(勧告4.10「ワイズユース概念履行のためのガイドライン」に基づき)、5つのカテゴリーに分けられた。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
ラムサール条約 国家湿地政策指針
以下の湿地政策文書の一覧表は、現在入手可能な多くの参考資料を基にした初期段階の概略を提供しているが、多くの国々で新たな取組が定期的に現れているので完璧なものとは言えないだろう。第7回締約国会議のために提出された、106ヶ国の国別報告書の中に記載されている詳細を基に、さらなる改訂が加えられており、またラムサール事務局のホームページからも入手することが出来る。もし見落としや記述の誤りがあった場合には筆者らの責任であり、陳謝したい。もし読者が特定の報告書を入手したい場合には、ラムサール事務局がコンタクトすべき住所を提供できる。この文書は、国別もしくは一般的な地域に分けてまとめられている。引用された各報告には分類を示す略語が記載されており、次のような意味を持っている:
ラムサール条約 国家湿地政策指針
アメリカにおける湿地保全は、公的機関の戦略と民間による戦略とを組み合わせて達成されている。すなわち、政府による規制、政府や民間NGOによる湿地購入、個人所有者によるNGOへの湿地の自主的な贈与、個人所有者による開発権の贈与や売却、そして政府補助金の変更等がそれにあたる。基本的に土地利用は州や、地方政府の責任と考えられている。一方で国や州の憲法は、私有地所有者の土地利用において、政府が財政的支払いなしに個人の土地所有者に対して制限を課すのを許していない。連邦といくつかの州政府は、湿地における目標として「No Net Loss(実質上の消失を生まないこと)」を採用している。けれども、憲法によって、特定の土地利用方法を指定する政府能力には限界があり、このことが他の国々によって作成されているような「国家湿地戦略」の採択が促進されない理由となっている。
土地権利の購入は、合衆国における湿地保護のための戦略としては、最も長い歴史を持ったものとなっている。土地所有者達は政府機関や民間の土地保護トラスト団体へ、湿地の開発権利を証書を作って譲渡することを奨励されてきた。この方法では、湿地は民間による所有のままにとどまり、地方政府に対する資産税を生むことになる。しかし、土地所有者は、売るか贈与することにより、湿地を開発するすべての権利を公的機関やNGOに永遠に譲渡することができる。多くの場合、証書による譲渡においても、政府機関による政策の将来的な変更が起こった場合に対して、その土地を保護することを恒久的な法的義務としている。湿地の獲得と贈与は、1930年代からの合衆国の湿地保護においてきわめて重要な戦略であったが、私たちの湿地の価値を保存するにはこれだけでは十分ではない。NGOによる湿地の所有は、合衆国における湿地保護を確実にする最も重要な戦略の1つである。民間の所有者から湿地を購入する機会に、政府が十分すばやく対応できない場合でも、NGOはすばやく行動しこれらの場所を獲得できることがある。NGOはまた、土地の購入者に証書によって恒久的に自然を保全するということを受け入れさせることができるだろうし、あるいは、NGOが継続的に監視する権利を保有するところもある。開発権利の売却や贈与は、多くの地域で定着してきており、湿地保全における中心的な役割を果たすことができる。
湿地に関する規制は、国家の湿地保全の目標を達成するための中心的なツールとして発展してきた。こういった規制プログラムに加えて、すべての沿岸の州は、州の潮間帯湿地についての規制を採択している。また、おそらく14の州で淡水湿地に関する規制をもっている。地方レベルでは、湿地に関する規制は、応用の仕方とその効果において著しく異なっている。同じ地域の州でも、しばしば異なる規制プログラムがあり、州をまたがる集水域についての首尾一貫したプログラムを確立するのを困難にしている。国家による湿地に関する規制プログラムも、異なる地域の間で応用の仕方も異なるという歴史を持っている。しかしながら、土地利用に制限を加える政府能力には限界があることから、規制プログラムは合衆国では重要なツールであり続けるだろう。しかし、これは他の国々ではそのまま適用されないだろう。
湿地に関する規制では、個人、企業、あるいは公的機関が、排水や埋め立てといった湿地の変更を行う前には、通常、担当の政府機関から許可を得なければならない。合衆国最初の湿地に関する規制プログラムは、マサチューセッツ州の地方レベルでスタートした。ここでは沿岸部での地域社会からの要請によって、州政府は、州の潮間帯の塩性湿原の破壊を止める規制を制定した。地域社会の市民たちはこれらの湿原が地域経済にとって重要な魚介類の大事な生育場であり、エサの供給源であると認識したのである。裁判所は人々の福利厚生を守るという点から、湿原所有者への補償が伴わなくてもこの規制を支持した。
時とともに、魚類及び野生生物の重要な生息地の保護は、合衆国の湿地に関する規制の公的目標として、法律的にもより広く受け入れられ始めている。治水における軌道修正、洪水に対する保険と災害軽減政策もまた受け入れられ始めた。これらのことは、大きな河川システムにおける氾濫源湿地の将来を約束するものであり、規則的で大規模な洪水発生の恐れがあるような氾濫源を人々が利用している場所においても、幅広く応用される具体的な原則となってきている。また、歴史的には農業が合衆国における湿地損失の中心的な原因となっているので、特定の作物を栽培させたり、土地の特定の取り扱い方法を採用させるような、農家に対する政府補助金は、合衆国における湿地保護のきわめて重要な課題となっている。農業が湿地保全に与える悪影響を減らすために、作物助成政策の修正をしたり、土地利用法の改善を促進することに、これまで以上の注意が払われている。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
トリニダード=トバゴでは国家湿地政策を準備することが、ラムサール条約履行のための国としての主要義務とみなされていたが、国内唯一のラムサール登録湿地であるナリバ湿地(もしくはナリバ沼 Nariva Swamp)が破壊されるのではないかと極めて大きな論議を呼んだ結果、緊急の課題となった。この問題は国内のみならず国際的にも重要であると考えられ、いくつもの組織が関与し議論は長引いた。その組織には、⒜林業管理部野生生物課(ラムサール条約担当の政府機関)、⒝Pointe Pierre 家禽トラスト(湿地問題に焦点を当てたNGO)、⒞他の環境NGOからこの問題に関心を持ち参加した人々、⒟ナリバ地域の利用者グループ、⒠とりわけ関心を持っている一般大衆からのグループ、等が含まれた。新聞雑誌及び放送関係双方のメディアの効果的利用や、そういったマスコミによる高い関心によって、こういった利害関係者グループの意見は広く伝えられる結果となった。
この過程で、議論全体の中心機関と位置づけられた国家湿地委員会による、利害関係者グループへの理解が自然と深められた。ナリバ湿地問題に関係しているいくつかの機関や個人も、国家湿地委員会のメンバーとなり、その結果最初の「国家湿地政策」草案編纂において、利害関係者としての見地から彼らの経験や専門知識を提供してくれた。利害関係者グループの中心となっている何人かは、この草案執筆に直接携わった。ここで協調すべき重要な点は、利害関係者の意見を求め、焦点をあてた議論や意味のある貢献を促すには、そのために統合整理された文書が必要であるということである。
「特定の問題に関心を持つ人」という、最も広義の定義による利害関係者を考慮に入れ、また、利害関係者が意見を表明できるプロセスを合理的に説明するため、2つの戦略が採用された。最初の戦略は、一般の中で関心を持つ人々、関係する政府省庁、NGO、研究機関や主要利用者グループの考えを把握するために、全国的な協議を行うことだった。これらの人々や機関を対象として、国家湿地委員会のメンバーによって「政策」草案が提出され、その後に段階的な議論のための期間が設けられた(会議の前にすべての参加者にコピーが提供された)。基調講演の形で閣僚による支持が表明されたことは、こういった取組に対する政府の決心を伝えるものとなった。
湿地のごく近くで生活している地域住民の大部分は、地域の資源に対する依存度合いが極めて高いのだが、そういった地域社会からのインプットが十分ではなかったことが、全国協議の結果明らかになった。社会経済的要因を含む数多くの要因により、彼らがこのような公式の雰囲気のものから遠ざかってしまったのである。それゆえ、国家湿地委員会の決定により、委員会メンバーのうち当該地域社会に詳しい人々が、これらの地域においてさらに協議を行うよう任命されることになった。地域におけるこの一連の協議は熱心に運営され、地域内のよく目に付く場所にチラシを掲示するなどして宣伝された。会議はくだけた雰囲気で行われ、簡単なプレゼンテーションに続いて、参加者は一見直接には関係なさそうな事柄も含めて自分達の意見を述べるよう促された。ここで表明された懸念と照らし合わせることによって、政策目標が現状に適したものであることが一層確信されたことは興味深い点だろう。
この経験から学ばれた重要な知見は、すべての利害関係者が参加すべきだということ、どういった参加の仕方をとるかは状況に応じて考慮しなければならないこと、そして考えられうる関係者のうち最も関係が深いと思われる利害関係者の意見を把握するためには、最大限の努力を払わなければならないということである。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
1987年初め、カナダ政府は『連邦湿地保全政策』策定に着手した。手始めに行うべきことは、カナダ中の利害関係者との協議を行うために、その範囲や手続きを考えることだった。そのための最初のステップとして、1987年2月に「国家諮問ワークショップ」が開催され、NGOとの協議が行われた。この会議には、全国的な環境団体の代表者と、罠かけ猟、農業、スポーツフィッシングといった湿地資源の利用者団体からの代表者、計25名が出席した。この会議の報告書が出版され、連邦及び州政府の関係する大臣に直接送付された。この中には、協議を実施するために連邦政府がこれまで用いてきた一連の行動が順序立てて説明されていた。これに引き続いて、連邦・準州・地方政府の幹部代表を含む、カナダ土地利用委員会の会議が開催された。この会議もまた報告書を作成したが、ここでは、提案されている法的拘束力を持つ湿地政策を創出するための作業の流れが図示されていた。これによりワンセットになったいくつかの政策群、もしくは一つの国家政策のどちらかが必要であることが認識された。
1987年の終わりに、連邦政府職員が最初の連邦政策草案を執筆し、情報収集のための最初の会議ひとしきりを実施した。それらの会議にはカナダ環境省や、他の関連する連邦政府機関の本部及び地方事務所の職員が参加した。これらの会議は政策草案の中心を定め、草案の長さや構成を再考するのに役立った。政策第二稿が用意され、これが綿密で全国的な協議プロセスの基礎となった。連邦政府は、3つの異なるレベルの協議のいずれかを実施することができると判断した。すなわち、1)閣僚間の協議、2)政府機関及び全国的環境団体や利害関係者グループの間の協議、あるいは3)一般市民の間における協議、である。カナダでは、地方において私有地を所有する者がその土地をどのように利用するかを決定する際に、連邦政策が直接影響を及ぼすことはない。すなわち、連邦政府の影響は連邦所有の土地管理及び連邦政府の管轄下にある地域に限られたものになる、と考えられたため、限定的な協議を行うという二番目のオプションが選ばれることとなった。協議のために利用できる資源的制約を考えると、このオプションが旅費やスタッフの時間の観点から、より簡単で費用もかからないと判断された。
1988−1989年の6ヶ月以上の期間に渡り、カナダ全土の12の州都すべてや他の地方都市において、連邦政府と州政府機関の両者が参加する形で合計18回の会議が運営された。これらの会議のために、提案されている政策が要約され、専門家の手により視聴覚機材を利用したプレゼンテーションが英語とフランス語で準備された。この中には標準的なQ&A(質疑応答集)も含まれていた。多くの場合、連邦政府内の検討チームから2名のメンバーがそれぞれの会議に出席し、ひとりがプレゼンテーションを行い、他方がコメントや質問を記録するという形をとった。特に北方の領土で目的地までの旅費がかさむ場合をはじめ、いくつかの会議ではチームからは1名のみが参加した。36団体のNGO、そして20団体の資源利用者グループや産業の連合会といった組織を対象として、協議会合、手紙によるやりとり、電話によるインタビューが実施された。プレゼンテーションは、財務省不動産局(the Treasury Board Real Property Bureau)や水に関する連邦部局委員会の年次会議といった連邦政府の会議においても発表された。それぞれの会議ですべての参加者に、二カ国語で作成された協議用資料が配布された。検討チームは、こういった会議でプレゼンテーションを行うために、広く航空機で旅行を行った。地域ごとの運営は手のかかるものであり、会合場所の設定から必要な資材の確保、多くの関連部局の主要職員に招待状を発送すること等、様々な準備に関係者の協力が必要となった。
政策第二稿に関する協議で表明された意見や懸念を基にして、1990年初めまでに政策第三稿が作成された。連邦内閣に提出する段階となり、第三稿における特定の表現をより受け入れられやすい形に書き直すため、枢密院での経験を持つ政策草案の専門家が雇われた。そうして、この政策実施によって影響を受けると考えられる連邦政府機関に対して、この草案が再び配布された。ここでの議論は実施のための資源や戦略を考慮し、政策の補完となる提案書を草案し財務省へ提出するといった最終ステップに焦点を当てたものとなった。1991年終わりに湿地政策は最終的な検討のために、『緑のプラン』と呼ばれる「政府環境イニシアチブ及び内閣への覚え書き」の一部分として、連邦政府機関へ配布された。これは1991年12月に採択され、その後も適切な機会を通じて政府機関内での協議が続けられ、最終的には1992年3月に連邦政府環境大臣によって公布された。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
連邦制をしいている国家においては、湿地の保全やワイズユースを確かにする適切な政策機構の考案策定はとりわけ大きな挑戦となる。オーストラリアの例でも、大部分の連邦制国家と同様、土地と水資源の管理について日常的な法的責務を持っているのは州政府である。したがってオーストラリアが、ラムサール条約のガイドラインに従って湿地政策について国家的な取組を行うことを決定した際、すべての州と領域の管轄とともに英連邦(国家)政府の関与を確実なものとすることが必要とされた。
オーストラリア政府が『オーストラリア連邦政府湿地政策』を1997年の「世界湿地の日」(World Wetlands Day)に立ち上げたとき、(全8州のうち)一つの州(ニューサウスウェールズ州)はすでに同様の政策を持っていた。連邦政府の湿地政策には6つの戦略があり、その中の一つには『州/領域及び地方政府とのパートナーシップでの活動』が含まれている。この戦略の下での優先事項は、「州/領域政府とのパートナーシップで、彼らがその管轄区域における湿地政策もしくは戦略を策定するために協力する」こととなっている。
この時点から、オーストラリア政府は中央政府の湿地政策の補完となる、州や領域における湿地政策の策定を奨励し、支援してきた。1997年終わりには西オーストラリア州政府が州湿地政策を採択した。ビクトリア州政府は、湿地に関わる特別なセクションを組み込み州全体を対象とした『生物多様性戦略』を採択した。他の4地域(ノーザンテリトリー、クイーンズランド州、南オーストラリア州、タスマニア州)は、いずれも政策の準備中でありそれぞれ異なる段階にある。こうして、中央政府とこれら7地域に続いて、湿地政策を考慮すべきはただひとつ、首都地域のみとなった。
このオーストラリアの事例からは学ぶべき多くの教訓がある。連邦政府がまずそれ自体の湿地政策を制定することによって、州政府に対してリーダーシップを見せることが重要であった。この政策は、取り組むべき幅広い問題を扱うという点において、モデルとなった。同様に重要なのは、連邦政府が連邦の湿地政策を策定する過程全般において、地方政府と協議を行ったことであった。このことは、これらの行政当局との業務パートナーシップに関する文書で確認されている。
いったん連邦湿地政策が採択されてからは、他の行政当局が湿地政策を策定するよう奨励する過程は、部分的には政治的手段や財政的手段を通じて達成されている。オーストラリアは連邦政府内に各州の環境大臣による協議会を有しており、彼らの間においても独自に協力業務に関して協議し合意形成を行うための定期的な会合を持っている。湿地政策の補完となる枠組み策定は、こういった会合の支持を得ている。また、ラムサール条約の国内での履行に関する「作業部会」があり、合意を得た上での国家的な取組に向けての活動を担っている。
連邦政府はまた、生物多様性保全と自然資源管理に資金を提供する主要プログラム(「自然遺産トラスト」)を設立している。このプログラムを通して、州政府によって優先される政策策定やその他の活動、さらに地域レベルでの現場プロジェクトに資金が配分されている。このプログラムの下で、連邦政府は8地域の州政府に対して、それぞれの湿地政策策定を含め、適切な湿地プロジェクトへの財政的支援を提供している。この協力基金アプローチは、政策策定過程を加速するのに役立っている。これはまた、湿地管理能力の改善や湿地に関する知見を高めるために必要となる資源を、州政府に提供している。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
湿地管理に直接あるいは間接的に影響を及ぼす、複数の政策が存在する場合がしばしばある。湿地の保全と管理は、たくさんの機関や組織が責任を共有している。「国家湿地政策」の策定では、重複を避けるために、これら分野別の政策の成功、失敗、そして関連性を考慮すべきである。同様に新しい政策が既存の法律と対立しないようにするために「国家湿地政策」は湿地に関わる既存の法律を考慮しなければならない。
既存の政策と法律の検討では、政策形成の過程を指導し、様々な省庁とそれらの機関に関する問題を「国家湿地政策」の中に正しく文書化され統合されるように図る、「関連省庁間の委員会」の設立が助けとなる。
ウガンダの場合、特に既存の法律を検討するために一連の研究が行われた。この研究によって、ウガンダ国内には湿地保全全般に直接関わる法律はないことが明らかになった。しかしながら『公有地法』と『公衆衛生法』において、沼地(湿地の一つにすぎないが)に関する言及があった。研究ではまた、これらの法律の執行は、湿地保全を保証する上では十分ではないということがわかった。この研究は「ウガンダ国家湿地政策」の最初の草案の準備において欠かすことのできないものとなった。
法律は、それ自体では十分でないとしても、特定の政策の支援するうえで役立っている。様々な分野別の法律に湿地問題を取り込んでいくことは、それぞれの部局に関する限りにおいて役立つだけであり、湿地の持っている様々な分野にまたがるという性質を反映しない恐れがある。湿地政策に先立って法律を制定する、あるいはその代わりとして法律を位置づけることは、好ましくない影響をもつかも知れない。ウガンダの場合、法律が過去において人間活動を制限するように意図されており、湿地保全のための奨励策は全くと言っていいほど含まれていなかったからである。
法律の検討はまた、湿地に影響を及ぼす政策の悪い側面や、法律を修正するために必要な行動を確認するために重要である。このようにして新しい法律が既存の法律と対立しないようにし、あるいはそれらが機能しなくなるようなことを避ける。こういった検討はさらに、湿地管理に責任をもつ機関が実施すべきことを見極めるのに役立つものとなる。
ウガンダで「湿地政策」が一旦採択されてからは、この政策の実施を支援するために法律を制定することが不可欠であると考えられた。このための法律は、国会が制定する法律として独立した法律、あるいは環境に関する法律、規則、条例の傘下の一部という形をとることができると確認された。ウガンダでは内閣が、「国家湿地政策」実施のための法律準備に関するガイドラインを承認している。政府は当時また、「国家環境政策」を考案中であった。この結果として、湿地保護のための条項が『国家環境法令』の中に組み込まれることになった。これは国家レベルでの詳細な規則、そして県および地方レベルではそれぞれ適切な条例や法令によって補足される。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
アメリカ合衆国では、アラスカとハワイを除く48州においてかつては8900万ヘクタールあったと推定された湿地のほぼ半分が1700年代以降に消失している。最近では消失の速度は劇的に減少してはいるものの、合衆国では毎年実質約4万ヘクタールの湿地が減少を続けている。我々の湿地への取組は、湿地を含む土地において個人や政府が行う活動の規制を、様々な連邦政府機関や自治体が実施できるように、法律をつなぎ合わせることで年々発展してきたと言える。
1899年以来、湿地に関係する25の連邦法が制定されている。最初の法令は、1899年の「河川及び港湾法」で、湿地を含む水路において運航を妨げる恐れのある、浚渫、埋立、その他の活動を行う場合には、陸軍工兵隊の許可を必要とするというものであった。これらの法律は全般的に見ると、⑴湿地として指定された地域で実施される活動の規制、⑵排水や埋立といった特定の活動を防ぐために、購入や保護のための地役権を通じた湿地の獲得、⑶破壊された湿地の復元や新しい湿地の創造、⑷湿地の改変を抑えるような方策、あるいは湿地を自然状態で保護するための奨励策、といった手法を含んでいる。
多数の法律と36の連邦政府機関が関わっているにもかかわらず、多分むしろそのせいでと言っていいだろうが、湿地に関する連邦政府の努力を改善し調整するための試みは、1970年代後半まで実施されなかった。カーター大統領は連邦政府機関の行動を指示する、2つの大統領令を発令した。一つ目は、湿地の破壊を最小に抑え、連邦政府による土地の収得や処分において責任を果たす際に湿地がもたらす恩恵を保存し向上するよう、また、湿地地域における新たな建造物の建設助長を避けるように指示し、水資源及び関連する土地資源における計画策定、規制実施、許可制度の運用といった、土地利用に影響するプログラムを連邦政府機関が実施する際の指針を提供したものであった。二つ目は、洪水管理に焦点を当てたものである。
1989年にブッシュ大統領は『湿地のNo Net Loss(実質上の消失を生まない)』を国家目標として設定した。彼はまた、国家目標として「湿地のNo Net Loss」を達成する方法を検討するため、「国内政策協議会」の中の「環境、エネルギー、自然資源作業部会」の下に、政府機関間の協議による最初の「湿地検討部会」を設立した。「検討部会」がやるべき業務は、⑴湿地の保護、維持、復元の強化、実施、執行のために連邦政府機関に明確な指示を提供すること、⑵「No Net Loss」目標達成のために政府機関の関与を調整すること、そして、⑶今後どのような段階が必要となってくるかを決めるために連邦、州、地方政府による「No Net Loss」目標の実施程度を評価すること、となっている。1993年、クリントン政権は、中期目標として国内に残っている湿地の「全体として実質上の消失を生まない」こと、そして長期目標として国内湿地の質と量とを向上することを宣言した湿地計画を発表した。1998年の「水質浄化行動計画」で、クリントン政権は2005年から毎年2万ヘクタールに及ぶ湿地を実質で増加させる(net gain)ための戦略を公表した。現在、「連邦湿地政策に関する政府機関作業部会(ホワイトハウス湿地作業部会)」が連邦湿地政策に焦点をあてた話し合いを進めている。この作業部会では、湿地資源を保護するための主要手段として規制措置に依存している連邦政府のやり方を改め、規制によらないプログラムを強化することによって、長期的に湿地を増加させることを目的としている。1998年6月には、連邦政府機関がそのプログラムと活動を、国内のサンゴ礁を保護するために利用するように、大統領令によって指示が行われている。
湿地の消失を生まないように、政府プログラムの効果が改善され続けるとしても、合衆国の湿地戦略全般において、湿地における規制とその執行は今後も重要な役割を果たすことになる。湿地の実質上の増加を達成するためには、規制プログラムによって全体として実質上の湿地消失が生じないようにすると同時に、湿地の復元や機能向上を奨励し支持するように、土地所有者や地域社会と協力的に行動することが必要となる。湿地を復元する連邦の努力と同時に、州、部族、地方、企業や個人において、継続的な前進を達成していくことが戦略の重要な構成要素となる。連邦政府のプログラムとそれ以外の努力との間のパートナーシップを強化することもまた、実質上の湿地増加という目標達成のために重要となる。
ラムサール条約 国家湿地政策指針
マレーシアは1994年にラムサール条約に加盟し、1995年に国家湿地政策策定を支援するために、条約の小規模助成基金から資金を受け取った。これは科学技術環境省(the Ministry of Science, Technology and the Environment: MOSTE)の政務官(Secretary General)が議長を務める、ラムサール条約国家運営委員会によって管理された。メンバーには、連邦及び州政府の関連機関、大学、研究機関、国際湿地保全連合アジア太平洋地区の代表等が含まれている。
最初の段階においては、他の国々のおける湿地政策の多くの例が検討、研究された。カナダの湿地政策の専門家が、ラムサール条約国家運営委員会が主催した連邦湿地保全政策策定会議に招待され、カナダの経験に基づいて講演を行った。3種類の異なる湿地所有形態に関する課題がとりあげられた。すなわち、連邦、州、そして私有地における課題である。政策を策定する手順と枠組みが提案され、委員会はこれを了承した。検討チームが作られ、そのメンバーは、農業省、林業省、灌漑干拓省、水産省、野生生物国立公園省、それと共にマレーシア森林研究所、経済企画局、法務長官官房室、マレーシア国立大学、科学技術環境省、国際湿地保全連合アジア太平洋地区の代表からなっていた。検討チームの業務は、背景説明文書及び政策要旨の作成、そして議論が進展し形が整っていくにつれてそれらの内容の再検討に協力することであった。
背景説明文書は、マレーシアの州及び連邦政府の主要機関及び関連すると思われる機関すべてに配布された。マレーシアには13の州がある。国際湿地保全連合アジア太平洋地区と科学技術環境省によって、1996年4月に「国家湿地政策枠組み策定に関する全国ワークショップ」が開催された。ワークショップの主要な目的は、背景説明文書を改善するために、様々な利害関係者による意見を交換しそれらを反映させることにあった。文書は3つのセクションに分かれていた。⒜湿地政策が必要な理由、⒝目標についての声明文、そして⒞戦略と提案された戦略それぞれの実行計画、であった。ワークショップから出された勧告はすべて背景説明文書に組み込まれた。全国ワークショップに十分な形で代表団を派遣できなかったいくつかの州においても、協議のための個別のワークショップがその後開催された。これらで論議された点は文書の中に反映され、さらに検討チームが改訂を行った。
1997年7月に、背景文書を基にして政策を準備するための「起草委員会」が組織された。科学技術環境省の政務官が、マレーシア森林研究所(the Forest Research Institute of Malaysia: FRIM)の所長を起草委員会の委員長に任命した。委員には、マレーシア森林研究所、科学技術環境省、連邦経済企画局、灌漑干拓省、マレーシア国立大学、そして国際湿地保全連合アジア太平洋地区の代表がなった。委員会は草案を考案するために、1997年7月から1998年5月までの間に5回会合を持った。こうして政策案は形となり、1998年3月に公布されたマレーシア国家生物多様性政策の策定に関わったメンバーによって補強された。1998年6月、政策案は科学技術環境省の政務官に、検討のために提出された。
国家委員会の勧告において、科学技術環境省は政策案を議論するために、最終的な全国ワークショップを企画することを求められていた。国際湿地保全連合アジア太平洋地区と科学技術環境省はこのワークショップを企画し、1998年11月に開催した。ワークショップに先立って、政策案は連邦政府機関、様々な州の経済企画局、そしてNGOに配布され、ワークショップに参加する前に意見をまとめるための十分な時間が与えられた。ワークショップでは、多くのコメントや提案がなされた。『湿地』の定義、「政策」が必要となる根拠、湿地の機能と恩恵、湿地への主要な脅威、湿地の管理主体、法的枠組み、目標に関する声明、目的、ガイドとなる原則、戦略と適切な行動計画、そして専門用語の解説といった事項で話が進められた。さらに参加者は、コメントを書いて1998年12月終わりまでに事務局に送付することが求められた。
この次にはどうなるのか? 起草委員会は1999年初めに会合を持ち、すべてのコメントを考慮することになっている。次のステップは、最終的な国家湿地政策案をすべての関係者、特に各州の経済企画局に送付することである。もし最終案が支持されれば、承認のため科学技術環境省に提出される。そして科学技術環境省の大臣が、『湿地に関する国家政策』の内閣承認を求めることになる。近い将来にこれが実現することを望みたい。
[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.6 Annex "Guidelines for developing and implementing National Wetland Policies", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/key_guide_nwp_e.htm.]
[和訳:日本弁護士連合会.2002.第45回人権擁護大会 シンポジウム第3分科会基調報告書 資料編「うつくしまから考える豊かな水辺環境−湿地保全・再生法制定に向けて−」:81−137頁.
許可を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2006年9月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページにおおむね従い.本文中に上向き[☝]及び下向き[☟]の指差し印を用いて頁内リンクを加えた.]
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_guide_nwp_j.htm
Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).