| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日
1.決議5.5において科学技術検討委員会(STRP)を設立し、適切な科学技術の知識を備えた人材から構成されるべく、その構成員は締約国会議(COP)が任命し、出身国の代表としてではなく個人的資格で参加するものと決議されたことを想起し、
2.また、STRPの構成員ならびにその作業を計画する方法を引き続き修正した決議Ⅵ.7及び決議Ⅶ.2を同じく想起し、
3.さらに、決議Ⅷ.28において2003−2005年の3年間に実施すべきSTRPの『運用規則』が確立されたことを重ねて想起し、
4.第8回締約国会議(COP8)以降のSTRPの構成員、オブザーバー機関、そして個別に招待された専門家による寄与、そして本締約国会議に決議Ⅸ.1付属書として提出された新指針や改訂指針ならびに「ラムサール技術報告」等、条約履行に重要な多くの科学技術的問題に関するその専門的助言に対し感謝し、
5.スウェーデン政府、WWFインターナショナル、IUCN、「ミレニアム生態系評価」(ならびにそれに対する国連大学からの資金援助)、世界魚類センター(WorldFish Centre)からのSTRPの2003−2005年における実質的作業を支える資金援助に対して、また南アフリカ水研究委員会、国際水管理研究所(IWMI)、バードライフ・インターナショナル、英国共同自然環境保全委員会(JNCC)、カナダのノバスコシア州自然資源省、オーストラリアの監督科学者環境研究所からのSTRP作業への様々な形の支援に対して、さらに国際湿地保全連合による2003−2005年の「STRP支援サービス」プログラムの実施に対して同じく感謝し、
6.STRP自身がその『運用規則』を検討して、その運営や所要の課題を達成するための能力と資金などの面について容易ならぬ懸念を表明し、そして能力や効率を高めるように立案された多数の提案を『運用規則』改正のために提出したことを意識し、常設委員会がその第31回会合において、STRPがその作業を効率よく時間内に達成しようとするにあたって余儀なくされているその構成や工程に関するこれらの懸念を確認したことを同じく意識し、
7.現存する膨大な知識と経験の恩恵を条約が享受するためには、STRPが各締約国内の科学者や専門家のネットワークと緊密な関係を確立する必要があることを再び強調し、
8.各国STRP担当窓口のネットワークの発展とSTRPの作業の全段階へのその関与が緊急優先課題であるということとともに、2006−2008年のSTRPを支える基本予算配分(決議Ⅸ.12)を意識し、
9.生物多様性条約、移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約)、砂漠化対処条約、世界遺産条約、ユネスコ「人と生物圏」プログラム等、「協力の覚書」や共同作業計画を結んだ条約や計画の科学技術諮問機関と協力してSTRPが作業することの重要性を認識し、
10.また、現存の専門家ネットワーク、専門家グループや学会の中には条約の「国際団体パートナー」と連携しているものもあり、STRPとこうした多くの専門家ネットワーク等とが引き続き協力することの必要性を認識し、
11.さらに、STRPの2006−2008年における緊急優先作業と最優先作業が決議Ⅸ.2付属書1に特定されたことを重ねて認識し、
締約国会議は、
12.締約国が条約を履行するために信頼できる手引きを締約国会議に提供するという、STRPの作業と助言が条約にとって決定的に重要であることを再確認する。
13.この決議に付属されるSTRPの改正『運用規則』を承認する。
14.「STRP監督委員会」を設立する。同委員会は、常設委員会に対して報告をなすものであり、常設委員会議長及び副議長、STRP議長及び副議長、条約事務局長及び事務局次長(職務上[ex officio])から構成され、この決議の付属書に提示される責任を果たすものとする。
15.常設委員会が引き続きSTRPの作業の全体責任をもつこと、ならびにSTRP議長は常設委員会会合で毎回、締約国会議及び常設委員会が確立した次の3年間のSTRP作業計画及び優先作業(決議Ⅸ.2)の進行状況を報告し、また同作業計画について必要と考えられる調整や新たに発生した問題に関する助言を提出することを確認する。
16.2006−2008年のSTRPへの支援機能は条約事務局が提供し、その緊急優先課題は各国STRP担当窓口のネットワークの発展とSTRPの作業へのその関与であることを同じく確認する。
17.STRPがその作業に効果的に取り組むために必要な資金と人材を確実に提供することと、条約事務局がSTRPの作業を支援するに十分な能力を持つようにすることのどちらもが緊急に必要であることを確認し、これらの資金の継続性を保証する貢献を締約国等に対して強く要請する。
18.各国STRP担当窓口のネットワークがSTRP作業に寄与するように、その関与を進展させその能力を伸ばすことが、2006−2008年の最優先課題であるということを同じく確認し、また同担当窓口を任命していない締約国に対して、すべての締約国がSTRPの作業に十分に寄与しかつSTRPからより効果的に支援を得るために、決議Ⅶ.2に従ってその任命を行うよう強く要請する。
19.2006−2008年のSTRP会合にオブザーバーとして招待されるべき機関や団体のリストを以下のように改定し、これら機関や団体に対して、共通の関心事項についてSTRPとの緊密な協力体制の確立を考慮するよう促す:
20.さらに、STRP構成員が締約国会議や常設委員会に参加することの価値を強調し、締約国ならびに常設委員会及び条約事務局に対して、この目的に必要となる追加資金の確保に努めるよう要請する。
21.そして、この決議に付属する『運用規則』がCOP8決議Ⅷ.28で採択されたものに置き換わることを確認する。
(原注.STRPの2006−2008年の作業の予定と工程の概要は図1を参照。)
1.この『運用規則』の重点目標は、STRPの仕組みが、湿地保全と賢明な利用に関して広く認められた専門家やネットワークによる作業を通じて、条約に対して最善の科学技術的助言を最も効率よく最大の費用対効果で提供できるような確実な手段を構築することである。
2.「STRP監督委員会」は、常設委員会に対して報告をなすものであり、常設委員会議長及び副議長、STRP議長及び副議長、条約事務局長及び事務局次長(職務上[ex officio])から構成される。同監督委員会の議長は、常設委員会議長が担う。
3.同監督委員会の責務は以下のとおりとする。
ⅰ)STRPの構成員、議長ならびに副議長を任命する。
ⅱ)STRPの運営と作業に対して、会期間の助言や手引き、支援を提供する。
ⅲ)この改正運用規則に基づくSTRPの運営について常に検討し、常設委員会へ助言する。
ⅳ)条約事務局に対して、STRPの予算項目に該当する支出について助言する。
4.常設委員会は引き続きSTRPの作業の全体責任をもち、STRP議長は常設委員会会合で毎回、締約国会議及び常設委員会が確立するSTRP作業計画及び優先作業(2006−2008年については決議Ⅸ.2付属書1の内容)の進行状況を報告する。
5.STRP構成員として任命される候補者は以下のとおりでなければならない。
ⅰ)地元から国内そして国際規模で湿地の保全と賢明な利用に関する専門家のネットワークと連携するか、ネットワーク化する能力が実証されていること[原注1]。かつ/あるいは、
ⅱ)湿地保全と賢明な利用にかかるひとつ以上の分野において、特にSTRPのそれ以降の作業として締約国会議が特定した優先作業の分野と課題に関係する分野で、広く認められた経験と専門的知識を有すること。
ⅲ)特に自国のSTRP担当窓口等、地元から全国レベルまでの湿地専門家と協働を行った経験を有すること。
ⅳ)会合と会合の間の期間は電子メールやインターネットを利用してSTRP作業が実施されるため、これらのシステムが完全に利用可能であること。
ⅴ)(英語が引き続きSTRPの業務言語として用いられるため)英語を理解し読み話すことが十分流暢であること。ならびに、
ⅵ)必要な場合には構成員が所属する団体や機関から関係する支援を得つつ、STRPならびにその「作業部会」の所要の作業を行う明確な意思を表明していること。
6.6つの条約地域から各1名が構成員に任命される。これらの構成員は(地元と地域レベル、もしくは国際規模の)湿地専門家のネットワークとの経験を有し、それらネットワークとの連絡が出来ること。さらに6名の湿地専門家を構成員とし、これらの専門家達は湿地の保全と賢明な利用にかかるSTRPの作業主題の各分野の経験と専門的知識が認められる人材であること。
7.(上記段落6の)後者6名については、異なる国や条約地域から、あるいはまた世界の北部と南部といった釣り合いを考慮する。性別の釣り合いも考慮する。
8.もう1名、広報・教育・普及啓発(CEPA)に関する専門的知識を有する人材を構成員に任命する。この構成員は、STRPの成果について、利用者に必要な範囲を特定するところから成果の最終的な形をまとめるところまで、STRP作業のすべての段階で、特に条約のCEPAネットワークや条約の国際団体パートナー(IOPs)のネットワークを活用して、助言を提供することがその役割である。
9.決議Ⅸ.2で承認されると予想される作業主題の分野は以下のとおりであり、各分野について構成員1名が任命されることになる。
ⅰ)指標を含む湿地目録と評価
ⅱ)賢明な利用と生態学的特徴
ⅲ)水資源管理
ⅳ)条約湿地の指定と管理
ⅴ)湿地と農業、および、
ⅵ)湿地と人の健康
10.条約の各国際団体パートナー(IOPs)は、条約を科学技術的に支援するという進行中のその役割を考慮し、引き続きSTRP構成員を1名ずつ提供することとする。但し、3年間のSTRPの作業工程や会合を通して確実に継続できる代表をSTRP構成員に指名することが要請される。またこの指名はSTRP監督委員会により、同監督委員会の構成員任命の役割の一部として、考慮され承認される。これら国際団体パートナーからの指名を受ける者は、湿地専門家として各団体の条約地域規模ならびに地球規模のネットワークが有する湿地の保全と賢明な利用の専門的知識を維持しその窓口となる役割を各団体において果たしている者でなければならない。
11.任命されたSTRP構成員は、(下記のように)締約国会議が承認した主題にかかる課題を達成するための責任を有する各STRP「作業部会」を率いる(あるいは共同して率いる)。また、作業部会のもとに特定の優先課題を達成するために設立される「特別作業班」の作業を監督する。従って、これらの役割を引き受ける心構えが必要である。
12.構成員を任命する作業主題の分野は3年ごとに検討し締約国会議の承認を得る。それら作業分野は、2006−2008年について特定した決議Ⅸ.2付属書1のように、常設委員会及び締約国会議がその次の3年間STRPの優先事項として特定した主題や課題に従う。
13.STRPの会合予定はSTRP監督委員会が確認する。3年間に2回の全体会合を、まず締約国会議の前回会合から6か月以内に初回を、次の締約国会議の6か月前までに2回目を開くことができる。
14.各3年間の構成員の任命はSTRP監督委員会が行なう。
15.以下の各主体から候補者の指名を受け付ける。
ⅰ)各国の条約担当政府機関
ⅱ)各国のSTRP担当窓口(条約担当政府機関との協議の上)
ⅲ)その時点でのSTRP議長及び副議長ならびに、
ⅳ)その時点でのSTRP構成員及びオブザーバー
16.候補者の指名には、それまでのSTRP構成員、オブザーバー、ならびにSTRPの作業にそれまで寄与してきたことを証明する記録を有する過去に招待された専門家を、対象に含めることができる。そのような専門家の任命は、STRPで進行中の作業主題の分野における継続性を保証するものとなる。
17.候補者の指名は指名する側と同じ国の出身者に限らない。求められているのは、ネットワークに寄与する能力ならびに関係する専門的知識であり、国籍や現住所にかかわらないからである。
18.候補者の指名は、候補者の専門的知識及び経験、ならびに次の3年間のSTRPの作業への妥当性を簡潔にまとめた概要を推薦状の形式にしてSTRP監督委員会へ提出する。
19.指名された候補者は、構成員への任命を検討されることを自身が望むこと、作業時間や会議への出席を含むSTRPの構成員として作業を果たすにあたって所属する団体や機関からの完全な支援が得られること、ならびに作業に十分に従事するに必要な水準の英語技能を有することを宣言にまとめて提出することとする。そこには、会議への出席に資金的支援を必要とするかどうかも示し、また「履歴書」と共に、STRP作業に貢献できると考える自身の技能と専門的知識の要約を提出するものとする。
20.受け付けられた指名に基づいて、条約事務局が評価と推薦を取りまとめて、STRP監督委員会による任命検討に供する。同監督委員会は、STRPが出来る限り速やかに作業計画を開始できるように、3年期間の開始後可能な限り早急に電子的対話や電話会議を通じて任命を決定する。
21.3年期間の途中で構成員に空席ができた場合は、STRP監督委員会が他の指名者から検討して実施可能な限り速やかに後任を任命する。
22.STRP監督委員会が構成員の任命を検討し、次の3年間に議長ならびに副議長の職務を取るよう促す候補者を特定する。その時点のSTRP議長及び副議長はこの決定に加わらない。
23.関連する他の科学技術的団体を締約国会議がSTRPのオブザーバーとして招くことによって、これらの団体やそのネットワークの参加とインプットをSTRPの作業に引き続き役立てる。各オブザーバー団体は、STRPへの代表者を指名して参加の継続性を確保するよう要請される。これらの代表者は、国内レベルから国際レベルまでの自身の団体の湿地専門家のネットワークの窓口となる能力がなければならない。多国間環境協定の履行を合理化し調和する努力に引き続き寄与するために、オブザーバーとしてSTRPに招かれる中に、他の環境条約や協定の相当する科学技術的補助機関の議長ならびに事務局の関連職員を含めることとする。
24.任命されたSTRP構成員は、条約事務局による支援の下、締約国会議が要請する課題を進展させるのに適切な場合には、3年期間の初めに「作業部会」を設立し、その座長あるいは共同座長の職務につく。これは2003−2005年の手法を継続するものである。
25.作業部会の構成は座長または共同座長が、STRP議長ならびに副議長及び条約事務局の助言を得て確立する。その構成員には、特に他のSTRP構成員、オブザーバー団体の代表、関係する専門的知識を持った各国STRP担当窓口、関係する専門的知識を持って参加している他の専門家を含むことができる。
26.STRPの新たな問題等関連事項を戦略的に検討する機能の作業の一部として、当該作業を率いるためにSTRPが任命する人材が、次の3年期間に実施すべき緊急優先作業、優先度の高い作業、新たな優先作業に関する次の締約国会議へのSTRPからの助言を、2006−2008年について決議Ⅸ.2付属書1に提供されているのと同様にとりまとめる。
27.STRPのCEPA関連作業については、決議Ⅷ.31(行動1.1.3[訳注])の実施に当たって、その各国内レベルから条約地域レベル、国際レベルまでのネットワークからSTRPの作業へCEPAにかかるインプットと助言を提供するために、2003−2005年期間に設立された「STRP/国際湿地保全連合CEPA専門家グループ」の役割が継承される。
28.各作業部会は当該3年期間の緊急優先作業または優先度の高い作業として締約国会議が要請する作業主題の分野においてなすべき助言や指針、検討、あるいはその他のアウトプットの範囲と内容を策定する。これらを達成するための仕組みを(必要性があり資金が得られる場合に専門家と顧問契約することも含めて)特定する。また、このような資料を起案し完成させるまでの作業の進行を監督し検討する。
29.作業部会の座長あるいは共同座長は、任命された後できるかぎり速やかにその構成員を決めて部会を立ち上げ、部会が担う緊急優先課題及び優先度の高い課題の各々についての作業範囲策定に着手して、当該3年期間で初めてのSTRP全体会合に先立ってその案を供覧し、その会合での議論に供する。
30.作業部会は、当該3年期間の計画の中の特定の緊急優先課題または優先度の高い課題を達成するためそれが適切な場合には、小規模の特別作業班を設置することができる。
31.各「作業部会」はその作業主題の分野において、STRPに要請されているその他の課題(決議Ⅸ.2付属書2に2006−2011年の課題として挙げられているもの)についても、常に開始の機会を検討しておき、能力的に可能な課題は、可能となった時点でその達成に向けた仕組みを策定する。当該3年期間に新たな課題を開始する機会が得られた場合は、STRP議長がSTRP監督委員会に対して当該作業を進める適切な手段の確立についての助言を求める。
32.各「作業部会」は効率よく作業を進めるために、その多くを電子的に(電子メール、ウェブ上でSTRPを支援する手法、ならびに電話会議を通じて)作業するが、資金が許すかぎり3年期間に少なくとも一度はワークショップを開催し会合を持つものとする。
33.各国及び各条約地域からSTRP作業へ十分なインプットを確保するための重要な鍵のひとつは、2006−2008年期間に各締約国が任命するSTRP担当窓口(NFPs)のネットワークを活性化することである。この重要なネットワークを確立するという期待は2003−2005年期間にはこの分野での資金削減のために達成されなかった。
34.特に、2006−2008年期間には、各国のSTRP担当窓口は:
ⅰ)当該3年期間のSTRP構成員の候補者を指名することが促される。
ⅱ)自身が関係し専門的知識を持つ湿地の保全と賢明な利用の主題分野を(簡潔な質問表に)特定することが要請される。その結果に基づいて、関係する「作業部会」の構成員の検討対象となる。
ⅲ)当該3年期間の作業が開始されてから関係する「作業部会」へ参加し、各課題を達成する機会の拡大に寄与することが促される。
ⅳ)ウェブ上でSTRPを支援する手法を十分活用して、STRPの作業のすべての段階にインプットを提供する。それには「作業部会」や特別作業班が準備した文書案の検討も含まれる。また、
ⅴ)「ラムサール技術報告書」シリーズに出版が検討されている報告等の原稿の査読に寄与することが促される。
35.前段落に記述された役割は、決議Ⅷ.28で採択されたSTRP担当窓口[訳注]の委託事項に追加されるものである。
36.条約事務局は、STRP担当窓口に必要な能力の特定を通じ、各国内でのネットワーク発展を支援する手段を追求することも含め、STRP担当窓口ネットワークの発展を支援する。
37.STRPへの各条約地域からのインプットやSTRP作業の各条約地域に対する妥当性を確保するためのもうひとつの側面は、STRPの任務の一部として各条約地域における科学技術的優先事項に対応するという課題である。このためにSTRPは各国のSTRP担当窓口を通じて締約国に助言を求める予定である。2006−2008年の期間中に、STRPはこの作業面を達成するための仕組みを進展させる。それには特に、条約地域会合や(決議Ⅸ.7[訳注]の)条約の枠組みの下に進められる地域イニシアティブが特定した条約地域における科学技術的優先事項への対応を含んでいる。
38.専門的知識や作業経験の継続性を確保するために、適切な場合にはSTRP構成員の最少3分の1は、その次の期間も再任されるべきである。
39.STRP議長はその時点の構成員と適切に相談し、STRPの作業への寄与や締約国会議が命じた優先課題に対する専門的知識の分野の妥当性をもとにして、再任されるべき構成員名をSTRP監督委員会に推薦する。
40.再任の推薦をうける構成員は、当該の作業に寄与する自己の効力を実証し、かつ再任を望む意思を確証しなければならない。
| 常設委員会(SC)と締約国会議の予定と工程 (2007年と2008年の予定は仮のもの) | STRPの予定と工程 (運用規則−決議Ⅸ.11) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005年6月 SC第31回会合 | |||||
| ↓ | ||||||
| 2005年8月7日 決議案12の締約国への回覧 | 2005年10月 2006−2008年STRP構成員の指名要請 | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| 2005年11月7日 SC第32回会合 | 2005年12月30日 2006−2008年STRP構成員の指名締切 | |||||
| 2005年11月8−15日 COP9 決議案12の採択 | ↓ | |||||
| 2005年12月/2006年1月 STRP監督委員会による議長と副議長の任命 | ||||||
| 2006 | ↓ | ↓ | ||||
| ↓ ↓ ↓ | 2006年1月 作業部会座長による構成員の特定と優先課題の作業範囲策定と起案 | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| ↓ ↓ ↓ | 2006年3月(仮) STRP第13回会合 全体会合と作業部会ワークショップ | |||||
| STRP作業計画を報告 | ↙ | |||||
| 2006年4月10−13日 SC第34回会合 | ↙ | ↓ ↓ | ||||
| ↓ ↓ | 作業進行状況を報告 | ↙ | 2006年4月−2007年2月 優先課題の成果の起案(10か月) | |||
| 2007 | 2007年1月/2月? SC第35回会合 | ↙ | ↓ | |||
| 2007年3月 作業部会中間ワークショップ 下案の検討と改善 | ||||||
| ↓ | ↓ | |||||
| ↓ ↓ | 2007年4月−2008年1月 優先課題の成果の原稿完成(9か月) | |||||
| 2008 | ↓ | ↓ | ||||
| ↓ ↓ ↓ ↓ | 2008年1月/2月 STRP第14回会合 全体会合と作業部会ワークショップ 成果の原稿の検討 | |||||
| SCの承認に向けて成果の原稿を提出 | ↙ | |||||
| 2008年春? COP10特別部会会合(仮) | ↙ | ↓ ↓ | ||||
| ↓ ↓ | SCの承認に向けて他のCOP10文書を提出 | ↙ | 2008年2月−4月 その他のCOP10向けSTRP文書の完成 | |||
| 2008年5月/6月? SC第36回会合 | ↙ | ↓ ↓ | ||||
| ↓ ↓ | 2008年春前半 2009−2011年STRP構成員の指名要請 | |||||
| 2008年秋 COP10 | ||||||
[ PDF(228㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]
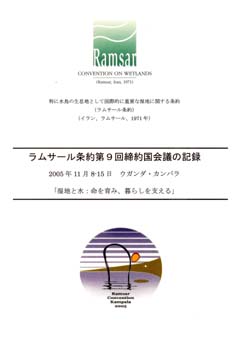 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.11.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.11.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_11_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).