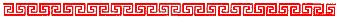
|
| |
隠元和尚擬寒山詩百詠
|
〔一〕391901
|
寒山徹骨寒 黄檗連根苦
寒盡自回春 苦中凉肺腑
先賢開後学 後進継前武
今昔一同風 利生非小補
|
|
寒山 骨に徹して寒く
黄檗 根(ね)に連って苦し
寒 盡きて自ら春を回(かえ)し
苦中 肺腑を凉しゅうす
先賢 後学を開き
後進 前武を継ぐ
今昔 一同の風(ふう)
利生 小補(しょうほ)に非ず
|
| |
〔大意〕
寒山の教えは彼の住む場所の寒さと同じように骨身に徹するほどに厳しく、
黄檗山にまで連なってあの黄檗樹(きはだ)の根の苦さとも同じである。
寒さがやっと過ぎた頃に自然と春が巡って来るように、
寒山の教えは自然と心中の苦しみを和らげてくれる。
寒山という優れた先哲がいたからこそ後進が出るのであって、
わたしたちも必ずや寒山の道風を受け継いでいくであろう。
時代が変わっても吹く風は同じで、
禅の教えが衆生を助ける様は少しなどと言うことはないはずだ。
〔注〕 この句は、廣録30首の中にも1句目に入っている。
|
|
| 〔二〕391902 |
孤迴寒山道 躋攀不等閒
奇峰高突兀 瀑布响潺湲
一陟三思退 十登九個還
若非眞鐵漢 爭透頂門關
|
|
孤迴(こけい)たり寒山の道
躋攀(せいはん) 等閒(なおざり)ならざるに
奇峰高うして突兀(とつごつ)
瀑布 响(はるか)にして潺湲(せんかん)
一陟(いっしょう)三思(さんし)して退き
十登(とう)九個して還る
若し眞の鐵漢に非んば
爭(いかで)か頂門の関を透らん
|
| |
〔大意〕
寒山の悟りは近づこうとしても広大深遠で到達し難い、
決していい加減に到達などできるものではない。
行く先々には進路を妨げるかのように奇形の峰々が兀兀と突き出ているか と思えば、
滝の流れる音 [水が飛び散る滝の音] が響き涼やかでもある。
一度登っても三度は退くことを考え、
十回登っても九回は戻る。
もし本当に堅固な精神を持った禅者でないならば、
この通り難い悟りへの肝心要の関門を一体どうやって通ったものやら。
〔注〕 この句は、廣録30首の中にも2句目に入っている。 但し、「瀑布响潺湲」部は「飛瀑响潺湲」となっている。
|
|
| 〔三〕392002 |
同心友拾得 来去無拘束
克腹飽残羹 養眞居洞壑
榮華不久留 貧賤常知足
省用世間財 免投驢馬腹
|
|
心を同じくする友は拾得
来去(らいこ) 拘束無し
腹に克ちて 残羹(ざんこう)に飽き
眞を養うて 洞壑(とうがく)に居る
榮華 久しく留らず
貧賤 常に足ることを知る
世間の財を用うることを省き
驢馬の腹に投ずることを免る
|
| |
〔大意〕
寒山は気持を同じくする拾得を友としているが、
来ようが行こうが拘束などせずにお互い自由自在だ。
腹に重過ぎるので [いっぱいなので] 吸い物を残したままだし、
真理を求める悟りの力を更に徹底するためにほら穴に起居している。
栄華の生活を長く続けることなど考えもしないし、
わずかなものがあれば十分に足ることを知っている。
欲心を捨て市井での生活をやめれば、
驢馬のように無能扱いをされることだけは免れるだろう。
〔注〕 この句は、廣録30首の中にも3句目に入っている。
|
|
| 〔四〕392101 |
正欲擬寒山 玉毫露一斑
天無少間息 人豈可偸閒
古聖混塵世 後昆力仰攀
墨池聊濺處 秀氣満林間
|
|
正に寒山に擬せんと欲し
玉毫一斑(いっぱん)を露わす
天 少間(しょうかん)の息(そく)無く
人 豈に閒(かん)を偸まんや
古聖(こしょう) 塵世に混じ
後昆(こうこん)仰攀(ぎょうはん)を力む
墨池聊か濺(そそ)ぐ處
秀氣(しゅうき)林間に満つ
|
| |
〔大意〕
まさしく寒山を真似て修行をしていたら、
仏の毛とも思える毛が一ヶ所現れた。
天はしばらくも休むことがないのだから、
人はどうして暇に過ごしておれようか。
聖人と呼ばれた寒山、拾得もこの濁世にまみれて修行をされたのだ、
後世の多くの聖人もそうであったようにわれわれもそれを範として努めな ければならない。
こんな事を考えつつ墨をすっていたら、
私を激励するかのように何とも言えない良い香りが林間に漂ってきた。
|
|
| 〔五〕392102 |
寒山路險隘 樹密不成行
高鑑無空隙 善登豈在忙
文章陳夢語 詩賦老枯腸
吹入今時調 呵呵咲一場
|
|
寒山 路(みち)険隘(けんあい)
樹(じゅ)密にして行(こう)を成さず
高鑑(こうかん) 空隙(くうげき)無く
善登(ぜんと) 豈に忙(ぼう)に在らんや
文章 夢語(むご)を陳(の)べ
詩賦(しふ) 枯腸(こちょう)に老ゆ
吹いて今時(こんじ)の調(ちょう)に入り
呵呵(かか)として咲(わら)うこと一場(いちじょう)
|
| |
〔大意〕
寒山への路も悟りの道も共に険しいことよ、
木々が生い茂り進むこともままならず修行が進まない。
目標はあまりにも高く隙間すらもないのでここからは見えないし、
巧みに登ってもどうして忙しくないなどと言うことがあろうか。
文章を書こうが夢のようなことを書き連ねるばかりだし、
詩偈を詠じても良い詩情も浮かばないことがいつものこととなってきた。
うそぶいてそのままの思いをふっと吐き出したが、
寒山にはハハッと一笑されるだけだろうし、自らも苦笑いするしかないありさまだ。
|
|
| 〔六〕392103 |
雲散長空月 花開不夜天
老人惟遠慮 浪子不歸田
堂上風光少 庭前栢影連
<眼中晷運遷>
未施如意福 爭得壽綿延
|
|
雲は散ず長空(ちょうくう)の月
花は開く不夜(ふや)の天
老人は惟(た)だ遠く慮(おもんばか)り
浪子(ろうし)は田(でん)に歸らず
堂上(どうじょう) 風光(ふうこう)少く
庭前栢影(はくえい)連る
<眼中 晷(ひかげ) 遷(うつ)り運ぶ>
未(いま)だ如意の福を施さずして
爭(いかで)か壽の綿延(めんえん)たるを得んや
|
| |
〔大意〕
雲が散って月がこうこうと照り、
花が咲き誇るようにさながら真昼のような光景である。
老いたわたしはといえば、ただ将来を心配するばかりだし、
弟子たちは修行すらしようともしない。
堂内に入ってくる風光とて少なく、
庭の柏樹の影だけが連なっている [目にはひかげが移り行くのが見える]。
自分はと言えば未だに期待される臨済禅の真骨頂を施すことも出来ない、
このようなことでどうしてのんびりと生き続けることなど出来ようか。
〔注〕 この句は、廣録30首の中にも4句目に入っている。 [ ]は廣録の詩。
|
|
| 〔七〕392201 |
百歳長宵夢 幾能醒一場
四生仝性命 何忍更残傷
布徳及鱗羽 興慈至善良
力行廣濟道 物我楽無彊
|
|
百歳 長宵(ちょうしょう)の夢
幾たびか能く醒むること一場ぞ
四生 性命(せいめい)を同じうす
何ぞ更に残傷するに忍びんや
徳を布(し)いて鱗羽(りんう)に及ぼし
慈を興して善良に至らしむ
力行(りよっこう)は廣濟の道
物我(もつが) 楽 彊(きわ)まり無し
|
| |
〔大意]
人生はその場限りの長い夢のようなものである、
何度生まれ変わろうが、はかない生涯というしかない。
人はもとより、鳥や魚と生まれに違いがあろうとも、授かった命という点では皆同じではないか、
どうしてこれ以上傷をつけることがあろうか。
徳を施すなら人ばかりか魚や鳥にも広げ、
慈愛の気持ちを興して人々を善良な方向へと導きたいものだ。
こうした努力こそがまさに衆生済度の道であり、
自分はおろか周りの人々の喜びもきわまれりと言うことである。
|
|
| 〔八〕392202 |
|
薫風来殿角 個個盡歡樂
毛孔忽生香 千年大夢覺
清凉界上行 魔佛掌中握
霹靂震雷聲 須彌驚倒卓
|
|
薫風 殿角(でんかく)より来り
個々盡く歓楽す
毛孔(もうく) 忽(たちま)ち香を生じ
千年の大夢(だいむ) 覺(さ)む
清凉(せいりょう)界上(かいじょう)の行(こう)
魔佛 掌中に握る
霹靂(へきれき)として雷聲(らいせい)を震えば
須彌 驚いて倒卓(とうたく)す |
| |
〔大意〕
迷いを誘うかのように初夏の快い風が大殿の角から吹いてきた、
案の定それぞれが好きなことをやってくつろいでいる。
私はと言えば、たちまち体中から何とも言えない香りが発散され、
迷いから一気に解放されて悟ったかのような境地である。
持戒に徹底し絶対境地に至るための修行をやっているからだ、
もう悪魔も仏もこの掌中に握りしめたも同然だ。
そんな境地を知ってか知らぬか突如の雷音のひと響きで、
須弥壇は驚きひっくり返ってしまったよ。
|
|
| 〔九〕392301 |
萬丈寒岩境 悠然出世間
俊英多意氣 耆徳獨安閒
稚鳥鳴新葉 歸雲投晩山
團圞微咲會 未易許君攀
|
|
萬丈(ばんじょう)寒岩の境
悠然として世間を出ず
俊英意氣多く
耆徳(きとく)獨り安閒(あんかん)
稚鳥(ちちょう) 新葉に鳴き
歸雲晩山(ばんざん)に投ず
團圞(だんらん)たり微咲の會
未だ君の攀(よ)づるを許し易からず
|
| |
〔大意〕
寒山のいる場所は、高い岩山がそびえたつ寒々とした厳しい地帯だが、
世俗から飛び出して悠然と入っていった。
才知は溢れ意気も盛んで、
徳の高い老人が独りもの静かに、まさに「日日是れ好日」の気持ちにひた っているようだ。
生まれたての小鳥が新緑の中で鳴き、
流れる雲はさながら夕暮れの山へと帰っていくようだ。
この団欒のような自然がほほえむ場に居ることを歓んでいるうちは、
まだお前さんがこの山に登ることを許してくれてはいないと言えよう。
〔注〕 この句は、廣録30首の中にも6句目に入っている。
|
|
| 〔十〕 392302 |
吾有一寶劍 可擬不可見
放去寂寥寥 拈來光燄燄
護身億萬秋 今朝畧顯現
魔軍若到來 斬作千萬片
|
|
吾に一つの寶劍有り
擬(ぎ)すべくして見る可からず
放ち去れば寂(せき) 寥寥(りょうりょう)たり
拈(ねん)じ來れば 光燄燄(えんえん)たり
身を護(ご)す億萬秋(ばんしゅう)
今朝(こんちょう) 畧(ほ)ぼ顯現す
魔軍若し到來せば
斬って千萬片と作(な)さん |
| |
〔大意〕
私は何ものをも断ちきる一ふりの宝剣を持っているが、
それが本物かどうかなどと疑って見てはならない。
ひとたび抜き放てば辺りは恐れて静まりかえりひっそりとし、
念ずる様に持てばその輝きは煌々たるものだ。
この私を生涯守ってくれるはずで、
その力が今朝ほぼ現れた。
もしわたしの修行を邪魔する悪魔たちが押し寄せたとしても、
この宝剣で斬って斬って斬りまくり千万片としてしまうだけだ。
|
|
| 〔十一〕 392401 |
寒山不可擬 擬則隔千尋
若昧先賢旨 活埋古聖心
八紘空眼界 一筆寫胸襟
併作巖中響 聲光應古今
|
|
寒山 擬すべからず
擬すれば則ち千尋を隔つ
若し先賢の旨(し)を昧ませば
古聖(こしょう)の心を活埋せん
八紘(はっこう) 眼界を空しうし
一筆 胸襟を寫す
併せて巖中(がんちゅう)の響と作し
聲光(しょうこう) 古今に應ぜしむ
|
| |
〔大意〕
寒山の生き方や悟りを真似ようなどとするべきことではない、
真似たところでますますその違いを思い知らされるだけだ。
もし寒山の教えに暗いようならば、
折角の彼の教えを空しく葬り去ってしまうだけだ。
宇宙の隅々にわたるまで何もかもを目に入らないようにすれば、
一走りの筆で心の中を露わに出来るはずである。
併せて寒岩中の響きと出来れば、
その響きや輝きは寒山はおろか、古今の聖人の教えに呼応するほどに響か せられるはずだ。
|
|
| 〔十二〕 392402 |
道情不可測 妄念亦難量
探海海無際 窮天天更長
外尋眞鹵莽 内省是賢良
古者既如此 今何徒自忙
|
|
道情(どうじょう) 測るべからず
妄念も亦た量り難し
海を探(さぐ)るに 海に際(きわ)無く
天を窮むるに 天更に長し
外(ほか)に尋ぬるは 眞に鹵莽(ろぼう)
内に省るは 是れ賢良(けんりょう)
古者(いにしえ) 既に此(か)くの如し
今何ぞ徒らに自(みずか)ら忙しうせん |
| |
〔大意〕
修行への想いは人それぞれで、それを窺い知ることなどとても難しいことだ、
ましてや、妄念などはもっと知りがたい。
広い海を知ろうとしてもその海の広さに際限があろうはずがなく、
天を窮めようとしても、その天は海以上に広大であるのと同じことだ。
外に向かって道を尋ねようなどとは本当に粗忽なことであり、
己事究明こそが賢明というものである。
昔からすでににこんなことだと分かっているのに、
今の私達がどうして自らを忙しくする必要があろうか。
|
|
| 〔十三〕392403 |
烏兎走雲霓 忙忙東復西
両輪相互照 萬物豁然齊
雲散千林暁 春歸百鳥啼
道高超象外 魔類絶攀躋
|
|
烏兎(うと) 雲霓(うんげい)に走り
忙忙として東復(ま)た西(にし)
両輪相互に照らし
萬物豁然(かつぜん)として齊(ひと)し
雲散じて千林(せんりん)暁(あ)け
春歸りて百鳥(ひゃくちょう)啼く
道(どう)高うして象外(しょうがい)を超え
魔類(まるい) 攀躋(はんせい)を絶つ |
| |
〔大意〕
太陽と月が雲や虹の間を行き過ぎ、
ただ忙しく東から西へと走り回っていくように年月が過ぎていく。
この世の中のことは、常に日月の両輪が相まって相互に照らしあい、
万物はこうして明確に保たれているのだ。
重苦しい雲が散った後は、森の木々が息づきはじめ、
春が戻ってくると多くの鳥たちが啼き騒ぐ。
わたしの求めている道は崇高で目で伺い知ることが出来る以上の世界だ、
悪魔が近寄ることすら絶ってしまう世界である。
|
| |
|
| 〔十五〕392502 |
拂拂南來風 青青楊柳色
閒談絶點塵 略試出標格
満腹是經綸 所行鬼途轍
嗟嗟大博士 返作狼煙客
|
|
拂拂(ほつほつ)たり南來の風
青青たり楊柳の色
閒談(かんだん) 點塵(てんじん)を絶し
略試(りゃくし)標格を出ず
満腹是れ經綸(けいりん)
所行鬼途轍(とてつ)
嗟嗟(ああ)大博士
返って狼煙(ろうえん)の客と作る
|
| |
〔大意〕
そよそよと南風が吹いてきた、
青々と柳も初夏の装いである。
雑談ですらも少しの汚れをも消し去り、
僅かの会話にも話し相手の品格が浮かび出てくるというものだ。
これは人としての全てが完成されているからで、
すること為すこと全てが物事の道理に叶い、度を外れた鬼のような存在だ。
ああ真の禅の師匠だ、と、
返って私はおだて上げられたのろしのような客人にされてしまったわい。
|
|
| 〔十六〕392503 |
隻手破天荒 大開正法場
聞風倶偃艸 返炤忽生光
法護舒明鑑 魔羣輙退蔵
一時露赤膽 千古爲金湯
|
|
隻手天荒(てんこう)を破り
大いに正法場を開く
風を聞いて倶(とも)に艸に偃(ふ)す
返炤して忽ち光を生ず
法を護り明鑑を舒ぶ
魔群 輙(すなわ)ち退蔵す
一時 赤膽(せきたん)を露し
千古金湯と爲る
|
| |
〔大意〕
独力で荒波を乗り越えて、
大いに仏法を伝える道場を開くことが出来た。
風が吹きぬけると草木がなびくように、師弟共に一体となるならば、
我が身に照り返して忽ちに輝きを増すだろう。
護法の気持ちをもってものごとの是非を見分けて説くならば、
悪魔たちもきっと退散して隠れてしまうに違いない。
一旦本来の面目を現わすならば、
いつまでも近寄りがたい立派な禅の道場となること請け合いだ。
|
|
| 〔十八〕392602 |
嗟嗟黄口兒 唯見巣中好
學語末成章 喃喃闢佛老
尺鷃咲鵾鵬 朝昏徒懊悩
那知天地外 更有無窮道
|
|
嗟嗟(ああ)黄口(こうこう)の兒
唯 巣中(そうちゅう)の好(こう)を見る
語を學んで末だ章を成さず
喃喃(なんなん)として佛老を闢(ひら)く
尺鷃(せきあん)鵾鵬(こんほう)を咲い
朝昏(ちょうこん)徒らに懊悩(おうのう)す
那(なんぞ)知らん天地の外
更に無窮の道有ることを
|
| |
〔大意〕
ああ、修行を始めたばかりの若者達よ、
ただ修行道場で頑張っている姿をじっと見つめる。
用語は覚えたようだが、未だにまともな文章すら作れないのに、
口ごもりつつも、仏や祖師の教えを語っている。
なんと巣立ちも出来ない小雀のくせに大鳥のことを笑い、
それでいて朝夕むやみに悩んでいる。
どうして知ろうとしないのか、もっと広い外の世界のあることを、
更に窮めがたい真理の世界の有ることに。
|
|
| 〔二十一〕392703 |
佛乃聖中聖 萬霊之祖考
龍天八部衆 仙鬼五通道
一切盡歸依 人間倶讃可
魔外自無知 云他不及我
|
|
佛は乃ち聖中(しょうちゅう)の聖
萬霊の祖考(そこう)たり
龍天(りょうてん) 八部の衆
仙鬼(せんき)五通(ごつう)の道
一切盡く歸依し
人間倶に讃可す
魔外(まげ) 自ら知ること無く
云う 他(た) 我及ばずと
|
| |
〔大意〕
仏は優れた方々の中でも最も優れたお方であり、
生きとし生けるものの祖先とも申すお方である。
龍が住むという天上界の八部衆はもとより、
仙人、鬼神といったあらゆる神通力を持った者たち。
それらの一切尽くが帰依し、
世間の人々もともに認め讃えあっているがなんと素晴らしいことか。
それなのに、悪魔、外道たちはそんなことを知ろうともせずに、
言っている、「俺に及ぶ奴はいないんだ」と。
|
〔二十三〕392802 |
錫寄重岩上 胸開一義天
日常自守拙 暗地獨推賢
不作繁華夢 惟談解脱禅
心無閒艸木 満眼是青蓮
|
|
錫は寄す重岩(ちょうがん)の上
胸(きょう)は開く一義の天
日常自ら拙を守り
暗地(あんち)独り賢を推す
繁華(はんか)の夢を作(な)さず
惟解脱の禅を談ず
心(しん) 艸木閒(へだ)つる無く
満眼(まんがん)是れ青蓮
|
| |
〔大意〕
錫杖は積み重なった岩の上に立てるもののように、
心の内は閉ざさずに天に向かって開くことを第一義とすべきである。
拙いところがあろうがそれなりに大切にするように心がけ、
人知れずたった一人であったとしても賢者として振る舞うことを勧める。
華やかな夢は追い求めず、
ただ悟りを得るための禅について語ろうではないか。
人にとって無用な草木など無いのだから、
どんなことも役に立ち、目に映るものは全て浄土の蓮の花のはずだ。
|
|
| 〔二十四〕392901 |
物物倶貪生 人人盡怕死
何事害他命 以肥我腹子
愚蠢好饕餐 聖賢返恕已
最憫互相殘 何時能抵止
|
|
物物(もつもつ)倶(とも)に生を貪り
人人(にんにん)盡く死を怕(おそ)る
何事ぞ他の命(めい)を害し
以って我が腹子(ふくす)を肥す
愚蠢(ぐしゅん)饕餐(ごうさん)を好み
聖賢(せいけん)返(かえ)って己を恕(じょ)す
最も憫む互いに相(あい)残(そこな)うことを
何の時か能(よ)く抵止(ていし)せん |
| |
〔大意〕
この世の物全てが生ということにどん欲で、
どの人もが死と言うことに恐れを抱いている。
それなのに、どういう訳か他人の命にも拘わる事についてまで害し
しかもそれで自分の腹を肥やしている。
無知で愚かな者は金銭を貪っているが、
聖人君子は、寧ろ自分に対して思いやりを持っているものだ。
最も哀れむべき事は、お互いに相争うことであるが、
いつでも止められる度量が欲しいものだ。
|
|
| 〔二十五〕392902 |
壽生廣物命 樹福布津梁
徳振乾坤大 心明日月長
擴充臨済脈 直接少林芳
正道通今古 眞風四海揚
|
|
生を壽にして物命を廣うし
福を樹(た)てて津梁(しんりょう)に布(し)く
徳を振うて乾坤大いに
心明かにして日月長し
臨済の脈を拡充し
直に少林の芳に接す
正道今古に通じ
眞風四海に揚がる
|
| |
〔大意〕
生命をながらうことを願えば物の寿命も広まり、
功徳を施せば多くの人を彼岸に渡せることが叶う。
徳を発揮してこの宇宙いっぱいに大きく羽ばたき、
心のなんたるかを明らめることが出来るならば、寿命も伸ばせるのだ。
臨済禅師の正脈をますます広げていけば、
すぐにも達磨大師の教えに近づくことが出来ようというものだ。
正しい教えというものは古今東西に通じている、
禅の教えは世界中で巻き起こるはずだ。
|
|
| 〔二十六〕393001 |
光陰忙似箭 世上幾人閒
聴法心無定 探花戀未還
浮雲掩白日 綠水映青山
無限丈夫子 活埋天地閒
|
|
光陰忙々として箭(や)に似たり
世上幾人か閒(かん)なる
法を聴いて心定まり無く
花を探りて恋て未だ還らず
浮雲白日を掩(おお)い
緑水 青山に映ず
限り無き丈夫子(じょうぶし)
天地の間(かん)に活埋(かつまい)す |
| |
〔大意〕
時の経つ様は早くせわしくて、放たれた矢にも似ている、
世の中、いったいどれだけの人が気持ちにゆとりを持っていようか。
せっかくの法を聴きながらも心は上の空だし、
花を愛でながらも世俗の華美に惑わされ、未だに自分自己を見失っている。
外は晴天だと想っていたら、いつの間にか雲が空を覆い、
雨が降って夏山が一段と緑を増している、なんと無常なことか。
遮る者とてない前途有為な修行者諸君、
そんなことではこの世の中に埋もれていってしまうよ。
|
| |
|
〔二十九〕393102
|
眼底幾春冬 少年易老容
無増閒碧落 不減舊青峰
大道離名相 善行絶朕蹤
夜来忘営帯 逗漏數聲鐘
|
|
眼底(がんてい)幾春冬ぞ
少年老容し易し
閒 碧落(へきらく)を増すこと無く
舊青峰を減ぜず
大道 名相(みょうそう)を離れ
善行 朕蹤(ちんしょう)を絶つ
夜来 営帯(えいたい)を忘れ
逗漏(とうろう)す 数聲(すうしょう)の鐘
|
| |
〔大意〕
思い出せば幾年が経っただろうか、
少年だったあの頃から、早やこんな年寄りになってしまったものだ。
かといって、その間に天が増えたわけでもなく、
青々した山々が減ったわけでもない。
求道の生活には、姿、形、人格など必要とせず、
こんな素晴らしいことを行ったとかあんなことを行なったという足跡など も必要としない。
こんなことを考えていたら夜の間、腰帯を付けるのを忘れてしまい、
起床の合図を知らせる鐘の音までも聞き漏らしてしまったワイ。
|
|
| 〔三十一〕393201 |
迷人自不惺 遺累百千生
久貪瞋作客 長虚誕為氓
鬼心假仏面 獣行儒名張
耳掩鈴盗漢 到頭一成無
|
|
迷人 自(みずか)ら惺(さ)めず
遺累 百千生ず
久しく貪瞋(とんじん)の客と作り
長く虚誕(きょたん)の氓(たみ)と為る
鬼心仏面を假(か)り
獣行(じゅうこう) 儒名(じゅめい)を張る
耳を掩うて鈴を盗む漢
到頭(とうとう) 一の成ること無し
|
| |
〔大意〕
世俗にまみれた凡夫は自分から覚醒することなどできはしない、
かえって、何百何千もの罪科を残し続けるばかりだ。
長らく諸欲の虜となり、
いつまでもでたらめな生活を続ける人間となりはてゝいるからだ。
鬼のような心を持ちながら仏であるかのような仮面を着け、
行動は獣のようでありながら儒者の名を語る。
悪事だと知りながら、それを考えないように悪いことを重ねる輩など、
結局、一生涯、何一つの大事も全うすることなど出来やしないのだ。
〔注〕 【耳掩鈴盗漢】中国諺。『耳を掩うて鈴を盗む』、『耳を塞いで鈴を盗む』とも。 良心に反することをしながら、強いてそのことを思わないようにするたとえ。 あるいは、罪を隠したつもりでもすっかり知れ渡っていること。
|
|
| 〔三十四〕393303 |
大道絶中邊 臨機契妙玄
有時鞭脳後 倏爾拶鋒先
逆順無増減 行藏豈變遷
吾家眞種艸 徹底潔如蓮
|
|
大道(たいどう) 中邊(ちゅうへん)を絶し
臨機(りんき)妙玄(みょうげん)に契(かな)う
時有って脳後(のうご)を鞭(べん)し
倏爾(しゅくじ)として鋒先(ほうせん)を拶す
逆順(ぎゃくじゅん)増減無く
行蔵(こうぞう) 豈(あ)に変遷せん
吾が家の眞の種艸(しゅしょう)
徹底 潔(きよ)うして蓮(れん)のごとし |
| |
〔大意〕
禅の道というものは中ほどを捨て、
臨機に対応することこそ奥深く優れているというものである。
いざというときには、機転を利かせて、
瞬時に鉾先を向けて一気に対処するのである。
こうしたことは正道にさからっているようだがそうではなく、
出処進退にどうして変わりがあろうか、ないではないか。
私の禅の本来の家風は、
徹底的に潔く蓮のごときものである。
|
|
| 〔三十八〕393503 |
学道難莫辞 萬仞巒登如
脚跟生鉄鋳 眼懸赤金丸
歩歩雲浪起 朝々宝壇踞
八風吹不動 一片玉心肝
|
|
学道は難きを辞すること莫かれ
萬仞の巒(みね)に登るが如し
脚跟の生鉄鋳(せいてっちゅう)
眼懸(がんきょう) 赤金丸(せききんがん)
歩歩 雲浪(うんろう)を起し
朝々 宝壇(ほうだん)に踞す
八風吹けども動ぜず
一片の玉心肝
|
| |
〔大意〕
参禅学道に困難を厭うようであってはならない、
そそり立つ崖をのぼるように命がけで挑まねばならない。
炉から出たばかりの鋳鉄がじわじわと周りを焦がしながら痕をつけていく ように一歩ずつ着実に踏みしめ、
眼はといえば爛々と黄金のように輝かせてあたりを見渡していく。
歩くたびに雲を蹴散らすかと思えば、
朝な仏前で坐禅に徹底する。
このようになったらしめたもので八風吹けども動ぜずである、
玉石で出来たような不動心をもった人物だと言えよう。
|
|
| 〔四十一〕393603 |
白面好郎君 内含黒漆々
潜心是非鼓 返照何益有
已昭昧無知 瞞人眼不識
業縁貫満時 未免阿鼻堕
|
: |
白面の好郎君(こうろうくん)
内含 黒 漆々たり
潜心 是非を鼓(こ)し
返照 何の益か有らんや
已昭(いしょう)を昧まして知ること無く
人眼 を瞞じて識らず
業縁 貫き満つる時
未だ 阿鼻(あび)に堕するを免れず
|
| |
〔大意〕
経験未熟な修行者諸君、
表は活かしているが内面はうるしのようにまっ黒でなんと毒毒しいことか。
潜んだ気持ちを奮い立たせて是非を判断しようともがきあがこうが、
己を省みれば明らかなようにどうしてそんなことで利益があろうか。
自己を欺き無知なことを隠し、
他人までをも欺きつづけ何も知らないことを隠そうとする。
業が満ち〳〵てそれが積もり積もったときは、
きっと阿鼻地獄に堕ちる事を免れないだろうに。
|
|
| 〔四十三〕393702 |
濁世鮮明眼 度生念益堅
内蔵淨寶月 外現老風顛
智者不全識 凡夫盡罔然
偸光擬陳跡 太似管窺天
|
|
濁世明眼に鮮に
度生の念益(ますます)堅し
内に浄寶月(じょうほうげつ)を蔵し
外に老風顛を現ず
智者は全く識らず
凡夫は盡く罔然(ぼうぜん)たり
光を偸(ぬす)んで陳跡(ちんせき)に擬す
太(はなは)だ管で天を窺うに似たり
|
| |
〔大意〕
この世が濁りきっていることは、心眼で見れば鮮やかに映る、
衆生を救いたいとの想いはますます固くなるばかりだ。
心の内には浄い三宝の念いを秘めてはいるのだが、
表には年寄りの風顛の様が露わで隠しおおせるものではない。
悟りきった人はどうか知らないが、
煩悩に束縛された我々はただぼんやりとするしかないざまだ。
努力をして時間を作り祖師方の事跡にあやかって励んではいるものの、
管で天を覗くような有様で、さあどうしたらよいものか。
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
| 〔五十〕394001 |
仏不孤人願 人須聖言奉
戒爲萬善本 得本自環源
定立空諸相 相空入慧門
三全通大道 兩足獨稱尊
|
|
仏は人の願に孤(そむ)かず
人は須く聖言(せいげん)を奉ずべし
戒は萬善の本たり
本を得ば自ら源に環(かえ)る
定(じょう)立ちて諸相(しよしょう)を空じ
相空じて慧門(えもん)に入る
三全(さんぜん)大道に通じ
両足独り尊と称す
|
| |
〔大意〕
仏というものは人の願いに背いたりはしないものだ、
だから人も仏祖の言葉を尊重し実践するべきである。
とりわけ戒を守る行為は全ての善行の基いとなる重要なことである、
根本を得ることが叶うなら人は自ずから人間としての本源にたち返れる。
禅定に入れば目にとまるこの濁世のすがたも滅することが出来ようし、
その姿を滅することが出来てこそ仏門に入れるというものだ。
戒、定、慧の三学が実践されるならば大道に到達できる道を確保できたも 同じこと、
万物の霊長と言われる我々人間こそが讃えられるべき尊い存在なのである。
|
| |
| |
|
| 〔五十一〕394002 |
師為洪匠範 範出法無違
萬物體鎔會 一大家鋳成
本来無二数 分別隔天涯
鐵巴鼻洩轉 共登百寶華
|
|
師は洪く匠を範と為す
範出づれば法違うこと無し
萬物の體を鎔會(ようえ)し
一大家を鋳成す
本来 二数 無く
分別 天涯を隔つ
鐵 巴鼻を洩轉(えいてん)し
共に百寶華(ひゃくほうげ)に登る
|
| |
〔大意〕
禅の師匠というものは鋳物に使う鋳型のようなものだ、
だから鋳型から出来上がった弟子の法は師匠とは寸分の違いも無いはずだ。
森羅万象のあらゆる法を一体化して溶かし込むのだから、
どの修行者も立派な禅者に仕上がる。
本来、法に別々の二つのものが存在するなどということはあり得ないはず だから、
違ったものが出来るというならそれは天と地ほどの差があるであろう。
牛の鉄の鼻輪を持ってひき廻すように皆を引き廻し、
ともに諸仏がおられる蓮華の上へと登らせたいものよ。
|
|
| 〔六十一〕394303 |
三界寄浮旅 百年頃刻間
何期瑞兆現 我而寒山夢
筆捉龍蛇動 追想仏祖顔
言々超聖諦 是等非閒閒
|
|
三界は寄浮の旅
百年は頃刻(けいこく)の間
何ぞ期せん瑞兆を現ずることを
我をして寒山を夢みしむ
筆を捉((と)れば龍蛇動き
仏祖の顔(かんばせ)を追想す
言々(げんげん) 聖諦を超ゆ
是れ等 閒閒(かんかん)にあらず
|
| |
〔大意〕
私たちが今いる世界は旅で立ち寄っただけの場所であり、
人生百年と言ってもほんの僅かな時間である。
とはいえ受け難き人身を受けたからには瑞兆が現れることを期待したいも のだ、
今、私は寒山と同じようにありたいとの夢を見ている。
筆を握れば龍が動き出すし、
仏や祖師方のお顔が思い浮かばれる。
一つ一つの言葉のはしばしにはとてつもない尊い真理が秘められているが、
これらは決して余暇のこととしているわけでは無いのだ。
|
〔六十九〕394602 |
隠々長松下 休休逸老人
嚢蔵格外旨 筆絶世間塵
擬渉寒山跡 収囘覺苑春
和峰増秀麗 又見一番新
|
|
隠々たり長松の下
休々たり逸老(いつろう)の人
嚢は蔵(かく)す格外の旨
筆は絶つ世間の塵
寒山の跡を渉らんと擬して
覚苑の春を収回す
和峰秀麗を増し
又一番の新なるを見る
|
| |
〔大意〕
高くそびえる松の下でぼんやりとたたずみ、
つつましやかな隠居姿の老人がいる。
今は特別な想いをかくし、
濁世にまみれた世間から離れようと筆も絶っている。
寒山の歩んだ悟りの足跡を自分も擬えてみようと、
悟りの世界の春を思い出し味わっているのだろう。
日本の山々が気高さを増して愈々と美しい。
また新たな優れた一面を見つけたよ。
|
〔七十〕
|
四海為吾家 隨方度歳華
片心含寶月 兩眼爍空花
饑食金牛飯 渴斟趙老茶
長伸雙脚睡 不覺在天涯
|
|
四海を吾が家と為し
方に随いて歳華を度る
片心宝月を含み
両眼空花を爍(と)かす
飢えては金牛の飯を食い
喝しては趙老の茶を斟(く)む
長く雙脚を伸べて睡らば
天涯に在るを覚えず
|
| |
〔大意〕
この全世界を我が家として、
世間の道理に従って歳月を重ねている。
心の片隅にきれいな月を思い浮かべ、
両眼には花を思い浮かべて輝かせている。
腹が減ったら金牛和尚と一緒にご飯を食べている気持で食事をいただけることに感謝し、
喉が渇いたら趙州和尚になった気分で無心にお茶を飲み干している。
長々と両足を伸ばしきって寝そべれば、
世俗から離れたことも異国の地にあることも忘れてしまうよ。
〔注〕 【金牛飯】碧巌録七十四則「金牛飯桶」
|
| |
|
| 〔七十一〕394702 |
自家寳識得 垂慈須急早
百年修骨間 万事一斉掃
命害根源損 生養壽老益
君能力受持 福禄長保可
|
|
自家の寳を識得せば
慈を垂るるに須く急早なるべし
百年修骨の間
万事一斉に掃う
命を害すれば根源を損じ
生を養えば壽老を益す
君能く力(つと)めて受持せよ
福禄 長く保つ可し
|
| |
〔大意〕
自分の持てる宝、即ち自己の命の大切さを見極め悟るならば、
他者に慈悲を施すことは速やかに行わなければならない。
百年と言ったところでたちまちのことである、
何ごとも不用なものは取り払うことだ。
生命を害するようなことはこの世の成り立ちの根源を損じることとなり、
生命を大切にすれば長生きに利益をもたらすこととなる。
お前さんよ、このことをよく理解して努めて大切にし、
幸せは長く保持するようにするべきである。
|
|
| 〔八十一〕395101 |
父母天倫重 生身徳莫量
分皮未足報 砕骨豈能償
心徹情無寄 道成名可揚
諭親歸佛乘 孝義始全彰
|
|
父母天倫重く
生身(しようじん)徳量ること莫れ
分皮(ぶんぴ)未だ報ずるに足らず
砕骨豈に能く償わんや
心(しん)徹して情寄る無く
道成って名を揚ぐ可し
親を諭して佛乗に帰せしめば
孝義始めて全く彰(あら)わる
|
| |
〔大意〕
父母を大切にする倫理は人として重要な徳目である、
仏になれる力を持った人間の品性ほど量りがたいものはない。
自分の身体の皮を剥いで父母に報いるなどということは、報告するほどのことではなく、
両親のためには骨を砕いてでも報いなければならない。
心を尽くしていれば情愛のみで動かされることも無いはずだ、
理屈では無く実際の行動によってこそ人としての名をあげるべきである。
両親を諭して仏道に帰依させることが出来るならば、
孝行というものについて初めて本来の意義が現れるだろう。
|
|
| 〔九十一〕395403 |
圓頂方袍士 唯禪是所依
更須參向上 豈可学卑微
透徹頂門眼 頓超過量機
是名真鐵漢 不愧出家兒
|
|
円頂方袍の士
唯 禅 是れ依る所
更に須く向上に参ずべし
豈に卑微(ひび)を学ぶ可けんや
頂門の眼を透徹し
頓に過量の機を超ゆ
是れを真の鉄漢と名づけ
出家兒に愧じず
|
| |
〔大意〕
剃髪し袈裟をまとった僧侶の諸君、
ただ参禅のみが頼るべきところだと認識しなさい。
今すぐにも一層向上するように修行に励むべきだ、
どうして卑しいことを学ぶ必要があろうか、学ばなくてもよいではないか。
頭の急所に眼を向けて坐禅に徹底し、
一気に思い切った努力が望まれるというものだ。
この様な人こそが真の禅者だと名付けられるべきで、
禅僧としてはじない人だといえよう。
|
| |
|
| |
|
|
 |
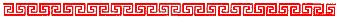
|
  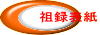 |
