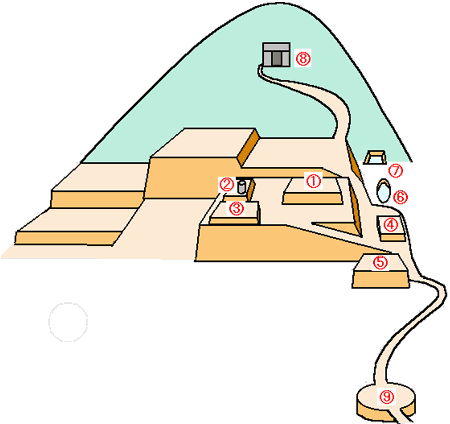|
頼朝供養塔 |
||
| 天吉寺滋賀県指定史跡
長浜市野瀬(旧東浅井郡浅井町野瀬) |
||
| ■創築年 | 貞観7年(865) | |
| ■創築者 | 安然上人(安円) | |
| ■形式 | 山寺城 | |
| ■遺構 | 郭、土塁、堀、石垣、石塔、礎石 | |
| ■別称 | 大吉寺 | |
| ■標高 | 700m | |
|
大吉寺は歴応元年(1338)の勧進帳によると、貞観7年(865)の草創と伝え、『吾妻鑑』『平治物語』には平治の乱のあと源頼朝が大吉寺にかくまわれたことを記している。 室町時代には幕府の祈躊寺として保護を受けていたが、大永5年(1525)の六角定頼の兵火や元亀元3年(1572)織田信長の破却などにより寺院は衰退の一途をたどり、現在、天台宗寂寥山大吉寺の一子院が遺存するのみである。 創建当時の堂宇は、天吉寺山の山頂付近に造営されており、本堂跡、門跡、塔跡、鐘楼跡、覚道上人入定窟、あか池などに石段を見ることが出来、更に、本堂へ至る山道の所々に堂宇が建立されていたと推定される平坦部がある。 滋賀県教育委員会案内板より転記
|