h
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v�����܂܂��@�@ �@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���j��-
����́u�L���b�`�{�[��
�䂪�ރI���K��
���� �� �����ϑz
�u���ɕ��Q�L �֎q�����킢�v�i�Ď��Îq���j�̊��z
���c���搶�̂��b
���Ȉ��Ȃ����
�X�c�Ö@�w��̉ۑ�
�f�@���O�̐����̃G���[���t�B�V�����z��
�ЂƂ�ł���\��
�[�Ö��ɂ�����l
�V�N���S�g�ǂ̎���
�����p�ւ̕s��
�~�J�ƐS�g��
�@ �A�N�Z�X�T�O�O�O�L�O�̑n�삨�b�ЂƂ�(1999)
�A�N�Z�X�T�O�O�O�L�O�̑n�삨�b�ЂƂ�(1999)
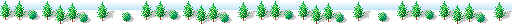
�@����̓L���b�`�{�[���@
�@��Ј��̂`�q����i�Q�S�j�́A�������O�ɑ�w�𑲋Ƃ��V���Ј��ɂȂ�܂����B�d���Ɋ����̂ɖZ�����܁A��i���炫������ꂽ���Ƃ��L�b�J�P�ɁA��Ђɍs���ӗ~���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���̍�����A�ЂƂ�ŕ����ɋ���Ƃ����X�g�J�b�g������悤�ɂȂ�A���r�ɉ��{���̐菝�̐Ղ��c���Ă��܂��B�`�q����́A�f�@���ŐE��̏�i�ւ̕s������邤���ɁA��������ĂĂ��ꂽ���e�Ɉ���݂��Ȃ��A�Ƃ����ߋ��ɂ��Č��n�߂܂����B��i�ƕ����A�`�q����̐S�̒��œ�d�f���ɂ��Ԃ��Č������̂ł��B
�@�`�q����̘b���܂Ƃ߂�Ƃ����Ȃ�܂��B�ǂ̂悤�ȏ������̂�������Ȃ����A���w���̂Ƃ����Ɂu���O�Ȃ���ł��܂��v�Ɠ{���܂����B���̌��t�ɋ����V���b�N�����`�q����́A�Ȍ㕃����̈���������邱�Ƃ��Ȃ��A�Ȃɂ��ɂ��ĕ��ɔ��������悤�ɂȂ�܂����B�`�q����̘b�Ɏ����X���Ă��邤���ɁA���̐S�ɂ́A�`�q����̕��e�͐̕��̊�ł��₶���Ƃ����C���[�W�������т܂����B�Q�S�ɂȂ������ł��`�q����́A���e�̐��i���D���ɂȂꂸ�A���܂���������Ȃ���Ԃł����B
�@�������`�q����́A��ʓI�ȕ��ʂ̉ƒ���ň�Ă��A�傫�ȕa�C�����邱�Ƃ��Ȃ���w�܂ő��Ƃ����Ă��炢�܂����B���e�̕ی�̉��ł���Ȃ�ɑ傫���Ȃ�ꂽ�Ƃ�������������܂��B�܂����e�͂ƂĂ������ȉ�Ј��ł����B�Ȃ̂ɁA���`�q����ƕ��e�̊Ԃɉ������A���݂܂ő����C�܂����W�B����͂��������A�ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���B�P�ɑ���������Ȃ��ƕЕt���邾���ł́A���s���̂܂܂ł���u�S�����Áv�ɂ��Ȃ�܂���B
���āA�l�����҂���̈�����A����Ƃ��ċ���ɂ͂������̗v�f���K�v�ł��B�v��Ǝ��̂R�ł��B����₷���悤�ɃL���b�`�{�[���ɂ��Ƃ��ď����Ă݂܂��傤�B
�@�@����i�{�[���j���A���ۂɑ��݂��邱��
�@�A�@���肪����̕\�������܂����Ɓi�����s�b�`���[�ł����j
�@�B�@�������������̂����܂����Ɓi�����L���b�`���[�ł����j
����́A���̑����Ǝ�̊Ԃōs����L���b�`�{�[���̂悤�Ȃ��̂ł��B�ǂ�Ȃɐ[������i�{�[���j�������Ă��A������肪�L���b�`�ł���Ƃ���ɓ����Ȃ���A����͈����S�������邱�Ƃ��ł��܂���B�܂�A�Ԃ̏�Ԃ��K�v�Ȃ̂ł��B
���ɁA�ǂ�Ȃɏ��Ɉ���̃{�[�����������Ă��A�������ׂ��{�l���L���b�`����\�͂Ɍ����Ă���A��͂�{�l�͈���������邱�Ƃ��ł��܂���B����͇B�Ԃ̉ۑ�ɓ�����܂��B
�`�q����̏ꍇ�ɂ��Ă͂߂Ă݂܂��ƁA�@�Ԃ̂悤�ɕ��e����̈�����ۂɂȂ������Ɖ�����̂́A�ǂ��l���Ă��s���R�ł��B�A�Ԃ̂悤�ɕ��e�̈���\��������ł������̂��A���邢�͇B�Ԃ̂悤�ɂ`�q�����܂��L���b�`���[�łȂ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������̂ł��B
�`�q����̕��e�́A�d�����I���ƂɋA���Ă���悭�������̂܂�Ă��܂����B���ɐ����Ƒ傫�Ȑ��ʼnƑ���{�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������Ƃ����܂��B�������Ȃ�������������ł������悤�ł��B�������Ƒ��̂��߂Ɉꐶ���������Ă�����������ɁA�Ƒ��ւ̈���Ȃ������Ƃ͎v���܂���B
�v����ɁA�`�q����̕��e�́A����\��������Ȑl�ł������̂ł��B���e�̉���ȓ����́A�`�q����̍���]�[���ɂ��܂�����܂���ł����B�t�ɁA�`�q���炷��ƁA�ǂ�Ȃɑ҂��Ă�������̃{�[���͂ЂƂ���������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă����̂ł��B�������A�{�[���i����j�͂�����ƁA���̂Ƃ��A�����ɍ݂����̂ł��B����A�q����̕��e�́A������X�g���[�g�ɕ\�����邱�Ƃ��ł����A�������ނ��Ƃŗ҂�����킹��Ƃ����A����̃L���b�`�{�[���Ɋւ��ĕs��p�Ȑl�������̂ł��B���̌�A���낢��ȉƒ�̘b���`�q����Ƃ��Ă����Ȃ��ŁA�₪�Ă`�q����́A���e�����͈���\���̉���ȃs�b�`���[�ł������Ɖ���悤�ɂȂ�܂����B�����āA�`�q���g������̂��܂��L���b�`���[�ł͂Ȃ������\��������ƍl���n�߂܂����B
�@���݂�ߋ��ɁA���������͂��爤����ǂꂾ�����Ă����̂��B�ƒ���̈���Ɍ��炸�A�E��ł̐l�ԊW��F����l����Ƃ����A�ȏ�̂悤�Ɂu����̓L���b�`�{�[���v�Ƃ����������𗧂Ǝv���܂��B�����āA�L���b�`�{�[���Ƃ������̂́A�{�[�������L���b�`���[���܂��s�b�`���[�Ɍ������ď��ȃ{�[���𓊂��Ԃ��Ȃ��Ƒ������Ȃ����̂ł��B
�@�{�[�����X�g���C�N�]�[���ɓ��������B�����āA������J�[�u�������B�s�b�`���O�����I�ł���悤�ɁA����ɂ��l�ɂ���Ă����Ȍ`�̕\��������܂��B���̂��ƂɎv�����߂��炷�ƁA����̃{�[���������ƑN���Ɍ����Ă���̂�������܂���B
�@�@�䂪�ރI���K���i��̑��nj�Q�j
�T�O�ɂȂ�����w�̂`�q����B������A�v���Ԃ�ɉƂ̃I���K����t�ł悤�ƃC�X�ɍ���܂����B����ƃI���K���̃P���Ղ��䂪��Ō�����̂ł��B�������`�q����͎��͂����܂������A�Ȃ����I���K���̃P���Ղ������䂪��Ō�����̂ł����B
�@�`�q����͐S�z�ɂȂ�A�v�►�ɑ��k���܂����B�������Ƒ��́A�C�̂������ƌ����đS������ɂ��Ă���܂���B���̌���A�I���K���̃P���Ղ͂����䂪��Ō����܂����B���̂��ߕa�@�Ŗڂ̌��������܂������ُ�͌�����܂���ł����B���̂����`�q����́A�s�����J���ɂ��Y�ނ悤�ɂȂ�܂����B���̌�������w�I�ɕs���ł����B�X�N���̎��Â����ʂ�����܂���ł����B�`�q����́A�m�l�̂����߂ŐS�Ó��Ȃ���f���܂����B
�@�ȉ��́A�`�q����Ƃ̐f�@���i�S�Ó��ȁj�ł̖ⓚ�̔����ł��B
�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@�u���Ȃ��́A���I���K�����Ђ��̂ł����H�v
�@�u�ɂȂƂ��ł��v
�@�u�ǂ�ȂƂ��A�ɂɂȂ�̂ł����H�v
�@�u�v�͋x���ɃS���t�ɏo�����邵�A�����ЂƂ莩���̎��Ԃ��y���ނ悤�ɂȂ��Ă��܂��A�b�����肪���Ȃ��Ƃ��ɂɂȂ�I���K�����Ђ��܂��v
�@�u����ȂƂ��́A�ǂ�ȋC�����ŃI���K�����Ђ��̂ł����H�v
�u�̂ƈ���āA�q�����傫���Ȃ������A�ŋ߂݂͂�Ȏ����̎��Ԃ��y����ł���悤�ŁB���ЂƂ���c���ꂽ�C���łЂ��܂��v
�u�I���K����ϋɓI�Ɋy����ł����Ԃł͂Ȃ��悤�ł��ˁv
�u�҂�������I���K���Ɍ�������ł��B�{���̓I���K�����Ђ��̂ł͂Ȃ��A�����ƉƑ��Ɖ�b��������A�ꏏ�ɏo�������肵�����̂ł��E�E�E�E�E�E�v
�@�@�@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�@����ȉ�b���J��Ԃ��Ȃ��ŁA�₪�Ă`�q����Ǝ��́A�I���K�����䂪�ވӖ��𗝉����܂����B�䂪�ރP���Ղ́A�ǓƂ��瓦����悤�ɃI���K���Ɍ������`�q����̐S�̊������ے�������̂ł����B�̂̂悤�ɉƑ��Ɛe�����������������`�q����ɂƂ��āA�I���K���͂����́u�䂪���v�ł����Ȃ������̂ł��B
�@�u��̑��nj�Q�v�Ƃ������t������܂��B�q�����������e���瑃�����Ă��������ɁA�����b����������|�b�J���������e�̋��S��\���Ă��܂��B�q�������_�I�ɓƗ����A�o�ϓI�ɂ����肷�钆�N����B�������������ɂȂ�̕s��������̂��H�@�`�q������̋����𗝉����邱�Ƃ͗e�Ղł͂���܂���ł����B�䂪�ރP���Ղ́A����Ȃ`�q����̐S�̊����𗝉����铹����ׂɂȂ�܂����B
�@�@�@�@�y �g�̌��� �z
�@�S�Ó��Ȃ���f���銳�҂���̏Ǐ�͂��܂��܂ł����A���Ӑ[���ώ@����ƁA���̔w��ɂ����Α����̈Ӗ����B����Ă��܂��B���I�Ȑg�̏ǏA���̐l�̉���\����������Ă���̂��B�g�̏Ǐ�錾�t���A�S�Ó��Ȃł́u�g�̌���v�ƌĂ�ł��܂��B�g�̌���́A�{�l�����������Ȃ��S�̉�����ق��Ă��邱�Ƃ�����܂��B���̉��[���Ӗ����Ƒ��⎡�Î҂����������A���҂���ƂƂ��ɗ������邱�Ƃ����ÂɂƂ��đ�ł��B
�@�u�g�̌���v�́A���̖��̒ʂ�A�g�̏Ǐ��������҂Ƃ̉�b��i�ł��B�������g�̌���́A�{���̌��t�łȂ����߁A���͂̐l�ɑ����̌����s������^������ł��B�Ƃ��Ɂu���a�v��������Ă��܂����Ƃ�����܂��B
�@�@���Âł́A�������₷���u�g�̌���v���A�{���́u���t�ɂ�錾��v�ɒu�������������Ɓi�Ǐ�̌��ꉻ�j�����C���ɂȂ�܂��B�ƌ����Ă��A����͗e�Ղȍ�Ƃł͂���܂���B�Ǐ�̌��ꉻ�Ƃ́A��߂�ꂽ�S�̊��������Ă�����Ƃɑ��Ȃ�Ȃ�����ł��B
�@�@�@���� �� �����ϑz
�@�@���鏭�N�����鏭���ɗ��������B���N�́A�����̓����p�A�b�����A�\��Ȃǂɗ��S���̂点��B�܂��Ɂu�������G�N�{�v�̌��t�ǂ���ɁE�E�E�E�E�E�B���ʂȂ猇�_�ƂȂ�悤�ȏ����̃��K�}�}���A���N�̔]���ɂ͐_��I�Ȗ��͂Ƃ��Ď������B
�@�@�������ď��N�̓��ɕ`���ꂽ�����ȗ��z�̏��������A�����̏����ɏd�˂��A���N�͂܂��܂������ւ̔M��Ȉ����傳����B����͂����鏃���̓T�^���낤�B�l���悤�ɂ���ẮA�����Ƃ͏��x�ߏ�ɂ��ϑz�̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B���N�̗��z�ɍ���Ȃ������́A�e�͂Ȃ����͓I�ȉ����ɕό`�����B���̃v���Z�X�����������̏����A���Ȃ킿�����ƌĂ�鏊�Ȃ��B�����ł͈�ʂɁA���N�̏�����ϑz�ƋK�肷�邱�Ƃ��Ȃ��B�u�����ȏ��N�ɂ��A�Ђ�����O�����ȏ����ł���v�ƒ�`�����̂��l�ԓI�ȉ��߂��낤�B
�@�@����A���鏭�N�����鏭���Ɂu�����͋���������Ă���ɈႢ�Ȃ��v�ƁA�����ɔ����Ďv�����ޏꍇ�͂ǂ����B���N�́A�����̓����p�A�b�����A�\��Ȃǂ��ׂĂ������Ɉ�����Ă���ɈႢ�Ȃ��Ɗ�����B�ޏ�������������邿����Ƃ����፷���������ɁA�����͂ƂĂ�������Ă���̂��Ƃ����M�O���\�z�����B���̂悤�ȏꍇ�͉��X�ɁA�a�I�Ȃ��̂Ƃ�����߂��Ȃ���A�u�����ϑz�v�Ƃ������b�e�����\���₷���B
�@�@�ǂ�����A�������^�[�Q�b�g�Ƃ����A���N�̏����䂦�ɍ\�z���ꂽ���_���E�Ȃ̂��B����������́u�����v�ł���A��������́u�����ϑz�v�Ƃ��ċ�ʂ����X���ɂ���B
�@�����Ƃ́A�����Ėϑz�I�Ȃ��̂ł���B�ϑz�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���ꂪ�������]�ɂȂ�����x�̂��̂Ȃ�A���ɂ���قǂ̂��Ƃł͂Ȃ��̂��낤�B�l�͖ϑz�Ȃ����Đ������Ȃ������Ȃ̂�������Ȃ��̂�����B
�@�u���ɕ��Q�L�֎q�����킢�v�i�Ď��Îq���j�̊��z
�@�@
�@�@����A�V�����ɂ���o�ł���Ă����Ď��Îq���u���ɕ��Q�L �֎q�����킢�v��ǂ݂܂����B�Ђǂ��ɂ݂̂��߂ɁA�֎q�ɂ����ƍ����Ă���Ȃ��B�����Ă���̂��炢�B����Ȏ育�킢�Ǐ�̂��߁A����Ƃ����鎡�Î҂�]�X�ƁA���ꂱ�����m��w�̎��Â���u�肩�����v�Ȃǂ̖��ԗÖ@�܂Ŏ�ꂽ�̌��k�̂��b�ł����B�ŏI�I�ɒɂ݂́A���؉p�l��t�ɂ��u��H�Ö@�{�X�c�Ö@�v�I�Ȏ��Âɂ���āA���������鎡�Ì��ʂɓ�����Ă����܂��B�ȒP�ɋ�����ǂ��܂��Ƃ��̂悤�Ȃ��b�ł��B
�@�@���N���̋ꂵ�݂̉ʂĂɍŏI�I�ɍs�����ꂽ��H�Ö@�B���̂Ȃ��ʼnĎ�����͂܂��s�v�c�ȑ̌�������܂��B���Ï����̂���Ƃ��̂��Ƃł��B�厡��̕��ؐ搶�Ɍ������ĕs�M����{����v����Ԃ��܂��Ĕ��U���Ă���Ƃ��A����قǕs���̌`�ő̂ɋ������Ă��������ɂ݂��y���Ȃ��Ă��邱�ƂɃt�b�ƋC�Â��܂��B�u����Ȍ������u�ɂ��S���Ő����Ă���͂����Ȃ��v�Ƃ������M���Ă����ޏ��ɂƂ��āA����͕s�v�c�ȑ̌��ł������ɂ���������܂���B�{������t�Ŕ��U���邱�Ɓi�J�^���V�X�j�ɂ���āA�u�ɂƂ����g�̏Ǐ��ꎞ�I�ɂ���Y���قǂ��y���Ȃ����̂ł�����B���̂Ƃ�����ޏ����u�ɂɊւ��鎩�ȗ��̍l�����������h�炬�n�߂��悤�Ɏv���܂��B���̌����H�Ö@�̌��ʂ₲���g�̐������ɂ��āA���҂̉Ď�����͎厡��Ɖ��x�����x���ӌ��킹�܂��B
�@�@��H�Ö@�ł́A�O���̐�H���������ƁA���Ɍ㔼�̕��H���ɂ͂���܂��B���H���ł͏������H�����Ƃ�͂��߂邱�ƂɂȂ�܂��B���̂���]�g�D�͋Q���Ԃɂ��A��ӌn���P�g���̗̂��p�Ȃǂɂ���ĕω�����������Ȃ��Ȃ�܂��B�����āA������ӎ��ϗe���(ASC
altered state of consciousness�j�Ƃ����A��Î��������܂�₷�����_�Ɏ��R�Ɠ�����܂��B�ӎ��ϗe��Ԃ́A����������Œ�ϔO�̏C���ɖ𗧂��܂��B�܂��A��H�ɂ��g�́A���o�A��A�v�l�A�s���ւ̓�����p�I�ȓ����������A�S�g�ǂ̎��ÂɗL���ɍ�p����Ɛ�������Ă���̂ł��B
�@��H�Ö@�́A���̖��̂Ƃ���A�������i�����͂P�O���ԁj�S�g���炢��H�̏�Ԃɒu���܂��B����䂦���҂���݂̂Ȃ炸���Î҂ɂƂ��Ă��A�O�Ȏ�p�ɕC�G����قǂ̊o���ӔC����K�v�Ƃ������̂ł��B�炢�v�������҂���ɂ�������ŁA�w
���ǂ��Ȃ��ɂ͌����܂���ł����� �x�Ƃ͕Еt�����Ȃ��B���̂悤�Ȑ^��������H�Ö@�̎��Â̏�ɂ͕Y���Ă��܂��B
�@�@���͎����g����B��w�t���a�@�ŁA�S�g�NJ��҂���ɐ�H�Ö@�����ÂɂƂ肢��Ă��܂����B���̌��ʂɂ��Ĉ�w��ʼn��x�����\�����Ă��������܂����B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�l�ԊW�̃X�g���X�ɑς���ꂸ�S�g�ǂɂȂ��Ă�����l�B�ɂ́A��H�Ƃ����g�̓I�X�g���X�͈ĊO�ς�������������悤�ł����B�l���ꂼ��ς��Ղ��X�g���X�̎�ނɍ�������̂ł��傤�B
�@�@��H�Ƃ́A�u�H�ׂ邱�Ƃ����Ȃ��v���Ƃł��B�܂�u���Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����v�ƌ����Ă������ł��傤�B���̑����̎��Ö@���u����������v���Ƃł���̂ɑ��āA���́u���Ȃ��v�Ƃ������������������グ�Ă��A���j�[�N�Ȏ��Ö@���ƌ��킴������܂���B�����ŋ��k�ł����A�����u���ɕ��Q�L�֎q�����킢�v�̖{�̂Q�O�U�y�[�W�Ɉ��p�����Ƃ��ď�����Ă�����H�Ö@�̑t���@���́A������B��w�̋Ζ�����Ɍ��C��̋���p�ɍl�@�����I���W�i���̕��͂ł����B�i�{�̒��ł́A���̂����k��̂r�������̕��͂̈��p�ƂȂ��Ă܂����E�E�E�H�j�@������ɂ��Ă��A���̂悤�ȗL���Ȗ{�̂Ȃ��Ŏ����̃I���W�i���ȕ��͂ɏo��邱�Ƃ͌��h�̂�����ł��B
�@�@��H�Ö@�ł́A�Ǐ�Ƃ����d��ۑ�ƁA��H�Ö@�Ƃ����_�C�i�~�b�N�Ȏ��Ö@�𒇗����ɁA���҂���Ǝ��Î҂����ʂ�������������ƂɂȂ�܂��B���̂��ߓ����늴���Ƃ�Ȃ��a�̈Ӗ���l�ԊW�̂�����ɁA�����̋C�Â��������炳��₷���Ȃ�܂��B�܂��a�̂��߂Ɏ��Ȕډ��I�ɂȂ肪���Ȋ����́A��H�Ƃ����u��s�v���I�������A���ɂ���āA���ȐM����������_�@�ɂȂ�܂��B�܂��H�Ö@�@fasting
therapy �i�f�H�j�́A���ȕϊv��F�����₷���w�C�j�V�G�[�V�����x�̕���Ƃ��Ă��@�\���Ă���悤�ł��B
�@�@�Ď�����̐�H�Ö@�̎厡��ł��������ؐ搶�Ƃ́A���������ɂ���Ƃ��w����҂֔̕��x�Ƃ����e�[�}�ň�w�G���ɘA�����_�������������Ƃ�����܂����B����͎�����t�ɂȂ��čŏ��ɏ�������w�_���ł����B�Q�T�N�ʑO�̘b�ł����E�E�E�E�E�E�B
�@�@�Ƃ����킯�ŁA���̏����ȕ��ɖ{�̂Ȃ��ɂ͎��ɂƂ��ĉ����������̂���T���̂悤�ɖ��܂��Ă��܂����B����䂦����ȁw�Ǐ����z���i�H�j�x�����������Ȃ����̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@���c���搶�̂��b�i�Q�O�O�U�D�P�D�j
�@�@��P�O��S�Ó��Ȋw��A����P�����{���������J����܂����B����́A�{�w�NPO�@�l�ƂȂ����L�O���ׂ������̂��̂ł����B���̋L�O�Ƃ��āA�`�F���m�u�C���̔�Ў������Ɏx�������͓I�ɍs��ꂽ���c���搶�i�z�K�����a�@���_�@���j�����ʍu���i�s���u���j������܂����B���̒��ŁA�Ƃ��ɋL���Ɏc�������b�ɂ��ďq�ׂ����Ǝv���܂��B
�@�@���c�搶�̓`�F���m�u�C���łP�P�l�̔����a�̎q���ɂ�������܂����B�c�O�Ȃ���A���̂����ЂƂ肪�M�S�Ȃ����Âɂ�������炸�S���Ȃ�ꂽ�����ł��B���Â̒��ŁA���̎q�͂������ɐH�~���Ȃ��Ȃ�A�قƂ�lj����H�ׂ��Ȃ��Ȃ�܂����B����Ƃ��A�ЂƂ�̓��{�̃i�[�X���A���̎q�ɁA�����H�ׂ�ꂻ�����Ɛq�˂܂����B���̎q�́u�̈�x�H�ׂ����Ƃ̂���p�C�i�b�v����H�ׂ����v�Ɠ����������ł��B���̌��t�����i�[�X�́A�����ɖ�̒��ɂł����܂����B�ЂƂ�Ő^�~�̒������u�p�C�i�b�v���͂���܂��H�v�ƈꌬ�ꌬ�X��q�˕����ꂽ�����ł��B�~�̃��V�A�ɁA�p�C�i�b�v���Ȃǔ����Ă�͂�������܂���B�������A���{�̃i�[�X���p�C�i�b�v����钆�T������Ă���Ƃ������������ɂ�������n���̕����A�ۑ����Ă����p�C�i�b�v���̊ʋl���ЂƂޏ��̂��Ƃɓ͂��Ă���܂����B
�@�@�܂��Ȃ��A���̎q�͖S���Ȃ�܂����B���c�搶�̔M�S�Ȃ����Â͖��O�ɂ��������Ȃ������̂ł��B�������A���̎q�̗��e�́A��̃p�C�i�b�v�������߂Đ^�~�̒����삯����Ă��ꂽ���{�̃i�[�X�̎p�ɂƂĂ��������ꂽ�����ł��B�䂪�q�̖��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�������A���{�l���^���Ă��ꂽ�D�����͌����ĖY��Ȃ��ƁE�E�E�E�E�E�B
�@�@���݂̊��c�搶�́A�ɘa��ÁA������^�[�~�i���P�A�ɑS�͂𒍂��ł����Ƃ̂��ƁB���c�搶�́A���̘b������邱�ƂŁu��Â̖{���v�����ł��邩���A���̕��X�ɔM������悤�Ƃ����̂ł��傤�B�l�͈�Â�ʂ��ĉ��悤�Ƃ��Ă���̂��B��Â��l�̐S�ɍ�p���A�l�̐S�Ɏc��������͉̂��ł���̂��B�����̔��k�ɏI��点�Ȃ��M���v�����A���c�搶�̒W�X�Ƃ��������Ɋ������܂����B
�@�@�{�w��̃e�[�}�́w�S�Ó��Ȃ͐��E��ς����x�ł����B���̐��E�Ƃ́A�{���̐��E�ɉ����āA���Ȃ�S�̐��E�i�C���i�[���[���h�j�ł�����̂��ƁA���̂Ƃ��i��҂��^�����q�ב�������܂����B���̌�̎��͂Ƃ����ƁA�A��̐V�����̂Ȃ��ŁA�u�S�v�Ƃ��������̕t���ꂽ��Âɂ��Ďv�����͂�����A�p�C�i�b�v����T���������i�[�X�̎p���܂�œ��b�̎�l���̂悤�ɐS�ɕ����сA���̂܂ܐS�n�悢����ɗ����Ă��܂��܂����B���c�搶�A�M�d�Ȃ��u�����肪�Ƃ��������܂����B
�@�@���Ȉ��Ȃ����
�@�@�y���Ȉ��Ƃ́z
�@�ŋ߁A�Տ��S���w�Łw���Ȉ��x�Ƃ������t���悭�g���܂��B���Ȉ��Ƃ͕����ǂ��舤�̂ЂƂ̌`�Ȃ̂ł����A�@����N�w�Ř_�c�����`����I�ȊT�O�Ƃ͏�������āA�����Ɠ���I�ȁu���M�ɂȂ���G�l���M�[�v�ƌĂׂ���̂ł��B�S�Ó��Ȃ̐f�ÂŎ��Ȉ����d������₷�����R�Ƃ��āA����̂��a��S�g�NJ��҂���ɁA���̎��Ȉ������܂��@�\���ĂȂ��l�������݂��鎖���������܂��B
�@���������Ă݂܂��傤�B���e�t�̂Q�S�̂`�q����́A���X�ΐl�ْ��������A���h���͂�₷���l�ł����B���N�O��e�̋}�������������ɁA���N�Ԃ����ɂ���M�Ȃǂ̑̒��s�ǂŋꂵ�ނ悤�ɂȂ�܂����B�N�ł��Ƒ��̎��ɂ���ĐS�g�̕s�������������Ƃ͈����Ԃ���ł��傤�B����͎��҂�����̐S���ł����āA�߂��݂�����̂ɕK�v�ȑr�ɕ��������ƌ����܂��傤�B
�@�������`�q����̂悤�ɉ��N����������ʂ��o���Ȃ��ꍇ�A���X�ɂ��Ď��Ȉ��̖�肪�[�����݂��Ă��܂��B���a�O�̂`�q����͎��������Љ�l�̂ЂƂ�ł����B��������e�̎����_�@�ɁA�������g�̐����鉿�l��������Ȃ��Ȃ�A�Ǘ������̐S���Ɋׂ��Ă��܂��܂����B��e�̎����`�q����ɂ���قǑ傫�ȈӖ��������炵�����R�̂ЂƂɁA�`�q���c���������e�ƃ����b�N�X�����ˑ��W��̌��o���Ȃ��������Ƃ��������܂��B�Â������̂ɊÂ����Ȃ��Ƃ����q�����ォ��̃W�����}����e�̎����_�@�ɋ����ӎ�����n�߂��̂ł����B�����Ă`�q����̌��X�̑ΐl�ْ����A���̂悤�ȑ��l�ɊÂ�����Â���ꂽ�肷�邱�Ƃւ̋����ƊW������܂����B
�y���l�����Ă̎��Ȉ��z
�@���͎��Ȉ��͎����ւ̈��ł͂���̂ł����A���l�ɂ���Č`����镔���������̂ł��B�����̑��݂�F�߁A��e���A�����A�g�����Ƃ�Ԃ��Ă����u���v�̂悤�ȑ��҂̈�т������݁B����͈ӎ����邵�Ȃ��Ɋւ�炸�A���N�Ȏ��Ȉ��i�قǂ悢���Ȉ��j���͂����ޑb�ɂȂ�܂��B�����āA�قǂ悢���Ȉ����S�ɍ��Â��Ă��Ȃ��ƁA�����̃L�b�J�P�Ŏ������g�̉��l����b����������A���Ȉ��͐Ǝ㉻���Ă��܂��܂��B�Ǝ�Ȏ��Ȉ��͑��l�Ƃ̊W�ɕs�����Ăт₷���A���l�ɂ����݂��悤�Ȉˑ��I�ԓx��A���l�̊��Ғʂ�ɂ����������Ȃ�����l�`�̂悤�ȁw�U��̎��ȁx���剻���܂��B�A���R�[���ˑ��ǂɂȂ��Ă��܂��l�������悤�ł��B��e�̎����`�q����ɓ˂������ۑ�́A���̂悤�Ȕޏ����g�̎��Ȉ����߂��銋���ł����B�Ƒ��̎��ɂ����炸�A��N�ł̎d���̑r���A�̎��s�A�����ȂǁA�l�X�ȑr���̌����L�b�J�P�ɁA���Ȉ��͎������@�ɒ��ʂ��₷���Ȃ�܂��B���������Ȉ��́A�a�C�]�X�Ƃ����ɂ́A���܂�ɐl�ԓI�ȉۑ�̂悤�ł��B
�@�y�l�E�������[�̔ߌ��z
�u�������[�nj�Q�v�Ƃ������t���������ł����H�@�c�����A�������[�͒g�����ƒ�Ɍb�܂ꂸ�Ǝ�Ȏ��Ȉ���������܂��D�Ɉ炿�܂����B�l���݂͂��ꂽ�������Ɍb�܂ꂽ�Ⴋ���̃������[�́A���̑A�]�Ə^����g�Ɏ邱�Ƃ��ł��܂����B�������N���ւ�ɂꎟ��ɐ��Ԃ���̒��ڂ�^�������A�A���R�[���Ɛ�����ɓM��A���ɔߌ��I�Ȏ����}���܂����B�������[���N�ƂƂ��Ɏ��������̂́A�ޏ��̐Ǝ�Ȏ��Ȉ����Ȃ�Ƃ������Ă����u���ԂƂ������v�������ƌ����Ă��܂��B
�@����A���̑O�̋M���͂ǂ��ł��傤�B���̊炪�Ȃ�ƂȂ��ɂ��ɂ����Ă���悤��������A�ЂƂ܂����Ȉ������܂��@�\���Ă���ƍl���A�אl�ɂ��v�����͂��Ă݂悤�ł͂���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@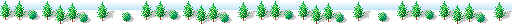
�@�@�X�c�Ö@�w��̉ۑ�
�@����P�O�����{�A�D�y�ő�P�W��X�c�Ö@�w��J����܂����B�X�c�Ö@�͐X�c���n�Ƃ�����t���\�z�������{�I�ȐS���Ö@�ł����A�������ɒ�����[���b�p�ȂǑ����ł����ڂ����悤�ɂȂ�܂����B�S���Ö@�Ƃ����A���_���͂�F�m�s���Ö@�A���W���[�Y�̃J�E���Z�����O�Z�@�Ȃǂ����ς�A�����߂ł����A�X�c�Ö@�͐����Ȃ����{���M�̎��Ö@�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�Ƃ���ŐX�c�Ö@�́u�s��v�u�ړI�{�Ӂv�Ȃǂ̌��t�������悤�ɁA���̌�������E�C��K�v�Ƃ��鎡�Ö@�ł��B���Ƃ��A�V���Ԃ̐�Ή���Ƃ������Ê��Ԃ��݂����Ă���A���̊Ԃ͎��R�ɕ�����鎖�͋֎~�ŁA�Ђ�����x�b�h�ł̉珰�𖽂����܂��B�{���A�X�c�Ö@�͍������z���Ȃ����̂Ɏ��ȂɌ������Ȃ肪�����X�c�_�o���Ƃ�����Ԃɂ����N�w�ɗp�����邱�Ƃ��������Âł��B�Ƃ��낪�ߔN���̐X�c�Ö@�����܂��s���Ȃ��a�I�Ȏ�҂��ӂ����ƌ����܂��B���Ƃ��A��Ή���̌��������[�������Ȃ��A���Èӗ~���ێ��ł��Ȃ��A���Â̏�ɂƂ����߂����ÊW�����Ȃ��Ƃ������P�[�X�������A�X�c�Ö@�̌��@��l�X�ɕς�����Ȃ����o�����Ă��܂��B����A�����ɂ����Ă��A���Ẵt���C�g�̕����I�ŋ֗~�I�ȃA�v���[�`����A��q�W���d������ꐫ�I�Ŏ�e�I�ȃA�v���[�`�����s�����܂��B�䂪���ɂ�����X�c�Ö@���l�I�����^�Ƃ��ĊO�����Â𒆐S�Ƃ������Â��s��ꂽ��A���̎��ÃG�b�Z���X�������̑��̎�e�I���Âƕ��p���ꂽ�肷��悤�ɂȂ�܂����B��P�W��X�c�Ö@�w��ł́A���̂悤�ȐX�c�Ö@�̕����鍡���I�ȉۑ�Ƃ���ւ̑Ή��@�ɂ��đ����̋c�_�����킳��܂����B
�@�@�@�@�@�@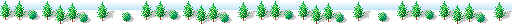
�@�@�킪�f�@���O�̐����̃G���[���t�B�V�����z��
�i���F���̋L���͎������s��a�@�ɋΖ����Ă������̂��̂ł��j
�@���̐f�@���̑O�ɂ����Ă��鏬���Ȑ����ŁA�����Q�C�̃G���[�����q��z�������܂����B�G���[���͔��ɒm�\���������̂悤�ŁA���Ƃ��K���X�z���Ɏ�����̊���L�����Ă���鎖������̂ł��B�Ƃ���ŃG���[���t�B�b�V���̒��Ԃ́A���̈玙���}�E�X�u���[�_�[�Ƃ������@�ōs���܂��B�}�E�X�u���[�_�[�Ƃ́A�댯�����܂�Ǝq���B�͐e�̌����ɂ��₭�������݁A�댯������ƍĂь��̊O�ɏo�Ă���Ƃ��������[���K���̈玙���@�������܂��B�G���[���t�B�b�V���̌������������J���K���[�̕��܂̖��������Ă���悤�ł��B
�@�S�Ó��ȊO�����҂��A���̎q��Ă̎p�ɖڂ��~�߂��A�u�e�̌����B��ƂɂȂ��Ă���v�Ƃ����e�q�̕s�v�c�Ȍ��т����ώ@���đՂ�����A������Ƃ��Ă��̂����Ȃ���тł��B�����i�H�j�ҍ����Ԓ��ɐ���������B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@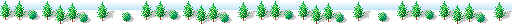 �@�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@�ЂƂ�ł����\��
�@����̓p�[�\�i���e�B���������_�Ö@���s����Ƃ��ɁA�悭�b��ɂȂ�e�[�}�ł��B
�u�ЂƂ�ŋ����\�́v�Ƃ́A�ЂƂ�ŋ��Ȃ���N���Ƌ���悤�Ȉ��S����ێ��ł��A�t�ɒN���ƈꏏ�ɋ��鎞�ɂ��������ЂƂ�ŋ���悤�Ɉ��肵����S���I�Ȕ\�́A�Ƃ��\������܂��B�����āA�ЂƂ�ŋ����\�͂̃��[�c�́A�S���w�I�ɓ��c�����̔��B�ۑ�̂ЂƂƍl�����Ă���A�l�X�Ȍ���a���l�@����ۂ̃L�[���[�h�Ƃ�������d�v�Ȏ��_�Ȃ̂ł��B
�@�l�͓��c�����ɁA���N�L���Ƃ������̂�S���I���B���C���ɉ����Ċl�����܂��B����͖ڂ̑O�ɑ��݂��Ȃ����̂�z���o���\�͂Ƃ����Ă��悢�ł��傤�B�����s���A�h���[�S���w�ɂ��ƁA�c������̎p��s���ɂȂ��Č�ǂ�������̂́A�܂����̊��N�L���̖����B�ɂ��Ƃ���܂��B���N�L���������ƂƂ��ɔ��B���邱�ƂŁA�l�͕s���ȏ�ʂŁA���R�Ɏ������Ԃ߂Ă����u���₵���u�v�̃X�C�b�`�����鎖���ł���悤�ɂȂ�܂��B�ŏ��́A��̎p������ɓ���鎖�Łu���₵���u�v�̃X�C�b�`�������ɂ��܂����A���̂�����̎p���C���[�W�őz�N���邾���ŁA�c���͎����̊������߂鎖���ł���悤�ɂȂ�킯�ł��B
�@�₪�āA�����̍����ł������u�ꂻ�̂��́v�́A�u��Ȃ���́v�u��I�Ȃ��́v�ɕϖe���A�ꂻ�̐l�̃C���[�W����A���̐l�ŗL�̏C�����ꂽ�u���₵���u�v����E�ɕێ�����悤�ɂȂ�܂��B���́u���₵���u�v�́A�����̉ߒ��ŗl�X�ȋL��������b��ƃ����N���Ȃ���A�҂�����s�����y���������p������悤�ɂȂ�܂��B
�@���āA����̎�ҒB�̋����I�Ƃ�������u�O���[�v���v�ւ̐�O�A��������a�O����邱�Ƃւ̋������|���A�����Đe�B�̂���܂������I�ȁu�q���̗F�l���v�ւ̊S�B�����̌��ۂ́A�ЂƂ�ŋ����\�͂̎���I�Ȍ����Ƃ݂Ȃ����Ƃ��o����̂ł��B
�@���I�ȁu���₵���u�v���[���ɕێ��ł����A����̊�����ЂƂ�ŃR���g���[�������҂́A���ǁA���͂ɂ��鑼�l�̐S���g���Ď����̊�����R���g���[�����悤�Ƃ��܂��B���̏ꍇ�A���_���͂ł����u���e�����ꎋ�v�Ƃ������Ȗh�q�̃��J�j�Y�����悭�g���܂��B�{��l�͑��l��{�点�A�s���Ȑl�͑��l��s���ɂ�����Ƃ����u���l���������ށv��@�ł��B�v����ɐh����{��Ȃǂ�����𑼐l�ɕ��z�������ƂŎ���̐����c���������A�Ƃ������̂ł��傤�B
�@�h���i�h�����j��Ԗʋ��|�Ƃ������X�c�_�o�ǓI�Ȏ�����l�ŔY�ރ^�C�v�̐_�o�ǂ�����������A���l�������^�̎��Ȉ��I�a�����Љ�ɖ��������錻�ۂ́A�₪�Ă��[���ȘV�N���S�g�ǂ̈�吢����Y�ނ̂ł��傤���B���悻�T�O�N��̂��Ƃł����B
�@�@�@�@�@�@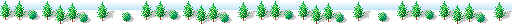
�[���Ö��ɂ�����l
�@���l�̖��߂ɏ]���悤�Ȑ[�Ö��ɂ�����l�́A���{�l�̂����l���̈���x�ƌ����܂��B���̑��̐l�́A����������Î������������܂���x�ł���A�e���r�Ȃǂ��������I�ɍs���Ă�����̂͋Â����O����������Ă���̂��낤�Ɛ�������܂��B�Ö��ɂ�����₷���l�Ƃ́A���X��Î����������A���҂ƐM���W�����ׂ�\�͂̂���l�A�x���S�̒Ⴂ�l�A���i�I�ɔ�r�I�f���Ȑl�A�Ö��ɂ����肽���Ƃ������@�̋����l�B�ł��B�܂�A�Ö��Î��Łu�Ȃ����܂܂ɈÎ��ɐg���ς˂܂��傤�v�A�u�S�ɂ��ĐS�g�̕ω��ɂ��������܂��傤�v�Ƃ������t�ɁA���܂�x���S���Ȃ��f���Ɉˑ�������l�B�ł��B
�@�ŋ߁A�S�g�ǂ̗Տ�����ōĂэÖ��Ö@�����ʓI�Ȏ��Ö@�Ƃ��Č�������铮��������܂��B����܂ōÖ��Ö@����Õ���̗̈�Œ���Ă������R�̂ЂƂɁA�Ö����u���҂���̈ˑ��S����������v�Ƃ����ᔻ�������������Ƃ��������܂��B�܂�S���Ö@�Ƃ͂����܂Ŗ{�l���{�������Ă���S�̋����������o���A�{�l�̎����𑣂��������Ƃ���܂��B�ˑ�������������Ö��Ö@�́A����ɋt�s�������Âł���Ƃ����ᔻ���������킯�ł��B
�@�����������̐S���Ö@�S�̗̂��ꂪ�A����̗v���䂦���A�ˑ��S�Ƃ������̂��ȑO�̂悤�ɓG�����Ȃ��Ȃ�܂����B���Â������߂Ă����ɂ����āA�ˑ��S�͎����S�Ɠ����ȕ]��������܂��B����̕���ł��A�����̑O�i�K�Ƃ��Ĉˑ��̒i�K�͕s���ƌ�����悤�ɂȂ�܂����B���̌��ʂƂ����S�g�ǂ̗Տ�����ł��A�Ö��Ö@�������������킯�ł��B�������������ƂɁA�J�ɍÖ������ׂ���ɗ��p��������u�G�Z���Îҁv���Ăщ��s���n�߂Ă��܂��B���ۂɁA�Ⴆ�P���ԂR���~�Ƃ������z�̎��Ô���Ƃ�A���̍Ö����ʂ͂����ς�ʖڂƂ����ꍇ�����ɑ����悤�ł��B
�@�@�@�@�@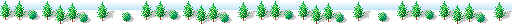
�V�N���S�g�ǂ̎���
�@�V�N���S�g�ǂ̓����Ƃ��āA�߂܂��A�s���A�葫�̂��тꊴ�A����ȂNJ�łɑ����g�̏Ǐ���A���͂̐l��焈Ղ���قǃN�h�N�h�i���邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B������s��D�i�Ƃ������̂ł���A�Ǐ�̑i�����Ȃɂ���܂�Ȃ���ۂ�����܂��B���L���Ȃ��Ƃ�����܂����A�����͂��ꂾ���ł͖����ł���Ǐ���P�݂͂��܂���B
�@�L���łȂ������ɁA�Ǐ��ɔ�r�I�L���ȕ��@������܂��B�Ƃ����̂́A�厡��A�J�E���Z���[�A�i�[�X�A�P�[�X���[�J�[�Ȃǂ̒N��������������荞��Řb�����Ă�����ƁA�s�v�c�Ȃقǂɗ����Ǐy��������̂Ȃ̂ł��B�܂肱�̂悤�ȍ���҂���́A���퐶���̒��ł�������b���������肪���Ȃ����Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂ł��B���̂��߈�Ԃ̘b������́A�u�����̐g�́v�Ƃ������ԂɂȂ��Ă���悤�Ȃ̂ł��B�u�����̏Ǐ�̂Ђǂ��́H�v�@�u�������Ǐ�͋������낤���H�v���X�A�ނ炪�u�g�́v�Ɍ�肩���錾�t�͖L�x�ł��B�����āu�g�́v�̑����K������Ȃ�ɉ������Ă����̂ł��B��Î҂͂��̂悤�Ȗ{�l�Ɓu�g�́v�̉�b�ɁA�^�C�~���O�悭��˒[��c�I�ɎQ�����Ă������ƂɂȂ�܂��B���Î҂́u�S�Ƒ̂̐^���ȉ�b�v�S�̂��炠�ӂ��s����̂Ȃ��s����҂��������Ɋە������邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��B���Î҂́A���鎞�͐S���̗����҂ƂȂ�A���鎞�́u�g�́v���̗����҂ƂȂ��āA�����ÂS�Ƒ̂�����݂����A�����肷��悤�ɉ�����Ă����܂��B�������A���ꂾ���Ŏ��Â��ςނ킯�ł͂���܂���B�b��������u�g�́v�ȊO�Ɍ����Ă�������̒��������Ă����˂Ȃ�܂���B�w��ɁA���N�̕v�w�W�̖���A�e�q�W�̃X�g���X�ȂǁA�l���̏W�听�Ƃ��Ă̏d���ۑ肪�������̂܂܉�������Ă���ꍇ������܂��B�����ł͊��҂̒~�ς��ꂽ�v���C�h�≿�l�ς�������ƂȂ����Â�i�߂�K�v������܂��B
�@�@��҂̐S�g�ǂƂ́A�ЂƖ�������A�v���[�`���K�v�ƂȂ�܂��B����̐S�g�NJ��҂���́A�Ǐ���܂��~�n���Ă���A���Ɏ育�킢�̂ł��B�@(7/18)
�@�@�@�@�@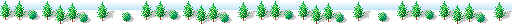
�����p�ւ̕s��
�@������͊Q�ł���ȂɂȂ邩��A�Ɛ��������ɕ|���銳�҂������܂��B������܂Ȃ��ł��ނȂ�A���̕��������͓̂��R�ł��B�������K�v�ȏ�ɕ|����̂����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����l�͑��ʂ̃r�[���𐇖����Ɉ��ނ悤�ɂȂ�܂����B������̕���p���|������A���R�[���ɂ������A�Ƃ����̂����̗��R�ł����B�͂����āA���ʂ̃A���R�[���Ə�p�ʂ̐�����A�ǂ��炪�g�̂�]�Ɉ��e�����y�ڂ��ł��傤���H�@�܂��A�ǂ���̕����ȂɂȂ�₷���̂ł��傤���H�@
�@�Ⴆ�ΊQ�Ɋւ��ĂȂ�A�S����̑��ɑ��Ă͂ǂ��ł��傤���H�@�����͐S���A�X���A�̑��A������A�]�ȂǁA�قƂ�ǂ��ׂĂ̑���ɂ����āA�A���R�[���̕���������������e�����y�ڂ��܂��B�u���������ʂ̃A���R�[���i�P���P���ȉ��j�́A�������Ď����������Ƃ�����w�f�[�^�[�����邶��Ȃ����E�E�E�E�E�E�v�ƁA����ɔ��_������������ꂻ���ł��B�m���ɂ���i�P���ȉ��j�������Ǝ����Ȃ�A�A���R�[���̕����Ђ���Ƃ����珟����������܂���B�Ȃ��Ȃ�Δ��Ɏc�O�Ȃ���A��p�ʂ̐����������������ǂ����Ƃ������Ƃ́A�܂��S����������Ă��Ȃ��̂ł�����B�@
�@�@�@�@�@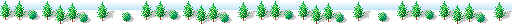
�~�J�ƐS�g��
�@�~�J�̎����ɂ́A�S�g�NJ��҂���̏Ǐ�͈������邱�Ƃ������B���ɂ���Ԃ̊��҂���ɂ����Ă��̌X��������������܂��B�����̂ЂƂɁA���Ǝ��Ԃ̏��Ȃ����w�E����Ă��܂��B
�@�l�ԂɁA�쐶�����Ƃ��Ă̏����̋L�������܂�Ă���Ȃ�A����͂�����x�[����������̂ł��傤�B�Ȃ��Ȃ�A���Ǝ��Ԍ�����J�́A���E���������A�H������������Ȃ邱�ƂɂȂ��邩��ł��B�H�~���ቺ���A�s�����ቺ���邱�Ƃ́A���̂܂܂Ƒ̓��̃G�l���M�[�����}���A��菭�Ȃ��l���Ő����邽�߂̐g�̂̑I������ƍ����I�Ɉ�v���܂��B�܂�A�~�J���̐S�g�́u���I�Ȋ����ቺ�v�́A�쐶����̖{�\���l�Ԃ̑̓��ɋL������Ă������������܂���B
�@�@�@�@�@�@

 �@
�@
 �A�N�Z�X�T�O�O�O�L�O�̑n�삨�b�ЂƂ�(1999)
�A�N�Z�X�T�O�O�O�L�O�̑n�삨�b�ЂƂ�(1999)