1.はじめに
陶芸仲間で、台湾に行ってみよう、ということになった。
故宮博物館で陶芸品を見るのが目的である。私の陶芸仲間は、陶芸の研究に
熱心な者が多い。不勉強な私は、陶芸はともかく、初めての土地を訪ねるこ
とは大好きなので、何はともあれ参加することにした。
日程や訪問先などは、全て長老の団長、副団長にお任せである。
有志7人で、3泊4日と銘打った(実質2日間の)格安旅行に出かけた。
2.航空事情
出発18:40の予定が1時間半の遅れとなった。
今回の航空機はノースウエストで、アメリカからの到着が遅れたためである。
出発ゲート付近の喫煙室で時間をつぶしていたとき、目についたことがある。
.jpg)
ライターが壁に吊り下げられ、
←「ライターをお持ちでない方はこちらをご利用下
さい」
という親切な案内文が表示されていたのである。
ようやく関空も顧客サービスに腰をあげたのか、
と思いつつ、近くにあった張り紙を見て合点がいっ
た。
去年(2005年)4月より、アメリカ行き航空
機にはライターの持ち込みが禁止されているのであ
る。さらに、行き先にかかわらず、アメリカの航空
機へのライター持ち込みが禁止されているのである。
つまり、ノースウエストなどの乗客は、ライターを持っていないハズなので
あるから、この喫煙室ではタバコを吸えないハズなのである。
たまたま近くにいた空港職員に聞いてみたところ、禁止されているのは機
内持ち込みだけでなく、飛行機に積み込むこと自体が禁止されているそうで
ある。ジッポもどきのライターをポケットに入れていた私は、愛着のある一
品を取り上げられてしまう恐怖に襲われた。
..が、結果として、行きも帰りも問題なかった。
関空から台北中正空港まで1,743Km、関空離陸から台北着陸まで2
時間32分、帰りは1時間49分だった。帰りは偏西風に乗ったためか、時
速1,180Kmの表示を見かけた。関空着陸直前の速度は時速151Km
だった。
3.龍山寺
翌2日目は、丸一日台北の市内観光だった。
予想に反して、台湾は日本と同じように、多分5℃位の寒さだった。台湾で
は珍しい寒さだという。加えてしとしとと雨が降り続いた。
最初に訪ねたのは龍山寺だった。
石の柱に緻密な彫刻が施されていたのが印象深かった。
.jpg)
お寺は中国風だったが、お祈りを捧げ
る人達の姿は、大陸中国とは心もち雰囲
気が違うようである。
仏教国のバンコクと同様に、人々の表
情が柔らかいように感じられた。
.jpg) 4.故宮博物院
4.故宮博物院
何気なく故宮博物館と呼んでいたが、正しくは「故宮博物院」らしい。
その故宮博物院は、緑に包まれた丘陵の一角にあった。
.jpg)
常設展示品だけでも、じっくりと鑑賞
するためには2日以上かかるだろう。
「宝石で作った白菜」「宝石で作った煮
豚」は、いつか「世界不思議発見」で紹
介されたことがある。
見事な陶磁器もあった。
いくつかをここで紹介したいところだが、あいにく館内は撮影禁止だった。
将来の(掲載の)可能性を想定して、スペースだけ用意しておこう。
.jpg) ←陶器の花入れ
↓宝石の白菜
←陶器の花入れ
↓宝石の白菜
.jpg) 5.忠烈祠
5.忠烈祠
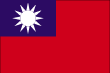
広大な敷地に建っている立派な廟があった。
「忠烈祠」という、戦争で殉死した人を祀って
いる廟である。
.jpg)
現地人ガイドの説明によれば、「日本
の靖国神社です」ということだった。
祀られているのが国民党関係者だけなの
かどうか、は聞き漏らした。
←本殿(柱を補修中)
正門と本殿の門には、警護の衛兵が立っている。
衛兵は直立不動で、ほとんど瞬きもしないで一点を見つめている。
.jpg)
1時間毎に交代するそうである。
毎日、1時間毎に交代式が行われている。
.jpg)
台湾では2年間の兵役義務が課されている。
台湾の若者は、男女にかかわらず、年寄りに親切だった。電車内では若い女
性がすぐ席を譲ってくれたし、券売機の前で迷っていたら、迷彩服の青年が
操作を教えてくれた。
6.228平和公園
観光の2日目、3月2日は終日自由行動の日だった。
この日は朝6時前に目が覚めた。朝食前に、同室のWさんと急遽228公園
を訪ねることにした。
Wさんは尺八の名奏者で、いつもお琴の和服美人と合奏を楽しんでいる紳士
である。酒と女性に強いWさんは、歴史にも手を出しているようである。
228公園はホテルから徒歩15分と近かった。
台湾に到着したのは228、つまり(2006年)2月28日である。
228という日付けは、台湾の人、特に本省人(大陸からきた外省人でなく、
もともとの台湾人)にとって重要な意味がある。
.jpg) ←228事件の記念行事が228公園で
(2月28日に)行われたことを報じる
3月1日朝のテレビ画面
↓228公園の西入り口
(赤い横断幕は、鳥インフルエン
ザに注意を呼びかけている)
←228事件の記念行事が228公園で
(2月28日に)行われたことを報じる
3月1日朝のテレビ画面
↓228公園の西入り口
(赤い横断幕は、鳥インフルエン
ザに注意を呼びかけている)
.jpg)
終戦後、日本に代わって台湾を支配した国民党政府の抑圧的政策や腐敗に
対し、反発する人が多かった。228事件とは、抗議行動を起こした人々に
向け、1947年2月28日、当局が発砲して多くの死傷者を出した弾圧事
件である。
この事件を契機に発令された戒厳令は、1986年まで40年間続いた。
.jpg) ←228記念碑
↓台北駅方面を望む
←228記念碑
↓台北駅方面を望む
.jpg)
公園の記念碑には、陳水偏さんの名で「二二八和平公園」と記されている。
.jpg)
現総統の陳さんが、台北市長の時代
に整備したものである。
←二二八和平公園記
↓公園に近い総統府
.jpg) 7.陶芸博物館
7.陶芸博物館
自由行動のこの日は、故宮博物院をじっくり見て回る予定だった。
しかし、前日のツアーで2時間ほど故宮を見た結果、団長と副団長の決断で、
この日は別の施設を見ることになった。
行く先は、「台北県立鶯歌陶磁博物館」だった。
鶯歌[いんが](うぐいすの歌?)というロマンを感じさせる駅は、台北の
南西の方向にある。台北から鶯歌までは電車を利用することになった。
ホテルから台北駅までは地下鉄を利用した。
.jpg)
地下鉄の自動券売機と自動改札機は、日本のメ
ーカー製(オムロン)だった。
鶯歌への途中、日本の技術を採用した新幹線と並
行して走る箇所があった。
←日本製の自動券売機と改札機
↓
.jpg)
台北駅の窓口で購入した指定席切符は31元(約110円)だった。
帰りに鶯歌駅の自動券売機で購入した指定なしの切符も31元だった。
(帰国後に調べたら、これは「復興」という列車の値段で、普通の列車は
23元のようである)
台北から鶯歌までは30分だった。
.jpg) ←台北駅で購入した指定席切符
↓鶯歌駅
←台北駅で購入した指定席切符
↓鶯歌駅
.jpg)
鶯歌駅の近くに陶器市場があったが、まずは博物館に向かった。
およそ20分位歩いた。鶯歌陶磁博物館は2000年に開館したそうで、4
階建ての立派な建物である。展示物も立派だった。
入館料は100元だったが、65歳以上は無料だった。
.jpg) ←鶯歌陶磁博物館
←鶯歌陶磁博物館
と掲示したいところであるが、面目な
いことに、電池切れで撮影ができなか
った。博物館を出てから、セブンイレ
ブンに走った。
館内は無論撮影禁止である。
博物館の次は陶磁器店の並ぶ一角を訪ねた。
博物館から30分位歩いた所の陶磁老街という一角は、きれいに整備され、
沢山の陶滋器の店が並んでいた。
.jpg)
ここはのどかな町で、町おこしとして陶芸観
光に力を入れているようである。
商品は豊富で、値段も手頃な感じだった。
きっと休日にはお客さんで賑わっているのだろ
う。
←小さな店が入っている老街陶館
8.全般の感想
はじめての台湾の印象としては、何となく親しみがもてたことである。
例えば、日本のテレビ番組がいくつか放映されていた。どれだけの番組を観
ることができるのかは分からないが、私が観たのは夜10時からのNHKの
ニュースで、これは日本と同時の放映だった。2年前に、上海の駐在員宅で
見たNHKの同番組は翌日の放映であり、検閲後の編集された録画だった。
駅や店などの漢字表記は、中国の簡体字表記と違って、日本人でもわかり
易かった。「関東煮」と書いた札を立てて「おでん」を売っている店もあっ
た。下町の、地元の人たちが食べている食堂では、豪華レストランとは違っ
た楽しみを味わえた。食べて呑んで、一人当たり700円前後だった。
下町の食堂では、片言の日本語を話す老婆が注文を受け、清算は若い奥さん
がお皿毎の値段をメモ用紙に書き出して合計金額を計算した、というほほえ
ましい場面もあった。
もうひとつの印象は、予想外に街がきれいなことだった。
景観についての私のこだわりは、どれだけ電線の地中化が進められているか、
にある。いずれ、新しいホームページを立ち上げ、最も見事に電線で被われ
ている地域に、「日本蜘蛛の巣大賞」「世界蜘蛛の巣大賞」と銘うった賞を
授与してみたい、と考えているくらいである。
.jpg)
その意味では、(幸いにも)台北も鶯
歌も受賞資格を欠いている。
←私が見た限りで、電線が目立った鶯歌
(蜘蛛の巣大国日本には到底及ばない!)
9.おわりに
団長以下、私以外は、陶芸に熱心である。
私は陶芸以外のことで覗き見をするため、一人で立ち止まることが多かった。
旅行の終わり頃、いつの間にか私はデパートに一人で置き去りにされていた
ことがあった。しかし、陶芸仲間から冷たい仕打ちを受けた、などと思って
はいけないだろう。総統府付近の散歩や女流陶芸家との出会いを楽しむこと
ができたのは、私一人だけなのだから。
私が台湾に関心をもったのは、日本語の指導法を学んだときだった。
日本語の指導法の研究は、台湾の統治をきっかけとして始まった。
台湾総督府には、各界の一流の人材があてられた。教育を担当する初代学務
部長には、日本近代音楽の育て親と言われた伊沢修二が任命された。台湾総
督府が設けられた明治28年(1895年)のことである。
伊沢が開設した学校で、教師6人が殺害された事件があった。
台北北部の芝山巌(しざんがん)という地に、教育に献身した6人の先生を
讃える「六士先生殉職」の記念碑が建てられているそうである。
伊沢は遺言により、六士先生の墓に埋葬されているという。
今回は、残念ながら芝山巌を訪ねる余裕はなかった。
(散策:2006年 2月28日
〜 3月 4日)
(脱稿:2006年 3月20日)
------------------------------------------------------------------
この記事に
感想・質問などを書く・読む ⇒⇒
掲示板


ライターが壁に吊り下げられ、 ←「ライターをお持ちでない方はこちらをご利用下 さい」 という親切な案内文が表示されていたのである。 ようやく関空も顧客サービスに腰をあげたのか、 と思いつつ、近くにあった張り紙を見て合点がいっ た。 去年(2005年)4月より、アメリカ行き航空 機にはライターの持ち込みが禁止されているのであ る。さらに、行き先にかかわらず、アメリカの航空 機へのライター持ち込みが禁止されているのである。 つまり、ノースウエストなどの乗客は、ライターを持っていないハズなので あるから、この喫煙室ではタバコを吸えないハズなのである。 たまたま近くにいた空港職員に聞いてみたところ、禁止されているのは機 内持ち込みだけでなく、飛行機に積み込むこと自体が禁止されているそうで ある。ジッポもどきのライターをポケットに入れていた私は、愛着のある一 品を取り上げられてしまう恐怖に襲われた。 ..が、結果として、行きも帰りも問題なかった。 関空から台北中正空港まで1,743Km、関空離陸から台北着陸まで2 時間32分、帰りは1時間49分だった。帰りは偏西風に乗ったためか、時 速1,180Kmの表示を見かけた。関空着陸直前の速度は時速151Km だった。 3.龍山寺 翌2日目は、丸一日台北の市内観光だった。 予想に反して、台湾は日本と同じように、多分5℃位の寒さだった。台湾で は珍しい寒さだという。加えてしとしとと雨が降り続いた。 最初に訪ねたのは龍山寺だった。 石の柱に緻密な彫刻が施されていたのが印象深かった。
お寺は中国風だったが、お祈りを捧げ る人達の姿は、大陸中国とは心もち雰囲 気が違うようである。 仏教国のバンコクと同様に、人々の表 情が柔らかいように感じられた。
4.故宮博物院 何気なく故宮博物館と呼んでいたが、正しくは「故宮博物院」らしい。 その故宮博物院は、緑に包まれた丘陵の一角にあった。
常設展示品だけでも、じっくりと鑑賞 するためには2日以上かかるだろう。 「宝石で作った白菜」「宝石で作った煮 豚」は、いつか「世界不思議発見」で紹 介されたことがある。 見事な陶磁器もあった。 いくつかをここで紹介したいところだが、あいにく館内は撮影禁止だった。 将来の(掲載の)可能性を想定して、スペースだけ用意しておこう。
←陶器の花入れ ↓宝石の白菜
5.忠烈祠
広大な敷地に建っている立派な廟があった。 「忠烈祠」という、戦争で殉死した人を祀って いる廟である。
現地人ガイドの説明によれば、「日本 の靖国神社です」ということだった。 祀られているのが国民党関係者だけなの かどうか、は聞き漏らした。 ←本殿(柱を補修中) 正門と本殿の門には、警護の衛兵が立っている。 衛兵は直立不動で、ほとんど瞬きもしないで一点を見つめている。
1時間毎に交代するそうである。 毎日、1時間毎に交代式が行われている。
台湾では2年間の兵役義務が課されている。 台湾の若者は、男女にかかわらず、年寄りに親切だった。電車内では若い女 性がすぐ席を譲ってくれたし、券売機の前で迷っていたら、迷彩服の青年が 操作を教えてくれた。 6.228平和公園 観光の2日目、3月2日は終日自由行動の日だった。 この日は朝6時前に目が覚めた。朝食前に、同室のWさんと急遽228公園 を訪ねることにした。 Wさんは尺八の名奏者で、いつもお琴の和服美人と合奏を楽しんでいる紳士 である。酒と女性に強いWさんは、歴史にも手を出しているようである。 228公園はホテルから徒歩15分と近かった。 台湾に到着したのは228、つまり(2006年)2月28日である。 228という日付けは、台湾の人、特に本省人(大陸からきた外省人でなく、 もともとの台湾人)にとって重要な意味がある。
←228事件の記念行事が228公園で (2月28日に)行われたことを報じる 3月1日朝のテレビ画面 ↓228公園の西入り口 (赤い横断幕は、鳥インフルエン ザに注意を呼びかけている)
終戦後、日本に代わって台湾を支配した国民党政府の抑圧的政策や腐敗に 対し、反発する人が多かった。228事件とは、抗議行動を起こした人々に 向け、1947年2月28日、当局が発砲して多くの死傷者を出した弾圧事 件である。 この事件を契機に発令された戒厳令は、1986年まで40年間続いた。
←228記念碑 ↓台北駅方面を望む
公園の記念碑には、陳水偏さんの名で「二二八和平公園」と記されている。
現総統の陳さんが、台北市長の時代 に整備したものである。 ←二二八和平公園記 ↓公園に近い総統府
7.陶芸博物館 自由行動のこの日は、故宮博物院をじっくり見て回る予定だった。 しかし、前日のツアーで2時間ほど故宮を見た結果、団長と副団長の決断で、 この日は別の施設を見ることになった。 行く先は、「台北県立鶯歌陶磁博物館」だった。 鶯歌[いんが](うぐいすの歌?)というロマンを感じさせる駅は、台北の 南西の方向にある。台北から鶯歌までは電車を利用することになった。 ホテルから台北駅までは地下鉄を利用した。
地下鉄の自動券売機と自動改札機は、日本のメ ーカー製(オムロン)だった。 鶯歌への途中、日本の技術を採用した新幹線と並 行して走る箇所があった。 ←日本製の自動券売機と改札機 ↓
台北駅の窓口で購入した指定席切符は31元(約110円)だった。 帰りに鶯歌駅の自動券売機で購入した指定なしの切符も31元だった。 (帰国後に調べたら、これは「復興」という列車の値段で、普通の列車は 23元のようである) 台北から鶯歌までは30分だった。
←台北駅で購入した指定席切符 ↓鶯歌駅
鶯歌駅の近くに陶器市場があったが、まずは博物館に向かった。 およそ20分位歩いた。鶯歌陶磁博物館は2000年に開館したそうで、4 階建ての立派な建物である。展示物も立派だった。 入館料は100元だったが、65歳以上は無料だった。
←鶯歌陶磁博物館 と掲示したいところであるが、面目な いことに、電池切れで撮影ができなか った。博物館を出てから、セブンイレ ブンに走った。 館内は無論撮影禁止である。 博物館の次は陶磁器店の並ぶ一角を訪ねた。 博物館から30分位歩いた所の陶磁老街という一角は、きれいに整備され、 沢山の陶滋器の店が並んでいた。
ここはのどかな町で、町おこしとして陶芸観 光に力を入れているようである。 商品は豊富で、値段も手頃な感じだった。 きっと休日にはお客さんで賑わっているのだろ う。 ←小さな店が入っている老街陶館 8.全般の感想 はじめての台湾の印象としては、何となく親しみがもてたことである。 例えば、日本のテレビ番組がいくつか放映されていた。どれだけの番組を観 ることができるのかは分からないが、私が観たのは夜10時からのNHKの ニュースで、これは日本と同時の放映だった。2年前に、上海の駐在員宅で 見たNHKの同番組は翌日の放映であり、検閲後の編集された録画だった。 駅や店などの漢字表記は、中国の簡体字表記と違って、日本人でもわかり 易かった。「関東煮」と書いた札を立てて「おでん」を売っている店もあっ た。下町の、地元の人たちが食べている食堂では、豪華レストランとは違っ た楽しみを味わえた。食べて呑んで、一人当たり700円前後だった。 下町の食堂では、片言の日本語を話す老婆が注文を受け、清算は若い奥さん がお皿毎の値段をメモ用紙に書き出して合計金額を計算した、というほほえ ましい場面もあった。 もうひとつの印象は、予想外に街がきれいなことだった。 景観についての私のこだわりは、どれだけ電線の地中化が進められているか、 にある。いずれ、新しいホームページを立ち上げ、最も見事に電線で被われ ている地域に、「日本蜘蛛の巣大賞」「世界蜘蛛の巣大賞」と銘うった賞を 授与してみたい、と考えているくらいである。
その意味では、(幸いにも)台北も鶯 歌も受賞資格を欠いている。 ←私が見た限りで、電線が目立った鶯歌 (蜘蛛の巣大国日本には到底及ばない!) 9.おわりに 団長以下、私以外は、陶芸に熱心である。 私は陶芸以外のことで覗き見をするため、一人で立ち止まることが多かった。 旅行の終わり頃、いつの間にか私はデパートに一人で置き去りにされていた ことがあった。しかし、陶芸仲間から冷たい仕打ちを受けた、などと思って はいけないだろう。総統府付近の散歩や女流陶芸家との出会いを楽しむこと ができたのは、私一人だけなのだから。 私が台湾に関心をもったのは、日本語の指導法を学んだときだった。 日本語の指導法の研究は、台湾の統治をきっかけとして始まった。 台湾総督府には、各界の一流の人材があてられた。教育を担当する初代学務 部長には、日本近代音楽の育て親と言われた伊沢修二が任命された。台湾総 督府が設けられた明治28年(1895年)のことである。 伊沢が開設した学校で、教師6人が殺害された事件があった。 台北北部の芝山巌(しざんがん)という地に、教育に献身した6人の先生を 讃える「六士先生殉職」の記念碑が建てられているそうである。 伊沢は遺言により、六士先生の墓に埋葬されているという。 今回は、残念ながら芝山巌を訪ねる余裕はなかった。 (散策:2006年 2月28日 〜 3月 4日) (脱稿:2006年 3月20日) ------------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ