1.はじめに
野菜は群馬県の特産品のひとつでしょうか。
私の住んでいる関西でも、下仁田のこんにゃく、高原キャベツ、ごぼうなど
の群馬県産野菜を見かけます。
もうひとつ特産品を挙げるとしたら、それは政治家でしょう!
福田赳夫、中曽根康弘、小渕恵三などの総理経験者をはじめとして、多数の
有名政治家を輩出しています。
ところが、群馬県の有名人として知られているトップは、政治家ではなく、
体制に逆らった
国定忠治 なのだそうです。
お尋ね者となった国定忠治は、赤城山に篭ったことで知られています。
その隠れ岩屋は、私の実家の近くにあります。
赤城山の南面にある忠治の隠れ岩屋を、久し振りに訪ねてみました。
2.赤城南面登山道
赤城山は裾野が長い山です。
裾野の広さでは富士山にひけをとらないでしょう。前橋あたりから見れば、
長く延びている裾野を実感していただけるでしょう。
す:
裾野は長し赤城山 (上毛かるた)
赤城山に登る自動車道のひとつに、南面登山道があります。
前橋市と桐生市を東西に結ぶ上毛鉄道がありますが、その中間にある大胡
(おおご)から北に延びる道です。

大胡から4キロほど北上すると、群馬
フラワーパークに着きます。
私が小学校へ歩いて通った通学路を潰
した公園です。
←実家付近から見た赤城山(南面)
↓群馬フラワーパーク

.jpg)
フラワーパークの近くから松並木が始
まります。春には、並木道の両側につつ
じが咲き誇ります。
私の実家はこの近くにあります。
昔、私が子供だったとき、ここで「名月
赤城山」という映画のロケがありました。
↑松並木の入り口
↓静かな散策路となっている並木道
.jpg) ↓自動車道は並木道の横に
↓自動車道は並木道の横に
.jpg)
この並木道を2キロほど上ると、赤城神社があります。
後述するように、赤城山の頂上付近にも赤城神社がありますが、並木道の終
着地点にあるのは「三夜沢(みよさわ)赤城神社」です。
.jpg)
大きな木の鳥居があります。
昔の記憶では、松並木の途中に石造りの
一の鳥居と二の鳥居がありました。
鳥居の上に小石を投げて載せようと夢中
になったことがあります。
←神社前の鳥居
↓鳥居の奥に拝殿が見えます
.jpg) ↓簡素な形状の拝殿
↓簡素な形状の拝殿
.jpg)
この神社は、延喜式内十二社ということで、社格の高いものです。
もっとも、インターネットで調べてみたところ、式社(最初から認知されて
いた本流)ではなく、論社(本流から派生した傍系)かも知れません。
境内には杉の大木が伸びています。そのうちの3本は「たわら杉」と呼ば
れています。弓の名手藤原秀郷が寄進したそうです。秀郷は、近江の三上山
でムカデを退治したという伝説がある俵藤太(たわらのとうた)です。
ムカデ伝説の三上山を毎日眺めている私が、故郷の赤城神社に俵藤太の名
前が刻まれていることを知って感動しました。
.jpg)
境内に神代文字(じんだいもじ)の碑
がありました。神代文字は漢字が伝わる
以前に使われていたとされる文字です。
明治3年3月に建てられたそうです。
なぜここなのかは分かりません。
←神代文字の碑
3.忠治温泉
赤城神社までは緩やかな傾斜を上ってきました。
赤城神社の少し手前の道を右に折れてしばらく進むと、谷間の急な山道にな
ります。赤城神社から2キロ近くで、赤城温泉郷に着きます。ここには3つ
の温泉があり、最初に目につくのが忠治温泉です。
.jpg)
宿の中を覗かせてもらいました。
江戸時代のさまざまな民具や三度笠、雨
合羽などが陳列され、江戸時代の雰囲気
が演出されていました。
←忠治温泉
忠治温泉の近くに滝沢温泉があります。
忠治温泉を右に折れて500メートル位の位置ですが、別の沢にあります。
忠治温泉も滝沢温泉も旅館は1軒だけです。
.jpg)
滝沢旅館には「日本秘湯を守る会」の
会員を示す提灯が吊られていました。
余談ながら、翌日、ここで兄弟会を楽
しみました。料理はすべて女将の手作り
だそうです。
←滝沢温泉
滝沢温泉の横に谷川があり、忠治の隠れ岩屋はその上流にあります。
昔、中学生か高校生のときに、この温泉付近から隠れ岩屋まで歩いた記憶が
あります。現在は少し上流に駐車場があるということなので、そこまで車を
進めました。
4.隠れ岩屋
駐車場から隠れ岩屋までは徒歩40分、という表示がありました。
熊の出没に注意、という表示もありましたが、観光客が何人かぱらぱら歩い
ていたので、熊の応対は先客にお任せすることにし、一人で歩き始めました。
.jpg)
道は遊歩道として整備されていました。
始めの内は、先日歩いた熊野古道みたいに杉山
の斜面でした。
しばらく歩くと、「見張り岩」がありました。
←遊歩道
↓忠治みはり岩
.jpg)
およそ20分歩くと、滝沢不動尊がありました。
ご本尊の不動尊は、600年前の応永13年(1406年)に奉祀されたも
のだそうです。
.jpg)
社殿は岩穴の中に建てられています。
社殿前で、経文を読み上げている数人の
グループに出会いました。
←不動尊の山門
↓読経する人たち
.jpg)
昔、沢伝いに歩いた時は、ここに不動尊が祭られているいることを知りま
せんでした。忠治が篭る場所としてこの先の岩穴を選んだのは、この不動尊
と、この先の不動大滝に通じる道が通じていたためだろう、と合点しました。
忠治がいつ岩穴に篭ったのか、本当に篭ったのかどうか、分かりませんが、
篭ったとすれば今から160年位昔のことと思われます。その当時、既にこ
こに通う山道は開けていたのでしょう。
国定忠治は文化7年(1810年)に生まれ、嘉永3年(1850年)に
刑死したそうです。
不動尊を過ぎると、沢沿いに歩かなければなりません。
大きな石がごろごろしています。やや急ぎ足で歩いたせいか、汗がしたたり
落ちました。
上州では11月から3月まで、毎日のように空っ風が吹いていたような気
がしますが、今年は、関西から帰省して5日経っても風が吹いていません。
上州では、空風も雷も、その頻度と激しさは関西の比ではありません。
ら:
雷と空風義理人情
.jpg)
川沿いに上ったり下りたりしながら進むと、
大きな岩がありました。
写真ではよく分かりませんが、高さ10メートル
位で垂直に切り立っています。
その岩の下の方に隠れ岩屋がありました。
←谷川沿いの道
↓切り立った岩
.jpg)
岩穴の入り口は川から4、5メートル上にありました。
30段近い階段を下りて岩穴に入るようになっています。
昔、50年近く前に来たときの記憶では、入口は川からあまり高くない所に
ありました。土砂が崩れ落ちてきたのかも知れません。
.jpg) ←岩穴の入口への階段
↓入り口から上を仰ぐ
←岩穴の入口への階段
↓入り口から上を仰ぐ
.jpg)
岩穴の中は真っ暗でした。
実は、階段の上に太陽電池が設置され、内部に照明用の配線がとりつけられ
ていました。しかし、スイッチを入れても反応しませんでした。
内部はかなり広そうです。縦横とも7、8メートル位はありそうです。
立っても頭がつかえることはありません。
たまたま後から入ってきた若いアベックの青年が内部の状況に詳しく、こち
らの方向には表示板、こちらには人形、と教えてくれました。
.jpg)
そこで、およその見当をつけてフラッ
シュを働かせて撮影しました。
←国定忠治乾分衆の表示板
(日光の円蔵などの子分13人)
↓子分と酒を酌み交わす忠治親分
.jpg)
国定忠治は賭博に明け暮れたやくざだったようです。
やくざの作法として、子分の仇を殺したこともあるようです。
しかし、やくざ同士の喧嘩には、役人はいちいち手を入れなかったでしょう。
忠治は役人に追われる身となりましたが、それは関所破りをしたためです。
関所破りは天下の法を犯す大罪です。
捕らえられた忠治は、破った関所に引き立てられ(上野国吾妻郡大戸村大戸
関所)、そこで磔(はりつけ)になったそうです。
嘉永3年(1850年)12月21日、享年41歳でした。
5.不動大滝
忠治の隠れ岩屋から200メートル位上流に、大きな滝があります。
.jpg)
不動大滝です。
高さは50メートルほどでしょうか。
滝の近くには縄が張られていました。
ここで行をする人がいるそうです。
←不動大滝
↓
.jpg)
かつて、赤城山は修験の場とされてきたようです。
先に述べた三夜沢赤城神社や、次に述べる赤城神社にも、修験僧が関わって
きたのだろうと思います。
駐車場に引き返す途中で、上品そうな年配の女性に出会いました。
小柄で知性が溢れている美人でした。そのご婦人は、引きこもりの子供を連
れて、しばしば滝で行をしている由。小柄で年配の、僧侶などでない普通の
おばさんが水行をする姿を見て、引きこもりの子供も一緒に水に打たれるよ
うになるそうです。
6.赤城山
忠治の岩屋を覗いたついでに、赤城山に登ってみましょう。
赤城山には、大沼・小沼と呼ばれている火口湖があります。
.jpg)
大沼の周囲には、観光用の建物が沢山
建っています。
大沼の湖畔にあった赤城神社は、現在は
大沼の中の小さな島に移っています。
←覚満淵(手前と中央)と大沼(奥)
↓大沼(右手奥に赤城神社)
.jpg)
小沼は、大沼よりも少し高い位置にあります。
冬の大沼はわかさぎ釣りで賑わい、小沼は氷の質がよいのでスケートで賑わ
います。(昔の記憶です。多分、現在もそうでしょう。)
大沼にも小沼にも、大蛇伝説があります。その伝説のため、16歳の娘は
赤城山に登るな、と言われてきたそうです。
.jpg)
小沼の周囲には建物が全くありません。
緑色の水を湛えた小沼は、静かに晩秋の
陽を受けていました。
小沼から流れ出た水は、不動大滝を落
ち、滝沢温泉の横を流れます。
←小沼
7.おわりに
上州で好んで歌われる八木節は、忠治の生涯を読み上げています。
忠治は義賊として讃えられた面もあるようですが、真偽のほどはどうだった
のでしょうか。天保の大飢饉(天保4−7年(1833−1836))で民
衆が苦しんでいたとき、関所破り(天保7年)をしたことに対して、民衆か
ら喝采が沸きあがったためかも知れません。
大前田栄五郎は、関東の大親分の一人と言われました。
国定忠治と同時代のやくざで、忠治に縄張りの一部を引き継いだそうです。
私が生まれ育った宮城村に、大字大前田(現・前橋市大前田町)という地区
があります。大前田栄五郎が生まれたのは、この大前田だろうと思います。
隠れ岩屋を見学して帰る途中、「国定村」の方向を示す道路標識がありま
した。国定忠治(長岡忠次郎)が生まれた国定村(現・伊勢崎市国定町)は、
隠れ岩屋の南の方角で、赤城山の裾野を下りきった平野にあります。
(散策:2006年11月 8日
(脱稿:2006年11月25日)
ご参考:群馬県に関する次の記事もご笑読ください。
・
俵萌子美術館
・
草津・嬬恋 上州の旅
------------------------------------------------------------------
この記事に
感想・質問などを書く・読む ⇒⇒
掲示板
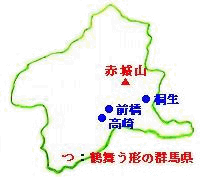
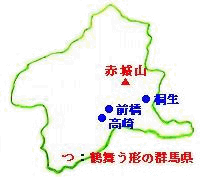
大胡から4キロほど北上すると、群馬 フラワーパークに着きます。 私が小学校へ歩いて通った通学路を潰 した公園です。 ←実家付近から見た赤城山(南面) ↓群馬フラワーパーク

フラワーパークの近くから松並木が始 まります。春には、並木道の両側につつ じが咲き誇ります。 私の実家はこの近くにあります。 昔、私が子供だったとき、ここで「名月 赤城山」という映画のロケがありました。 ↑松並木の入り口 ↓静かな散策路となっている並木道
↓自動車道は並木道の横に
この並木道を2キロほど上ると、赤城神社があります。 後述するように、赤城山の頂上付近にも赤城神社がありますが、並木道の終 着地点にあるのは「三夜沢(みよさわ)赤城神社」です。
大きな木の鳥居があります。 昔の記憶では、松並木の途中に石造りの 一の鳥居と二の鳥居がありました。 鳥居の上に小石を投げて載せようと夢中 になったことがあります。 ←神社前の鳥居 ↓鳥居の奥に拝殿が見えます
↓簡素な形状の拝殿
この神社は、延喜式内十二社ということで、社格の高いものです。 もっとも、インターネットで調べてみたところ、式社(最初から認知されて いた本流)ではなく、論社(本流から派生した傍系)かも知れません。 境内には杉の大木が伸びています。そのうちの3本は「たわら杉」と呼ば れています。弓の名手藤原秀郷が寄進したそうです。秀郷は、近江の三上山 でムカデを退治したという伝説がある俵藤太(たわらのとうた)です。 ムカデ伝説の三上山を毎日眺めている私が、故郷の赤城神社に俵藤太の名 前が刻まれていることを知って感動しました。
境内に神代文字(じんだいもじ)の碑 がありました。神代文字は漢字が伝わる 以前に使われていたとされる文字です。 明治3年3月に建てられたそうです。 なぜここなのかは分かりません。 ←神代文字の碑 3.忠治温泉 赤城神社までは緩やかな傾斜を上ってきました。 赤城神社の少し手前の道を右に折れてしばらく進むと、谷間の急な山道にな ります。赤城神社から2キロ近くで、赤城温泉郷に着きます。ここには3つ の温泉があり、最初に目につくのが忠治温泉です。
宿の中を覗かせてもらいました。 江戸時代のさまざまな民具や三度笠、雨 合羽などが陳列され、江戸時代の雰囲気 が演出されていました。 ←忠治温泉 忠治温泉の近くに滝沢温泉があります。 忠治温泉を右に折れて500メートル位の位置ですが、別の沢にあります。 忠治温泉も滝沢温泉も旅館は1軒だけです。
滝沢旅館には「日本秘湯を守る会」の 会員を示す提灯が吊られていました。 余談ながら、翌日、ここで兄弟会を楽 しみました。料理はすべて女将の手作り だそうです。 ←滝沢温泉 滝沢温泉の横に谷川があり、忠治の隠れ岩屋はその上流にあります。 昔、中学生か高校生のときに、この温泉付近から隠れ岩屋まで歩いた記憶が あります。現在は少し上流に駐車場があるということなので、そこまで車を 進めました。 4.隠れ岩屋 駐車場から隠れ岩屋までは徒歩40分、という表示がありました。 熊の出没に注意、という表示もありましたが、観光客が何人かぱらぱら歩い ていたので、熊の応対は先客にお任せすることにし、一人で歩き始めました。
道は遊歩道として整備されていました。 始めの内は、先日歩いた熊野古道みたいに杉山 の斜面でした。 しばらく歩くと、「見張り岩」がありました。 ←遊歩道 ↓忠治みはり岩
およそ20分歩くと、滝沢不動尊がありました。 ご本尊の不動尊は、600年前の応永13年(1406年)に奉祀されたも のだそうです。
社殿は岩穴の中に建てられています。 社殿前で、経文を読み上げている数人の グループに出会いました。 ←不動尊の山門 ↓読経する人たち
昔、沢伝いに歩いた時は、ここに不動尊が祭られているいることを知りま せんでした。忠治が篭る場所としてこの先の岩穴を選んだのは、この不動尊 と、この先の不動大滝に通じる道が通じていたためだろう、と合点しました。 忠治がいつ岩穴に篭ったのか、本当に篭ったのかどうか、分かりませんが、 篭ったとすれば今から160年位昔のことと思われます。その当時、既にこ こに通う山道は開けていたのでしょう。 国定忠治は文化7年(1810年)に生まれ、嘉永3年(1850年)に 刑死したそうです。 不動尊を過ぎると、沢沿いに歩かなければなりません。 大きな石がごろごろしています。やや急ぎ足で歩いたせいか、汗がしたたり 落ちました。 上州では11月から3月まで、毎日のように空っ風が吹いていたような気 がしますが、今年は、関西から帰省して5日経っても風が吹いていません。 上州では、空風も雷も、その頻度と激しさは関西の比ではありません。 ら:雷と空風義理人情
川沿いに上ったり下りたりしながら進むと、 大きな岩がありました。 写真ではよく分かりませんが、高さ10メートル 位で垂直に切り立っています。 その岩の下の方に隠れ岩屋がありました。 ←谷川沿いの道 ↓切り立った岩
岩穴の入り口は川から4、5メートル上にありました。 30段近い階段を下りて岩穴に入るようになっています。 昔、50年近く前に来たときの記憶では、入口は川からあまり高くない所に ありました。土砂が崩れ落ちてきたのかも知れません。
←岩穴の入口への階段 ↓入り口から上を仰ぐ
岩穴の中は真っ暗でした。 実は、階段の上に太陽電池が設置され、内部に照明用の配線がとりつけられ ていました。しかし、スイッチを入れても反応しませんでした。 内部はかなり広そうです。縦横とも7、8メートル位はありそうです。 立っても頭がつかえることはありません。 たまたま後から入ってきた若いアベックの青年が内部の状況に詳しく、こち らの方向には表示板、こちらには人形、と教えてくれました。
そこで、およその見当をつけてフラッ シュを働かせて撮影しました。 ←国定忠治乾分衆の表示板 (日光の円蔵などの子分13人) ↓子分と酒を酌み交わす忠治親分
国定忠治は賭博に明け暮れたやくざだったようです。 やくざの作法として、子分の仇を殺したこともあるようです。 しかし、やくざ同士の喧嘩には、役人はいちいち手を入れなかったでしょう。 忠治は役人に追われる身となりましたが、それは関所破りをしたためです。 関所破りは天下の法を犯す大罪です。 捕らえられた忠治は、破った関所に引き立てられ(上野国吾妻郡大戸村大戸 関所)、そこで磔(はりつけ)になったそうです。 嘉永3年(1850年)12月21日、享年41歳でした。 5.不動大滝 忠治の隠れ岩屋から200メートル位上流に、大きな滝があります。
不動大滝です。 高さは50メートルほどでしょうか。 滝の近くには縄が張られていました。 ここで行をする人がいるそうです。 ←不動大滝 ↓
かつて、赤城山は修験の場とされてきたようです。 先に述べた三夜沢赤城神社や、次に述べる赤城神社にも、修験僧が関わって きたのだろうと思います。 駐車場に引き返す途中で、上品そうな年配の女性に出会いました。 小柄で知性が溢れている美人でした。そのご婦人は、引きこもりの子供を連 れて、しばしば滝で行をしている由。小柄で年配の、僧侶などでない普通の おばさんが水行をする姿を見て、引きこもりの子供も一緒に水に打たれるよ うになるそうです。 6.赤城山 忠治の岩屋を覗いたついでに、赤城山に登ってみましょう。 赤城山には、大沼・小沼と呼ばれている火口湖があります。
大沼の周囲には、観光用の建物が沢山 建っています。 大沼の湖畔にあった赤城神社は、現在は 大沼の中の小さな島に移っています。 ←覚満淵(手前と中央)と大沼(奥) ↓大沼(右手奥に赤城神社)
小沼は、大沼よりも少し高い位置にあります。 冬の大沼はわかさぎ釣りで賑わい、小沼は氷の質がよいのでスケートで賑わ います。(昔の記憶です。多分、現在もそうでしょう。) 大沼にも小沼にも、大蛇伝説があります。その伝説のため、16歳の娘は 赤城山に登るな、と言われてきたそうです。
小沼の周囲には建物が全くありません。 緑色の水を湛えた小沼は、静かに晩秋の 陽を受けていました。 小沼から流れ出た水は、不動大滝を落 ち、滝沢温泉の横を流れます。 ←小沼 7.おわりに 上州で好んで歌われる八木節は、忠治の生涯を読み上げています。 忠治は義賊として讃えられた面もあるようですが、真偽のほどはどうだった のでしょうか。天保の大飢饉(天保4−7年(1833−1836))で民 衆が苦しんでいたとき、関所破り(天保7年)をしたことに対して、民衆か ら喝采が沸きあがったためかも知れません。 大前田栄五郎は、関東の大親分の一人と言われました。 国定忠治と同時代のやくざで、忠治に縄張りの一部を引き継いだそうです。 私が生まれ育った宮城村に、大字大前田(現・前橋市大前田町)という地区 があります。大前田栄五郎が生まれたのは、この大前田だろうと思います。 隠れ岩屋を見学して帰る途中、「国定村」の方向を示す道路標識がありま した。国定忠治(長岡忠次郎)が生まれた国定村(現・伊勢崎市国定町)は、 隠れ岩屋の南の方角で、赤城山の裾野を下りきった平野にあります。 (散策:2006年11月 8日 (脱稿:2006年11月25日) ご参考:群馬県に関する次の記事もご笑読ください。 ・俵萌子美術館 ・草津・嬬恋 上州の旅 ------------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ