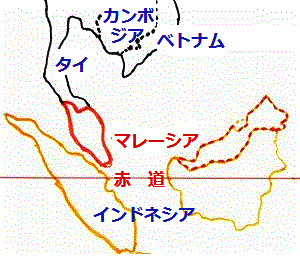
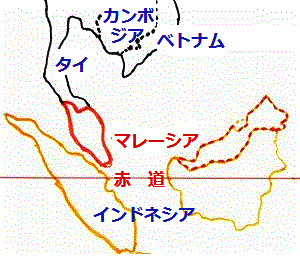
マラッカ クアラルンプール キャメロン・ハイランド
ペナン島 ツインタワー 蛍狩り など マ レ ー シ ア1.はじめに←マレーシア国旗 (星と月はイスラム、赤白14本のストライプは 13州と1特別区 を表す) アジアの、親日的な国でありながら、私はマレーシアについてほとんど知 りませんでした。昨年(2010年)夏、日本の大学院で学んでいるボルネ オ島出身の女性からマレーシアの概要を聞く機会がありました。 マハティールさん、という強いリーダーによって急成長してきた国、多民 族が共存しているという国、赤道直下に近い暑い国です。暑いけど一度は訪 ねてみたい国だと思いました。 暑い所は冬に限ると思い、2月末に行ってきました。 2.マラッカ 今回訪ねたのは西マレーシア(マレー半島)の一部(主としてマラッカ、 クアラルンプール、キャメロンハイランド、ペナン島)です。 (東マレーシアはボルネオ島の北部にあり、インドネシアと国境を分けてい ます)
マレーシアの歴史はマラッカが起点に なっている、と言えるでしょう。 マラッカは古くから海のシルクロード の中継地として栄えていたようです。 15世紀に成立したマラッカ王国は、大 航海時代の波にもまれ、16世紀初頭に ポルトガルに占領されました。 マラッカは、マレー半島とスマトラ島(インドネシア)で挟むマラッカ海 峡に面しており、晴れた日にはスマトラ島が見えるそうです。
←マラッカ(という名の木) ↓丘から見下ろしたマラッカ海峡
日本にキリスト教を布教したフランシスコ・ザビエルは、マラッカを振り 出しに活動したそうです。
←要塞址 ↓丘の上の教会址
ポルトガルの占領後、オランダ、イギリスと統治国が変わりました。 日本も短期間ながら、第二次世界大戦中に、占領しました。
←オランダ統治時代の教会 ↓飾り立てたトライショー
マレーシアには世界遺産が3点あります。 ひとつは「マラッカ海峡の歴史的都市群」という文化遺産(2008年)で す。これはマラッカとペナン島の古い町並みが対象になっています。
あとのふたつは自然遺産で、今回は行 かなかったボルネオ島です。 ←マラッカ ↓ペナン島(インド人街)
3.ルックイースト マレーシアは高い経済成長を続けています。 昨年(2010年)の経済成長率は10%弱だそうです。マレーシアの近代 化を推進した第一人者は、1981年から2003年まで22年余り首相を 歴任したマハティールさんでしょう。マハティールさんは大の親日家で、 「ルックイースト政策」(東=日本に学べ)を掲げました。
←国家記念碑 ↓林立する高層建築
1998年に完成したクアラルンプールのツインタワーは、マレーシアの 意気込みを象徴していると言えます。88階建て高さ452mで、アジア一 の高さを誇っています。
錫はマレーシアの特産品ですが、タ ワーのイメージは錫製品の工場で見か けたカップに似ている感じがしました。 ←ペトロナス・ツインタワー ↓錫細工の工場
もう一度、別の角度からツインタワーを眺めてみましょう。 撮影のために、思い切ってチャーター機を奮発しました。(もちろん、チャ ーター代は私が払った...わけではありません)
マレーシアの特別番組を 私の旅行一週間前に放映し てもらいました。 2011年2月19日放映 の「世界ふしぎ発見」より ←緑の多いクアラルンプール ↓宝石のようなツインタワー
タイやベトナムなどに比べ、バイクはあまり多く走っていませんでした。 自動車は多いのですが、いまにも潰れそうな汚い車は見かけませんでした。 クアラルンプールから北に向けてマレー鉄道に乗ったとき、自動改札機が設 置された駅を見かけました。
←クアラルンプール市内 ↓クアラルンプール郊外
4.多民族共存 マレーシアは多民族国家です。 人口比率は、マレー系65%、中国系25%、インド系7%だそうです。 それぞれの民族は異なる宗教を奉じており、イスラム教が国教とされていま すが、信仰の自由は保障されているようです。 いくつかの宗教寺院を訪ねました。
←国立モスク(クアラルンプール) ↓
マラッカには中国系の人が多く住んでいるようです。
←仏教寺院(マラッカ) ↓
マラッカもペナン島も海上交通が盛んなため、多くの宗教の寺院が多数あ ります。
←ビルマ寺院(ペナン島) ↓涅槃仏寺院(ペナン島)
大きなヒンズー教寺院がありました。 岩山の中腹にある巨大鍾乳洞(バツー洞窟)内に寺院が鎮座していました。 猛暑の中、洞窟まで272段の石段を上ると汗が滴りました。
←ヒンズー教寺院 ↓(クアラルンプール近郊)
残念ながら、マレー人の伝統的な祭祀施設を見ることはできませんでした。 スマトラ島などの田舎には残っているかも知れませんが、多分、先住民族が 祀るのは自然神に違いなく、一般観光客の見学には向いていないのかも知れ ません。 5.避暑地 マレーシアは私が訪ねた中でもっとも赤道に近い国です。 冬でも平地の午後は35度を超えていたのではないかと思います。しかし、 快適な避暑地があります。キャメロンハイランドという高原地帯で、各国の 資産家が別荘を構えています。日本人の長期滞在者も多いそうです。 私の泊まったホテルは標高1600mの位置にあり、朝は寒さで震え上が りました。
←高原に広がる茶畑 ↓高原のホテル
1967年3月26日、タイシルクの王と呼ばれていたアメリカ人のジム ・トンプソンがキャメロンハイランドで忽然と姿を消しました。姉は5か月 後にペンシルベニア州の自宅で何者かによって殺害されました。 二つの事件はいまだに謎のままです。
松本清張さんはこの事件を基 に、「熱い絹」という小説を書 いています。 現地を綿密に取材した長編で す。(文庫本で900頁超) ←「熱い絹」所収の地図 ↓先住民の住居(走るバスから)
キャメロンハイランドの周囲は深い密林で覆われています。 かつて、マレー半島に進駐した日本軍は密林で苦しみ、命を落とした人も多 かったようで、戦後に遺骨収集団が訪れています。 清張さんはそのような事情にも想いを馳せています。 私は清張さんの地図を見ながら現場を歩いてみたいと思っていました。 残念なことに、ホテルに到着したのは夜で、翌日は現地を散策する余裕もな いパック旅行の悲しさに泣きました。 キャメロンハイランドは昆虫の宝庫だそうです。 キャメロンハイランドだけに生息する「ネッタイミドリシジミ」という蝶が 「熱い絹」に登場しています。
←蝶の標本(土産店で) ↓ネッタイミドリシジミ
6.南国風景 風景の写真を順不同で少し抜き出しておきます。
マレーシアの国王は(9州の)スルタン (マレー人の首長)9人が5年毎に輪番制 で交代するのだそうです。 ←シンガポール郊外 ↓王宮
ヤシ油を採るための油椰子があちこちで栽培されています。 林の中に、新しい住居が並ぶ集落がいくつも目に入りました。行政による住 居の改善が進んでいるのではないか、と思いました。
←油椰子の植林 ↓新居の並ぶ村(マレー鉄道から)
マレーシアでは1年中蛍を鑑賞できるそうです。 沢山の蛍が川の両岸の木に止まって明滅していました。驚いたのは、点滅速 度が大変せわしないことでした。ガイドさんによれば、メスは毎秒1回、オ スは2回とのことでした。帰国後にインターネットを覗いてみたら、日本で は2秒から4秒に一回で、関東は4秒に1回、関西は2秒に1回とのことで した。 川の水は濁っていました。ちなみに、クアラルンプールとは「濁った」(= ルンプール)「川」(=クアラ)という意味だそうです。
←蛍の見える川 ↓蛍の群れ(パンフレットから)
マングローブの炭焼き場を見学しました。 炭は主に日本へ輸出されているそうです。
←炭焼き場 ↓
ペナン島には水上生活者の家があります。 水の上は税金がかからないということを、中国人が思いついたのだそうです。 ペナン島に高層マンションが並ぶ一角がありました。現地の人たちは日本人 村と呼んでいるそうです。
←水上生活者の家(ペナン島) ↓日本人村(ペナン島)
清張さんの「熱い絹」には吹き矢を操る先住民が登場します。 矢に塗る毒はイポーという木の樹液が使われるようです。イポーは30mも の樹高になるそうです。なお、キャメロンハイランドに近いマレー鉄道に、 この木の名に由来するという「イポー」駅があります。
←イポー(植物園で) ↓ドリアン
生のドリアンを賞味してみたいものだ、と思っていましたが、実現しませ んでした。マレーシアでは、熟して落ちたドリアンを食べるからおいしい、 のだそうです。 旅先ではいつも蜘蛛の巣(張り巡らされた電線)が気になります。 マレーシアでは日本のように空を覆い尽くしている蜘蛛の巣は見当たりませ んでした。(蜘蛛の巣については こちら をご覧ください)
←電柱のある風景 ↓(クアラルンプール郊外)
7.おわりに 今回はイスラム教、仏教、ヒンズー教、キリスト教の寺院を見学しました。 各宗教は他の宗教を互いに許容しているそうです。しかし、宗教と民族が結 びついているため、民族間の血の融合はあまり進まない、と聞いています。 マレー先住民独自の祭祀、伝統芸能も存在していると思うのですが、今回は まったく触れることができませんでした。 歴史的に見て、マレー人は他民族から格差をつけられてきました。 そこで、マレー人を優遇するため、ブミプトラ政策が採られてきました。例 えば、国立大学の入学定員、公務員の採用枠、企業の採用枠、などにマレー 系が多く割り当てられています。宗教の自由が保障され、民族が共存してい るとはいえ、根底において許容できない部分が残ることは否定できないのか も知れません。 今回は陶芸仲間との恒例の陶芸研修旅行でした。 これまでは私たちだけのグループで移動する旅行プログラムでしたが、今回 は完全なパック旅行でした。参加者は女性が多かっただけでなく、意外なこ とに24名の参加者全員が年配者でした。 (散策:2011年2月25日〜3月1日) (脱稿:2011年3月30日) ----------------------------------------------------------------- この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ