| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部●主要な決議等 |
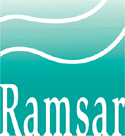
添付文書E:戦略的枠組み用語集
悪条件(基準4) 長期化した干ばつ、洪水、寒さ等の厳しい気象条件が続く期間中に起こるような、動植物種の生存にとってきわめて不利な生態学的条件をいう。
適当な(基準1) 基準1のように「生物地理区」 ☟ という用語に対して「適当な」という言葉が用いられる場合には、締約国が、その時点でとることのできる科学的に最も厳格な方法を実施するために決定した、地域区分をいう。
生物非単一性(基準7、8の適用に関するガイドライン) 群集内における形態または生殖形態の幅をいう。湿地群集の生物非単一性は、生息地の時間的、空間的多様性と予測可能性によって決定される。
生物地理区の個体群 「個体群」にはいくつかの種類がある。
ⅰ.単型種の個体群全体
ⅱ.認識されている亜種の個体群全体
ⅲ.一つの種または亜種の個体群であって、渡りを行う集団に分散したもの、つまり、同一の種または亜種の集団であって、他の集団とほとんど混じることのないもの
ⅳ.一方の半球から移動して、もう一方の半球や地域にある比較的独立した部分で非繁殖期を過ごす鳥の「個体群」。多くの場合、こうした「個体群」は、繁殖地で他の個体群と広範囲に混じりあったり、渡りの季節中や非繁殖地で、同一の種の定着個体群と混ざりあったりする。
ⅴ.定着性、遊走性、または分散性の鳥類の地域的な集団であって、明らかにかなり連続的に分布しており、通常の遊走的な渡り期間や繁殖後の分散期間に、他の個体と交流がないほどの大きな格差が、繁殖単位間にないように見えるもの。
生物地理区の水鳥の個体群に関する手引き(及び、データがある場合には、各個体群に対して提案される1%基準)は国際湿地保全連合が提供しており、最新の手引きは Delany & Scott (2002) が作成したものである 編注。アフリカと西ユーラシアにおけるカモ科(Anatidae)の個体群については、Scott & Rose (1996) による文献中に詳しく説明されている。
編注 最新の手引きは第4版:Wetlands International. 2006. Waterfowl Population Estimates — Fourth Edition. Wetlands International, Wageningen, The Netherlands, 239 pp. ISBN: 9058820319[そのうち日本で用いることができる水鳥個体群の1%基準値一覧をアジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略国内事務局(2007)が準備した ☞ 日本の水鳥の一覧].
生物地理区(基準1、3) 気候、土壌の種類、植生被覆等の生物学的なパラメーターや物理的なパラメーターを用いて確定した、科学的に厳密な地域区分をいう。島国でない締約国にとって、生物地理区は、事実上国境にまたがることが多く、代表的湿地、固有な湿地等の湿地タイプを確定するには、複数の国の間での協力が必要となる。「バイオリージョン」という用語が生物地理区と同じ意味で使われる場合もある。この区域分けの性質は、自然の変異を測定するパラメーターの性質に応じて、湿地タイプごとに異なる可能性がある。
生物多様性(基準3、7) すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息または生育の場のいかんを問わない)の間の変異性をいい、種内の多様性(遺伝的多様性)、種間の多様性(種の多様性)、生態系の多様性、生態学的過程の多様性を含む。(この定義の大部分は、生物多様性条約第2条に定める定義に基づいている。)
生態学的特徴の変化 条約第3条2項を履行する目的にとって、生態学的特徴の変化とは、あらゆる生態系の構成要素、プロセス、または生態系のもたらす恩恵/サービスの、人為による否定的な変化のことである(決議Ⅸ.1付属書A)。
近絶滅種(基準2) IUCN(国際自然保護連合)の種の保存委員会が用いている定義による。動植物ともに「IUCNレッドリストのカテゴリーと基準 IUCN Red List Categories and Criteria」に示される評価基準によって、ある分類群がごく近い将来高い確率で野生では絶滅に至る危機にある場合、その分類群を近絶滅種という。後述「地球規模で絶滅のおそれのある種」 ☟ も参照のこと。
重要な段階(基準4) 湿地に依存する種の生活環の重大な段階をいう。重要な段階とは、妨げられたり阻止された場合に、種の長期的な保全を脅かしかねない活動(繁殖、渡りの途中の中継地での休息等)をいう。種によっては(カモ科等)、換羽の場所もきわめて重要である。
生態学的特徴 ある時点において湿地を特徴付ける生態系の構成要素、プロセス、そして恩恵/サービスの複合体である[ここでは、ミレニアム生態系評価による生態系サービスに従って、生態系の恩恵は「人々が生態系から受け取る恩恵」として定義される](決議Ⅸ.1付属書A)。
生態学的群集(基準2) 共有する環境に生息し、食物の関係を中心として互いに交流しあい、他の集団から比較的独立している種の集団であって、自然に成り立っているものをいう。生態学的群集の大きさは様々であり、小さな生態学的群集が大きな生態学的群集に含まれていることもある。
移行帯,エコトーン(基準2) 二つ以上の異なる生物群集が接する部分で,狭い幅でその輪郭を明確に示して群集が移り変わる境界の帯.このような周縁部の群集は典型的に種数が多い。
絶滅危惧種(基準2) IUCNの種の保存委員会が用いている定義による。動植物ともに「IUCNレッドリストのカテゴリーと基準 IUCN Red List Categories and Criteria Version 3.1」(IUCN 2001)に示される評価基準によって、ある分類群が、近絶滅種には相当しないまでも、それに次いで近い将来高い確率で野生では絶滅に至る危機にある場合、その分類群を絶滅危惧種という。後述「地球規模で絶滅のおそれのある種」 ☟ も参照のこと。
固有種(基準7の適用に関するガイドライン) ある特定の生物地理区にのみ見られる種、つまり世界の他の場所には見られない種をいう。ある一群の魚類がある亜大陸の在来種である場合、そのうちの一部分の種は、当該亜大陸に含まれる一地域の固有種であることがありうる。
内湖 endorheic / endorrheic 水が蒸発によってのみ失われる水域、つまり流出河川のない水域。
科(基準7) 共通の系統学的起源をもつ属と種のまとまりをいう。例えば、ピルチャード類、イワシ類、ニシン類は、ニシン科という科に属する。
魚類(基準7)(fish) ひれのあるすべての魚をいい、これには無顎口魚類(メクラウナギ類とヤツメウナギ類)、軟骨魚類(サメ類、エイ類、ガンギエイ科の魚類、軟骨魚綱)、硬骨魚類(硬骨魚綱)、特定の甲殻類、その他の水生無脊椎動物が含まれる(下記参照)。
魚類(基準8)(fishes) 複数の魚種が関わっている場合には、「魚類」という用語を用いる 訳注。
訳注 日本語の場合には、魚種の数に関係なく、「魚類」という用語を用いている。
(ラムサール条約で定義された)湿地に一般的に生息する魚類の目であって、湿地の利益、価値、生産性または多様性を表すものには、以下が含まれる。
ⅰ)無顎口魚類---無顎綱
ⅱ)軟骨魚類---軟骨魚綱
ⅲ)硬骨魚類---硬骨魚綱
ⅳ)いくつかの甲殻類
ⅴ)その他特定の無脊椎動物
漁業資源(基準8) 魚類の個体群のうちで潜在的に利用可能な部分をいう。
代表種 flagship species 一般の人々に対して魅力があり,保全に関する対話に適する他の特徴も兼ね備える種.[編注:『代表種』という日本語は「第7回締約国会議の記録」において用いられたもの.他に『象徴種』という用語に訳される場合も見られる.]
渡りルート(基準2の適用に関するガイドライン) 渡りルートとは、渡り性水鳥が世界で利用する地域を表すために作られた概念であり、繁殖地と越冬地との間を移動する水鳥の個体群が利用する、渡り経路と場所をいう。個々の種及びそれぞれの個体群は異なる経路を通って移動し、繁殖地、中継地、越冬地として利用する場所の組み合わせも、それぞれ異なっている。したがって一本の渡りルートには、水鳥の個々の個体群や種の移動系統が多数交わっており、そのそれぞれに生息地の好みや渡りの戦略がある。こうした各種移動系統に関する知見をもとにすれば、水鳥が利用する渡り経路を大まかな渡りルートに大別できる。各渡りルートは、毎年の移動の間に多くの種によって利用され、同じ様な方法で利用されることも多い。多数のシギ・チドリ類の種の移動に関する最近の研究では、例えばシギ・チドリ種の移動が次の8つの渡りルートに大別できると指摘している。すなわち、東大西洋ルート、地中海・黒海ルート、西アジア・アフリカルート、中央アジア・インド亜大陸ルート、東アジア・オーストラレーシアルートのほか、アメリカ大陸と新熱帯区にある三つの渡りルートである。
渡りルートは明確に分かれているものではなく、生物学的に重要な意味を持たせるためにこうした分類を用いようとしているのではない。渡りルートという考え方は、種や個体群の移動を多少なりとも簡単にグループ分けできる大まかな地理的単位で、他の移動種と同じように水鳥の生態と保全について考察できるようにするための貴重な概念なのである。
地球規模で絶滅のおそれのある種(基準2、5、6) IUCNの種の保存委員会の専門家グループまたはレッドデータブックにより、近絶滅種、絶滅危惧種、危急種のいずれかに分類されている種もしくは亜種をいう。多くの分類群の場合、地球全体の現況に対する知見は乏しく、それを反映して特に無脊椎動物については、IUCNのレッドデータリストの内容は不完全なだけでなく激しく変動することに注意されたい。つまり、「危急」「絶滅危惧」「近絶滅」という用語については、対象となる分類群の現況に関してその時点で得られる最善の科学的知見に照らして、各国のレベルで解釈すべきである。
過湿生成土壌 hydromorphic soils 湿原、沼沢地、浸透域、または干潟のような排水の悪い条件下で発達する湛水土壌。
重要(基準2の長期目標) その湿地を保護すれば、種または生態学的群集の長期的な生存可能性を、その地方ひいては地球全体で高めることになる湿地のことをいう。
指標種 indicator species その種の状況が,生態系全体ならびにその生態系の他の種の状態に関する情報を提供する種.環境条件に敏感であり,ゆえに環境の質を評価するために用いることができる分類群.
固有な種(基準7) 特定の国を原産として、その国に自然に存在する種をいう。
移入種(外来種) その国を原産とせず、その国に自然には存在しない種をいう。
カルスト(第Ⅵ章A) 可溶性岩石上に作り出された景観であって、効果的な地下排水のあるものをいう。カルストは、洞窟、ドリーネ、地表排水の欠如を特徴とし、必ずとはいえないまでも主として石灰岩上に形成される。カルストという名称は、スロベニアの古典的カルストである「クラス」という地方名に由来する。この最初に研究された温帯地域のカルストではドリーネ地形が優勢だが、それとは対照的な地形として、熱帯地域の針峰カルスト、円錐カルスト、塔カルストのほか、フルビオカルスト、寒冷地域の氷河カルストがある。「クラス」という言葉は、もともと、むきだしで岩だらけの土地を表すスロベニア語である。
以下のサブセクションではカルストに関する用語を扱う。
外来性排水: 隣接する不透水岩地域からの流出に由来するカルスト排水をいう。異地性排水とも呼ばれる。
難透水層: 帯水層に対して境界の役目をする比較的不透水な地層をいう。
帯水層: 十分な透水性を備えて地下水を運び、井戸や泉に水を供給する含水層準をいう。
半透水層: 帯水層への水の出入りを全面的には遮断しないものの遅らせる岩石層をいう。
被圧地下水流: 被圧帯水層という帯水層全体が飽和状態にある帯水層を通り、静水圧下にある流れをいう。
自生排水: カルスト岩石表面に吸収された降水に全面的に由来するカルスト排水をいう。原地性排水ともよばれる。
逆流洪水: 主要な地下河道内の狭窄部の後ろ側に余剰水量が詰まったために起こる洪水をいう。
層理面: 堆積岩中の堆積面をいう。
層理面洞窟: 層理面に沿った洞窟通路をいう。
盲谷: 水流が地下へ消失する地点、またはかつて消失していた地点で終わる谷をいう。
崩落: 洞窟崩壊と同義。アメリカの用法では、崩壊によって発生した岩砕とも同義。
炭酸カルシウム: 天然に産する化学式CaCO3の化合物であり、石灰岩、大理石などの炭酸塩岩の主成分である。
炭酸岩塩: 単一または複数種の炭酸塩鉱物から構成される岩石をいう。
洞窟: 地中に自然にできた穴で、人間が十分に入れるほどの大きさをもつものをいう。これには水文学上きわめて重要な地下河道や裂罅を含まない。洞窟は中に入ることのできる単一の短い通路のこともあれば、フリント・マンモスケイブシステムのように、何百キロメートルにもわたって広範で複雑なトンネルが網の目状に連なっている場合もある。ほとんどの洞窟は石灰岩の溶解によって形成されるが、砂岩洞窟、溶岩洞窟、氷河洞窟、テクトニック洞窟もある。洞窟というものを、ポットホールやヤマのように縦の開口部、あるいは自然にできた縦のシャフトではなく、水平の開口部とみなしている国もある。
洞窟湖: 堆積物の堤防やグーアの壁の後ろに水がたまってできた湖であって、通気帯洞内にあるすべての地下の湖をいい、これが水没部の入り口になっていることもある。
チェンバー: 洞窟の通路や洞窟系の中にある広い空間をいう。現在知られている最大のチェンバーはサラワク州にあるサラワクチェンバーであり、長さ700メートル以上、最大幅400メートル、最大高さ70メートルである。
古典的カルスト: スロベニアあるクラスと呼ばれる地方をいい、これがカルスト景観の語源となった。
地下河道: 拡大した裂罅や管状の空間など、溶解による空隙をいう。水で満たされた空隙に限ってこの用語が使われることもある。
地下河道流: 地下河道内の地下水流をいう。
溶食: 岩石の侵食であって、溶解を引き起こす化学作用によるものをいう。
ドリーネ: 円形の閉じた凹地で、受け皿型、円錐型、場合によっては円柱型のこともある。ドリーネは、溶解、陥没、または両者の組み合わせによって形成される。ドリーネは石灰岩カルストに一般的に見られる特徴だが、可溶性岩石の中や上にも形成されるものである。また、沈降ドリーネは、不溶性堆積物が下位に分布する洞窟が、形成された石灰岩中へ流出したり陥没することによって形成される。例えば、スロベニア最大のドリーネであるスムレコバ・ドラガは、長さ1キロメートル以上、深さ100メートル以上もある最大のドリーネである。
乾谷: 恒常的には地表水が流れていない谷をいう。地下排水が形成されたり、再活動したときに水がなくなる。
掘削: 自由に流れる水の流れによって谷を形成する侵食をいう。
吸い込み吐出穴: 地下水位に応じて、シンクホールか湧水かのいずれかの役割を果たす開口部をいう。
地下水面帯: 地下水面の水位が変動するゾーンをいい、上部飽和帯ともいう。
淡水レンズ: 透水性石灰岩の島や半島状の土地の下にある淡水の地下水をいう。塩分躍層に沿った淡水と塩水の地下水に挟まれた混合域が、淡水レンズの上下の境界となっている。
グーア: 方解石の沈積によって形成されるプールをいう。グーアは、何メートルもの高さと幅をもつ大きなダムになることもある。トラバーチンは野外で形成されたグーアである。
地下水: 飽和帯中の地下水面より下にある地下の水をいう。
セッコウ: 硫酸カルシウム二水和物を成分とする鉱物または岩石をいい、化学式はCaSO4·2H20である。
セッコウ洞窟: セッコウは非常に溶解性が高く、通気帯洞や飽和帯洞がこの中にできることがある。最大の洞窟はウクライナのポドリー地方にあるオプティミスティチェスカヤ洞であり、ここの通路だけで約180キロメートルの長さがある。
塩分躍層: 淡水地下水と塩水地下水との境界面をいう。
動水勾配: 帯水層内における地下水面の傾斜をいう。
氷洞: 岩石中に形成された洞窟で、洞内に年間を通じて氷が存在するものをいう。
流入点: 地下排水流路または帯水層の開始点をいう。
石灰岩: 炭酸カルシウムが少なくとも重量で50%を占める堆積岩をいう。
降水: その形態を問わず、大気中から降下した水をいう。
ムーンミルク: 方解石やアラゴナイトの細粒鉱物が堆積したものであり、ほとんどがバクテリアの堆積作用によるものである。
流出点: 地下排水流路または帯水層から水が流れ出る点をいう。
通路: 洞窟系のうち、人間が通過でき、垂直やほぼ垂直な部分でない水平な部分をいう。洞窟の通路はサイズも形も様々であり、知られている最大のものはサラワク州ムル国立公園にあるディア・ケイブで、幅は最高170メートル、高さは最大で120メートルある。
浸透水: 石灰岩の網目状につながった裂罅を通ってゆっくりと移動する水をいう。浸透水は、表土から石灰岩に浸入するのがふつうである。石灰岩帯水層に貯えられている水のほとんどは、浸透水によるものである。浸透水は、吸い込みから流入する水と比べて、洪水に対する反応が遅い。
透水性: 水を通過させる岩石の能力をいう。透水性は、初生的には連結した岩石中の間隙や開口した構造的な割れ目の作用であり、また二次的には、裂罅が溶解により拡大して地下河道の透水性が高まることがある。
飽和帯: 地下水面より下にある地下水で飽和した岩石の部分をいい、この中ではすべての地下河道が水で満たされている。
飽和帯洞: 地下水面よりも下に形成された洞窟をいい、飽和帯内にあるすべての空隙は水で満たされている。飽和帯洞は地下水面下深くにある湾曲部を含むことがあり、カルストの十分な発達に伴って、地下水面のすぐ下に浅い飽和帯洞が形成されることもある。
静水面: 観測井戸(静水管)で水柱が上昇する水位をいう。
ピット(竪穴): 地表または洞窟内部から延びるシャフト(竪坑)またはポットホールをいい、ギャラリー(大きな通路)の垂直部分である。
袋小路谷: 水源が無く突然始まっている谷をいい、カルスト湧水のある場所から、またはその下に形成されるものをいう。
ポリエ: 大きな平坦地をもつ閉じたカルストの凹地をいい、一般的には沖積低地を伴う。地表流や湧水はポリエに流れ込み、ポノール(吸い込み穴)を通って地下に流入する。一般にポノールは、洪水のような大量の水を通すことはできないので、多くのポリエは雨期には湖になる。ポリエの形状は地質構造による場合もあるが、純粋に横方向の溶解と平坦化作用による場合もある。
ポノール: シンクホールまたは吸い込み穴ともいう。
ポットホール: 単一のシャフト(竪坑)、またはほぼ垂直な洞窟系全体をいう。
偽カルスト: カルストに似た特徴の景観を呈すが、基盤岩の溶解によって形成されたものではないものをいう。
残存洞窟: 水の流れが他へ逸れた後に残された、活動洞窟でない洞窟部分をいう。
岩塩カルスト: 岩塩または岩塩に富む岩石に発達したカルスト地形をいう。
シャフト(竪坑): 洞窟の通路のうちで、自然の垂直または急峻な傾斜を呈すものをいう。知られているシャフトで最も深いものは、スロベニアのカニン高原にある入口のシャフトである。これはまったく岩棚がなく、深さ643メートルに及ぶ。
吸い込み: 水の流れや河川が狭窄部を通って地下へと姿を消す地点、または水流や河川が開口した横穴洞窟や垂直のシャフトへと流れこむ地点をいう。吸い込みから流入する水の特徴は、開口した洞窟にすぐ直接に流れこむことであり、浸透水とは区別される。吸い込みから流入する水は、地中流出とも呼ばれる。
洞窟学: 洞窟に関する学術的研究をいい、これには、地形学、地質学、水文学、化学、生物学等の科学的な側面のほか、数々の洞窟探検技術が含まれる。
鍾乳石: すべての洞窟鉱物堆積物を表す一般的用語であり、すべてのつらら石、流れ石、石華等を含む。
湧水: 地下水が地表に湧出する地点をいう。石灰岩に限らないが、一般に洞窟が発達する岩石に大きな湧水ができる。世界最大の泉は、トルコにあるデュマンリの泉で、平均流量は毎秒50㎥以上である。
地表下風化帯: 土壌の下にある一般にきわめて風化の進んだ部分をいい、この下にはカルスト帯水層の比較的風化していない主岩盤がある。
サンプ(水没部): サイフォンともいい、水没した通路部分をいう。
トラバーチン: 流水によって堆積した石灰質鉱物であり、流水から植物や藻類が二酸化炭素を抽出することによって沈殿を引き起こし、トラバーチンの多孔質の構造ができあがる。毛管の力、水頭損失、空気混和もトラバーチンの堆積に影響する。
真洞窟性動物: 洞窟の外光が到達する部分より奥の地下に恒常的に生息する生物をいう。多くの真洞窟性の種は、何らかの形で暗黒の環境中で生息できるように順応している。
好洞窟性動物: 洞窟の外光が到達する部分より奥に意図的に侵入し、習慣的かつ一般的に一生の内の一部分を地下の環境で過ごす動物をいう。
外来性洞窟動物: ときどき洞窟に入るが、一時的にも恒常的にも洞窟を生息地として利用しない動物をいう。
通気帯洞: 大部分が地下水面より上の通気帯中に形成された洞窟をいい、水は重力によって自由に流れる。通気帯に存在する水が重力の作用を受けているということは、すべての通気帯洞窟通路は水を下方に排水するということであり、通気帯洞窟はカルスト帯水層の上部をなし、水は最終的に飽和帯または地表に排水される。
通気帯: 地下水面よりも上にある岩石帯であって、水が自由に下方に向かって流れ、部分的にしか水で満たされない層をいう。不飽和帯とも呼ばれ、土壌、地表下風化帯またはエピカルスト帯、それに自由排出浸透帯から成る。
ボークリューズ型湧出: 湧水または湧泉の一種であり、被圧された飽和帯からの直接排水が、水中洞窟内を流れて地表に流出するものをいう。このような湧出は、南フランスにあるボークリューズの泉にちなんで名付けられたものである。ボークリューズの泉の平均流量は毎秒26㎥であり、垂直で深さは243メートルである。水量は季節によって変動する。
地下水面: 岩盤内の間隙を満たしている地下水体の上表面をいう。地下水面の上には自由排水される通気帯があり、地下水面の下側には常に飽和状態にある飽和帯がある。個々の地下河道は、地下水面の上にあるか下にあるか、つまり通気帯にあるか飽和帯にあるかのいずれかであり、地下水面とは結びついていないのがふつうである。石灰岩中では、透水性が高いために地下水面の傾斜(動水勾配)は低く、水位は出口の湧水や地域的な地質によって制御される。流量が多いと動水勾配も急になり、湧水とは関係なく水位が上昇することになる。フランスのグロット・ドゥ・ラ・リュイール(リュイール洞窟)では、洞窟の水位、したがってその地域の地下水面が、450メートルも変動する。
地下水追跡: 入口側の水にラベリングし、それを下流側の地点で識別することにより、未探検の洞窟を通ってつながっている地下の流路を確認すること。一般的なラベリング技術では、蛍光色素(ウラニン、フルオレセイン、ローダミン、白色素胞、ピラニンなど)、ヒゲノカズラの胞子、またはふつうの塩のような化学薬品を使用する。これまでに成功した最長の地下水追跡例はトルコで行ったものであり、全長130キロメートルに及んだ。
中枢種 keystone species 生態系からその種を失なうと他の種の個体群や生態系プロセスに平均よりも大きな変化を招く種.この種が健全でありつづけることが群集全体の機能に必須である.例えば北大西洋のニシンや南極のオキアミなど.
生活史の段階(基準7) 魚または甲殻類の発育上の一段階をいう。例えば、卵、胚、幼生、レプトセファルス、ゾエア、動物プランクトン段階、幼若体、成体、後成体など。
回遊経路(基準8) サケやウナギなどの魚類が、産卵場や採食場、稚魚の成育場との間を移動する際に遊泳する経路をいう。回遊経路は、しばしば国境や、各国の国内にある管理区域の境界をまたぐ。
自然度が高い(基準1) 基準1で使われている「自然度が高い」とは、ほぼ自然とみなされる態様で機能しつづける湿地という意味である。基準にこの語を盛り込むことで、自然のままではない湿地であっても価値のあるものを、国際的に重要な湿地として登録できるように図るためである。
稚魚の成育場(基準8) 発育早期にある幼魚に対して隠れ家、酸素、食物を提供する目的で、魚類により利用される湿地の部分をいう。親が巣を守るティラピアのように、親が稚魚の成育場に残ってそれを守る魚類もあれば、親が巣を守らないナマズのように、稚魚が親によってではなく、卵を産みつけた生息地の提供する隠れ家によってのみ守られる魚類もある。稚魚の成育場の役割を果たす湿地の能力は、冠水、潮の交換、水温の変動、栄養分の変化など、湿地の自然の周期がどの程度保たれるかにかかっている。ウェルカム(1979)によれば、湿地で行われた漁業の場合、漁獲量の変動のうち92%は、その湿地の直近の洪水の履歴によって説明できることが示されている。
植物(基準3、4) 維管束植物、コケ植物、藻類、菌類(地衣類を含む)をいう。
個体群(基準6) この場合には、関係する生物地理区の個体群をいう。
個体群(基準7) この場合には同一の種で構成された魚類群をいう。
個体群(基準3) この場合には、特定の生物地理区内における一つの種の個体群をいう。
避難場所(基準4) 「重要な段階」 ☝ も関係しているので、その定義も参照のこと。重要な段階とは、妨げられたり阻止された場合に、種の長期的な保全を脅かしかねない活動(繁殖、渡りの途中の中継地での休息等)をいう。避難場所とは、干ばつ等の悪条件の期間中に、こうした重要な段階をある程度保護するような場所を表すものと解釈する。
定期的に(基準5、6)(「定期的に支える」) 以下の場合、湿地はある大きさの個体群を定期的に支えているという。
ⅰ)3分の2の季節において必要数の鳥類が存在していることがわかっており、それに関して適切なデータが入手でき、しかも季節の合計数が3以上の場合。
ⅱ)最低5年間かけて調査した結果、その湿地が国際的に重要である季節の最大平均値が、必要水準に達している場合(3−4年の調査の平均は、暫定的な評価にのみ使用できる)。
鳥類がある湿地を長期的に「利用」していることを確定するには、特に、存在する個体数の生態学的必要性と関連づけて、個体数水準の自然の変動を考察する。つまり、(半乾燥または乾燥地域において、干ばつ時もしくは寒冷時の避難場所もしくは一時的な湿地として重要な湿地であって、その程度が年毎に大きく変動する場合など)、状況によっては、湿地を利用している鳥類の数を年数で単純に算術平均しただけでは、その湿地の真の生態学的重要性が反映されないことがある。このような場合、湿地が特定の時期(生態学的ボトルネック)において決定的に重要であっても、他の時期にはそれより少ない数しか収容していないことがありうる。こうした状況においては、湿地の重要性を万全を期して正確に評価するために、適切な期間を対象としたデータについて解釈する必要性がある。
しかしながら、たいへんな奥地に生息する種や特に希少な種の場合、または国の調査実施能力が特に限られている場合など、状況によっては、少ない回数の計測をもとにしてその地域を適当とみなすことができる。情報がほとんどない国または湿地については、一回だけの計測でも、一つの種に対する当該湿地の相対的重要性を確定する一助となりうる。
国際湿地保全連合が編集している国際水鳥調査は、主要な参考情報源である。
代表的湿地(基準1) ある地域で見いだされる湿地タイプの典型例である湿地についていう。各湿地タイプについては添付文書B ⎗ で定める。
遷移過程の途中の段階 seral stage(基準2) 極相群集が連続的に発達しつつある植物の遷移段階.
相当な割合(基準7)(魚類の基準について) 極地の生物地理区において「相当な割合」とは、3−8の亜種、種、科、生活史の段階または種間相互作用をいい、温帯域においては15−20の亜種、種、科などをいい、熱帯域では40以上の亜種、種、科などをいう場合があるが、これらの数字は地域により異なる。種の「相当な割合」にはすべての種が含まれ、経済的に価値のある種に限らない。種の「相当な割合」を擁する湿地の中には、魚類にとって限界ぎりぎりの生息地であるものもあり、熱帯域であっても、わずか数種の魚類しか生息していないこともありうる。例えば、マングローブ湿地の淀み、洞窟湖、死海周辺のきわめて塩分濃度の高い水たまりなどである。たとえ劣化した湿地であっても、それを復元した場合に種の「相当な割合」を支える可能性については、同じく考慮する必要がある。高緯度地方、最近氷結した地域、魚類にとって限界ぎりぎりの生息地などのように、もともと魚類の多様性に乏しい地域では、遺伝的に分けることのできる種以下の魚類分類も数に含めることができる。
産卵場(基準8) 求愛、交配、配偶子(精子、卵など)の放出、配偶子の受精、受精卵の放出のために、ニシン、コハダ、ヒラメ、ザルガイなど、淡水湿地に生息する多くの魚類が利用する湿地の部分をいう。産卵場は、河川域、河床、湖沼の沿岸または深水域、氾濫原、マングローブ、塩生湿地、ヨシ原、河口、浅海域の一部分等の場合がありうる。河川から流入する淡水が、隣接する海岸に格好の産卵条件を作りだすこともある。
種(基準2、4) 野生状態で交配しまたは交配することのできる、自然に存在する個体群をいう。基準2、4及びその他の基準においては、亜種もこれに含まれる。
種間相互作用(基準7) 種間における、特定の利益や重要性をもつ情報やエネルギーの交換をいい、例えば、共生、片利共生、相互資源防衛、共同抱卵、托卵行動、親から子どもへの高度な保護、社会的狩猟、捕食者と被捕食者の例外的な関係、寄生、高次寄生などがある。種間相互作用はあらゆる生態系内で起こるが、サンゴ礁、古い湖沼など、種が豊富な極相群落であって、そうした作用が生物多様性の重要な構成要素となっている群落においては、特に発達している。
支える(基準4、5、6、7) 生息地を提供すること。ある期間にわたり、ある種または種の集合にとって重要であることを示すことのできる地域は、その種を支えているという。地域に対する占有は連続的である必要はなく、洪水や(地域的な)干ばつ条件といった自然現象に左右されうる。
生存(基準2の長期目標) 種または生態学的群集の地域的な生存及び全体的な生存に対して非常に寄与する湿地については、長期的にその地理的範囲を維持するようにできる。種が長期的に存続する可能性が最も高いのは以下の場合である。
ⅰ)対象となる種の個体数動態データにより、現在、その種が自然の生息地の生存可能な構成要素として、長期的に自己を維持していることが示されており、
ⅱ)予知できる未来において、当該種の自然の範囲が狭まらず、また狭まる可能性もなく
ⅲ)現在だけでなくおそらく将来においても、長期的にその個体群を維持するのに十分な大きさの生息地が持続的に存在する場合。
絶滅のおそれのある生態学的群集 生態学的群集の大きさ、生存または進化を脅かす状況と要因が作用し続けるならば、事実上絶滅する可能性のある生態学的群集をいう。
絶滅のおそれのある生態学的群集の目安となるのは、その群集が、以下の現象のうちの一以上によって実証されるような絶滅につながるおそれのある脅威に、現時点でも継続的にもさらされているということである。
ⅰ)地理的分布の著しい減少。分布の著しい減少は測定可能な変化とみなされており、これによって生態学的群集の分布が前回の幅の10%未満か、もしくは生態学的群集の全面積が前回の面積の10%未満になり、あるいはパッチ状になった生態学的群集のうちで、25年以上生存し続けられるのに十分な大きさの面積のあるものが10%未満しかない場合である。(10%という数字は参考値であり、もともとかなり広範な面積を占めていた群集などについては、違う数字をあてはめるほうが適切な場合もありうる。)
ⅱ)群集構造の著しい変化。群集構造には、構成要素となって生態学的群集を形成している種の名称、数、こうした種の相対的及び絶対的量、当該群集内で働いている生物作用及び非生物作用の数、種類及び強度などが含まれる。群集構造の著しい変化は測定可能な変化であり、この変化によって、25年以内には当該生物学的群集の機能回復が実現しそうにない程度まで、当該群集の構成要素である種の量、非生物的相互作用または生物的相互作用が変化する場合をいう。
ⅲ)生物学的群集において主要な役割を果たしていると考えられる在来種の消失または減少。このガイドラインは、群集の構造上重要な構成要素となっている種、例えば海草、シロアリの巣、藻類、優占木本種等、群集を存続させる過程または群集内で重要な役割を果たす過程で重要な種について言及するものである。
ⅳ)脅威的作用によって生態学的群集が急速に消失しうるような、地理的に限られた分布(国別に判定)。
ⅴ)群集構造が著しく変化するような程度まで、群集の過程が変化していること。群集の過程は、火災、洪水、水文学的変化、塩分や栄養分の変化等、非生物的なものの場合もあれば、受粉媒介者、種子散布者、植物の発芽に影響するような脊椎動物による攪乱等、生物的なものの場合もある。このガイドラインでは、生態学的な過程(火災の形態、洪水、サイクロンによる被害等)が、生態学的群集を維持する上で重要な力を持っていること、また、こうした過程が破壊されれば、生態学的群集が減少しうることを認識している。
入れ換わり数(基準5、6) 渡りの期間中に一つの湿地を利用する水鳥の累積合計数をいい、この入れ換わり数は、どの時点におけるピーク時水鳥数よりも多い数になる。
固有な(基準1) そのタイプのうちで、その生物地理区内にのみ見られるタイプをいう。湿地タイプの定義については添付文書B ⎗ に記載する。
絶滅危惧Ⅱ類(基準2) IUCNの種の保存委員会が用いている定義による。動植物ともに「IUCNレッドリストのカテゴリーと基準 IUCN Red List Categories and Criteria Version 3.1」(IUCN 2001)に示される評価基準によって、ある分類群が、絶滅危惧ⅠA類(Critically Endangered)や絶滅危惧ⅠB類(Endangered)には相当しないまでも、中期的な将来において高い確率で野生では絶滅に至る危機にある場合、その分類群を絶滅危惧Ⅱ類という。既述「地球規模で絶滅のおそれのある種」 ☝ も参照のこと 訳注 。
訳注 本訳は、環境庁による日本版レッドデータブックによる分類を根拠とした。
水鳥(基準5、6) ラムサール条約は、水鳥を「生態学的に湿地に依存している鳥類」(条約第1条2)と実施のために定義している(条約中で使われている "waterfowl" という用語は本基準及び本ガイドラインの適用上、"waterbird" と同義とみなされる)。したがってこの定義には、湿地に生息するあらゆる鳥類種が含まれる。また、目という広義のレベルの分類群では、特に以下がこれに含まれる。
湿地の利益(基準7) 湿地が人に提供する便益をいう。例えば、洪水調節、表流水の浄化、飲料水や魚類、植物、建築材料、家畜用水の提供、アウトドアレクリエーション、教育など。決議Ⅵ.1も参照のこと。
湿地タイプ(基準1) ラムサール条約湿地分類法の定義による。添付文書B ⎗ を参照のこと。
湿地の価値(基準7) 湿地が自然生態系の機能の中で果たす役割をいう。例えば、洪水の軽減と調節、地下水と表流水の維持、堆積物の捕捉、侵食の調節、汚染の軽減、生息地の提供など。
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.国際的に重要な湿地のリスト(ラムサール条約湿地リスト)に関する展望、目標、短期目標
Ⅲ.国際的に重要な湿地とラムサール条約における賢明な利用原則
Ⅳ.優先的に条約湿地に指定する湿地を特定するための体系的方法の採用に関するガイドライン
Ⅴ.国際的に重要な湿地を特定するための基準並びにその適用のためのガイドラインと長期目標
Ⅵ.個別湿地タイプを特定し指定するためのガイドライン(カルスト等の地下水文系,泥炭地、湿性草地、マングローブ、サンゴ礁,一時的な湿地,人工湿地)
[編注:以上の章Ⅰ−Ⅵをトップページに構成.]
添付文書A:ラムサール登録湿地情報票
添付文書B:ラムサール条約の湿地分類法
添付文書C:国際的に重要な湿地の選定基準 [編注:この添付文書Cは本指針本文第Ⅴ節のサマリーである.]
添付文書D:ラムサール条約湿地のための地図や他の空間データの規定のための追加ガイドライン
[編注:以上の添付文書A−Dは湿地情報票のページに構成.]
添付文書E:戦略的枠組み用語集 [このページ.]
| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部●主要な決議等 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop10/key_guide_list_apdxej.htm
Last update: 2012-03-27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).