
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
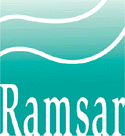
日本語訳:日本弁護士連合会,2002年[許可を得て再録].
英語 フランス語 スペイン語 (以上,条約事務局) PDF (300㎅)

(ラムサール条約決議Ⅶ.7にて採択)
Ⅰ.法制度再検討の目的
Ⅱ.法制度再検討の準備
2.1.再検討に関する政治的、制度的な責任を確立する
2.2.再検討チームを設置する
2.3.再検討の方法論を決定する
Ⅲ.法制度再検討の実施
3.1.法的・制度的措置の知識データベースを確立する
3.2.知識データベースを評価する
3.3.湿地の保全と賢明な利用を支援するために必要な法的・制度的な変更を勧告する
1.ラムサール条約締約国会議は賢明な利用に関する適切な法的、制度的枠組みに関する手引き[注1]を採択してきており、またラムサール戦略計画1997−2002[注2]にもこの問題が組み込まれた。これらの条約文書は各締約国会議に対して、賢明な利用を支援し、 各国の湿地に関連したすべての問題と活動に対処するために国家湿地政策を制定することを促す。この湿地政策は、独立したものであっても他の計画過程(たとえば国家環境行動計画や国家多様性戦略および行動計画)の中に明確に特定できる構成要素となったものであっても構わない[注3]。
2.この長期にわたる政策策定過程の一部として、締約国会議は特に各締約国に対して、その法的・制度的枠組みを再検討し、それらが賢明な利用という義務に全体として矛盾しないようにすることを求めている。再検討は、国家レベルのみならず、国家の下部機関や、超国家レベル(たとえば地域経済統合機構)[注4]の法律および制度に対しても行わなければならない。本付属書は、そのような再検討に際し実践的支援となるような技術的指針の提示を意図する。
3.この再検討過程は、各締約国の行う現行の法律および制度が湿地の保全と賢明な利用にいかに貢献し、またいかに阻害しているかについての検討に役立つであろう。これによって目的の達成に向けての取り組みがより合理的になるはずである。再検討の主な目的は、次の2つである。
4.再検討のために集めた情報は、締約国会議にむけた各締約国の国別報告書作成の有効なデータとなるはずである[注5]。再検討は可能な限り定期的に行って、法律および制度と条約第3.1条に基づく賢明な利用に関する義務との矛盾を確実に解消するようにしなければならない。
5.再検討は、2つの基本的な段階に分け、当該締約国の状況に合わせて実施するとよいだろう。すなわち、⑴準備段階(2.0節参照)と、⑵実施段階(3.0節参照)である。
6.締約国会議は、法的・制度的再検討が湿地の賢明な利用計画にとって重要な部分であることを正式に認めた。したがって締約国は再検討の準備、実施、ならびに再検討に基づく活動に対して高度の政治的支援を与えねばならない。
7.湿地関連事項を目的として設置された国内湿地委員会、省庁間委員会その他の調整機関[注6]が、再検討の責任主体となって監督するだけでなく、再検討チームによる勧告を考慮するその後の働きにとっても最適である(2.2節参照)。このような機関の存在しないところでは、省庁間の運営委員会を作り、関係の政府部署すべての意見が再検討の全期間を通して確実に代表されるようにするとよい。
8.連邦制または地方分権組織をもつ締約国においては、再検討の政治的責任は、湿地と(渡り鳥を含む)湿地資源の管轄が政府のどの層にあるかによる。いくつかの国においては、管轄権が中央政府と準中央政府の間に分割されている。また別の国では、それがほとんど全て準中央政府に委譲され、また他の国では、地方政府が広く湿地管理と決定過程に力を持つ。
9.湿地に対する管轄権が準中央政府に帰属する締約国の場合、このレベルの監督官庁が独自の再検討を行うことが適切であろう。しかしながら、国家の政策や法律の中で湿地に適用できるものとの整合性を確保するため、国家のレベルで再検討過程の調和をとることは有効であろう。
10.再検討チームには第2.1節で定められた機関に対して、再検討と報告をする任務上の責任がある。このチームは、意欲、客観性、広範な代表、そして専門性という特徴をすべて兼ね備えたとき効果をあげるようである。
11.再検討チームのメンバーは、各締約国の個別の状況や許容限度によって異なるであろう。国によっては、国家湿地政策を作成する目的ですでに再検討にふさわしいチームが作られていたり、すでにある横断的なラムサール委員会/湿地委員会からチームを作ることができたりするかもしれない。再検討チームは法律の専門知識を持った人を一人含む必要があるが、一方で、他の分野についても考慮しなければならない。すなわち:
再検討チームのメンバーは、慣習法などを含むその国の法と制度が理論と実践の両面でどのように機能しているのかについて詳細な知識をもっていなければならない。
12.再検討チームは再検討の方法論を決定する責任がある。すなわち、再検討の各段階をどのように、どれだけの時間をかけて行うか、また各メンバーの具体的な責任の分担、再検討の範囲の特定について決定しなければならない。
13.この準備段階の間に、その国の「湿地」の定義にあてはまるもの[注8]の再検討をする目的について再検討チームのメンバーの共通理解を得ておくことが重要である。
14.図1に、再検討を実行するにあたって考えられる方法論の一つの実例を示す。これは再検討を、「⑴関係の法律と制度についての知識データベースを確立する;⑵確立した知識データベースを評価する;⑶湿地の保全と賢明な利用を推進するために必要な法的、制度的な変更を勧告する」という基本的3段階の進行的 ongoing(循環的)過程とする。
15.締約国は、各国の事情に応じてこの循環的段階のどこから再検討を始めても良い。たとえば、ある国では、「国家湿地政策」を作成したり、生物多様性条約(1992)や、砂漠化防止条約(1994)に基づく横断的計画義務を実施したときに、既に科学的、法律的、制度的知識データベースが確立されている。他の国では、近代的な環境法規の案文作成や、法律の成文化のためにすでに再検討が行われたかもしれない。
16.一旦準備段階が完了すれば、再検討チームは、選択した方法論を使って法的、制度的な再検討の実行に入ることができる。以下、再検討の3つの段階についてより詳細に説明する。
17.再検討チームの主要責務は、湿地に適用される法律と制度についての総括的集積、すなわち知識データベースを作ることである。知識データベースの内容は各国の状況によって異なる。したがって、知識データベースはその国に固有のものである。
18.知識データベースは多くの多様な法律資料をもとにして構築される。一般的に言って、これらの資料源の法律が役所の手続き、決定や行動、また私企業部門や地域社会、個人の権利と義務を決定付ける(可能な資料源についての暫定的なリストについては図2を参照のこと)。形式的な面では、法令ならびに施行規則が、湿地に対してプラスまたはマイナスの影響を与える計画や活動に対する規制力、政策立案規則、公費支出、課税および経済的措置の法的根拠である。これと反対の面では、慣習法が湿地資源に関する先住民と地域共同体の権利と義務について定めた法の主要な資料源となるだろう。
19.知識データベースを確立するための情報は、再検討チームがそのまま利用できるものもあるだろうが、また新たな委託が必要なものもあるだろう。国内湿地や、より広範な環境政策立案過程の一部として作られた報告書、研究、政策文書や目録なども有益な資料源となるだろう。これとは別に地域レベルで湿地管理計画のために作られた情報も有益だろう。
20.知識データベースを確立するにあたって、関連の法律資料を概念上、⑴「湿地関連」の法的・制度的措置(3.1.1節参照)と、⑵湿地に直接、間接的に影響する部門に関する法的・制度的措置(3.1.2節参照)という2つのカテゴリに分類することは助けになるだろう。
21.湿地関連の法的・制度的措置とは、ラムサール条約の実施を直接に支援するなどして、湿地の保全と賢明な利用を直接に推進する措置である。すべての締約国は湿地の保全と賢明な利用を支援したり、そのために利用できる何らかの形の環境法と環境行政を持っている。もちろん特別な湿地法が制定されているのは比較的わずかであるが。国によって異なるが、保全と賢明な利用のための措置は環境保護あるいは自然の保全、保護区、環境影響評価ならびに監査、土地利用計画、沿岸管理、水資源管理、公害防止に関する国家または準国家レベルの法律および規則の中に含まれるだろう。地域レベルでは、慣習法や地域共同体をベースとした制度があてはまることもあるだろう。
22.これに続く分析にあたって、この知識データベースの要素を「賢明な利用のための追加手引き」に定められた4つのカテゴリに従って組み立てることは助けとなるであろう。すなわち、⑴個々の湿地によらない措置;⑵個々の湿地に関わる措置;⑶管轄権上ならびに制度上の調整;そして、⑷国境をまたぐ協力および国際的な協力のためのメカニズムである(図2を参照)。以下に法的・制度的措置に含まれる可能性のある事項を暫定的にリストにあげてみる。
23.再検討チームは、国境をまたぐ湿地関連の問題を含め、どの制度と機関が湿地保全と賢明な利用に機能上の責任を持つのかを確認しなければならない。連邦制または地方分権制を持つ締約国において、再検討チームは、湿地と湿地の産物に対する管轄権が国家および準国家政府の間でどのように分割され、またこの二つのレベルの間の調整を行う何らかの機構が存在するかどうかを明確にしなければならない。
24.湿地に直接、間接的に影響する部門に関する法的・制度的措置を確認するにあたって再検討チームが活動過程と活動分野[注9]のどれが国内の湿地の機能ならびに価値と利益の損失をもたらしているかを特定することが重要なステップである。このために、再検討チームは既存の科学的、政策上の報告書や研究、目録を利用してその国の湿地への主な脅威を割り出すことができる。これらが得られないところでは、情報について新たな委託が必要なこともあるだろう。
25.湿地の自然的特性を改変する過程は広く4つのカテゴリに分類されるだろう:
この種の過程は湿地の中と外における人間活動によって発生する。あるタイプの人間活動(例えば、下水、汚染や都市の拡大)は、個々の活動や、その累積的な働きを通して、ほとんど常に湿地を傷つける過程を生み出す。他のタイプの活動(例えば、釣りや、農業、エコツーリズムなど)はある限界の中では賢明な利用と矛盾しないが、活動の行われる水系、沿岸域または湿地の許容限度を超えるならば、損傷を与える過程が生じることもある。
26.知識データベースのこの要素をさらに分析するために、国の領土内または国境にある公有地もしくは私有地にある湿地の喪失と劣化につながる主な過程のリストを作るのもよいだろう。そして、各見出しの下に、活動そのものとともに個別の過程をもたらす活動に責任を持つ部門を記載するのもよいだろう。関連する部門には農業、林業、漁業、公共衛生、国土の開発、エネルギー、産業、投資、鉱業、通航、観光、貿易および輸送などがあるだろう(図2参照)。集められた情報は、引き続いて個別の活動の法的・制度的な基盤を確認し、関連づけ、それに基づいて評価するための技術的な基礎となる。
27.再検討チームは、知識データベースが確立されてしまえば(3.1節参照)、法的・制度的措置をその2つの要素に従って評価することができる。評価段階の主なステップは次のとおりである:
この評価は、国内における湿地の保全と賢明な利用についての法的・制度的な制約をチームが判断する助けとなるはずである。この判断はチームが法的・制度的な変更に必要な勧告を作成する際に必要である(下記3.3節参照)。
28.再検討分担チームにとって、特定された法的・制度的措置を客観的に分析するための枠組みを設計することは役に立つだろう。これは3.1.1節と3.1.2節に示された知識データベースの2つの要素の組織的な枠組みに対応し、その上に組み立てるとよい。
29.再検討チームの評価に際しては、伝統的に法と制度というものが、ほとんど部門を超えた調整なしに、湿地をあまり考慮することもなく、個別に発展してきたものであることを心に留めておく必要がある。したがって、湿地に関連した部門ごとの法的・制度的措置同士の競合に対する監視を怠ってはならない。これがあると、費用対効果に優れた湿地政策を実施したり、または国内全体で賢明な利用を達成したり、湿地を損なう可能性のある活動を規制または管理したり、湿地の所有者、利用者、地域共同体および私企業部門との長期的なパートナーシップを作る妨げとなるだろう。
30.また、この評価の一環として、再検討チームは湿地の保全と賢明な利用を達成する努力を妨げることになる別の法的・制度的措置を監視することを怠ってはならない。これには次のようなものがある:
ギャップや、重なり、矛盾はすべて評価に関連するので、再検討に記載しなければならない。
31.再検討チームは、湿地保全と賢明な利用を推進するために既存の湿地関連の法的・制度的措置の有効性を評価しなければならない。さまざまなやり方で保全と賢明な利用を推進することができるが、締約国会議は、この目的のために適切な法的、政策的、制度的、組織的措置が基本的に重要であることを強調した。再検討チームが国家の既存の法的・制度的措置を評価するにあたって、「賢明な利用についてのガイドライン」を出発点とするとよい。また、国の情況に合わせて有効性の指標を作ることもできるだろう。以下32−35項は考慮すべき問題点の暫定的なリストである。
32.個別湿地によらない措置について考慮する項目は次のようなものが考えられる。
33.個々の湿地については以下の項目を考慮するとよいだろう:
34.管轄権上ならびに制度上の調整に関しては以下の項目を考慮するとよいだろう:
35.国境をまたいだ、または国際的な協力に関しては項目には以下のものを考慮するとよい:
36.部門別法的・制度的措置の中で第3.1.2節に挙げた活動の過程や分野を支援するものはラムサール義務の効果的な実施を損なうことになるだろう。再検討チームは国内の湿地とそれらの法的・制度的基盤を脅かす活動の過程と分野を特定した後、これらが湿地の喪失をどのように後押ししているのかを特定しなければならない。
37.再検討チームは以下の質問に沿って再検討を行うとよいだろう:
38.再検討チームは国の法的・制度的枠組みの長所と短所を特定を終えた後、再検討過程の成果物として少なくとも3つのタイプの勧告について考えるとよい。
39.まず、そして優先して再検討チームがしなければならないのは、湿地の喪失をもたらしている法的・制度的措置を保全と賢明な利用という目的により良く調和させる手法について勧告することである。または、これができないときは、再検討チームはこれらの法的・制度的措置の破棄を勧告すべきである。これが短期的に実行できない場合は、そのような措置による影響を次第に減少させるため可能なあらゆるステップを採らなければならない。
40.2つ目として再検討チームがしなければならないのは、既存の法的・制度的措置が新しい法律や規制の必要なしにより効果的に実施することができるような手法を示し、勧告することである。
41.3つ目に再検討チームがしなければならないのは、法と制度を改訂・強化すべき分野や、新しく法的もしくは経済的な機関をつくるべき分野を示し、優先順位をつけることである。
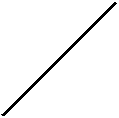 |
再検討を準備する
|
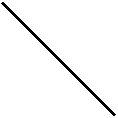 |
|||||||||
湿地に関連する法的・制度的措置の知識データベースを作る
|
|
湿地の保全と賢明な利用のために必要な変更を勧告する
|
|||||||||
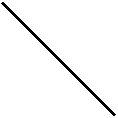 |
知識データベースを評価する
|
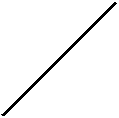 |
可能性のある法資料源(3.1節)
| ||||
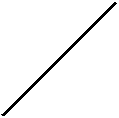 | 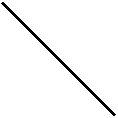 | |||
湿地に関連した法的・制度的措置を確認する(3.1.1節)
|
湿地に直接・間接に影響を及ぼす部門別法的・制度的措置を確認する(3.1.2節)
|
|||
原注
1.「湿地の賢明な利用についてのガイドライン」(勧告3.3);「賢明な利用の概念実施のためのガイドライン」(勧告4.10);「賢明な利用の概念実施のための追加手引き」(勧告5.6)。
2.1996年、於ブリスベン。第6回締約国会議で採択。
3.「国家湿地政策の作成と実施のためのガイドライン」(決議Ⅶ.6)を参照。
5.「ラムサール戦略計画」の行動2.1.1は、国別報告書で「賢明な利用についてのガイドライン」がどう適用されるのかを示すように締約国に求めている。
6.「賢明な利用についての追加手引き」第Ⅰ.1.2節でそのような機関の設立を勧告している。
7.湿地の管理への地域社会および先住民の参加を確立し強化するためのガイドライン(決議Ⅶ.8)第12項参照。
8.いくつかの国には、湿地法的な定義についての合意がない。条約は、「天然のものであるか、人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、さらには水が滞っているか、流れているか、淡水であるか、汽水であるか、塩水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地または水域」で、「低潮時での水深が6mを超えない海域」の内陸および沿岸湿地を含む広い定義(2.1条)を採用している。
9.生物多様性条約が、締約国に生物学的多様性に悪い影響を与える活動の過程とカテゴリを確認して、規制、または管理するよう要請していることに注目(第7条)[編注:生物多様性条約条文(環境省生物多様性センター所載)参照]。
[英語原文:ラムサール条約事務局,1999.Ramsar Resolution VII.7 Annex "Guidelines for reviewing laws and institutions to promote the conservation and wise use of wetlands", May 1999, Convention on Wetlands (Ramsar, 1971). http://ramsar.org/key_guide_laws_e.htm.]
[和訳:日本弁護士連合会.2002.第45回人権擁護大会 シンポジウム第3分科会基調報告書 資料編「うつくしまから考える豊かな水辺環境−湿地保全・再生法制定に向けて−」:138−148頁.
許可を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2006年9月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページにおおむね従う.]
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第7回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop7/key_guide_laws_j.htm
Last update: 2006/09/27, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).