
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部● |
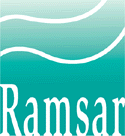
「国際的に重要な湿地のリスト拡充の戦略的枠組み,第3版(2006年版)」の添付文書A−D
英語 フランス語 スペイン語 (条約事務局) PDF (668㎅)
「ラムサール条約湿地情報票(Information Sheet for Ramsar Wetlands (RIS))」は,1990年にはじめて締約国に採択され,国際的に重要な湿地を条約湿地に指定する際にそれら湿地のすべてについて基礎情報を提供できるように設計された.それは,いつでも世界中の条約湿地の分析を可能にするためであった.RISはまた条約湿地の生態学的特徴の変化を測るための基準を提供するものでもある.加えて,条約湿地について広報する出版物の資料にもなる.記入済のRISは,各締約国が公式に任命した条約担当政府機関からのみ受け付けられる.RISならびにそのための指針は,条約湿地指定基準とともに条約事務局および専門家による条約の補助機関である科学技術検討委員会(STRP)が不断の検討を重ねている.
第8回締約国会議(バレンシア,2002年)で決議Ⅷ.13に採択され,つづく第9回締約国会議(カンパラ,2005年)で採択された決議Ⅸ.1付属書Bにより部分的な追加と改正をうけて,最新のRISならびにその記入のための注釈及び指針がある.このRISは「国際的に重要な湿地のリスト拡充の戦略的枠組み」のもとに位置づけられるものであり,同枠組み(2006年版)本文により詳しい説明がある.
[編注]以上2段落は条約事務局HPのRISトップページの記述を参考のために示す(「国際的に重要な湿地のリスト拡充の戦略的枠組み,2006年版」のページにも,RIS本体のページにもない).☞ 英語原文:http://ramsar.org/ris/key_ris_index.htm.
条約事務局原注:[RISを条約湿地について記入する用途には直接ワードファイルを用いられたい。] [編注]英文ワードファイル ☞ http://ramsar.org/ris/key_ris_e.doc (352㎅).
締約国会議の勧告4.7(1990年)によって承認され、決議Ⅷ.13(2002年)、ついで2005年の第9回締約国会議の決議Ⅸ.1付属書B、Ⅸ.6、Ⅸ.21、Ⅸ.22で修正された分類。
1.ラムサール条約湿地情報票(RIS)は、本書付随の「ラムサール条約湿地情報票記入のための注釈及びガイドライン」にしたがって作成されるべきこと。本票への記入の前に、必ず上記ガイドラインを読むよう強く促す。
2.条約湿地の指定を支援するさらなる情報ならびに手引きは「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」に提供される。ラムサール湿地賢明な利用ハンドブック第2版第7巻収録の2002年版に第9回締約国会議決議Ⅸ.1付属書Bによる改正を施した、同ハンドブック第3版が準備中であり、2006年中には利用できるようになる予定である。
3.完成した湿地情報票(及び付随する地図)をラムサール条約事務局まで提出すること。記入者は、本票の電子媒体(MS Word形式)及び可能ならば電子媒体地図のコピーを提供すること。
| DD MM YY | |||||||||
| 登録を受けた日 | 湿地参照番号 | ||||||||
1.本票記入者の氏名、住所:
(例:環境省担当者氏名)
環境省自然環境局野生生物課
東京都千代田区霞ヶ関1‐2‐2
tel 03-5521-8284 fax 03-3581-7090
xxx_xxxx@env.go.jp
2.本票記入日、更新日: 年 月 日
3.国名: (例:日本)
4.条約湿地名称:
指定地の正確な名称を条約の3つの公式言語(英語、フランス語、スペイン語)のどれかひとつで記載する。地元の言語による名称などの代替名称は正式名称のうしろに括弧に入れて示す。
5.新たな指定か、既存の条約湿地の情報更新か:
本情報票は新規か更新か(どちらかのボックスにチェック(✓)を記入する):
a)新たな条約湿地の指定 ❑
b)既存の条約湿地の情報更新 ❑
6.更新の場合のみ、登録時あるいは過去の更新時からの変更点:
a)湿地の区域と面積(該当する場合のボックスにチェック(✓)を記入する)
指定地の区域も面積も変更は無い: ❑
あるいは
次のように湿地の区域の変更がある:
ⅰ)区域をより精密に引きなおした ❑
ⅱ)区域を拡大した ❑
ⅲ)区域を限定した ** ❑
かつ/あるいは
次のような面積の変更がある:
ⅰ)面積をより精密に測定しなおした ❑
ⅱ)面積を拡大した ❑
ⅲ)面積を縮小した ** ❑
** 重要:指定地の区域や面積が限定または縮小される場合は、締約国は決議Ⅸ.6で確立された手順に従い、同決議の付属書段落28に指示される報告を、更新された本湿地情報票に先立って提出されていなければならない。
b)当該湿地の生態学的特徴の変化について、選定基準の適用も含み、前回の湿地情報票以降に主要な変化があれば簡潔に述べる:
7.湿地の地図の添付:
電子媒体地図を含む適切な地図の提出について細目の手引きは「注釈及びガイドライン」の添付文書Ⅲを参照のこと。
a)指定地の地図をその区域を明確に示して次のように添える:(該当する場合のボックスにチェック(✓)を記入する)
ⅰ)紙媒体(ラムサール条約湿地リストへの登録時、必須) ❑
ⅱ)電子媒体(例:JPEG 画像、 ArcView 画像) ❑
ⅲ)GISファイルによる区域のベクトルデータと属性表 ❑
b)区域の線引きに適用した様式を簡潔に述べる:
例えば、既存の保護区域(自然保護区や国立公園など)と同じ区域であるとか、集水域の範囲に従うとか、地方自治体の管轄範囲など地政学上の区域、道路などの物理的区域、水域の岸沿いに従うなど。
8.経度緯度: 東経 度 分、北緯 度 分
指定範囲のおよそ中心の緯度経度と、指定地の緯度経度の範囲のどちらかまたは両方を記す。指定地が二つ以上の区域に別れている場合は、区域ごとに緯度経度を記す。
9.一般的所在地:
所在地の地方名、地方行政区名、条約湿地に最も近い都市名を記述すること。
10.海抜: T.P.(東京湾中等潮位) m
11.面積: ㏊
12.概要:
湿地の主な生態学的特徴や重要性の概要を、短文にまとめること。
13.ラムサール条約湿地選定基準:
該当する基準の番号の下のボックスにチェック(✓)を記入すること。選定基準及びその適用についての手引きは「注釈及びガイドライン」の添付文書Ⅱ(決議Ⅶ.11で採択)を参照のこと。適用する全ての基準を記すこと。
| 1 ❑ | 2 ❑ | 3 ❑ | 4 ❑ | 5 ❑ | 6 ❑ | 7 ❑ | 8 ❑ | 9 ❑ |
14.記載項目13.で選定した基準の根拠:
選定した基準毎に、順次明確に記述すること。(根拠に合致した書式についての手引きは添付文書Ⅱ参照のこと)
15.生物地理学(指定にあたって、基準1や3、また確実に基準2が適用される場合必須):
ラムサール条約湿地を含む生物地理学的地域を記載し、採用した生物地理学的地域区分システムを明記する。
a)生物地理学的地域:
b)生物地理学的地域区分法(引用も記入;引用した文献の完全な記載は記載項目34に記述):
16.湿地の物理的特性:
地質、地形、天然または人工等の起源、水文学的特徴、土壌タイプ、水質、水深、水の永続性、水位の変動、潮汐の変化、流域面積、気候等を適宜記述。
17.集水域の物理的特性:
表面積、一般的な地質学及び地形学的特性、一般的な土壌タイプ、気候(気候タイプを含む)を記述。
18.水文学上の価値:
地下水涵養、洪水調節、堆積物捕捉、安定した海岸線の保持等の機能と価値を記述。
19.湿地タイプ
a)出現度:
ラムサール条約湿地の「湿地分類法」の湿地タイプに該当するコードに○か下線を記入する。各々の湿地タイプの記述は、「注釈及びガイドライン」の添付文書Ⅰに記載されている。
海洋沿岸域湿地:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Zk(a) |
内陸湿地:
| L | M | N | O | P | Q | R | Sp | Ss | Tp | Ts | U | Va | Vt | W | Xf | Xp | Y | Zg | Zk(b) |
人工湿地:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Zk(c) |
b)優占度:
a)で明記した湿地タイプを、第一にその湿地内で最も広い面積を有する湿地タイプから始めて(面積による)優占度に従って順に列記する。
20.一般的な生態学的特性:
主な生息地と植生の種類、動物群集・植物群落など、また生態系サービスやそれに由来する恩恵を適宜記述する。
21.特記すべき植物:
特筆すべき種についての追加情報、またなぜそれらが特記すべきなのか、(「14.基準の適用の根拠」で述べている記述を必要に応じて発展させる)例えば、固有種、稀少種、絶滅危惧種、生物地理学的に重要であるのはどの種・群集であるか、などを記入する。但し本項に湿地に現存する種の分類学的リストを記入しないこと−それらは本情報票の追加情報として提供すればよい。
22.特記すべき動物:
特筆すべき種についての追加情報、またなぜそれらが特記すべきなのか、(「14.基準の適用の根拠」で述べている記述を必要に応じて発展させる)例えば、固有種、稀少種、絶滅危惧種、生物地理学的に重要であるのはどの種・群集であるか、などを個体数データも含んで記入する。但し本項に湿地に現存する種の分類学的リストを記入しないこと−それらは本情報票の追加情報として提供すること。
23.社会的、文化的価値:
a)湿地の持つ社会的、文化的価値の一般を述べる。例えば、漁業生産、林業、信仰上の重要性、考古学的重要地、湿地との社会的関係など。例えば湿地の、漁業生産、林業、宗教上の重要性、考古学的遺跡、社会的な関係等。歴史的、考古学的、宗教上の意味と現行の社会的経済価値とは区別すること。
b)有形無形を問わず湿地の起源や保全あるいは生態学的機能に結合する文化的価値の重要な例を保有することによって、その生態学的価値に加えて、国際的に重要であると考えられるか?
考えられる場合はこのボックス ❑ にチェック(✓)を記入し、以下の範疇で該当する一以上のものについて当該湿地の重要性を記述する:
ⅰ)伝統的な知識や管理利用方法の適用が湿地の生態学的特徴を維持していることを実証する、湿地の賢明な利用のモデルを提供している:
ⅱ)湿地の生態学的特徴に影響を及ぼしてきた非凡な文化的伝統やかつての文明の記録がある:
ⅲ)湿地の生態学的特徴が地元社会や先住民との相互作用に依存する:
ⅳ)聖地のような無形の価値があり、その存在が湿地の生態学的特徴の維持に強く結びついている:
24.土地保有権、所有権:
⒜湿地:
⒝周辺地域:
25.現在の土地(及び水)利用:
⒜湿地:
⒝周辺地域、集水域:
26.土地利用(水利用も含む)の変更、開発計画等、湿地の生態学的特徴に悪影響を及ぼす要因(過去、現在、将来):
⒜湿地:
⒝湿地周辺地域:
27.実施されている保全策:
a)条約湿地との区域の関係を含めて、国レベルならびに国際レベルでの保護区の種類と法律的地位を記す:
特に世界遺産やユネスコの生物圏保存地域に部分的にあるいは全域となっている場合は、それらの指定地名称を記す。
b)適宜、該当するIUCN保護地域カテゴリー(IUCN 1994)を記す(以下で該当するもののボックスにチェック(✓)を記入する):
| Ⅰa ❑ | Ⅰb ❑ | Ⅱ ❑ | Ⅲ ❑ | Ⅳ ❑ | Ⅴ ❑ | Ⅵ ❑ |
c)公的に承認された管理計画の有無とその実施の有無:
d)その他の現在の管理手法を記述する:
28.実施に移されていない保全策案:
例えば、策定中の管理計画、法的保護区とする正式提案の提示等。
29.科学的研究及び施設の現状:
生物多様性モニタリング等を包む、現行の調査プロジェクトの詳細、現地調査事務所の有無等。
30.現在の広報・教育・普及啓発(CEPA)活動:
ビジターセンター、観察用小屋及び自然遊歩道、情報冊子、学校見学用施設等。
31.レクリエーション、観光の現状:
湿地がレクリエーションや観光用に使われているかどうか、使われている場合にはその種類、頻度や利用度等。
32.管轄:
国、地方自治体等の領土上の管轄及び農水省、環境省等の機能上の管轄等。
33.管理当局:
湿地の管理を現地で直接に所管する機関または組織の現地事務所の名称、住所を記入する。また、可能であれば必ず、上記事務所で湿地管理に携わる人物の所属・氏名を記入すること。
(例:環境省 自然環境局 xx地区自然保護事務所 xxx支所)
34.参考文献:
科学、技術分野のみ。もし、記載項目15で生物地理学的地域区分法の適用がある場合はその引用文献の完全な記載を掲げる。
記入済みの情報票は、次の住所宛にご送付ください:
Ramsar Convention Secretariat, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Switzerland
電話番号: +41 22 999 0170、ファクス番号: +41 22 999 0169、電子メール: ramsarⓐramsar.org
締約国会議勧告4.7は、「ラムサール・データベース、及びその他の適切な場合に情報を提供するときには、締約国及びラムサール条約事務局は、ラムサール条約湿地の記載のために作成された『データシート』を使うよう」定めた。同勧告は、「選定の理由(ラムサール条約湿地選定基準)」及びラムサールの「湿地分類法」と合わせて、「データシート」に記載する情報の種類を掲げた。
決議5.3では、国際的に重要な湿地(ラムサール条約湿地)への指定に際して、「ラムサール・データシート」を完成させて湿地の地図とともに提出することを再確認した。このことは、続けて決議Ⅵ.13とⅥ.16でも繰り返し述べられた。正式には「ラムサール条約湿地情報票」(RISと略す)と題するこのデータシートが、ラムサール条約湿地に関する情報とデータを記録するための標準様式を提供する。
決議5.3はまた、ラムサール条約湿地リストへ登録するための選定基準、湿地の機能・価値(水文学、生物物理学、植物、動物、社会、文化の各面での価値)、そして実施方法や計画などの保全策が、特に重要な情報の種類であることを強調し、RISに湿地について記載する際に、ラムサール条約の「湿地分類法」を適用する事の重要性を強調した。
「国際的に重要な湿地の選定基準」は、1974年に最初の基準が採択され、その後の締約国会議によって洗練されてきた。基準の現在の様式は勧告4.2(1990年)において設定され、決議Ⅵ.2が採択した魚類に基づく追加基準が加わった。「基準」は再び根本的に見直しが行われ、適用のための詳細手引きをつけて、「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」の一部として決議Ⅶ.11によって採択された。2005年の第9回締約国会議において基準9を追加して適用の手引きの改正とともに決議Ⅸ.1付属書Bに採択された。されこれらの基準とガイドラインは、本「注釈」の添付文書Ⅱに含まれる。
「ラムサール条約湿地情報票(RIS)」は、締約国が湿地をラムサール条約湿地として指定する際に完成し、ラムサール条約事務局に提出する。ラムサール条約湿地として登録された湿地の状態は、その生態学的特徴、その特徴に対する脅威と、また進行中のその保全管理の過程と行動との両面において変化する可能性があり、また変化するという認識から、決議Ⅵ.13は、締約国に対して、少なくとも6年おきにRISの内容を更新することを強く要求した。
RISとその付随する地図は、ラムサール条約事務局が保管する。締約国が提供したRISの情報はラムサール・データベースへ入力する基礎データや情報として利用され、ラムサール条約事務局との契約の下に、条約の代りに国際湿地保全連合が管理する。データベースと条約湿地の関連情報は、、国際的に重要な湿地のリストのための戦略的枠組みとガイドライン(決議Ⅶ.11)や、締約国会議のその他の決議の実施に向けた進行状況の分析や締約国会議への報告など、ラムサール条約湿地に関する情報サービスを提供するために運用される。
締約国がRISならびに追加情報に提供し、条約湿地データベースに入力された情報はまた、「条約湿地情報サービス」のウェブサイトを通じて一般に公開されている(http://www.wetlands.org)。
RISは、条約の3つの使用言語である英語・フランス語・スペイン語のいずれかを使って完成されなければならない。RISと、付随するこの「注釈及びガイドライン」は、3つの使用言語のいずれでも入手可能である。
RISに提供される情報は、明瞭、簡潔に記載し、通常12ページを越えてはならない。
良く研究され、また文献が豊富な湿地、つまり特別な現地調査の対象となった湿地の場合、情報がRISに組み込むことのできるよりもずっと多いこともある。条約湿地に生息する種の状況についての分類リスト、管理計画、公表された内容の写しや報告書のコピーなどの追加情報はRISに添付されるべきもので、条約湿地の公式記録の一部とみなされる。また(プリント、ポジ(スライド)や電子写真などの)湿地の写真は、特に歓迎する。あらゆる追加情報の出典を記載すべきである。
ラムサール条約湿地として指定される場所が、非常に広く、複雑な湿地システム、またはいくつかにわかれた湿地からなる条約湿地の場合には、二つのレベルで対応することが望ましい。つまり湿地系全体に対する大まかな報告と、その湿地系の中にある主要な部分や小湿地に対する詳細な報告である。したがって特に大きな湿地複合については、湿地全体に対する情報票に加えて、そこに含まれる主要地域に対する一連の情報票を作成することが適切と考えられる。
決議Ⅵ.1では、湿地の生態学的特徴を維持するためのラムサール条約湿地のモニタリングの根拠として、その生態学的特性を明瞭に確定することが重要であると強調している。維持されねばならない湿地の生態学的特徴の鍵となる特性には、登録にあたってその根拠とした各々のラムサール基準の下の特性を含めなければならない。さらに、「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」(決議Ⅷ.14)に、生態学的特徴である特性を明確化し記述するための手引きが提供されている。
登録された湿地について管理計画が準備されているところでは、RISに提供された情報は、管理計画に記載された生態学的特徴の特性、湿地の価値や機能、その特徴に影響を与え、または与えうる要素、価値や機能、そしてモニタリングを包む管理計画策定プロセスと合致していなければならない。
湿地がラムサール条約湿地に指定された後に、管理計画が管理計画策定プロセスの一部として準備されたとき、RISに提供された情報をチェックしなければならず、また必要であれば、RISを改訂して完成させ、ラムサール条約事務局に提出しなければならない。
決議Ⅵ.1の付属書では、条約湿地の生態学的特徴の説明・評価のために集められた情報の価値を高める必要があること、及び以下に重点を置く必要があることを記している。
国際的に重要な湿地に利益や価値を与える湿地の機能・生産物・属性を記載し、ベースラインを確定すること。(現在のラムサール条約湿地選定基準では、湿地での変化に伴って起こりうる影響を評価する際に、考慮すべきすべての湿地の利益や価値を網羅しているわけではないので、これが必要となる)。RISの14、16、18、19、20、21、22、23の各記載項目がこれに該当。
国際的に重要な利益や価値にすでに影響を及ぼした、あるいは重大な影響を及ぼしうる人為的要因に関する情報を提供すること。RISの記載項目26がこれに該当する。
条約湿地ですでに行われている(あるいは計画中の)モニタリングや調査の方法に関する情報を提供すること。RISの記載項目27、28がこれに該当する。
湿地の生態学的特徴にすでに影響を及ぼした、あるいは及ぼしうる、季節的もしくは長期的な「自然の」変化(例えば、植生遷移、ハリケーンのような偶発的・破壊的な生態学上の出来事など)、またはその両方について、自然の変異やその大きさに関する情報を提供する。RISの記載項目18、26がこれに該当する。
1.情報票記入者の氏名、住所:情報票の記入を行った人の氏名、組織名(機関名)、住所、電話番号、ファクス番号、電子メールアドレスを記載。
2.日付:情報票の記入日(または情報票を更新した日)を記入。記入に際し、月は数字ではなく月の英語名で記入すること。
3.国名:締約国の正式名称(短縮形)を記入。
4.条約湿地名称:条約の使用言語である英語、フランス語、スペイン語のいずれかにより、条約湿地に指定された湿地の正式名称を記入。日本語の名称など、別の名称は正式名称の後に括弧をつけて記入すること。使用される湿地名称は、本項と地図で使用される湿地名称を確実に同一とすること。本項で記入した名称がそのままラムサール条約湿地リストに登録されるときにも使用される。
5.新たな指定か、既存の条約湿地の情報更新か:このRISが新たな条約湿地の指定のために提供されるのか、あるいは既存の条約湿地の情報更新のために提供されるのかを示す。情報更新の場合は次の記載項目6も記入する(次項参照)。
6.更新の場合のみ、登録時あるいは過去の更新時からの変更点:小項目a)には、RISの以前の版を提出した以降に区域の表示ならびに指定面積に変更があるかないかを示す。変更がある場合は指定区域と面積のどちらについても該当する内容のボックスにチェックを記入する。条約条文には新たな湿地の指定や既存の湿地の拡張についての規定はあるが、すでに登録簿に掲げられた湿地の面積の縮小やその廃止についての規定が無く、このために第9回締約国会議の決議Ⅸ.6「登録基準をもはや満たさない条約湿地またはその一部についての取扱い手引き」において廃止や縮小を熟慮するにあたってとるべき手順が確立された。すでに指定された湿地の区域や面積を限定したり縮小する場合に締約国は、この決議Ⅸ.6で確立された手順に従い、同決議付属書の段落28に従った報告を、更新されたRISに加えて、提出しなければならない。
小項目b)には、当該湿地の生態学的特徴の変化について、指定基準の適用も含み、前回のRIS以降に主要な変化があれば簡潔に述べる。
7.条約湿地の地図:湿地の公認された最新で適切な地図を、紙媒体でRISに添付。(可能であれば電子情報も提出すること)いずれにせよ、紙媒体の地図は、国際的に重要な湿地のリストへの登録のための必須事項である。RISに地図を添付したかどうかに関して、該当するボックスにチェックを入れる。地図には、ラムサール条約湿地の境界を明確に示すこと。添付文書Ⅲで、ラムサール条約湿地の適切な地図及びその他の地理情報に関する規定の詳細な手引きを示す。注として、供給された地図及びラムサール条約湿地に関連する他の地図のリストをRISに添付しなければならない。地図がGIS形式で得られる場合は、GISファイルによる区域のベクトルデータと属性表、ならびに指定地区域を明確に示した画像ファイル(TIFF、BMP、JPEG、GIF等一般的形式)もあわせて提出する。
8.経度緯度:湿地のほぼ中心の地理的座標を、緯度、経度の度、分で表す(南緯 01°24′ 東経 104°16′ または北緯 010°30′ 西経 084°51′ など)。対象湿地が互いに離れた構成単位から成る場合には、その個数を明記する。複数の構成単位が最低 1.6 km四方(*)以上離れて位置する場合、構成単位ごとの中心地の座標を記入する(例えば「A、B、C、」毎など、個別の名称や標識(ラベル)の区別に応じて)。いかなる別個の構成単位であっても、RISで区別したものは、条約湿地地図上でも明確に分類すること。また単独で 1,000 haを占める湿地に、中央の地理的座標一点では、不充分である。広大なラムサール条約湿地の地理情報は、湿地の南西及び北東の隅の地理的座標を与える事によって補うこと(記載項目7及び11も参照のこと)。
(*)緯度・経度の1′が、約1.6 kmであるため(経度1′は赤道の場合)。
ほぼ中心の地理的座標を簡単に明記出来ない場合、またその点が条約湿地範囲外にはずれてしまう場合や非常に狭い部分に落ちてしまう場合はその旨を注記して、条約湿地の大半を占める部分のほぼ中央の点を明記すること。
9.一般的所在地:湿地の全体としての所在地を記述。この記述には、行政上の大きな括りの地域名(例:都道府県といった行政区分)とそれが属する地方名(例:宮城県/東北・本州、沖縄県/沖縄・九州、など)、「県」「地区」や、大きな行政上の中心となる都市、町、市で最も近くにある所から湿地までの直線距離と方位を含めて記載すること。中心となる都市の人口や行政地方名(可能であればすぐ上のレベルの行政区分/管轄区分も含める)も記載する。
10.海抜:湿地の平均海抜、または最高海抜及び最低海抜を平均海面上のメートル数で記入する。「平均」、「最高」、「最低」など数値の意味する語をはっきりと記入すること。
11.面積:指定した条約湿地の総面積をヘクタールで記入。個別の構成単位に分かれた個々の面積がわかっている場合、これらの構成単位を識別・区別する名称をそえて、その各々の面積を記入する(「7.地図」も参照のこと)。
12.概要:湿地タイプやその重要性、主要な物理的・生態学的特徴となる特性、最も重要な価値や機能、また特に興味深い特徴などを、「精彩のある文章」で、湿地を簡単な短文にまとめる。特に、19b)項で最も優占度が高いと特定されるような最も重要な湿地タイプも注記すること。
13.ラムサール条約湿地選定基準:「国際的に重要な湿地の選定基準」のうち、対象湿地に当てはまる記号の下のボックスにチェックを入れる。当該選定基準に関しては、添付文書Ⅱに提供される「基準の適用にあたっての詳細手引き」(決議Ⅶ.11で確定され、決議Ⅸ.1付属書Bで改正された「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」)を参照のこと。
多くの湿地は1個以上の基準を満たすことに留意して、合致する全ての基準を完全にかつ精確に選ぶこと。各々の選定基準の適用を正当づける個別の理由は、次項14に記述する。この記載項目13では根拠とする基準を選ぶ。
14.記載項目13で選定した基準の根拠:記載項目13で選定した上記のラムサール条約湿地基準に関し、どういった理由で条約湿地の基準を適用するかを、個々の基準について記述。RISの中で本項は、「国際的に重要な湿地」の概念の根幹である。基準コード単独では、各々の基準が個々の条約湿地に適応している事についての、道筋だった明確な情報を伝達しない−従って、ラムサール基準コードの選択にあたっての説明及び裏付けに、充分に正確な記述を提供することが肝要である。本項の記述は、基準をそのまま繰り返すだけでなく、選定された基準が個々のラムサール条約湿地にどのように当てはまるのかを説明するのに必要な詳細情報を記述しなければならない。添付文書Ⅱ「基準の適用のための詳細手引き」(決議Ⅶ.11で採択され、決議Ⅸ.1付属書Bで改正された)を参照のこと。
登録のために選択した基準の適用に対する根拠を準備するにあたって、個々の選定基準とその適用のためのガイドラインの正しい使用方法に関して、いくつかの点を考慮に入れなければならない:
ⅰ)基準1及び3の適用のためのガイドラインは、これらの基準を、それが起こる生物地理区という文脈の中で、湿地に適用すべきことを強調する。しかし、生物地理区が湿地タイプによって異なる場合があることは認める。生物地理区の文脈は、基準2による、脅威を受けている生態学的群集の選定のための、ある理由に対して適用することができる。条約湿地の周囲にある生物地理区と、適用した生物地理学的地域区分の方法は、「15.生物地理学」の項に記入しなければならない;
ⅱ)基準5に関して、ガイドラインは、実際の水鳥の飛来数の合計をはっきり述べ、また望ましくは、入手可能な場合、最近数年間の平均飛来数を述べなければならないこととしている。湿地が水鳥2万羽以上を支えているなど、単に基準をなぞって書くだけでは不充分である;
ⅲ)基準6を選定の根拠とすることに関しては、この基準は、水鳥の種または亜種の地域個体群の総数の1%以上を定期的に支えていることに対して適用しなければならないことを認識すること、また水鳥の飛来数の生物地理的範囲の該当するケースのほとんどは、締約国1国の国土よりも広い範囲となることを認識することが特に重要である。基準6の下に記載する地域個体群のリストには、この鳥の個体群が湿地内で通常観察される個体数だけでなく、生物地理学的な個体群の名称を記載しなければならない。基準6を適用するための最低1%の推奨基準は、国際湿地保全連合発行の『水鳥個体数推計 Waterbird Population Estimates 第4版』(2006年)
(2006年なかばには同団体ウェブサイト www.wetlands.org にて利用できるようになる予定)[編注]
に記載されており、またそこには個々の個体群の生物地理的範囲も記載されている。なお同推計の旧版はもやは無効であり基準6の適用に用いてはならない。この基準をこれら生息数の最低1%基準が得られた水鳥個体群だけに適用すべきであることは注意を要する。しかしながら、『水鳥個体数推計第4版』に個体数が記載されていない水鳥種に対して、ガイドラインは、他の情報源からの確かな生息数推定値と最低1%が得られたときにはこの基準を適用してもよい、しかしそのデータの情報源は明確にしなければならない、と記す。単に湿地が個体群の1%以上を支えている、と基準をそのまま記載するだけでは充分でなく、また個体群がその国の固有種である場合を除き、「国内」の個体数の1%以上の個体群を、個体数をつけて、リストに記載することもまた正当な根拠とはならない;
[編注]第4版は国際湿地保全連合 http://www.wetlands.org/wpe/ に提供されている。そのうち日本で用いることができる水鳥個体群の1%基準値一覧をアジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略国内事務局(2007)が準備した ☞ http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/ovwpe4d.htm。
ⅳ)基準2、3、4、5、6、7、8及び9の全てまたはいくつかが適合するとき、該当する種の名前(学名及び英語、フランス語、スペイン語による種名)は、根拠の中に記載しなければならない。
ⅴ)魚類や貝類の多様性についての基準7を適用することに関して「手引き」は、この基準を利用するには、種のリストだけでは根拠の記述として充分でないこと、また、生活史の段階、種の相互作用、地域的固有性のレベルなど、この基準に適合する高度の多様性を表す他の特性を要求している。
ⅵ)鳥類以外の動物種についての基準9の適用の手引きは上記項目ⅲ)で水鳥の基準6について示された内容と似かよっている。特に、この基準は湿地に依存する動物種の種または亜種の生物地理学的個体群の1%以上を定期的に生息することに対して適用しなければならない。また多くの場合に当該動物種の生物地理学的範囲は締約国1国の国土よりも広い範囲となることを認識することが特に重要である。基準9の下に記載する個体群の各々について、その生物地理学的個体群の名称と指定地内で定期的に生息する個体数を記す。この基準9を適用するために推奨される1%基準値は資料「条約湿地指定基準9を適用するための湿地に依存する鳥類以外の動物種の個体群推定と1%基準値」[☞ 条約事務局英文PDF,152㎅] に提供される。この論説には各個体群の生物地理学的分布範囲の記述も提供される。この基準は1%基準値が明らかになった動物種に対してのみ適用可能であることに注意する。ただし、添付文書Ⅳに現在のところ含まれていない分類群に属する種の個体群については、信頼できる個体群推定と1%基準値が他の資料から得られる場合に適用可能であること、またそのような場合は用いた情報資料の原典を明示しなければならないことが指針に指示される[訳注.添付文書Ⅳは本文書にまだ添付されていない]。適用にあたっては、単に湿地が個体群の1%以上を支えている、と基準をそのまま記載するだけでは充分でなく、また個体群がその国の固有種である場合を除き、「国内」の個体数の1%以上の個体群を、個体数をつけて、リストに記載することもまた正当な根拠とはならない。
15.生物地理学:条約湿地を取り巻く生物地理区と、適用された生物地理学的地域区分法とを(全ての参考文献の引用とともに)記載しなければならない。生物地理学上の明細は、基準1と3を正しく適用し、また基準2のある種の適用にとって本質的である。(「13.ラムサール基準」及び「14.基準の根拠」を参照)この記述の中で、ラムサール基準適用のためのガイドライン(添付文書Ⅱを参照のこと)は、「生物(地理)区」を「気候、土壌の種類、植生など、生物的及び物理的パラメーターを利用して確定した、科学的かつ厳密な地域の判定」と定義している。島国でない締約国は、生物地理区は本質的に国境を超越していること、またさまざまな湿地タイプの典型的な、または希少、固有である例の所在を確定するには、国同士の協力が要求されるケースが多いことに留意されたい。また、生物地理学的区分の性質は、自然な変異を決定するパラメーターの性質に従い、湿地タイプによって異なるであろうことも認識されている。(添付文書Ⅱを参照)
さまざまに異なった地球規模的、超国家的、地域的な生物地理学的区分法が一般に使われている。国際的に適切であると受け入れられているもの区分法は一つもない。従って、締約国は、(決議Ⅶ.11に対する附属書によって)入手可能な、最も適切であり、科学的に厳密なアプローチであると各国自身が認める、地域区分法を採用するよう強く要請されている。またその際は決議Ⅸ.1付属書Bに採択された追加の手引きに示されるように、国や地方規模の区分ではなく、大陸規模、地域規模、超国家的な区分法を用いることが一般に適切であるという点を考慮する。
16.湿地の物理的特徴:該当する場合には以下の特徴を含めて、湿地の主な物理的特徴を簡潔に説明:
17.集水域の物理的特徴:簡単な集水域の特徴の描写。以下を含むこと:
18.水文学上の価値:湿地の水文学上の主要な「価値」について説明。例えば、湿地がその生態系を通してもたらす便宜等。洪水調節の役割、地下水の涵水、海岸線の安定化、堆積物や栄養分の保持や受入れ、気候変動の緩和、そして水質浄化や水質の保持なども含まれるが、これに限る必要はない。(湿地の水文学上の価値や機能から外れる)湿地の水文学は、「16.物理的特徴」に記載すること。
19.湿地タイプ:まず最初に、対象となる湿地の範囲内に見出される湿地タイプの全てを○で囲むか下線によって列挙し、次に、記載した最も広い面積の湿地タイプを先頭にして、(面積による)それらの優占度の高さの順に湿地タイプを列挙する。「ラムサール条約湿地分類法」(本「注釈及びガイドライン」添付文書Ⅰを参照のこと)に、各湿地タイプコードにどんなタイプの湿地が当てはまるかが記されている。湿地タイプは海洋沿岸域湿地、内陸性湿地、人工湿地の3群に分類されること、また特に広大な条約湿地の場合、ひとつの湿地にはこれら三つの主な湿地タイプのうちふたつ以上が含まれてよいということに留意すること。
いくつかの海洋沿岸域湿地タイプ(例えば河口水域(タイプF)や干潟の森林性湿地(タイプI))が海岸線から遠く内陸に存在することがありうるし、また逆に、内陸性湿地は海岸線近くに存在することもありうるので、本項の追加記述として、内陸・沿岸性、または海洋・沿岸性、のように海岸線を基準とした湿地の一般的地理学的な位置もぜひ記載していただきたい。
湿地タイプの面積による優占度を列挙したら、もし可能なら、指定された湿地の合計面積に対する、構成するそれぞれの湿地タイプの面積や面積割合を記載する。とはいえ、幅広い多様性を備えた広大な湿地に対し、それを記述する事は難しいであろう。もし湿地が複数の単位から成り、それぞれ異なった湿地タイプや優先度の異なったタイプが別々の湿地単位内に現存するのであれば、各々の構成単位に対する湿地タイプの優占度もまた列挙すること(「7.地図」、「8.緯度経度」、と「11.面積」に関する手引きも参照)。
もし、選定された湿地が、非湿地性生息域の範囲を含む場合、例えば集水域のどこかにその様な部分が含まれる場合、このような生物的特徴を備えた湿地の面積、或いは全面積に対する割合をここに列挙することは助けとなる。
20.一般的な生態学的特徴:主要な生息環境や湿地、植生タイプをもって湿地生態系を記述。帯状分布や季節的変化、長期的な変化等も記載する。当該湿地を特徴づける生態系サービスやその生態系サービスに由来する恩恵を維持する生態学的過程を簡潔に述べる。隣接地域の生息環境や植生タイプを簡潔に記入するのも良い。重要な場合は、その顕著な食物連鎖に関する情報もこの項に記入する。
21.特記すべき植物:湿地が特に重要、また意義深いとされる理由に関わる植物の種または群集に関する追加・付加的情報を記入。湿地の国際的な重要性を根拠付けるために用いた情報(「14.基準の根拠」)や、「20.一般的な生物学的特徴」で既に提供された情報と重複させないこと。それぞれの種または群集が特記すべきであると結論付けられた理由を明記すること。(例えば、経済的に重要な種の場合、など)
地域の固有植物種に関し、もしそれらが、その湿地に対する基準3の適用に向け考慮されなかった場合(例えば地域固有種の個体数が、基準のための手引きに従って、「重要」と結論づけられなかったとき)、本項に記載してよい。
(偶発的に、あるいは故意に)外から移入された種や、侵略的な植物種もまた、ここに掲載すること。(侵入種や移入種による湿地への影響の記述は、「26.湿地の生態的特徴に悪影響を及ぼす要因」に記載すべきである。)
(出現する)一般的な種のリストは、本項やRISのその他の記載項目に記載する必要はないが、(湿地の詳細に基づいて正確に分類されていれば)その様なリストは、完成次第RISの附属文書とすること。
22.特記すべき動物:湿地が特に重要、また意義深いとされる理由に関わる動物の種または群集に関する追加・付加的情報を記入。湿地の国際的な重要性を根拠付けるために用いた情報(「14.基準の根拠」)や、「20.一般的な生物学的特徴」で既に提供された情報と重複させないこと。それぞれの種または群集が特記すべきであると結論付けられた理由を明記すること。(例えば、経済的に重要な種の場合、中枢種〔キーストーン種〕である場合、高度な湿地生物多様性の価値に関係する種、例えばカメ、ワニ、カワウソ、イルカなど)。
地域の固有動物種に関し、もしそれらが、その湿地に対する基準の適用に向け考慮されなかった場合(例えば、固有種の個体数が「重要」と結論づけられない(基準3)、または固有魚種の割合が、基準7への適合のための閾値に到達しない、など)、本項に記載してよい。特記すべき動物地理学的特徴(遺存種やまれな分布域の拡張など)も本項目に記載する。
(偶発的に、あるいは故意に)外から導入された、または侵略的な動物種もまた、ここに掲載すること。(侵入種や移入種による湿地への影響の記述は、「26.湿地の生態的特徴に悪影響を及ぼす要因」に記載すべきである。)
(出現する)一般的な種のリストは、本項やRISのその他の記載項目に記載する必要はないが、(湿地の詳細に基づいて正確に分類されていれば)その様なリストは、完成次第RISの附属文書とすること。
23.社会的、文化的価値:まず小項目a)に、湿地の主な社会的及び経済的価値と機能、そしてラムサール・ハンドブック第1巻から6巻にある「賢明な利用」の特性(例えば観光、野外レクリエーション、教育及び科学的調査、農業生産、放牧、水源、漁業生産等)、また主な文化的価値と機能(例えば考古学的場所、歴史的意味あい、また先住民にとっての意味を含む宗教上の重要性、等)、の概要を記入する。詳細な情報については、決議Ⅷ.19の付属書「湿地を効果的に管理するために湿地の文化的価値を考慮するための指導原則」を参照のこと。可能な場合には必ず、記入した価値のうち、自然の湿地の過程と生態学的特徴の維持と両立するものはどれか、を示す。
小項目b)には、有形無形を問わず湿地の起源や保全あるいは生態学的機能に結合する文化的価値の重要な例を保有することによって、その生態学的価値に加えて、国際的に重要であると考えられるかどうかを示す。もしそう考えられるならば、決議Ⅸ.21に採択された範疇に従ってその重要性に関する情報を記す。
持続不可能な利用に由来するもの、また、深刻な生態学的変化を招くものの詳細は、「26.湿地の生態的特徴に悪影響を及ぼす要因」に記載しなければならない。
24.土地保有権、所有権:条約湿地と周辺地域の所有権・保有権について詳述。もし可能であれば、さまざまな保有者・所有者の分類を各々の割り当てられた土地の所有率として明示すること(例えば、半分は州保有地、など)。複雑な保有権の取り決めや規定はすべて説明すること。国または関係地域において特別な意味をもつ契約条項については、その意味を説明する。本項と土地利用の詳細の項で記述するさまざまな土地保有者間の関係を次の項(「25.現在の土地利用」)で記述すること。
25.現在の土地(及び水)利用:(a)条約湿地、(b)周辺地域及び集水域、における全ての主な人間活動を記入。湿地における主な人間活動と主要な土地及び水利用の形態(家庭用水、工業用水の供給、潅漑、農業、家畜の放牧、林業、漁業、養殖、狩猟)の説明に加えて、その地域の人口も記入する。湿地における調査や教育、娯楽・観光に関係する行動や利用もまた本項で言及すること。ただし、これらの事柄の詳述は、それぞれ記載項目29、30及び31に記述すること。土地及び水のそれぞれの利用の規模や傾向等に関係する相対的な重要性、規模、及び傾向を可能な限り記述すること。(例えば、広大な湿地の一部分のみ、または明確な一帯や、ある湿地タイプの部分など)もし行動や利用が、湿地の明確に独立した部分に限られている場合は注記すること。(b)では、指定された湿地の状態に、直接または間接的に影響のある湿地周辺及びその広大な集水域における土地及び水利用と、湿地の影響を受ける可能性のある下流地域の土地利用についてまとめる。水利用についてさらに詳細には決議Ⅷ.1で採択された「湿地の生態学的機能を維持するための水の配分と管理に関するガイドライン」、ならびに決議Ⅸ.1付属書C「ラムサール条約の水に関連する指針の統合的な枠組み」、決議Ⅸ.1付属書Cⅰ「河川流域管理:ケーススタディー分析のための追加的な指針及び枠組み」、決議Ⅸ.1付属書Cⅱ「湿地の生態学的特徴を維持するための地下水管理ガイドライン」を参照のこと。
26.土地及び水利用の変化や開発計画などによる変化を含む(過去・現在・未来の)湿地の生態学的特徴に悪影響を及ぼす要因:湿地の内部及び周辺(適切な場合は、より大きな集水域を含める)から、湿地の生態学的特徴に影響を及ぼす人為的及び自然的要因。これらは湿地の自然生態学的特徴に対して、過去に悪影響を与えていた、現在与えている、あるいは将来与えるであろう、新しいまたは変化中の行動・利用、また主な開発計画などを含むものとする。全ての悪影響、また変化の要因を報告するにあたり、計量可能な、定量的な情報(データが存在するのであれば)、及び変化の要因やその影響の規模、大きさ、動向といった情報を提供すること:この情報は、湿地の生態学的特徴をモニタリングする際の基盤として提供されなければならない。
変化を招く作用因(例えば水路の変更、排水、干拓(土地改良)、汚染、過放牧、過度の人為的撹乱や過度の狩猟、漁業など)と、その結果の変化とその影響(例えば土砂の堆積、侵食、魚類の大量死、植生体系の変化、生息域の分断、種の繁殖の撹乱、気候変動に起因する自然または生態系の変化など)を明記する事が重要である。湿地自体に起因する要素と、湿地の外から発生するが湿地に与える影響を現時点で持っている、または持つ可能性がある要素を区別することもまた重要である。悪影響を与える要素が、可能性であるのか、既に存在するのかについてもまた識別すること。
汚染について記入する場合には、具体的な有害化学汚染物質とその汚染源を記載すること。これには、工業起源及び農業起源の化学物質の排水その他の排出物が含まれる。
湿地の生態学的特徴に過去、現在において悪影響を与えたり、将来において悪影響を与える可能性のある、エピソード的な突然の大変動(例えば地震や火山の噴火など)や植生の遷移等の自然現象がある場合には、円滑にモニタリングできるようにするために詳述する。
「21.特記すべき植物」と「22.特記すべき動物」で明らかにした、侵略的移入種または移入種、及び影響のあるあらゆる侵入について(偶発的か、或いは故意か、)の導入の歴史について、情報を提供すること。
27.実施された保全策:以下の領域について適宜詳細を提供する。
小項目a)に、国の保護区についての法的地位、また(ラムサール条約湿地以外の)国際的な保全の指定、また湿地が国境をまたいでいる場合は、湿地の全体または一部分に適用される二国間或いは多国間の保全対策について、その詳細を記入。もし保護区が設立されている場合は、設立の日付及び保護区の面積を記載すること。湿地の一部分だけが保護区に含まれる場合は、保護されている湿地生息域の範囲を注記すること。
小項目b)適宜、該当するIUCN保護地域カテゴリー(IUCN 1994)を記す。同カテゴリーは次のとおり:
| カテゴリー | 定義 |
| Ⅰa.厳正保護地域:学術研究を主目的として管理される保護地域 | その生態系や地質学的あるいは生理学的特徴や種について傑出したあるいは代表的なものを持つ陸域または海域。主として科学研究あるいは環境モニタリングに利用される地域。 |
| Ⅰb.原生自然地域:原生自然の保護を主目的として管理される保護地域 | 広い範囲で改変されていないかわずかしか改変されていない陸域または海域で、その自然の特質や影響力が保持され人の定住あるいは有意な居住がないもの。保護され、その自然状況を保存できるように管理される地域。 |
| Ⅱ.国立公園:生態系の保護とレクリエションを主目的として管理される地域 | 自然の陸域または海域で、⒜一以上の生態系の現在および将来世代が生態学的に完全であるように保護するために、⒝保護指定の目的に合わない人による利用や居住を排除するために、⒞精神的、科学的、教育的、余暇的、および訪問者の機会の基盤を、但しどの場合でも環境的にかつ文化的に矛盾が無い限りにおいて、提供するために、指定される地域。 |
| Ⅲ.天然記念物:特別な自然現象の保護を主目的として管理される地域 | 固有の希少性や、代表性あるいは美的特質、あるいは文化的重要性がゆえに傑出した価値あるいは比類なき価値を有する特定の自然的あるいは自然的文化的特徴をひとつ以上含む地域。 |
| Ⅳ.種と生息地管理地域:管理を加えることによる保全を主目的として管理される地域 | 生息環境の確実な維持や特定の種の必要条件を満たすための管理目的の活発な干渉の対象となる陸域または海域。 |
| Ⅴ.景観保護地域:景観の保護とレクリエーションを主目的として管理される地域 | 時代を超えた人々と自然との相互作用によって美的に、生態学的に、また文化的に重要な価値をもつ特徴が生み出され、しばしば高度の生物学的多様性とともに維持される、適当な沿岸域や海域を伴う陸域。このような伝統的相互作用の完全性を守ることがこのような地域の保護、維持および進化に欠かせない。 |
| Ⅵ.資源保護地域:自然の生態系の持続可能利用を主目的として管理される地域 | 改変されていない自然体系が優占して含まれる地域で、確実に生物学的多様性が長期的に保護され維持されるように管理され、また同時に地元社会の需要を満たすように持続可能な水準で自然の生産物やサービスが供給されるように管理される地域。 |
生物学的多様性の保護と維持にその目的を特定し、法制度あるいは他の効力のある方法を通じて管理される陸域または海域。
小項目c)には、もし湿地のための管理計画が展開され、また実行されているとすれば、そのすべてを含めて、管理計画策定手段を本項で記述。公に承認を得たものかどうかを含めること。その管理計画を、「34.参考文献」に記載すること。また可能ならば、RISに対する追加情報として管理計画の複写を提供する事。
小項目d)に、その他、開発に関する制限、野生生物に有益な管理の実施、狩猟の封鎖など、湿地で実施されるその他の保全対策について、どのようなものでも記述すること。
現在、湿地で実施されているモニタリング計画や調査について、その方法や方式に関する情報をここで記載。ラムサール条約の「湿地の賢明な利用及び生態学的特徴の維持のための概念的な枠組み」(決議Ⅸ.1付属書A)が湿地で適用されている場合、或いはその他「ラムサール賢明な利用ハンドブック」に編纂された条約の手引きの実施の実例について説明する。(「賢明な利用」は持続可能な利用と同義であり、ラムサール条約の基本理念である)
既存のラムサール条約湿地のRISを改訂するとき、もしモントルーレコードに記載される場合、或いはそこから除外される場合、それについて言及し、またラムサール諮問調査団の視察のあるときはその詳細を記載すること。
統合型流域・集水域管理、あるいは、統合型沿岸域・海域管理が適用されている場合には、その旨を記載すること。保護地域の法律制定や個々の保護地域における法的地位の効果に関する簡単な評価を記載すること。地域住民及び先住民を条約湿地の参加型管理に巻き込んでいる場合は、このプロセスに関するラムサールガイドライン(決議Ⅶ.8)とのつながりで、それを記載する。
28.提案されたが実施に移されていない保全策:立法、保護及び管理についての提案など、その湿地に対して提案された、または準備中の保全策があれば、それについて詳述する。長い間懸案となったままで実施されていない提案があればその経緯をまとめる。また、適切な政府当局に対して既に正式に提出した提案と、正式の承認を得ていない提案とを区別する(例えば、公表された報告書における提言と専門家会議の決議等)。準備中ではあるが、まだ完成していない、承認されていない、或いは実施されていない管理計画があれば、それについても記載する。
29.科学的研究及び施設の現状:現在行われているモニタリングを含む科学的研究計画の詳細、および湿地内の土地利用計画をすべてここに記載。また「25.現在の土地(及び水)利用」に記された研究用特別施設に関する情報を提供する。
30.湿地に関連または利益のある、現在の広報・教育・普及啓発(CEPA)活動:「25.現在の土地(及び水)利用」で記述された研修を含む、CEPAに関する既存の計画や行動、施設がある場合には本項に記載。湿地の、教育における可能性についてのコメントも記載すること。CEPAの問題とラムサール条約に関する詳細な情報は、条約のウェブサイト http://ramsar.org/outreach_index.htm を参照のこと。
31.レクリエーション、観光の現状:「25.現在の土地(及び水)利用」で説明された、レクリエーションと観光に関する湿地の現在の利用について詳細を記載。レクリエーションや観光のための既存または計画中のビジター施設やセンターがあれば、その詳細を記載し、もしわかれば湿地を訪れる年間観光客数も記載する。どのようなタイプの観光か、また観光が季節的なものかどうかも記載する。
32.管轄:以下に係る政府当局の正式名称及び住所を記入。a)湿地の「領土上の管轄権」を有する行政当局(国、地域、市等);b)保全を目的とする「機能上の管轄権」を有する当局(環境省、漁業省等)。
33.管理当局:湿地の現地で保全と管理を直接に所管する機関または組織の現地事務所の名称、住所を記載。可能であれば、湿地の現地での所管に係る人物の氏名や所属も、必ず記載すること。湿地の管理に関する、特別な或いは独自の取決めがある場合は、それも記入する。
34.参考文献:湿地に関係する主要な技術的参考文献のリスト。管理計画、主要な科学論文、文献がある場合はそれらを含む。ラムサール条約湿地のための、またその湿地を特別に扱う(例えば国内の全ラムサール条約湿地の詳細を紹介するウェブサイトなど)、機能的・活動しているウェブサイトのアドレス及び最新の更新日も列挙する。湿地に関して多数の刊行資料が入手できる場合には、記載すべき最重要文献のみをここに記載し、その際には、広範な文献目録が掲載されている最近の文献を優先する。可能ならば常に、管理計画のコピーなど最重要文献は抜き刷りまたはそのコピーを添付する。
このコードは、勧告4.7によって承認され、締約国会議の決議Ⅵ.5及びⅦ.11によって修正されたラムサール条約湿地分類法に基づいている。ここに掲げる分類は、各条約湿地が表す主要な湿地生息地を速やかに特定できるように、大まかな枠組みだけを提示するものである。
RIS記載項目19に掲げる正しい湿地タイプの特定を援助するために海洋沿岸域湿地と内陸湿地について各タイプの特徴のいくつかをまとめた表が末尾にある。
海洋沿岸域湿地
A -- 低潮時に6メートルより浅い永久的な浅海域。湾や海峡を含む。
B -- 海洋の潮下帯域。海藻や海草の藻場、熱帯性海洋草原を含む。
C -- サンゴ礁。
D -- 海域の岩礁。沖合の岩礁性島、海崖を含む。
E -- 砂、礫、中礫海岸。砂州、砂嘴、砂礫性島、砂丘系を含む。
F -- 河口域。河口の永久的な水域とデルタの河口域。
G -- 潮間帯の泥質、砂質、塩性干潟。
H -- 潮間帯湿地。塩生湿地、塩水草原、塩性沼沢地、塩生高層湿原、潮汐汽水沼沢地、干潮淡水沼沢地を含む。
I -- 潮間帯森林湿地。マングローブ林、ニッパヤシ湿地林、潮汐淡水湿地林を含む。
J -- 沿岸域汽水/塩水礁湖。淡水デルタ礁湖を含む。
K -- 沿岸域淡水潟。三角州の淡水潟を含む。
Zk(a) -- 海洋沿岸域地下カルスト及び洞窟性水系。
内陸湿地
L -- 永久的内陸デルタ。
M -- 永久的河川、渓流、小河川。滝を含む。
N -- 季節的、断続的、不定期な河川、渓流小河川。
O -- 永久的な淡水湖沼(8haより大きい)。大きな三日月湖を含む。
P -- 季節的、断続的淡水湖沼(8haより大きい)。氾濫原の湖沼を含む。
Q -- 永久的塩水、汽水、アルカリ性湖沼。
R -- 季節的、断続的、塩水、汽水、アルカリ性湖沼と平底。
Sp -- 永久的塩水、汽水、アルカリ性沼沢地、水たまり。
Ss -- 季節的、断続的塩水、汽水、アルカリ性湿原、水たまり。
Tp -- 永久的淡水沼沢地・水たまり。沼(8ha未満)、少なくとも成長期のほとんどの間水に浸かった抽水植生のある無機質土壌上の沼沢地や湿地林。
Ts -- 季節的、断続的淡水沼沢地、水たまり。無機質土壌上にある沼地、ポットホール、季節的に冠水する草原、ヨシ沼沢地。
U -- 樹林のない泥炭地。潅木のある、または開けた高層湿原、湿地林、低層湿原。
Va -- 高山湿地。高山草原、雪解け水による一時的な水域を含む。
Vt -- ツンドラ湿地。ツンドラ水たまり、雪解け水による一時的な水域を含む。
W -- 潅木の優占する湿原。無機質土壌上の、低木湿地林、淡水沼沢地林、低木の優占する淡水沼沢地、低木カール、ハンノキ群落。
Xf -- 淡水樹木優占湿原。無機質土壌上の、淡水沼沢地、季節的に冠水する森林、森林性沼沢地を含む。
Xp -- 森林性泥炭地。泥炭沼沢地林。
Y -- 淡水泉。オアシス。
Zg -- 地熱性湿地。
Zk(b) -- 内陸の地下カルストと洞窟性水系。
注意:「氾濫原」とは、一以上の湿地タイプを表すのに用いられる意味の広い用語であり、R、Ss、Ts、W、Xf、Xp等のタイプの湿地を含む。氾濫原湿地の例としては、季節的に冠水する草原(水分を含んだ天然の牧草地を含む)、低木地、森林地帯、森林等がある。本ガイドラインでは、氾濫原湿地を一つの湿地タイプとしては扱ってはいない。
人工湿地
1 -- 水産養殖池(例 魚類、エビ)。
2 -- 湖沼。一般的に8ha以下の農地用ため池、牧畜用ため池、小規模な貯水池。
3 -- 潅漑地。潅漑用水路、水田を含む。
4 -- 季節的に冠水する農地(集約的に管理もしくは放牧されている牧草地もしくは牧場で、水を引いてあるもの。)
5 -- 製塩場。塩田、塩分を含む泉等。
6 -- 貯水場。貯水池、堰、ダム、人工湖(ふつうは8ヘクタールを超えるもの)。
7 -- 採掘現場。砂利採掘抗、レンガ用の土採掘抗、粘土採掘抗。土取場の採掘抗、採鉱場の水たまり。
8 -- 廃水処理区域。下水利用農場、沈殿池、酸化池等。
9 -- 運河、排水路、水路。
Zk(c) -- 人工のカルスト及び洞窟の水系。
| 塩水 | 永久的 | 6メートルより浅い | A |
| 水面下の植生 | B | ||
| サンゴ礁 | C | ||
| 海岸 | 岩礁性 | D | |
| 砂、礫、中礫 | E | ||
| 塩水または汽水 | 潮間帯 | 干潟(泥質、砂質、塩性) | G |
| 沼沢地 | H | ||
| 森林性 | I | ||
| 礁湖、潟湖 | J | ||
| 河口域 | F | ||
| 塩水、汽水または淡水 | 地下 | Zk(a) | |
| 淡水 | 潟湖 | K | |
| 淡水 | 流水系 | 永久的 | 河川、渓流、小河川 | M |
| デルタ | L | |||
| 泉、オアシス | Y | |||
| 季節的、断続的 | 河川、渓流、小河川 | N | ||
| 湖沼、水たまり | 永久的 | >8㏊ | O | |
| <8㏊ | Tp | |||
| 季節的、断続的 | >8㏊ | P | ||
| <8㏊ | Ts | |||
| 無機質土壌上の沼沢地 | 永久的 | 草本優占 | Tp | |
| 永久的、季節的、断続的 | 低木優占 | W | ||
| 樹木優占 | Xf | |||
| 季節的、断続的 | 草本優占 | Ts | ||
| 泥炭土壌上の沼沢地 | 永久的 | 樹林のない | U | |
| 森林性 | Xp | |||
| 無機質土壌上または 泥炭土壌上の沼沢地 | 高山 | Va | ||
| ツンドラ | Vt | |||
| 塩水、汽水、 またはアルカリ性 | 湖沼 | 永久的 | Q | |
| 季節的、断続的 | R | |||
| 沼沢地、水たまり | 永久的 | Sp | ||
| 季節的、断続的 | Ss | |||
| 淡水、塩水、汽水、 またはアルカリ性 | 地熱性 | Zg | ||
| 地下 | Zk(b) | |||
本基準は、第7回締約国会議(1999年)で採択され、従来使用されていた第4回と第6回締約国会議(1990年及び1996年)で採択された基準に代わるもので、ラムサール条約湿地の選定における第2条第1項の実施のガイドとなる。
種及び生態学的群集に基づく基準
水鳥に基づく特定基準
魚類に基づく特定基準
他の分類群に基づく特定基準
(「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」に基づく)
1a)この基準を体系的に応用する場合、締約国には以下を奨励する。
1b)適用する生物地理学的地域区分法を選択する際は、国内レベルや地方レベルの区分法よりも、大陸レベルか条約地域レベルあるいは超国家レベルの区分法を用いることが一般的に適切である。
1c)「戦略的枠組み」の目標1には、特にその中でも目標1.2には、この基準に基づく別の検討事項として、当該湿地の生態学的特徴が、主要河川流域または沿岸系の自然の機能において重要な役割を果たしている湿地を優先することを掲げている。水文学的機能については、この基準の下で締約国が優先的に登録する湿地の決定について検討しやすくするために、以下の手引きを提示する。生物学的役割及び生態学的な役割に関する手引きについては、基準2を参照されたい。
1d)水文学的重要性。ラムサール条約第2条に定める通り、湿地は、水文学上の重要性にしたがって選定されるべきであり、これには特に以下の属性が含まれる。
2a)登録湿地は、地球規模で絶滅のおそれのある種や生態学的群集の保全にとって、重要な役割を担っている。関係している個体数や生息地が少ないにもかかわらず、また、入手できる定量的なデータや情報の質が低いことが多いにもかかわらず、生活環のいずれの段階であれ地球規模で絶滅のおそれのある群集や種を支えている湿地を、基準2または3を用いて登録するよう、特に検討する。
2b)「戦略的枠組み」総合目標2.2では、絶滅のおそれのある生態学的群集を含む湿地、または、絶滅のおそれのある種に関する国内法もしくは国家計画、またはIUCN(国際自然保護連合)レッドリスト、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の付属書Ⅰ、及び移動性野生動植物種に関する条約(ボン条約)の付属書等の国際的な枠組みにより、危急種、絶滅危惧種または近絶滅種と特定された種の生存にとって重要な湿地を登録湿地に加えるよう、締約国に要請している。
2c)締約国がこの基準に基づいて登録湿地候補を検討する場合、希少種、危急種、絶滅危惧種、または近絶滅種の種に対して生息地を提供する湿地のネットワークを登録湿地に選定すれば、最大の保全価値を達成できる。理想的には、このネットワークに含まれる湿地が以下のいずれかまたはすべての特性を備えていることが望ましい。
2d)絶滅のおそれのある生態学的群集をもつ湿地を特定する場合、次の特性のひとつ以上を有する生態学的群集が生息する湿地を選定すれば、最大の保全価値を達成できる。
2e)段落2d)のⅰならびにⅱのもとで適用する生物地理学的地域区分法を選択する際は、国内レベルや地方レベルの区分法よりも、大陸レベルか条約地域レベルあるいは超国家レベルの区分法を用いることが一般的に適切である。
2f)「戦略的枠組み」第46〜49節の「湿地の境界の決定」で述べられる生息地の多様性と遷移に関する問題についても留意すること。
2g)地下カルストと洞窟性水系の多くのものがもつその生物学的重要性についても意識すること。
3a)締約国がこの基準に基づいて登録湿地候補を検討する場合、以下のいずれかまたはすべての特性を備えている一連の湿地を選定すれば、最大の保全価値を達成することができる。
3b)地下カルストと洞窟性水系の多くのものがもつその生物学的重要性についても意識すること。
3c)適用する生物地理学的地域区分法を選択する際は、国内レベルや地方レベルの区分法よりも、大陸レベルか条約地域レベルあるいは超国家レベルの区分法を用いることが一般的に適切である。
4a)移動性の種または渡り性の種にとって重要な湿地は、生活環の特定の段階において比較的狭い地域に集まる個体群のうちの、きわめて大きな割合を収容するものである。これは、一年のうちの特定の時期の場合もあれば、半乾燥地域や乾燥地域においては、特定の降雨パターンを示す年の場合もある。例えば多くの水鳥は、繁殖地域と非繁殖地域の間にある長い渡りの道程の途中で、比較的狭い地域を主な中継地(採食及び休息用の場所)に利用する。カモ科の種にとっては、換羽の場所も同じく重要である。半乾燥地域または乾燥地域にある湿地には、水鳥その他湿地に生息する移動性の種がきわめて高い集中度で収容され、個体群の生存にとって重大な鍵を握っていることがある。しかしながら、降雨パターンが年によってかなり変わることから、見た目に明らかな重要性は年毎に大きく変動する可能性がある。
4b)湿地に生息する非渡り性の種は、気候等の条件が好ましくない場合でも生息地を変えることはできず、一部の湿地だけが、中長期的に種の個体群を維持するための生態学的な特性を備えることになる。こうして一部のワニや魚類は、乾期になって適当な水生の生息地の範囲が狭まるにつれて、湿地複合の中にある水深の深い所や池へと避難していく。そうした湿地では、雨期が再びめぐってきて湿地内の生息範囲が再び広がるまで、この狭い地域が動物の生存にとって重大な鍵を握る。非渡り性の種に対してこのような機能を果たす湿地(生態学的、地形学的、及び物理的に複雑な構造の場合が多い)は、個体群の存続にとって特に重要であり、優先的に登録湿地候補として考慮する。
5a)締約国が、この基準に基づいて登録湿地候補を検討する場合、世界的に絶滅のおそれのある種や亜種を含む水鳥の集合に対して生息地を提供する湿地のネットワークを登録湿地に選定すれば、最大の保全価値を達成できる。現在のところ、こうした湿地はあまり登録されていない。
5b)外来種の水鳥については、特定湿地の総個体数に含めてはならない。
5c)基準5は複数の種の集合地に対して適用するだけでなく、定期的にどれかひとつの種を2万羽以上支えている湿地に対しても適用する。
5d)2万羽以上の水鳥を支える湿地を国際的に重要とみなすこの基準5に基づいて、200万羽以上の大きさの水鳥の個体群については、2万羽がその1%基準値として採用される。当該湿地の当該種に対する重要性を反映させるために、基準6にも当該種を掲げることが適切である。
5e)この基準は、各締約国の様々な大きさの湿地に等しく適用される。この数の水鳥が存在する面積を正確に示すことは不可能だが、基準5に基づいて国際的に重要と特定される湿地は生態学的な単位を構成しているはずであり、したがって1か所の大きな地域を構成しているか、または小規模な湿地の集合である。データが得られる場合には、累計を把握できるように、渡りの期間中における水鳥の入れ換わり数も考慮すること。
5f)特に渡りの時期はそうであるが、個体の入れ換わりの結果、ある時点で数えられる生息数よりも多くの水鳥がその湿地を利用していることになる。従って、水鳥個体群を支える湿地の重要性は、単純な生息数調査から明らかになるよりも高いことがしばしばである。
5g)一方、個体群の大きさや、ある湿地を利用する個体群の入れ換わり数や利用総個体数を正確に算定することは困難であり、例えば同齢出生集団の標識とその再観察による分析や時間を追った生息数変化の集計分析といったこれまでも時折り用いられてきたいくつかの方法ですら統計的に信頼がおける正確な算定は達せられない。
5h)現在のところ唯一入れ換わり数の信頼できる算定が得られると考えられている方法は、生息地で捕獲し個体別に標識された鳥を再観察ならびに再捕獲することによって算定する方法である。しかし、この方法で信頼できる算定を得るためにはかなりの能力や資源が必要であり、特に広大な生息地や到達困難な生息地では(対象種が広く分散するようなところではさらに)その実施は克服不可能なほどの困難をきたすことがある。
5i)当該湿地で水鳥の入れ換わりがおこっていることがわかっているが、正確な渡りの総数が得られない場合でも、当該湿地の渡り鳥の中継地としての重要性が確実に当該湿地の管理計画策定に十分認識されるための基礎として、基準4を適用してこのような重要性を認識するように締約国は引き続き検討する。
6a)締約国が、この基準に基づいて登録湿地候補を検討する場合、世界的に絶滅のおそれのある種や亜種の個体群を収容する一連の湿地を登録湿地に選定すれば、最大の保全価値を達成できる。データが得られる場合には、累計を把握できるように、渡りの期間中における水鳥の入れ換わり数も考慮すること。
6b)締約国は、国際的に矛盾のないようにするため、可能な場合には、この基準に基づく登録湿地の評価基準として、国際湿地保全連合が発表して3年ごとに内容を更新している国際的な推定個体数と1%基準を用いる [編注] 。決議Ⅵ.4ならびに決議Ⅷ.38が要請しているように、締約国は、この基準のより良い適用を図るために、将来における国際的な水鳥推定個体数の更新と改訂に向けてデータを提供するだけでなく、当該推定数データの大多数の出所である国際湿地保全連合の国際水鳥調査に関し、自国内での実施と発展を支援する。
[編注]2006年版が国際湿地保全連合 http://www.wetlands.org/wpe/ に提供されている。そのうち日本で用いることができる水鳥個体群の1%基準値一覧をアジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略国内事務局(2007)が準備した ☞ http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/ovwpe4d.htm。
6c)湿地によっては、同一種の複数の生物地理学的個体群がする場合が、特に渡りの時期に、また異なる個体群の渡り経路が主要な湿地で交差するようなところで見られる。当該個体群が野外で区別できない場合がふつうに見られ、実際にどの1%基準値を適用するか問題になることがある。このような複数の個体群が混じる場合(かつ野外で区別できない場合)は当該複数個体群の1%基準値の大きいものの値を用いて当該湿地の重要性を評価することが示唆される。
6d)一方、前述のような際でも一方の個体群が保全優先度が高いものの場合は特に、この手引きは弾力的に適用し、締約国は、当該湿地のそのような重要性が確実に当該湿地の管理計画策定に十分認識されるための基礎として、基準4を適用して両方の個体群にとっての当該湿地の全体的な重要性を認識するように検討する。この手引きが個体群サイズが小さいほうの保全優先度の高い個体群に不利になるように適用されてはならない。
6e)上の段落6c)と6d)の手引きは複数の個体群が混じる時期(必ずしもではないがしばしば渡りの時期にあたる)のみに適用される。他の時期には、生息する個々の個体群に対して正確に1%基準値を割り当てることができるのが普通である。
6f)特に渡りの時期はそうであるが、個体の入れ換わりの結果、ある時点で数えられる生息数よりも多くの水鳥がその湿地を利用していることになる。従って、水鳥個体群を支える湿地の重要性は、単純な生息数調査から明らかになるよりも高いことがしばしばである。入れ換わりの算定についての手引きは基準5についての手引きの段落5f)から5i)を参照。
7a)魚類は、湿地と結びついている脊椎動物の中で、最も数が多い。世界全体でみると、一生を通じて、あるいは生活環の一部分だけを湿地で過ごす魚類は、1万8000種以上にのぼる。
7b)基準7は、魚類及び甲殻類の高い多様性があれば、その湿地を国際的に重要な湿地に指定できることを示している。この基準は、多様性というものが、分類群の数、様々な生活史の段階、種間相互作用、及び分類群と外部環境との相互作用の複雑さ等、様々な形をとりうることを強調している。したがって、種の数だけで個々の湿地の重要性を評価するのは不十分である。さらに、種がその生活環の様々な段階で果たす様々な生態学的役割についても考慮する必要がある。
7c)この生物多様性の解釈には、高水準の固有性と生物非単一性が重要だということが暗黙のうちに含まれている。多くの湿地では、高い固有性を持つ魚類相がその特徴となっている。
7d)国際的に重要な湿地の特定には、固有性の度合いを測る何らかの尺度を用いる。少なくとも魚類の10%が、一つの湿地または自然にまとまっている湿地群に固有のものならば、その湿地を国際的に重要とみなす。しかし固有の魚類がいなくとも、他に相応の特徴があれば、重要な湿地に指定される資格がないわけではない。湖のなかには、アフリカのグレートレイクスと呼ばれる湖群(ビクトリア湖等を含む)、ロシアのバイカル湖、ボリビアとペルーにまたがるチチカカ湖、乾燥地域にあるシンクホール湖や洞窟湖、島にある湖等のように、固有性のレベルが90〜100%という、きわめて高い数字に達するものもあるが、世界全体に適用するには10%という数字が現実的である。固有の魚類種が生息していない地域では、地理的な亜種のように、種以下の区分での遺伝的に異なる固有性を尺度に用いる。
7e)世界中で魚類の734種が絶滅の危機に瀕しており、少なくとも92種がこの400年間に絶滅したことが知られている。希少種または絶滅のおそれのある種の存在については、基準2で取り扱う。
7f)生物多様性の重要な構成要素は、生物非単一性、すなわち群集内における形態または生殖形態の幅である。湿地群集の生物非単一性は、生息地の時間的、空間的多様性と予測可能性によって決定される。すなわち、生息地がより異なって予測できないものになれば、魚類相の生物非単一性はそれだけ大きくなる。例えば、マラウィ湖は安定した古代からの湖であり、そこには600以上の魚種が生息しているが、そのうち92%は口の中で稚魚を育てるカワスズメ科の魚類であって、科の数にすれば2〜3科の魚類しか生息していない。これとは対照的に、ボツワナのオカバンゴ湿地という雨期と乾期の間で変動する沼地の氾濫原では、生息する魚種は60種に過ぎないが形態や生殖形態が非常に多様であり、生息する魚類の科の数は多く、つまり生物多様性はマラウィ湖よりも豊富である。湿地の国際的な重要性を評価するには、生物多様性と生物非単一性の両方を尺度として利用すべきである。
8a)多くの魚類(甲殻類を含む)は、その産卵場、稚魚の成育場、採食場が広く分散しており、かつそれらの場所の間を長距離にわたって移動する等、複雑な生活史を有している。もし魚類の種や系統を維持しようとするなら、魚類の生活環を完結させるのに不可欠な場所をすべて保全することが重要である。沿岸の湿地(沿岸の潟湖や河口、塩生湿地、海岸の岩礁や砂丘を含む)は、水深が浅くて生産性の高い生息地を提供しており、成魚の段階を開放水域で過ごす魚類は、採食場や産卵場、稚魚の成育場として沿岸の湿地を広範に利用している。したがってこうした湿地は、大きな成魚の個体群の生息地になっていないとしても、漁業資源にとって不可欠な生態学的過程を支えているのである。
8b)さらに、河川や沼地、湖に生息する多くの魚類は、当該生態系の一部分で産卵したとしても、他の内水面や海洋で成熟期を過ごす。湖に生息する魚類は、産卵のために河川を遡上するのがふつうであるし、河川に生息する魚類は、産卵のために河川を下って湖や河口、あるいは河口の先にある海へと移動するのがふつうである。沼地に生息する多くの魚類は、より永続的で深い水域から、浅いところや、一時的に冠水している場所へと産卵に向かう。したがって、水系の一部をなす湿地は、一見したところ重要ではないように見える場合であっても、当該湿地の上流、下流にわたる広い河川流域の適切な機能を維持するのに不可欠な場合がある。
8c)本ガイドラインはあくまでも手引きを目的とするものであり、個々の湿地その他において漁業を規制する締約国の権利を妨げるものではない。
9a)締約国が、この基準に基づいて登録湿地候補を検討する場合、世界的に絶滅のおそれのある種や亜種の個体群を支える一連の湿地を登録湿地に選定すれば、最大の保全価値を達成できる。移動性の動物種についてはその移動時期における個体の入れ換わりも、データがある場合に考慮すると累計個体数が得られる(基準5の手引きの段落5f)から5i)の水鳥における入れ換わり数に関する手引きがこの基準9の鳥類以外の動物種についても適用可能であるので参照のこと)。
9b)締約国は、国際的に矛盾のないようにするため、可能な場合には、この基準に基づく登録湿地の評価基準として、IUCN専門家グループがIUCN種の情報サービス(IUCN Species Information Service (SIS))を通じて提供し定期的に更新し、また「ラムサール技術報告」シリーズに出版する最新の国際的な個体群推定と1%基準値を用いる。対象個体群とその1%基準値のはじめての一覧は、資料「条約湿地指定基準9を適用するための湿地に依存する鳥類以外の動物種の個体群推定と1%基準値」[☞ 条約事務局英文PDF,152㎅] に提供される。
9c)この基準9はまた各国固有の種や個体群に対しても、信頼できる国内個体群の大きさの推定が存在すれば適用可能である。このような適用をする場合は、個体群の大きさの推定の出典となる出版物の情報を適用の正当な根拠として明記する。そのような情報はまた、「ラムサール技術報告」シリーズに出版される個体群推定と1%基準値の情報に収録される分類群の範囲を拡張することに貢献しうるものである。
9d)この基準9は鳥類以外の以下の分類群の個体群や種に適用可能なことが予測される:哺乳類、爬虫類、両生類、魚類、水生大型無脊椎動物。ただし、信頼できる個体群推定が提供される、あるいは出版されている種や亜種についてしか、この基準を適用した正当な根拠には含められない。このような情報を欠く場合は、締約国は基準4の下に重要な鳥類以外の動物種のための指定を検討する。締約国は、この基準のより良い適用を図るために、将来における国際的な個体群推定の更新と改訂を支援するために、このようなデータをIUCN種の保存委員会(IUCN−SSC)およびその専門家グループに、可能な範囲で、提供して援助する。
以下の手引きは、国際湿地保全連合とラムサール条約事務局、世界遺産条約、UNEP世界保全モニタリングセンターの経験から、また同様に「世界遺産条約, 1999, 世界遺産登録地指定及び保全報告の状態に向けたデジタル及び地図学ガイドラインを提案する会議」(WHC-99 / CONF.209 / INF.19. Paris, 15 November 1999. WWW document: http://www.unesco.org/whc/archve/99-209-inf19.pdf に掲載)に提供された手引きから書かれたものである。
1.適切な地図を提供することは、条約第2条1項の下の要請であり、それは国際的に重要な湿地(ラムサール条約湿地)選定の手順の基本であり、また「ラムサール条約湿地情報票(RIS)」に提供する情報の本質的な部分である。湿地に関する明確な地図情報もまた、湿地管理の核心である。
2.この追加手引きは、(例えば、地理情報システム(GIS)ソフトを使用することで)ラムサール条約湿地の地図を電子形式で準備、提供すること、また全地球測位システム(GPS)による正確なウェイポイントの確定を通じて、締約国が湿地の境界を明確に描写することについての能力を高めてきていることを認める。
3.ラムサール条約湿地の指定に際して締約国が提出する地図は、出来るかぎり、そして高優先順位で:
ⅰ)専門的地図作成の基準に合わせて準備しなければならない。(専門的地図作成の基準に合わせた地図が準備されない場合は問題が生じる。)普通に不透明にした手書の湿地境界線や斜線引き(例:区分表示のための)が、それ以外の重要な地図の特徴をぼやかしてしまうことがしばしばある。色付けされた注釈は、地図の原本では、地図の特徴を示す説明書きから明白に区別出来るものの、白黒のコピーではほとんどの色分けが区別出来ないということを認識するのは重要である。そのような追加情報は、概略図を追加して提供されるべきである;
ⅱ)ラムサール条約湿地の自然な、または改変された環境を示すべきこと。また条約湿地の大きさに応じ、以下に示す地図の縮尺の範囲内で明記しなければならない;
ⅲ)ラムサール条約湿地の境界を明瞭に示し、既存、または提案されている緩衝帯からこれを区別すること;
ⅳ)もし湿地が以前登録されたラムサール条約湿地に接し、または以前の条約湿地を包含する場合、それら以前の条約湿地の全ての境界を表示し、前に登録された範囲全ての現在の状況を明らかにしなければならない;
ⅴ)境界及び地図上に示される条約湿地の指定に関連する特性の分類をそれぞれ示す記号表や判例表をつけ;そして、
ⅵ)地図の縮尺、地理学上の座標表示(緯度・経度)、方位表示(北の方向)、また可能であれば地図の投影法を明記すること。もし可能であれば、地図(または手引き地図)にいくつかのその他の特徴もまた明示すること。
4.ラムサール条約湿地に指定するために最も相応しい地図あるいは一連の地図はまた、以下の項目を明瞭に示すこと。しかし、これらの情報を蓄積することの優先順位は、上記段落3に記載された属性よりも低い:
ⅰ)基本的な地形情報;
ⅱ)関連する保護区指定の境界及び行政上の境界(例:(州または)県や市、郡など);
ⅲ)条約湿地の湿地と非湿地の部分の明瞭な輪郭、そして条約湿地の境界に対する湿地の境界の描写。これは特に登録する湿地の範囲を越えて湿地が広がるときに当てはまる。可能ならば、主たる湿地生息タイプ及び主要な水文学的特性の分布に関する情報もまた有益である。湿地の広がりの中にはっきりとした季節的変化があるときは、湿った季節と乾いた季節における湿地の広がりを別の地図で示す事は役に立つ;
ⅳ)主なランドマーク(例:街、道、など);そして、
ⅴ)同じ集水域内における土地利用の分布。
5.締約国の領土内におけるラムサール条約湿地の一般的所在地を示す地図はまた、きわめて有用である。
6.地図を切り取ってはならない。データ管理者やラムサール条約事務局のスタッフが、縁に印刷された注記や、緯度・経度の印を参照できるようにするためである。
7.地図が上記属性の全てを備えており、適切な縮尺(以下手引きを参照)によっていれば、もし地図(や地図集)が印刷書式(紙媒体)のみで提供される場合(すなわち電子地図媒体がまだ用意されていない場合)も、位置情報システム(GIS)に組み込むための地図のデジタル化は容易になる。
8.その後のデジタル化を正確に歪みなしに行うために、地図は原版(コピーを2部提出する)でなければならず、コピーは認めない。
9.追加項目として、コピーや発表用資料作成の上で、他に主要な地図の次の2つバージョンがきわめて有益である:
ⅰ)A4サイズに縮小した地図のカラー写真;
ⅱ)GISファイルによる区域のベクトルデータと属性表(可能な場合);
ⅲ)TIFF、JPEG、BMP、GIFファイル他の一般的なデジタル画像ファイル。
10.地図の最適縮尺は、描かれる条約湿地の大きさによる。さまざまな大きさのラムサール条約湿地の地図に対する最適な縮尺は以下のとおりである:
| 条約湿地の大きさ(㏊) | 地図の適用(最低限の)縮尺 |
| 1,000,000以上 | 1:1,000,000 |
| 100,000〜1,000,000 | 1:500,000 |
| 50,000〜100,000 | 1:250,000 |
| 25,000〜50,000 | 1:100,000 |
| 10,000〜25,000 | 1:50,000 |
| 1,000〜10,000 | 1:25,000 |
| 1,000以下 | 1:5,000 |
11.要約すれば、地図は、RISに記述した湿地の特徴を可能な限り明確に描写し、また特に正確な境界を示すのに適当な縮尺でなければならない。
12.中程度から大規模な湿地に関しては、標準のA4(210 ㎜ × 297 ㎜)やレターサイズ(8.5インチ × 11インチ)の用紙では充分な詳細を示す事がしばしば困難なので、一般的にはそのサイズよりも大きな用紙を利用する方がより適切である。しかしながら、その後のコピー作業等が困難となるので、いずれの地図も、可能なときは必ず、A3(420 ㎜ × 297 ㎜)を越えるべきではない。
13.条約湿地が大規模または形状が複雑なときや、また境界が互いに分かれたいくつかの小湿地から構成されるとき、各部分や小湿地の互いの位置関係がわかる高縮尺の湿地の全体地図と同時に、各々の部分や小湿地の地図の拡大版を提供すべきである。そのような地図は全て上記縮尺に関する手引きに従うこと。
14.詳細な地勢図が入手できないとき、地図に付随して、条約湿地の境界の記述をすべきである。この記述には地理上その他の国家、地方の法律上、または国際的な境界を示したうえで、条約湿地の境界と共に、ラムサール条約湿地とラムサール条約湿地の一部又は全体を覆う他の既存保護区の関係を示すものとする。
15.もし湿地境界の正確な場所が全地球測位システム(GPS)を使って確定されている場合、締約国は、条約湿地の地図上に、確定また確認した各々のGPSウェイポイントの緯度・経度を列挙し、それを湿地の紙の地図上に記入した電子ファイルまたは紙媒体を含むことが奨励される。
16.以下に示す状況のいずれか、またはいくつかがあって、決議Ⅷ.21「ラムサール条約湿地情報票におけるラムサール条約の湿地境界の正確な記述」に従い、登録されたラムサール条約湿地の境界が変更された場合:
a)ラムサール条約湿地境界の描写が不正確であり、また実質的な誤りがあるとき;
b)ラムサール条約湿地境界がRISで規定する境界の記述と正確に合致しないとき;
c)科学技術の向上により、ラムサール条約湿地境界を、登録当時よりも高度な解像度でより精密に確定することが可能になったとき;
変更は全て、RISを改訂し湿地の地図で明確に示されなければならない。また改善の理由をRISに記述しなければならない。
17.締約国は、可能な場合、GISに組み込むのに適した電子形式のラムサール条約湿地に関する地理的情報を提出することが奨励される。
18.境界と緩衝地帯を線引きするために、ベクター形式で、最大縮尺のデータを提出しなければならない。
19.その他の情報、例えば湿地タイプや土地利用などは、可能な限り大きな縮尺で、一つ以上のベクターあるいはラスター形式のレイヤーにして提出すること。
20.電子フォーマットに関するメタデータは、電子地図に付随させ、電子化のスケール、投影法、各レイヤーの属性テーブル、ファイル形式、そしてレイヤーを準備するために利用したレイヤー仕様を含まなければならない。
21.ESRI株式会社系列の「Arc-Info」GISやマップ・インフォ株式会社の「MapInfo」GISが開発したもとの地域言語ファイル形式(ネイティブ・フォーマット)は、きわめて幅広く利用され、また多くのGISソフトにインポートして利用出来るようになってきた。
22.工業会のリーダーを含むGIS組織の大きなグループであるGIS標準化(オープン化)協会(OGC)は、地理情報技術界において現在互換性のない標準の問題に対処している。OGC発案の下におけるGISの標準化、互換性、そして相互運用可能性の進捗状況は、特記されるべきであり、また、ラムサール条約湿地の電子地図供給のためのGISファイル仕様の更新を準備するときに考慮されるであろう。
[英語原文:ラムサール条約事務局,2006.Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS) 2006-2008 version. http://ramsar.org/ris/key_ris.htm.
ならびに,ラムサール条約事務局,2006.「Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Wetlands of International Importance of the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971), Third edition, 2006」(http://ramsar.org/key_guide_list2006_e.htm)の添付文書A−Dをなす.]
[和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)所載の決議Ⅷ.13の2002年版RISの和訳に,第9回締約国会議の決議によって修正された部分を琵琶湖ラムサール研究会が仮訳し,英語原文に従って加筆修正した,2006年4月.環境省の第9回締約国会議の記録が刊行された時点でその日本語訳に整合するように再調整する予定.「水鳥個体数推計 Waterbird Population Estimates 第4版」についての情報を付加した,2007年4−5月.]
[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページにおおむね従い,同RISトップページ(☞ 英語原文)の記述(琵琶湖ラムサール研究会訳)をこのページのはじめに加えた.2006年5月に掲載された「国際的に重要な湿地のリスト拡充の戦略的枠組み,2006年版」の統合的な一部になるようにリンクを再構成した,2006年5月.]
 |
琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部● |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/key_ris_j.htm
Last update: 2007/05/22, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).