| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日
1.2003年後半以来、その地理的な発生範囲と毒性において、歴史上先例のない高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)(H5N1亜型)の発生が、家畜化された鳥類(主に家禽)の飼育に直結した農村の生計、及び自然保護上の価値(少なくとも3箇所のラムサール条約湿地における水鳥の大量死を含む)に多大な影響を及ぼしてきたことを認識し、またHPAIがユーラシア大陸を西に拡大するに伴い、HPAIが最近確認された国が増加しつつあることを意識し、
2.現在のHPAIの亜型が遺伝子再集合を起こすか、適応的に変異して人から人への感染が可能な型となった場合、ヒトインフルエンザの大流行がもたらす地球規模での人々の健康、社会及び経済への影響を強く意識し、
3.特に多くの国々において家畜化された鳥や野鳥が農村の生計基盤として重要であることに鑑み、今回のHPAIの伝播について十分な対応をとることについて、特に途上国が直面している困難に留意し、
4.しかしながら、現在までに知られているHPAIの株の人間へ感染について、今まで知られている症例はすべて、感染した家禽との接触あるいはその消費によるものであり、野鳥との接触によるものではないことに留意し、HPAI(H5N1亜型)の伝播に水鳥が関与しているかもしれないという懸念が、湿地保全、特にラムサール条約湿地や他の水鳥にとって国際的に重要な湿地に対する一般の人々の態度及び支援に、負の影響を与える可能性のあることを認識し、
5.HPAIは、家禽やその他の家畜化された鳥類、愛玩鳥の移動、そしてそれぞれの産業を補助する関連活動、合法及び非合法の鳥類の取引、渡りを行う水鳥等、数多くの異なる媒介者によって国々の間を広がってきたこと考えられることに留意し、これらの異なる伝染経路の相対的な重要性は異なっており、多くの事例でこれらの因果関係を示す証拠は弱いか、あるいは全く欠けていることを意識し、
6.国連食糧農業機関(FAO)、世界保健機関(WHO)及び世界動物保健機関(OIE)が、2005年5月の『高病原性鳥インフルエンザの積極的な制御のための世界戦略』の発行とその実施,とりわけ、「鳥インフルエンザの早期発見と予防のための緊急支援」という地域プログラムの実施を通じ、この問題に深く取り組んできたことを大いに歓迎し、
7.さらに、モニタリング体制及び緊急対策の構築等は、各国毎に決定されなければならないが、それらの策定に関し、国際協力による大きな利点があることについても再び留意し、
8.特にボン条約によって2005年8月後半に召集され、国連の4機関を含む9つの国際機関の代表やオブザーバーによって組織された「鳥インフルエンザ対策科学委員会」を始めとする、様々な調整機構へのラムサール条約の参画を認識し、また、アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定(AEWA)の「鳥インフルエンザ」に関する決議3.18にもまた留意し、
9.しかしながら、多くの国々で、HPAIの伝播、それがもたらしうるリスク、及びHPAIの大流行をどのように予測し、対応するかということに関連する重要事項の情報が著しく欠けており、また一般の誤解がある国もあることを大いに懸念し、
10.渡り鳥の渡りルート沿いにある比較的リスクの高い地域を特定することや、発生に対してとりうる政策手段に関する情報提供支援を行う際に、それらが果たしうる役割といった、現在のHPAIの広がりから考えうるシナリオを描く際に不可欠な情報源として、鳥類の移動や水鳥個体数調査に関する広範かつ長期的なデータ集とそれらを扱う専門家のネットワークがとりわけ重要であることを認識しつつ、そのようなデータとネットワーク、その他の情報を入手し分析すること、そしてこれらの要素を科学的に理解するために欠けている重要事項を埋めることが緊急に必要とされていることに留意し、
11.さらに、1997年の香港、2004年の日本におけるH5N1の発生、2003年のオランダ、ベルギー、ドイツにおけるH7N7の発生は、厳格な管理と生物安全保障の手段を用いることによって、すべて成功裡に撲滅されたが、今やアジアの一部地域では、HPAIは定着しているように見え、獣医学上の能力が限られている国における鳥インフルエンザの制御が実際上困難であることを浮き彫りにしていることを想起し、
12.HPAIのため、湿地及び水鳥個体群に関するモニタリングの行動及び計画が各国で進められていることを認識し、
13.リスク評価の実施・改善を行い、また水鳥保全の改善と将来的な鳥疾病発生の管理を進めるため、特に「鳥インフルエンザ対策科学委員会」によって特定された調査について、野鳥個体群における疾病の進行のみならず、水鳥の渡りや水鳥の取引に関する調査やモニタリングを強化する必要性、そして鳥類保全及び個体群の調整に関する情報が持つ潜在的な重要性に鑑み、これらの情報を速やかかつ継続的に共有する必要性に留意し、
14.さらに、動物福祉の観点から求められる事項と湿地センターや動物公園が湿地の広報、教育、普及啓発に果たす重要な役割に配慮しつつも、このような施設において、野生の水鳥と飼育下の鳥やその他の動物との間でHPAIが伝染する潜在的な危険性を認識し、
15.さらに、HPAIのリスク評価を含めた、広範囲の国家的及び国際的な保全政策に情報提供を行う手段として、特に「国際水鳥センサス」及びその成果、さらにはラムサール条約決議Ⅷ.38を通じて、水鳥個体群の長期的なモニタリング体制を構築するための長期的な資金提供の枠組を確立するよう、ラムサール条約等の支援を要請した「アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定」の決定(決議3.6)を意識し、
締約国会議は、
16.鳥類学、野生生物及び湿地管理の専門家と、獣医学、農学、ウイルス学、疫学そして医学の専門家を始めとした、これまで公衆衛生及び人畜共通感染症を管轄してきた部門とが連携して高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)に対処するよう、国家レベル及び国際的レベルの双方において、十分に統合された取り組みをするよう求める。
17.間引き等の殺傷手段により、野鳥個体群のHPAIを根絶させる方法は実施不可能であり、感染した鳥を分散させてしまうことにより問題を悪化させる恐れがあるというWHO、FAO及びOIEの結論を支持する。
18.家畜化された鳥と野鳥との接触を少なくする目的で湿地生息環境を破壊あるいは大規模に改変することは、条約第3条1項において強く要請されている賢明な利用にあてはまらないこと、また、感染した鳥のさらなる拡散を引き起こすことにより問題を悪化させる恐れがあることを強調する。
19.「鳥インフルエンザ対策科学委員会」の通信手段が、資源的かつ能力的に可能な限り、電子的なものであることに留意しつつ、条約が(科学技術検討委員会(STRP)および事務局の適切な代表者を通じて)この委員会に継続的に参画するよう要請する。
20.病気伝染の潜在的なリスクに対して、各国が緊急対策計画あるいは緊急行動計画を策定し、実施することが重要であること、そして鳥類、特に湿地に依存する種からHPAIが検出された場合に対する国家的な準備が必要であることを強調する。
21.条約事務局長に対して、条約の関心事項としてふさわしいモニタリング計画に対する長期的な資金提供の枠組の構築を支援できるようなパートナーシップの確立の可能性について、可能な限り早期に検討するよう要請する。
22.農業及び水産養殖業のための適切な基準を規定する必要性、また生物安全保障を強化することで野鳥と飼育下の鳥類との間の病気伝染のリスクを制限するための戦略を策定する必要性に留意する。
23.STRPに対して、「鳥インフルエンザ対策科学委員会」とともに、HPAIに関連する緊急対策及び湿地管理計画を策定している機関に対し、野鳥、飼育下の鳥、家畜化された鳥の間での病気伝染の危険性を減少させる実用的な手段に関する適切な情報を提供するよう強く要請する。
24.条約事務局に対して、STRPと協働しつつ、関係する国際機関及び「鳥インフルエンザ対策科学委員会」と共同して、この深刻かつ急速に展開しつつある状況に対処できるように各国を支援する実用的な助言を始めとする情報の共有について支援を行うとともに、常設委員会及びCOP10に進捗を報告するよう要請する。
[ PDF(167㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]
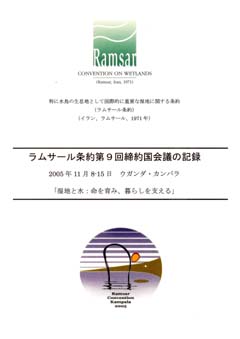 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.23.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.23.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_23_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).