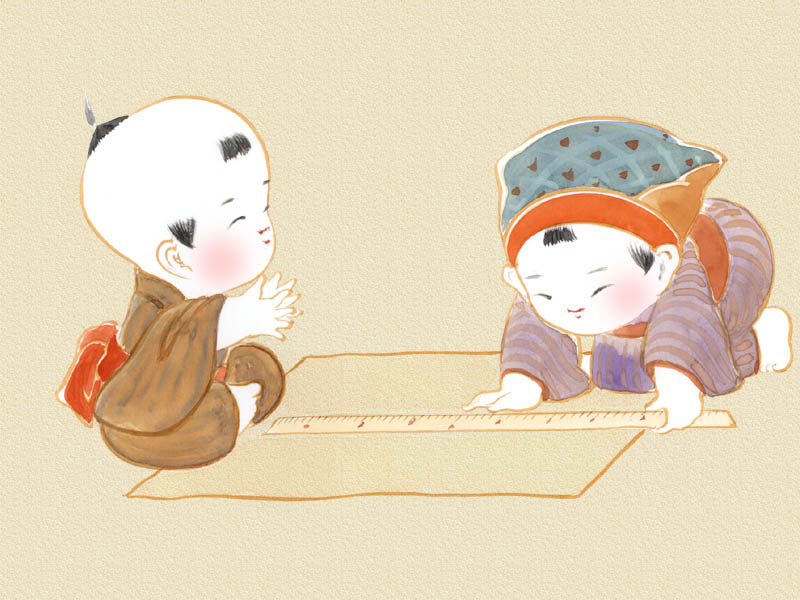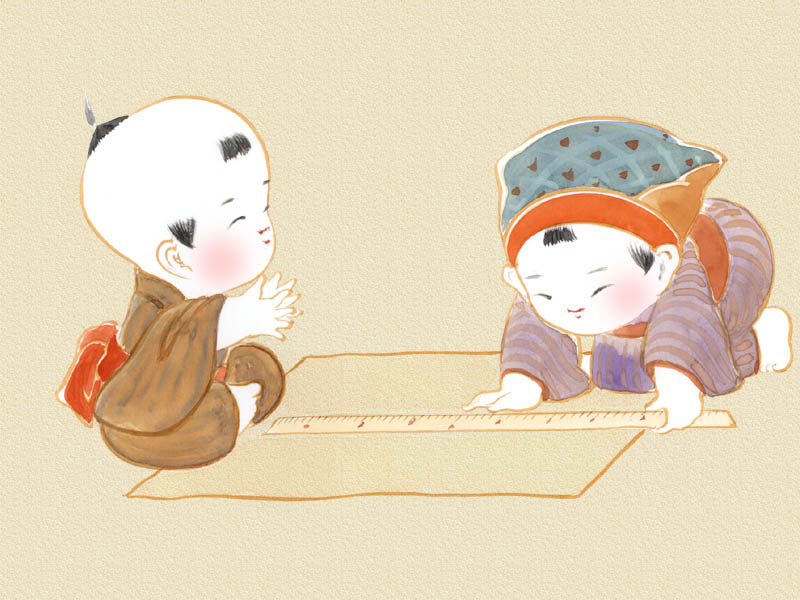
メートル法公布記念日 メートルほう こうふ きねんび
大正10年(1921)の4月11日に改正「度量衡法」が公布されて
日本も長さの単位にメートルを使用することが決まりました。
その日から今年でちょうど80年になります。
昭和41年の「計量法」でさらに厳しく尺貫法での定規や升は
禁止されますが、やはり日本人の生活に根ざした計測法は捨てがたく
作家の永六輔さんたちが尺貫法の復活を求める運動し、
「酒一升」や「土地坪単価」、和服の世界では「身丈四尺何寸」などの
単位は使われてきました。
和菓子の世界でも菓子折り何寸箱などと寸で言い表しています。
さて、メートルの起源はフランス革命だそうで「地球の子午線の赤道から
北極までの1000万分の1」と決めたのが最初です。
1879年、1メートルの基準となる白金製のメートル原器が作成されましたが
その後の計測で地球の子午線の赤道から北極までの距離が
標準器の1000万倍より長かったり、原器自体が変化を起こしていたりして
何だかメートル原器が意味を成さなくなってしまいました。
今のメートル定義は『1秒の2億9979万2458分の1の時間に、
光が真空を進む距離』となっています。
でもこの2億9979万2458分の1秒ってどんな時計が測るのでしょうね?
ちなみに私の小さなころは30センチメートルの定規は竹製でした。