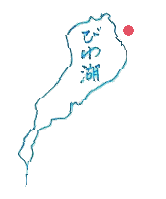 1.はじめに 平成2年(1990年)5月、韓国の盧泰愚(のてう)大統領が日本を訪 問しました。 歓迎の宮中晩餐会で、天皇陛下は「今後両国の相互理解が一層深まることを 希望する」旨のおことばを述べられました。
1.はじめに 平成2年(1990年)5月、韓国の盧泰愚(のてう)大統領が日本を訪 問しました。 歓迎の宮中晩餐会で、天皇陛下は「今後両国の相互理解が一層深まることを 希望する」旨のおことばを述べられました。盧泰愚大統領は、次のようなことを答 辞で述べられました。 「...二百七十年前、朝鮮との外交に たずさわった雨森芳洲は、<誠意と信義 の交際>を信条としたと伝えられます。 彼の相手役であった朝鮮の玄徳潤は、 東莱に誠信堂を建てて日本の使節をもて なしました...。」 ↑宮中晩餐会 雨森芳洲(あめのもりほうしゅう)は、滋賀県の北部、長浜市の北西に位 置する高月(たかつき)町の出身です。 高月町の「雨森芳洲庵」を訪ねてみました。 2.朝鮮通信使について 雨森芳洲を語る前に、朝鮮通信使について振り返ってみましょう。 1)日韓両国の相互訪問による交流は、室町幕府の第3代将軍足利義満のと きから始まったようです。(1404年に日本国王使を朝鮮に派遣) 2)徳川家康は天下を掌握した後、朝鮮との国交を回復し、朝鮮からの使節 団(将軍の襲職祝賀)を受け入れました。 3)使節団は、慶長12年(1607年)から文化8年(1811年)まで の200年余りの間に12回来日しました。 4)初めの3回は、秀吉が朝鮮出兵の折に連れてきた朝鮮人の返還交渉が含 まれていましたが、第4回(寛永13年・1636年)からは朝鮮通信使 と呼ばれました。(通信とは「信」を「通」じるの意)
5)朝鮮通信使一行は、300−500 人にのぼり、6ヶ月以上におよぶ大規 模の外交使節団でした。 6)使節団は、沿道各地の農民や町人に も歓迎され、朝鮮の面影を残した踊り や行列などが今日まで伝わっています。 ←通信使行列の再現風景(近江八幡市) 3.雨森芳洲庵 寛文8年(1668年)に生まれた雨森東五郎(雨森芳洲)は、第8次 (正徳元年・1711年)と第9次(享保4年・1719年)朝鮮通信使の 接待責任者を務めました。 朝鮮語と中国語に通じ、分別のあった芳洲は、通信使から高い信頼を寄せら れたようです。
芳洲を顕彰する「雨森芳洲庵」が、昭和 59年(1984年)、生地の高月町雨森 に建設されました。 当時の滋賀県知事だった武村正義さんは、 この事業を積極的に推進されたようです。 私の訪問した日(2005年12月20 日)は、私が住んでいる湖南の野洲市には 雪が積もっていませんでしたが、湖北の高 月町は雪におおわれていました。 ↓芳洲庵付近
芳洲庵は「東アジア交流ハウス 雨森芳洲庵」と記されています。 芳洲庵を建設したときのキャッチフレーズは、「湖北の村からアジアが見え る」だったそうです。 ↓芳洲庵前
↓入り口
↓芳洲庵内部
芳洲は信念を通した人でした。 新井白石の非を指摘したり、朝鮮の非を指摘したこともあったようです。 芳洲は61歳のとき、朝鮮外交の基本的な心構えを52項目に分け、「交 隣提醒」(こうりんていせい)として著しました。 その最終項「誠信の交(まじわり」で、「誠信と申し候は..互いに欺かず 争わず、真実を以って交わり..」と述べています。
通信使の正使は、大臣級の人だったよう です。 ←通信使の正使と副使 ↓雨森芳洲
高月町は、住民による町作りが大変熱心な地区です。 また国際交流にも熱心で、毎年韓国の中学生、高校生をホームステイで受け 入れているそうです。 私が初めて訪れたのは十数年前の夏でしたが、どの家の前にも花が一杯飾 られ、澄んだ水が流れている道路脇の水路には鯉が泳ぎ、水車が回っていま した。
私が特に感心したのは、道路脇の電柱 を各家の敷地に自費で移動させて道路の 景観を向上させた、ということでした。 ←水車の取り付け台 県主催「わがまちを美しくコンクール」で金賞、国土庁第1回「農村アメ ニティコンクール」優秀賞、全国花いっぱい協会「全国花いっぱいコンクー ル」最優秀賞、京都新聞社第1回「市民国際交流賞」など、多数受賞してお られるそうです。 4.朝鮮人街道 朝鮮通信使の使命は、将軍職の就任祝いであり、江戸城で朝鮮国王の国書 を伝達することでした。
使節団一行は江戸時代に12 回来日しましたが、そのうちの 10回は江戸まで行列を連ねま した。 ←朝鮮通信使の行程
朝鮮通信使は、近江では特 別の経路を通行しました。 野洲から鳥居本まで、中山 道から外れた道を進みました。 家康が上洛のときに通った道 だそうで、この道の行列が認 められたのは将軍と朝鮮通信 使だけだったそうです。 この道は、「朝鮮人街道」 と呼ばれています。 ↑近江の朝鮮人街道 通信使の彦根での宿舎は、彦根城のすぐ南にある宗安寺でした。 このあたりは数年前に観光客向けに整備され、キャッスルロードと名づけら れました。宗安寺はキャッスルロードに面しています。
←道路の石に刻まれた表示 ↓キャッスルロード
この宗安寺には、正門(赤門)の左に、黒門があります。 通信使を肉料理でもてなすためとはいえ、四足の獣肉をお寺の正門から運び 入れることははばかられたため、正門の脇にもうひとつの門を作ったのだそ うです。 ↓黒門 ↓赤門(正門)
通信使を迎えた幕府にとって、対馬から江戸まで、400人以上の使節団 一行を往復半年以上も接待するのは、当時の年間国家予算を上回るくらいの 出費を伴った大事業だったようです。 来年(2007年)は、江戸時代の朝鮮通信使を迎えてから400年目に なります。彦根市と静岡市では、記念事業を開催するようです。 (なお、通信使の呼称は、室町時代の延長元年:1428年から使われたそ うです。江戸時代の第1回使節団:1607年は、回答兼刷還使と呼ばれた ようです。) 余談: 「琵琶湖」という呼称はいつから使われているのでしょうか。 もしかしたら伊能忠敬(1745−1818)以降か、などと考えたことが ありましたが、もっと前から使われていたようです。 朝鮮通信使の製述官(記録係)が書き残した「海游録」という日本見聞記 (1719年当時)に、 「..行くこと六、七里にして、倭人が「琵琶湖です」と告げた。... 琵琶湖は、もともとその状が琵琶の如きゆえにこの名があり、また地が 近江州に属するをもって一名近江湖ともいう。..」 との記述があります。 5.おわりに 朝鮮との交渉には対馬藩があたりました。 雨森芳洲(1668−1755)は若い頃から対馬藩に出仕し、何度も釜山 に渡りました。88歳で対馬で亡くなりました。 江戸時代における朝鮮との交流は、通信使を受け入れただけではありませ ん。日本から朝鮮への使節団派遣も頻繁にありました。 釜山には草梁和館(1678年)という日本の商館兼在外公館が設けられ、 常時600人位の役人や商人が駐在していたそうです。敷地は10万坪で、 これは長崎のオランダ人商館の出島の25倍も広いものでした。 私は浅学にして、朝鮮通信使のみならず、日韓交流の歴史を最近まで知り ませんでした。日本に一番近い国との交流を考えるためには、まずは歴史の 理解が必要であると感じている次第です。 なお、私は朝鮮人街道の近くに住んでいます。 朝鮮人街道を、それと知らずに散策したことがありました。そのときの記事 もご参照ください。⇒妓王井川 (散策:2005年12月20日) (脱稿:2006年 1月26日) ------------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ 報告書メニューへ トップページへ
.jpg)