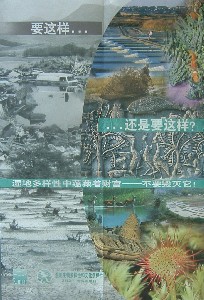世界湿地の日(ワールド・ウェットランド・デイ)を活用しよう
宮林 泰彦,琵琶湖ラムサール研究会(2006年8月)[追記:2012年7月]
[追記]2013年の世界湿地の日の主題は「湿地と水の管理 Wetlands and Water Management」です(SC42-34[条約事務局英文])。この主題は、2013年の国際水協力年 International Year of Water Cooperation (国際連合総会決議 A/RES/65/154[国際連合英文])にちなみ、湿地部門と水部門との協働に特に焦点を合わすものです。
要約ラムサール条約が1971年にイランのラムサールで締結されたのが2月2日でした.この日を記念して,毎年2月2日を「世界湿地の日 World Wetlands Day (WWD)」と定め,世界中で湿地を祝い,湿地の保全と賢明な利用を達成するための啓発の機会に活用するという取り組みが1997年から始まりました.その取り組みはこの日だけでなく,この日をはさんだ1週間を「世界湿地週間」としたり,2月ひと月を「世界湿地月間」としたり各国各地で工夫されています. 日本でも条約湿地各地でこの日の活用が進められています.これまで以上にこの日を活用して,各地の湿地の保全と賢明な利用を高め,また条約の使命である世界中の湿地の保全と賢明な利用に寄与するための取り組みが求められています. |
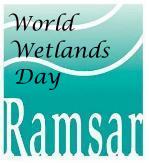
世界湿地の日(ワールド・ウェットランド・デイ,WWD)とは?
- *
- 条約事務局HPの WWD 英文ページ.
- *
- 解説:普及啓発プログラム,香川 裕之,2001年.
- *
- 2003−2008年CEPAプログラム,決議Ⅷ.31付属書和訳.
ラムサール条約が1971年にイランのラムサールで締結されたのが2月2日でした.この日を記念して,毎年2月2日を「世界湿地の日 World Wetlands Day (WWD)」と定め,世界中で湿地を祝い,湿地の保全と賢明な利用を達成するための啓発の機会に活用するという取り組みが1997年から始まりました.その取り組みはこの日だけでなく,この日をはさんだ1週間を「世界湿地週間」としたり,2月ひと月を「世界湿地月間」としたり各国各地で工夫されています.これは,1996年の第6回締約国会議(COP6)オーストラリアのブリズベンで採択された条約の「1997−2002年戦略計画」の行動3.1.6(決議Ⅵ.14)で正式に設定され,その次のCOP7(1999年コスタリカのサンホセ)の決議Ⅶ.9に採択された条約の「1999−2002普及啓発プログラム」にその取り組みが組み込まれました(そして続く2003−2008年の同プログラムにも引き継がれています).
条約事務局はこの取り組みを支援するために,ポスターやステッカー,あるいは資料などをつくって締約国に提供しています.ただ,それらは条約の公用語である英語と仏語および西語の3か国語で作成されるために日本で十分に活用するためには日本語化が必要です.国によっては資金を(条約以外から)独自に工面して,条約事務局より提供されたDTPファイルを加工して自国語のものをつくっているところもあります.
- [追記]
- その後の主題は次のとおりです(年度降順):
- 2013年
- 「湿地と水の管理」(予定)
- 2012年
- 「湿地とツーリズム」
- 2011年
- 「湿地と森林」
- 2010年
- 「湿地や生物多様性と気候変動」
- 2009年
- 「河川流域管理」
- 2008年
- 「健全な湿地、健康な人々」(に変更されました)
- [
- 上記のリンク先は,特定非営利活動法人 日本国際湿地保全連合による各年のテーマ紹介ページです.]
また毎年テーマやスローガンが設定され,必ずしもそれを採用する必要はありませんが,世界中でそれに沿った取り組みが推奨されています.
1998年「湿地のための水,水のための湿地」
1999年「人々と湿地−生命のつながり」
2000年「国際的に重要な湿地をたたえよう」
2001年「みなおそう!湿地の世界」
2002年「湿地:水,生命,そして文化」
2003年「湿地なくして水は無し」
2004年「山々から海まで,湿地の役割」
2005年「失なうな!湿地の豊かな多様性」
2006年「水なくして湿地無し,湿地なくして貧しい暮らし」
でした.
そして,これからについては,
2007年「湿地と漁業」(決定)
2008年「河川流域管理」(提案)
と,どちらかというと対象や目標を絞ったテーマが考えられているようです.
個々の湿地での取り組みの課題
日本でのこれまでの取り組み
日本の湿地ではこれまでどんな取り組みがされてきたのでしょうか.本稿執筆時点にインターネット上でたどることができる主要なものをリストしてみます:
- 琵琶湖ラムサール条約連絡協議会「琵琶湖一斉水鳥観察会」☞ 高島市のイベント情報:2007年2月の観察会案内.
- ラムサールセンターのアジア湿地ウィークの取り組み(日・中・韓・印・他)2003−2005年の報告 ☞ 同センター活動報告のページから;その英語版:2003年,2004年,2005年.
- 環境省から条約事務局への2006年の日本での活動の報告(英文).
- 宮城県内各地『ワールド・ウェットランド・デイ・in・みやぎ』,1997−2001年.
- *
- 条約事務局HPの2006年のWWD活動報告,英文ページ.
- [追記]
- 琵琶湖からの報告(年度降順):
- *
- 世界湿地の日を祝う in 湖北 2012 報告・同英文.
- *
- 世界湿地の日を祝う in 湖北(2011年2月24日)報告・同英文.
- *
- 第18回びわ湖一斉水鳥観察会,琵琶湖ラムサール条約連絡協議会会報 No.25(同協議会事務局 PDF 147KB).
- *
- 西の湖(滋賀県近江八幡市)における世界湿地の日2011の報告・同英文.
[参照]
- *
- 2007年のWWDテーマ「湿地と漁業」解説,原文:条約事務局,BRK和訳.
[参照]
- *
- 「CEPA行動計画づくり手引き」,原文:条約事務局,BRK和訳.
では,どんな取り組みがされているのでしょうか.条約事務局HPのWWDのページには,世界各国各地からその取り組みの報告が毎年まとめられています.それを見わたすと,観察会や野外授業,こどもたちの取り組みや研究成果・演劇などの発表会,シンポジウム,研修の機会やワークショップ,対話集会,植林,侵入種の除去作業など,さまざまな活動に取り組まれていることがわかります.
日本でも条約湿地各地でWWDの活用は進められています.一方で日本の条約湿地のようにいわゆる「湿地センター」をもつところでは教育や普及啓発の活動は年間を通じて実施されていることがふつうで,WWDだからなにか特別の取り組みをするという動機づけが大きくないのかもしれません.その結果として,また言語の問題もあり,条約事務局への報告は十分にされていないように思われます.
さて,2007年のWWDのテーマは,上記のように「湿地と漁業」と決まりました.またその翌2008年には「河川流域管理」が提案されています.2006年までのテーマ/スローガンとは少し趣きが変わったのではないでしょうか.条約事務局では2007年のテーマを紹介する文書をHPに掲載しています(左欄のリンクから和訳をどうぞご一読ください).それを読むと,2007年の取り組みでは,個々の湿地において持続可能な漁業をいかに達成するかをみんなで考えてほしいという条約からのメッセージが読み取れます.
筆者は水鳥が専門なので,この2007年のテーマを知ってはたと困ってしまいました.実はここがポイントかと思います.このテーマに取り組むためには,この分野に明るい人々の支援や参画が欠かせません.そして取り組みによってその湿地のさまざまな関係者の意識の向上が確実に図れるような企画を立てることが重要でしょう.また,催しにおいてガイドする方々がそのテーマについての研修する機会も必要でしょう.そのような企画・取り組みで無ければ,例えば「持続可能な漁業」といった目標を達成することは望み薄ではないでしょうか.
このように,多岐にわたる湿地の保全と賢明な利用の分野をカバーして普及啓発を進めてゆくためには,さまざまな分野の専門家や関係団体等の協力体制の確立が欠かせないわけです.その協働の場をつくりあげることが個々の湿地での重要な課題ではないでしょうか.WWDはそのような機会を提供してくれるでしょう.そのような場や協力体制ができれば,すでにできているのであれば,さらに自律的に個々の湿地がかかえる課題のそれぞれに対して計画的に普及啓発活動を企画してゆくことが期待されています(☞ 「CEPA行動計画づくり手引き」).その段階でもWWDは協力体制や取り組みをさらに発展させる機会として活用することができるに違いないと思います.
条約への報告を充実させよう
- *
- 環境省から条約事務局への2006年の日本での活動の報告(英文).
- *
- オーストラリア環境省のWWD活動報告のページ(英文).
前述のように条約はWWDの取り組みを条約事務局に報告することを要請しています.この解説文で海外の取り組みを参照したように,日本での取り組みも条約を通じて世界に報告し,しかして条約の使命である「世界中の湿地の保全と賢明な利用」に寄与することが(条約湿地では特に)求められているわけです.
2006年は環境省が国内のWWDの取り組みをまとめて条約事務局へ報告されました.2007年以降も各湿地での取り組みの報告を実施ののち速やかに届けて,条約事務局に報告してもらうように環境省へ要請することが一案です(そうすれば個々の湿地で報告を必ずしも英文化しなくてもよいかもしれません).
あるいはまた,例えば琵琶湖のように大きな湿地で複数の自治体や関係団体等が取り組みを進めるような場合であれば,各々の取り組みをまとめるページをどちらかの団体のウェブサイトに設けて,各団体の報告のページとリンクさせる.そしてそれらの英文化も行ない,環境省から条約事務局への報告にそのページへのリンクを組み入れてもらう,といったアレンジも可能でしょう.