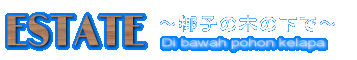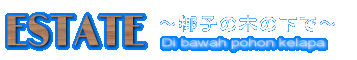|


「最 近物価の値上がりがすごいねぇ」
「いや まったくですね」
こういった会話は、僕がバリ島に移住して以来、絶えることなく交わされてきたものだが、ここ最近は特にそれを強く感じるようになってきた。
どの程度物価が上昇してきたかの一つの指標として、僕の愛車(ディーゼル)に入れる軽油を例にとってみると、移住当初の1998年3月頃は、当時のレートでの邦貨換算で¥10/リットルほどだったのが、今(2007年1月)は¥58/リットルだ。
全ての物価が軽油ほど上昇しているわけではないが、大部分の物流をトラックに頼るインドネシアでは、オイルの値上げが他の物価上昇を引張ってきたといえる。
我が家の食料品は、主に、スーパーマーケットで調達されることが多かったのだが、この物価高騰を受け、少しでも安く仕入れしようと、最近では自宅からバイクで10分ほどの中央市場に通うようにしている。
市場といっても4層のビルで、総面積は日本の中堅百貨店なみの広さがある。ここでは、食料品以外にも、衣類、生活雑貨、祭事グッズなど、バリ人として生活する必需品は全て揃う。
僕が訪れるのは主に食料品フロアだ。そこでは専門の食材を扱う1〜2坪の店が、所狭しと軒を並べている。
その中で圧巻なのは、やはり生鮮肉売り場だろう。まるで解体場だ。肉は冷蔵ガラスケースなどに陳列されているのではなく、店頭に生のままパーツ別に並べられているんだ。確かにその朝に屠殺された新鮮なものとはいえ、こんな暑い国でこんな売り方で大丈夫?とこちらが心配してしまう。臭いもちょっと勘弁して欲しい。肉売り場一帯に近づくと僕の呼吸も自然と浅くなりがちだ。
そこで販売する人は何故か100%おばさん。そのおばさんらが僕のリクエストに応えながら、マニキュアを塗った手で生で肉をつかみ、骨を断つべく出刃包丁を激しく振り下ろすさまには、いつも違和感を覚える。
なんだか女性の板前さんに寿司を握ってもらっているような。やはり肉屋のブッチャーは、白いビニールエプロンをしたちょっと小太りなおじさんが一番似合うと思うのだが。
そうこう独りで買い物をしていると、1分おきくらいに、空の籠を頭に乗せた女性が声をかけてくる。この食料品フロアの通路は、狭いところで50cmくらい、広くても1m強ほどなので、混雑時は前に進むのも大変なほどだ。だからスーパーのようにトロリーなどは使用され得ない。
そこで登場するのがこの「荷物運びおばさん」だ。
最初の頃は声をかけられても、このくらい自分で持てる、という思いと、扱い方(どの程度のチップ?)がわからなかったのでいつも断っていたのだが、ある時、持ちきれないほどの量になりそうだったので、やむ無くお願いしてみた。
僕の買い物の邪魔をしない程度の距離をキープし、その店での支払いが済むと、頭に載せている籠(直径約60cm)に自分でさっさと商品を入れて、また付いてきてくれる。その繰り返しだ。僕は両手を空けたままずっと買い物に集中できる。気の利いたおばさんになると、僕に買い物のアドバイスまでしてくれるんだ。
「それを探しているんだったら、あそこの店の方が良いものが揃っている」
「今は海が荒れているから魚は高い」
などなど。有難い事だ。
そして買い物が終わると、駐車場まで運んでくれて、そこでチップを渡して終了となる。チップの額は、荷物の量や拘束時間によっても様々だと思うが、僕は気が小さいせいか、いつもちょっと多めに渡してしまう。
と言っても日本円換算すれば、こんな小額でもいいの、ていう金額だ。
最初の頃は、華奢なおばさん(中にはおばあさんもいる)たちに、自分の荷物を持ってもらうなんて、と躊躇していたが、手伝ってもらってからは大変に便利なことがわかり、今ではほとんど毎回依頼するようになってしまった。

『スーパー』と『市場』の一番大きな違いは、「価格の違い」以上に「コミュニケーションの有無」ではないだろうか。
スーパーでの買い物のメリットは、掛値なしの定価なため、安心して買い物ができるということと、人と会話せずともトロリーに商品を入れ、レジに持ってさえいけば誰でも買い物ができる。
しかし、市場ではそうはいかない。価格交渉にはじまり、前出の「荷物持ちおばさん」など、会話無くしては買い物ができない。そこが楽しい事でもあり、また煩わしいところでもあるのだろう。
|

Back|Next
|
格安国際電話

インドネシアまで20円/分
ジャカルタなら11円/分
|