| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」
"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"
湿地条約(ラムサール,イラン,1971)
第9回締約国会議
ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日
1.内陸湿地、沿岸湿地、そして沿岸近くの海域湿地が、水生生物個体群と漁業資源を支える重要な役割を果たしていることを認識し、
2.漁業が世界中で社会的、文化的、経済的にも極めて重要なものであることを意識し、
3.漁業資源は数百万の人々にとって不可欠の食糧と収入源であり、これは貧困のさらなる削減を支援することができることを認識し、世界の多くの地域で、持続可能でない収獲、生息地の劣化、漁業資源の孵化場や稚魚の成育場ならびに採食と避難の場所の喪失などによって、漁業収量が減少しつつあることを「ミレニアム生態系評価」(MA)が報告したことを憂慮し、湿地の内部もしくは近隣において、さまざまに異なる漁業技術そして(捕獲から消費までの)関連活動が他の生物相に影響を及ぼす可能性に留意し、
4.漁業資源の損失と、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに地球規模で絶滅のおそれのある種[globally threatened]として記載される水生生物種の数が増加していることを憂慮し、いくつかの条約湿地が絶滅が危惧される[endangered]水生生物相の保全に果たす重要な役割を意識し、
5.多くの湿地において漁業資源に関して適切な科学的データが不足していることを意識し、
6.条約が採択した、湿地の保全と賢明な利用の河川流域管理への統合(決議Ⅶ.18)、同じく沿岸域管理への統合(決議Ⅷ.4)の手引きが、漁業資源が依存する湿地生態系の統合的管理を確保するために適切であることを想起し、
7.決議Ⅷ.2において締約国会議が「締約国に対して、可能かつ適切である場合には、ダムを通過する在来魚種などのための移動経路の維持に必要な手段を講じる」よう奨励していることを再び想起し、
8.生息地の再生、川の中の構造物を通過できるような魚道の設置、競合する侵略的な外来種の防除、持続可能でない水産養殖手段の規制、水質汚濁の影響の削減等を通じて、在来の水生生物種個体群及びその生息地の保全もしくは再生のための行動をとってきた締約国を賞賛し、
9.持続可能な漁業から蛋白質が供給され、それによって土地への農業の圧力が緩和され、また水質汚濁も削減できるといった、生態系のもたらす大きな恩恵があることに留意し、
10.水産養殖の広範囲な成長、漁業資源を増大させ環境コストを下げるというその潜在的な利益、また在来の水生生物種と湿地生態系に対する悪影響を避けるための綿密な計画策定と管理の必要性に再び留意し、
11.『責任ある漁業のための行動規範』(1995)とそれに続く一連の「技術ガイドライン」を国連食糧農業機関(FAO)が採択したこと、またこれらのガイドラインが持続可能な漁業資源の活用を推進する必要性と水産養殖手法の悪影響を緩和する必要性を認識していることを意識し、
12.国際水管理研究所(IWMI)が取り仕切る『農業における水管理の包括的評価(CA)』の進行中の業務と、湿地、捕獲漁業、また水産養殖の問題におけるその業務の妥当性を再び意識し、
13.ラムサール条約『2003−2008年戦略計画』の行動1.2.6が「ミレニアム生態系評価(MA)や他の評価プログラムからの情報を活用するなどして、条約湿地や他の湿地が水産業の存続にもたらす便益を評価」することを求め、「また『出来れば2015年までに枯渇する水産資源を持続可能な最大限の漁獲をもたらすレベルに維持、もしくは回復させる』という WSSD(持続可能な開発に関する世界首脳会議)の目標に貢献できる持続可能な管理の実践を推奨」していることを想起し、生物多様性条約(CBD)の内陸水及び沿岸海洋域の生物多様性に関する作業プログラムを再び想起し、
14.サンゴ礁は海洋生態系の中でも最も複雑で、種が豊富かつ生産的であり、海洋面積の1%以下しか占めていないのにも関わらず全ての海産魚種の3分の1のすみかであり、サンゴ礁漁業は毎年 600万トンの漁獲をもたらすと推定されており、世界の魚の生産の4分の1が発展途上国におけるサンゴ礁漁業であり、またサンゴ礁は海洋生物多様性のかなりの比率に生息地を提供していることを認識し、
15.マングローブ生態系は、沿岸の保護、栄養物と沈殿物の保持と二酸化炭素吸収源、様々な水生生物の成育場としてサンゴ礁や海草藻場など近接する生態系への特別な関連性、ならびにそれら近接の生態系の保護的な役割を含む、いくつもの環境的な恩恵/サービスを提供することを認識し、また、マングローブ生態系が付随する潮汐干潟や河口部と合わせて、漁業資源の供給源として沿岸地域の社会にとって重要であることを強調し、
16.FAOの『世界マングローブアトラス』によれば、漁業生産との関連にも関わらず、毎年1%の割合でマングローブ領域が破壊されているということを意識し、
17.海草藻場は、たくさんの海洋種の生活環の異なる段階において、産卵場、生息地、避難所としてきわめて重要であることを再び意識し、
18.これらの生態系が条約湿地リストに十分に指定されていないことを認識した決議Ⅷ.10を想起し、
19.WSSDの海洋保護区の設立に関する実施行動計画案、CBDの第7回締約国会議における海洋沿岸域の生物多様性に関する決定Ⅶ.5、CBDの保護区に関する作業計画(決定Ⅶ.28)、ならびに漁業管理に果たす海洋保護区の役割に関するFAO漁業委員会の最近の取組みを意識し、「保護地域のための国家計画」を通して、海洋沿岸域生息地および内陸水域において保護地域が十分に指定されていないことに緊急に対処する必要性があることに留意し、
20.ラムサール条約『2003−2008年戦略計画』の行動1.2.6の実施に際して、IUCN、WWF、及び世界魚類センターが提供した資金援助、ならびに水界資源と持続可能な漁業に関する彼らの支援と技術顧問としての役割に、満足しつつ留意し、「ラムサール技術報告書」として発行予定の「条約湿地と漁業維持に関する総説」の準備や、この決議に付属する、湿地及び漁業資源の保全と持続可能な利用に関する課題と勧告をまとめるにあたり、それらの団体が条約の科学技術検討委員会(STRP)と協力したことに重ねて留意し、そして
21.国際湿地保全連合とIUCNが、締約国や河川流域を扱う団体その他に対して淡水魚保全のための優先行動を助言しようとする「淡水魚専門家グループ」を組織したことに再び留意し、
締約国会議は、
22.本決議は、ラムサール条約の第1条に規定される湿地および同じく第2条1に規定される条約湿地における、内陸、沿岸、海洋域の漁業における問題を扱うものであることを確認する。
23.締約国に対して、条約湿地とその他の湿地における保全と賢明な利用に関連して、漁業資源の持続可能な利用に関する問題に対処する際に、適宜この決議に付属される勧告を適用するよう強く要請する。
24.締約国に対し、国家湿地政策に関する決議Ⅶ.6及び法制度の見直しに関する決議Ⅶ.7に沿って、政策の枠組みと制度措置を見直して、全国、地方から地元までの規模の条約実施の努力を、漁業管理当局や水界生物多様性の保護管理にかかる当局が意識して補完し支えることを保証できるようにすることを強く要請する。
25.条約湿地の内部や隣接区域における漁業あるいは条約湿地に関連する漁業を管理する責任を有する漁業当局に対して、関係する条約湿地の生態学的特徴の維持を、自らの活動を通して支えることを保証するよう要請する。
26.締約国に対して、空間的管理のアプローチを適宜導入することを含め、漁業による環境影響を緩和する管理施策の導入または継続を裏書きするため、条約のうち生息地と種の保全に関する条項を活用することを強く要請し、同じことを、関連団体に対して促す。また条約事務局に対して、生物多様性保全と自然資源の管理に関する他の条約や制度ならびに(FAOを含む国際的または条約地域レベルの)団体と協働して、漁業資源の保全と持続可能な管理に役立つ計画策定や管理のアプローチの相乗作用や連携、そしてCBDの目標やWSSDの最終目標及びミレニアム開発目標の達成に貢献するという認識を促進するように同じく強く要請する。
27.締約国に対して、関連パートナーと連携して、湿地に依存する漁業資源の目録作り、評価、またモニタリングに取り組むよう奨励する。
28.条約湿地の管理責任者に対して、管理計画策定に関する決議Ⅷ.14に沿って、持続可能な漁業を含む湿地生態系の恩恵/サービスを維持する施策を、自らの管理計画策定プロセスに組み入れるよう要請する。
29.締約国に対して、条約湿地と近接地域に関連する職人的なものを含む漁業の生態学的、社会経済的データ、及び水産養殖に関するデータを組織的に収集する国や地方のプログラムを見直し、また必要な場合には強化するよう要請する。
30.締約国に対して、水の配分に関する決議Ⅷ.1、統合的沿岸域管理に関する決議Ⅷ.4、またマングローブ生態系に関する決議Ⅷ.32に採択されたガイドラインを考慮した上で、水生生物相の移動経路を維持または回復させ、特定汚染源の影響を削減し全ての形態における汚染を希釈させ、水生生物相の保全を支える環境のための水流配分を確立し実施し、重要な産卵場と成育場を保護し、そして劣化した生息地を再生するために、各々の河川流域と沿岸域の統合的管理の枠組み内で必要な措置を取ることを強く要請する。
31.締約国に対し、FAOの1997年の『責任ある漁業のための行動規範』の条項及び関連する「責任ある漁業のための技術ガイドライン−養殖開発」、また「水産養殖開発のための2000年バンコク宣言及び戦略」(アジア太平洋養殖センターネットワーク(NACA)/FAO)を適用し、湿地の生態学的特徴の劣化を防ぐために、条約湿地や、条約湿地及び他の湿地に影響を及ぼす区域における、水産養殖手法(例えば養殖池や囲い養殖)を注意深く制御することを強く要請する。
32.各締約国に対して、潮間帯の湿地に関する決議Ⅶ.21に沿って、湿地に有害で持続可能でない水産養殖活動の促進も、そのための新たな養殖設備設置も、そのような活動の拡大も中止させるように、既存の政策と法律の施行を強化するよう極めて強く要請する。
33.マングローブ生態系が領域内にある締約国に対して、決議Ⅷ.32を考慮し、これらの生態系に対して有害な影響をもたらしている、あるいはもたらす可能性のある国家政策と戦略を検討して、適切な場合には修正すること、また人々の権利や利用及び伝統的慣習ならびに生物多様性の維持を認めて、人類へのこれらの生態系からの恩恵を保全及び再生する施策を実施すること、そしてこれらの生態系の維持のために条約地域規模ならびに地球規模の戦略に合意するように国際的なレベルで協力することも、同じく極めて強く要請する。
34.各締約国に対して、湿地の生態学的特徴を維持するために決議Ⅷ.18に沿って、水産養殖と熱帯魚飼育産業のための水生生物相の移入を規制する政策、法律、計画を見直すこと、例えばバラスト水を介する場合のような種の偶発的な移動を規制すること、侵略的外来生物種の移入を避けること、ならびに、既知の外来の侵略的な水生生物相(侵略的外来遺伝子を含む)の移入や蔓延を防ぐために必要な方策に着手することを、重ねて極めて強く要請する。
35.サンゴ礁や海草藻場及びそれらに付随する生態系が領域内にある各締約国に対して、効果的な保護区域の設置や、モニタリングプログラム、啓発プログラム、及びサンゴ礁や海草藻場及び付随する生態系の革新的な再生事業のための協力などを通して、これらの生態系を保護する国家施策を実施するよう強く要請する。
36.各締約国に対して、内陸、沿岸域及び海域の保護区域を、生物多様性保全と漁業資源管理のツールとして設置し、そのことが認知されるように、自国の保護区政策及び制度の範囲で必要な措置をとることを同じく強く要請する。
37.各締約国に対して、漁業資源の保全と持続可能な利用のために、政策や行動及びプログラムにおいて検討されるべき参加型管理の重要性を強調した決議Ⅷ.36の条項を考慮することを要請する。
38.条約事務局に対して、進行中の広報・教育・普及啓発(CEPA)活動、とりわけ「世界湿地の日」の記念行事や催しを通して、漁業資源の保全と持続可能な利用における湿地の重要な役割に注意を促すよう要請する。
39.条約事務局長に対して、漁業資源や資源保全と持続可能な利用に関わる世界魚類センターやFAOなどの専門機関や組織からラムサール条約が今後も助言を得てその任務を全うするために、これらの機関・組織と適切な協力を続行するよう要請する。
40.STRPに対して、湿地及びその持続可能な漁業との関連性に関して締約国にさらなる手引きを提供するために、ミレニアム生態系評価(MA)、「農業における水管理の包括的評価」(CA)、そして他の適切な評価の所見を考慮に入れて、この決議の付属文書をさらに練り上げる手段を検討するよう要請する。
41.締約国に対して、漁業者が環境にやさしい漁業技術及び関連活動の技術を容易に入手できるよう助けることを奨励する。
原注:以下の勧告は、条約第1条に規定される湿地、および同第2条1に規定される条約湿地における、内陸及び沿岸域の漁業における問題を扱う。
条約湿地か、条約湿地に影響を及ぼす区域での水産養殖手法(例えば養殖池や囲い養殖)は、注意深く制御されなければならない。具体的には、各国政府は、関連する国内の法律を施行し、また、国連食糧農業機関(FAO)の「責任ある漁業のための技術ガイドライン−養殖開発」(FAO 1997)の条項(条約の科学技術検討委員会(STRP)はガイドラインであるのか、ガイドラインと行動規範の両方かを確認すること)、そして「水産養殖開発のための2000年バンコク宣言及び戦略」(NACA/FAO 2000)を適用することが推奨される。
持続可能な水産養殖は、可能な場合には在来種や在来ゲノムを利用すること、そして化学物質の使用を最少限にすること、養殖のための新しい持続可能な技術の利用を優先課題とすることを通じて促進することができる。
条約湿地での持続可能な稲の栽培における漁業の意義がさらに探究され実証されなければならない。それによって「稲−魚」管理法のいっそう効率のよい組み合わせが可能になる。
稲とともに在来魚種を養殖し同時に化学物質の使用をできる限り減らすことを奨励することによって湿地保全を高めることができる。
それが適切な湿地では参加型管理をとることが奨励され、また参加型管理を阻むいかなる既存の法律や規制も改訂し、研究を支援し、また国際、国内、流域レベルで適切な管理体系を確立することによって促進しなければならない。
漁業の法律と規則は、資源管理方針をまとめる際の利害関係者の参加を促進するものでなければならない。
条約湿地その他の湿地では、まだ採用されていなければ、漁業利用を制御する措置を採用しなければならない。
適切な漁業技術の利用を通して混獲を最少限にするか防止するための措置をとるべきである。
生態学的損害を与える漁法や漁具(生息地の構造を著しく改変する、種の移動を妨げる、その他生態学的特徴を改変する活動も含まれることもある)が、条約湿地に影響を及ぼしている、あるいは影響を及ぼしかねない場合においては、それらの利用によって生じる条約湿地への損害という脅威に対処するための適切な行動をとらなければならない。
多くの内陸と沿岸の漁業は、定期的な放流プログラムに依存している。これらの放流プログラムでは、望ましくは原産の魚種かゲノムを用いるべきである。
締約国は、湿地内への外来もしくは侵入種の移入を、防止するか最少限にする効力のある法的手段やプログラムを採用することが推奨される。
国際海洋探査委員会(ICES)の「海洋生物の移入及び移動の実施規定」に類似の規定、ならびに地球環境ファシリティ(GEF)/国連開発計画(UNDP)/国際海事機関(IMO)による『船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約』が厳正に適用され、条約湿地が無計画な水生生物種の移入によって危機に陥ることのないようにすべきである。
放流プログラムが規制されないことによって生じるリスクを減少させるために、理にかなった手法が採用されるべきである。
ダムの建設や、河川水路での堤防建設、及び取水といった水流を改変する活動によって脅かされている全ての河川と関連する湿地における環境上の水流の評価には、漁業資源と漁業に関連する側面に具体的に注意を払うことが含まれていなければならない(決議Ⅷ.1と決議Ⅸ.1付属文書Cも参照)。
水界資源の他の利用者の活動がもたらす環境への悪影響を緩和するための戦略をまとめなければならない。そのような影響を与える利用がなくなった場所では、損傷した生態系の回復の可能性を探らなければならない(第8回締約国会議(COP8)決議Ⅷ.16を参照)。
漁業にとって重要なものとして選ばれた湿地に、保全や収獲のための公的な保護区を設立することを考慮しなければならない。
水界資源、特に漁業資源を保護するためには、必須資源をどのように分配すべきなのかについて全ての資源利用者の間で交渉するような仕組みを、地域、国、及び国際的なレベルで、適宜確立しなければならない。競合する利用者の間の対立の解決にはこのような仕組みが必要である。
漁業を含む湿地の管理と保全に関わる多様な部門の問題に関する相互理解を促進するために、条約の広報・教育・普及啓発(CEPA)プログラムのもとで、研修プログラムを実施すべきである。
地域社会における普及活動、野生生物のモニタリング、行動規範、履修や教育、意識向上など、それ自体で動機付けできるような取り組みを、条約湿地内や隣接域で、あるいは条約湿地内に影響を与える方法で漁業を行なっている地域社会の中に育成すべきである。
国境をまたぐ河川や、沿岸域の潟湖や礁湖、海域、湖沼などで漁業が有意に伴うところでは、関係する国々が、水界資源及び特に漁業に関して、研究、情報共有、そして管理のための共通の仕組みの確立が図るべきである。できれば、そのような仕組みは既存の制度に組み入れられるべきだが、そのような制度が存在しない場合は、それらが確立されるような措置をとらなければならない。
『責任ある漁業のための行動規範』(FAO 1995)とその様々な「技術ガイドライン」を、海域及び淡水域における漁業及び養殖を規制する際の指導原則として採用すべきである。この「技術ガイドライン [訳注]」は以下の範囲を扱っている:1巻「漁業実施手法」(1996年)、2巻「捕獲漁業と種の移入に関する予防原則に基づくアプローチ」(1996年)、3巻「沿岸域管理への漁業の統合」(1996年)、4巻「漁業管理」(1997年)、5巻「養殖開発」(1997年)、5巻補足1「養殖開発:良質な水産養殖飼料生産法」(2001年)、6巻「内水漁業」(1997年)、7巻「海洋捕獲漁業の持続可能な発展のための指標」(1999年)、8巻「責任ある魚の利用」(1998年)、9巻「違法、未報告、未規制の漁業を防止し、阻止し、除去するための国際行動計画の実施」(2002年)、及び10巻「漁業への生態系アプローチ」。
特に条約湿地に関連した、漁業と水生生物相保全のための管理戦略は、決議Ⅸ.1付属文書Bによる改訂版の「国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」(決議Ⅶ.11)による基準2の適用に従い、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)」の付属書Ⅰに記載されている絶滅危惧種を考慮すべきである。
条約湿地と付随する区域における漁業データの体系的な収集のための全国的及び地方ごとのプログラムを開始し、または補強するべきである。そこには最小限でも、漁獲重量と規模、漁業者の数と作業量、及び漁業の社会経済的側面が含まれていなければならない。
魚類個体群にとって国際的に重要な湿地の地球規模のネットワークを完成させるために、特に基準7もしくは8による条約湿地をまだ指定していない締約国は追加の条約湿地を指定すべきである。
原注:
1.『漁業資源』は、魚類、甲殻類、軟体動物、藻類を指す。
2.ミレニアム生態系評価(MA)は、「捕獲漁業と淡水という二つの生態系サービスの利用の仕方は、将来においてはもとより現在の需要においても持続可能なレベルをはるかに超えている。重要な商業的漁業資源量の少なくとも4分の1は過剰捕獲されている(確実性は高い)。利用可能な資源のありとあらゆる部分をも利用しようとすることによって、人類は1980年代まで海洋魚類の捕獲を増やしてきた。この資源の過剰利用の結果、今や海洋魚類の水揚げは減少している。貧しい人々に対し高品質の食糧を提供する面で特に重要な内水面漁業もまた、生息地の改変、漁獲過多、取水によって減少しつつある」と重要な指摘をしている。(Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC)。
[ PDF(240㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]
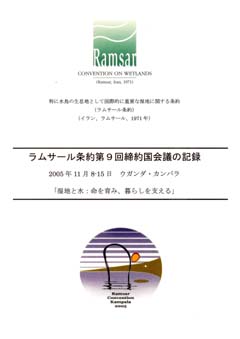 「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.04.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この決議のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.04.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]
| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |
URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_04_j.htm
Last update: 2008/06/01, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).