

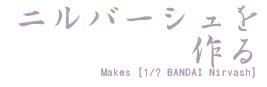
| 第五回 リフボードの製作に入ります。 前回が足で何で今回いきなりリフボードに移ったかというと、単にデカくて作りでがありそうだったからです。特に理由はありません。行き当たりバッタリ万歳。 組み立て的にはまったく面白いところはありません。ディテールアップに関しては中心部の接続部の削り込みのみ。ただ、リフボードに乗せる気がなければ固定用のピンホールをパテなりプラ板なりで埋める必要があります。 今回割と悲しい事が怒りました。泣きそうです。 |
| 9 リフボードの作成 |
| 組み立てについては特に書く事はありません。リフボードのパーツは全部で四つ。基本どおり接着剤たっぷり塗って、くっつけて、完全乾燥させた後削って合わせ目を消して完成です。以上。 ただ、真ん中の接続部分の合わせ目の処理について書いておきます。
リフボードはパーツを左右対称のパーツを真ん中で合体させて一枚のボードになる設計なので、どうしても真ん中にしわが寄ります。表面はたいしてパーツ同士の段差はありませんが、裏面は割と大きな段差が出来ていました。 よって、パテで段差を左右で合わせます。上の写真の灰色の部分は段差を修正した部分です。灰色はパテです。段差が無くなったら罫書き線をPカッターで弾き直して修正してください。表面の三つの彫り込みは足パーツときと同じくリューターで削り込んでます。
古いサーフェーサーがあったので薄めて使う事にしました。こいつが、今回かなり悲惨な結果をもたらしてくれました。が、それはともかくパーツにサフを吹いて小傷消しと塗装の下地作りをします。
サーフェーサーを吹き付けて傷も段差もなく美しい仕上がりになりました。満足! これに塗装をしていきます。 大ざっぱに言ってリフボードの色は「白・赤・黒・緑」です。効率よく作業するために最初に塗る順番を考えます。 まず下地として白 次に赤。これは面積が広いからではなく、赤色は透過率が高く、下地の色に大きく左右されるためです。綺麗な赤色を塗るためには白・薄い灰色。もしくは黒(かなり厚く塗る必要がありますが…)で行う必要があります。素材色が赤色でも問題ないと思います。 次に黒と緑です。何とでもなる色ですから。
下地の白を塗るには何の考えも必要ありません。ただ、すべて平坦になるようにまんべんなく塗って下さい。それだけです。 赤色からは塗り分けが必要になるのでマスキングをします。幅広のマスキングテープを短冊状にきり、細かい縁のマスキングに使います。それ以外の大まかな部分はマスキングシートを使って一気にマスクします。縁部分のテーピングをちゃんとしておかないと隙間から塗料が入り込みますので爪楊枝や綿棒などを使ってしっかり付けておきましょう。 終わったら一気に吹き付け作業です。
ここである事実が判明します。さっき使った古いサーフェーサーなのですが、どうも腐っていたようです。マスキングテープを剥がすと、べりべりとクリスピーな手触りとともにパーツから剥がれ落ちました。ポロポロと
写真は別のパーツですが、こんな風にポロポロと下地材ごと塗料が落ちます。困った事にすべてのパーツにすでにサフ拭きをしており後戻りが効かない。泣きそうです。 シンナーで落とす手てもあるのでしょうが、運悪くそこかしこにパテを使っているので、シンナーでパテ部が溶けるのでその手は使えません。これは辛い… ここで作業を停滞させるとやる気がなくなるので、とりあえず作業を無理矢理進める事にしました。しかし、ポロポロ崩れます。マスキングで下地材が崩れるのは、いったん肌に密着させて粘着力を弱めてから張る事で解決することにしました。とはいえ気を抜くと剥がれるので完全な解決とは言いませんが…
無理矢理作業を続けてますが、罫描き線の着色については、エナメル系塗料を使用します。ここで単純に黒を薄めて流し込んでも良いのですが、色的に面白味に欠けますので青色(フラットブルー)を薄めて使いました。ベース色の赤の対比色なので割と栄えます |
| 10 リカバリー |
僕はチャットやよそ見しながら色塗ったりするので色々なミスをします。だから慌ててリカバリーをするハメになります。 パテが知らないうちに固まってたとかならリカバリーも楽なのですが、上記のように筆からボタって塗料が落ちたりするとかなり凹みます。ボタって… 塗料は乾くと膜になるので当然リカバリーポイントには段差が生まれます。この上から吹きつけをしても、この段差ごと新しい膜でカバーする事になります。そこで1500〜2000番程度の細めの紙ヤスリでいったん元の塗装ごと薄く削って平坦にしてしまいます。 その上から少し厚めに吹き付けて乾いてからまた平坦になるように削るとリカバリー終了です
作例
|