|
||||||||||||||||||||||||||
| か | ||||||||||||||||||||||||||
| かいえすち(戒会須知) | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| かいき(戒記) |
||||||||||||||||||||||||||
| かいき(開基) | ||||||||||||||||||||||||||
| 寺院建立の発願者をいう。 因みに黄檗山万福寺の開基は江戸幕府第四代将軍・徳川家綱公である。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かいきょう(戒経) | ||||||||||||||||||||||||||
| 弘戒法儀のこと。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かいさんしょうき(開山祥忌) 宗門でいうところの開山祥忌はいうまでもなく、宗祖・隠元禅師のご命日法要で、示寂された四月三日に実施される。他の臨済宗各派では毎齊忌と呼ばれている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かいさんどう(開山堂) |
||||||||||||||||||||||||||
| 万福寺にあっては開山隠元禅師を、末寺にあっては当該寺院の開山をお祀りするお堂をいう。 万福寺開山堂は南向重層瓦葺。延宝3(1675)年創立。 開山(宗祖)隠元禅師の尊像を奉祀し、塔頭寺院が交替制で管理することとなっている。 堂内正面の梁には、各天皇から下賜された国師号が額にして掲出されている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かいさんどう・くりあげのひも(開山堂繰り上げの紐) |
||||||||||||||||||||||||||
| かいさんはつとう(開山髪塔) 宗祖・隠元禅師の遺髪塔。 滋賀県彦根市旧景徳寺境内の一角に建てられている。 高さ約二メートル。 石碑正面には「開山大光普照國師琦老和尚髪塔」と彫られていることから、宗祖の國師号授与が公にされた以降に建立されたものであろうが、その由緒は不明である。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かいし(戒子) 授戒を受ける人、即ち受戒者のこと。 黄檗派が三壇戒会を始めるまでは授戒は僧侶となろうとする者が受けるべきものとされていたから、戒子は僧侶に限定されていたが、黄檗派が挙行した戒会は、僧俗分け隔て無く実施したことから、一般人も含んでいる。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かいちょう(戒牒) 授戒を受けた戒子(→)に受戒証明として渡される証明書。 中には、過去七仏以降、戒子までの伝法系譜を記したもの、授戒役位名を記したもの、得戒阿闍梨の詩偈等が入っている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かいちんだいこ(開静(枕)太鼓) | ||||||||||||||||||||||||||
| まさに就寝を促す合図である。 黄檗山では毎正21時、禅堂接版七・六・七(しちろくしち。→)の後に打ち鳴らされ、三十分にも及ぶ長いものである。 その敲き方は、「七五三の刻み打ち(→)」と称され、七ツ、五ツ、三ツを基調としたもので、どちらかというと陣中における触れ太鼓を想起させる。 この敲き方は、後に祇園祭りの囃子や小倉祭り太鼓に採用されたというし、山鹿流の陣太鼓(→)に採用されたと言うが、果たして・・・・・・?。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かいぱん(魚梆、開板) | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄檗山のシンボルのように扱われた木製の大きな魚。 木魚(→)の原型とされ、一本の丸太を魚形に彫刻し、側面を敲いて音が鳴るように胴をくり抜いた鳴り物法器。黄檗山のそれは一見鯉を連想させる姿をしている。 右下の写真は、長崎・興福寺の開板であるが、雌雄があって、雄の頭部は龍のようにも見えるが、雌は普通の魚姿をしている。 製作者によって、あるいは、地方や寺院によって姿、形が違うのがおもしろい。 ところで、開板は、行事や儀式、または法会の刻限を報せるための法具(法要に使用される道具)として使用され、食事の時間前に鳴らされるなど、山内での時計の役割を果たしている。上図は清規に記載された当初のもので飯梆と記載れているが、魚梆と書かれている書物もある。 ただ、今日では呼称に文字を合わせて開板と記すことが多い。 |
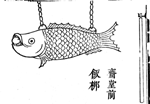 ↑ 清規に書かれた 開板と現物(右 |
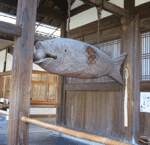 ↑ 現在の黄檗山の 魚梆(開板) |
||||||||||||||||||||||||
| その姿は魚が珠を口に喰わえて泳ぐ姿に見えるが、その実は逆で、魚は、この珠を今まさに吐き出そうとしている姿を表しているとされる。 つまり珠は、人にとって忌むべき、貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)の三毒になぞらえられている。 また、魚は夜も目を開けていることから、それを見習って修行するようにと諭すために、法器として使用されたとも言われている。 魚の形も、国や地域によって異なり、頭部は龍、胴体は魚と想われるような形から、まさしく魚と思われる形まで様々である。使用方法は、太さ7~9㎝の長い棒で、粥座(斎座)前の一声(一時間半前)、二声(一時間前)、三声(30分前)と30分間隔で一回ずつ敲き、棒を置く位置も定められている。 粥座半時間前の三声は一回敲いた後、析を三回打ち鳴らす。 粥座の時間になると、「打ち上げ(→)」と言い、一打ちした後、開板前に設置された石槻(→)と呼ばれる石を棒でガツンと敲く。 この音で禅堂の前門が開けられる。 門の開かれる音を確認して、開板が二回敲かれ、打ち上げ完了となる。 このように開板の敲き方と棒の置き方で、山内の僧には時間が分かる様になっている。 なお、現在の黄檗山の開板は三代目で、宗祖三百年遠忌を記念して新調されたものである。 色も当初の黒色から赤茶色に、現在は木質の生地そのままの色に変わってきている。 なお、現在および先代は鯉のように見えるが、初期の型は不明である。 一般には、龍の頭部に似せたものが多かったようである。 今日、木魚(→) と呼ばれ一般家庭で使用されている法具は、この開板を小型化したものと言われている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| がきだん(餓鬼壇) |
||||||||||||||||||||||||||
| かくしょうえ(鶴裳衣) 宗門衣の種類。 あたかも鶴の羽根をかたどったように袖が羽根を広げたように丸くなり、縁を墨色でふちどっていることからこの名称がある。 売茶翁が好んで着用していたとされ、茶会用、道中衣として用いられているが、最近では見かけることが少なくなってきた。 また、他宗では見かけない。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かくしょうえんみょうこくし(覚性円明国師) |
||||||||||||||||||||||||||
| 文政6(1823)年、隠元禅師の百五十回忌に際し、仁孝天皇から禅師に贈られた謚号(しごう→)。 唐韻読みは、「キョシンエンミンコースー」。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かこうぞうばん(嘉興蔵版) |
||||||||||||||||||||||||||
| 宗祖が渡来時に帯来された明版一切経の種類をいう。 宗祖は、鉄眼が一切経の開刻を発願したことを木庵から聞き、大いに喜ばれ本人に偈と共に直接与えられたという。 鉄眼は一切経の開刻に当たり、この経典をそのまま底本(→)としたことから今日残ってはいないが、こんにちなお印刷されている鉄眼一切経は嘉興藏版大蔵経そのままといえる。(→鉄眼一切経) |
||||||||||||||||||||||||||
| かこうだいし(華光大士) |
||||||||||||||||||||||||||
| 昭和47(1972)年、隠元禅師三百年遠忌に際し、昭和天皇から禅師へ贈られた謚号(→)。 唐韻読みは、「ファーカンダースー」 |
||||||||||||||||||||||||||
| かこうぼさつ(華光菩薩) | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄檗山伽藍堂に祭祀されていることから伽藍聖衆菩薩と呼ばれている仏像。 この像は三ツ目で、髭はなく文官風の衣をまとい、手には「金磚(きんせん)」という投擲用の三角形の武器を持っている。 中国の元、明時代に信仰された道教の「華光神」と同一視されているが、民間では仏教神として意識されていたようで、「西遊記」(第96回)には、三蔵法師が『華光菩薩は火炎光仏の徒弟である。しかし毒火鬼王を殺した罪により、職を下ろされ、五顕霊官となられたのである。』と言う下りがある。 今日、中国国内でも広東地方を除いてはほとんど見られず、この像は、明末の中国信仰の姿を今日に伝える重要なものであるとともに、黄檗山ならではの仏像と言いうることが出来よう。 →〔二階堂義弘著「万福寺伽藍堂の華光菩薩像について」文華122号〕 なお、筆者の調査では、宗門系寺院数ヶ寺にもこの像が遺されていることが判明している。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ↑ 黄檗山伽藍堂に安置された華光菩薩 額の真ん中に目があるのが分かる。(右写真) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| かしましんでん・ごせんごくかいはつ(加島新田五千石開発) 鉄牛禅師が推奨した社会事業。 富士川下流のデルタ地帯は地勢上治水対策の難しい地帯であったことから、古郡(ふるこおり)重高(しげたか)は新田開発に着手した。 度重なる洪水で工事は難航し、結局、長男の重政に引き継がれ、正保2(1645)年頃、既に一部の完成を見るに到ったものの、難工事のため、重政の代でも全てを完成するには到らなかった。 このため、工事を引き継いだ重政の次男・重年は椿沼の干拓事業を完成させた鉄牛の指導協力を得、その助力によって工事が完成され、五千石の美田をみることとなった。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かたんえ(華誕会) 在住の住持の誕生日をお祝いする日で、本山では、山内の僧が祝聖の諷経を行う。 最近では、住持から、お礼の紅白饅頭が本院の職員に配られる。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かちょうでん(華頂伝) 施餓鬼法要の伝授の一種で主として、江州地方の中で使われた言葉。 華頂如秀が一派に伝えた法要方法といわれる。 密印等の所作が大ぶりで派手だったといわれている。 これに対して観輪行乗が伝えた伝授法を観輪伝(→)と言う。 |
||||||||||||||||||||||||||
| がっさんしょう(合山鐘) | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄檗山内の鼓楼(ころう)から開山堂につながる廻廊(新廊下)の途中にある釣鐘のこと。 鐘楼の釣鐘は戦時中に供出されてしまったが、この合山鐘は宗祖・隠元禅師の銘が入っていたことから供出を免れたと言われている。 毎月三日の開山忌、法皇忌等、開山堂で実施される法要時だけに鳴らされる。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かはん(火版) | ||||||||||||||||||||||||||
| 雲版(→)の別称。 今日ではこの名称を用いることは皆無であり、また知る人すらなくなりつつある。 粥を炊くとき、煮え立ってきた時にすぐに火を引き、雲版を三打するところからこの名称が生まれたという。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かべい(花米) 落慶法要等の演浄儀で播かれる洗米に花片を混ぜたもの。 散華と同様の意味合いを持つ。 |
||||||||||||||||||||||||||
| がまん(賀饅) お祝いの紅白鏡餅のこと。 住寺晋山式等に壽位の間に供えられる。 |
||||||||||||||||||||||||||
| からもん(唐門) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総門(漢門とも称する。→)のこと。 中国の牌楼(ぱいろう)形式(中国の伝統的建築様式の門)を取り込み、我が国にない様式の門であることから明治期頃まではこの名称で呼ばれていたようである。 |
||||||||||||||||||||||||||
| からようさん(唐様桟) | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国風障子の桟のこと。 と言っても、特に障子の桟の様式そのものが日本のそれと大きく異なるわけではない。 違いは、障子そのものの嵌め方そのことにある。 我が国では桟の側を部屋の内側に向けて嵌めるが、中国の建築物では、これとは逆方向に嵌める。 つまり唐様桟とは、部屋の外側に向けられた障子の桟のことを指すのである。 ところで、ここからが重要である。 大切なことは、この障子の嵌め方が何故起こるのかということである。 実は、日本文化は家の中から外を見ると言うことに主眼を置いているのである。 これに対して中国文化は、外から家を見る方に主眼が置かれていると言うことに気づかされる。 つまり、日本と中国とでは視点がまったく異なるのである。 「似て非なり」という言葉があるが、日本文化と中国文化は、正に正反対の側面を持っているのである。 黄檗山を見学する場合は、この様な点にも留意しながら見学していただけるとより妙味があるでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||
| がらんどう(伽藍堂) | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄檗山伽藍の一宇。 重要文化財。 寛文8(1668)年創立。 北向単層瓦葺。 伽藍とは僧房(修行僧の道場)のことで、その守護佛をお守りするお堂のこと。 本尊は、伽藍聖衆菩薩(華光菩薩)、左右に三面大黒天(福の神)、弁財天(健康の神)を祀り、合わせ関帝像を併祀している。 |
||||||||||||||||||||||||||
| がりょうあん(臥龍庵) | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄檗山専門道場(禅堂)の寮舎。 昭和55(1980)年12月20日竣工。 総工費1,090万円。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かわぐち えかい(河口慧海) | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本人として初めてチベットへ単独入国し、多くの仏典を持ち帰るなど優れた業績を残した元檗僧(後、還俗)。 本名・河口定治郎。慶応2(1866)年1月12日、堺市の樽桶職人の子として生まれる。 15才の時に釈尊伝を読み発心し、明治17(1884)年、18歳で大阪北区にある黄檗宗正徳寺の佐伯蓬山禅師に師事した。 明治21(1888)年、哲学館(現・東洋大学)に入学後、25才で五百羅漢寺の海野(うんの)希禅禅師から得度を受け、慧海仁廣(えかいじんこう)と名乗る。 明治30(1897)年インドに渡りチベット語を学んだあと、ネパールを経由して鎖国状態のチベットに渡り未踏の調査を行った。 実に、日本人として初めての快挙であった。明治33(1900)年にラサに到着したが、国籍が発覚し37年に出国、翌年「西蔵旅行記」を上梓した。大正3(1914)年には、再度チベットへ入国している。帰国後、大正5年に東洋大学講師として勤務し、大正10 (1921)年2月に黄檗宗を最終離脱。 大正15年からは還俗宣言をし、大正大学講師となっているが、昭和20 (1945)年2月24日、80才で亡くなるまで慧海の僧名で通した。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かんがくいん・がくもんしょ(勧学院学問所) | ||||||||||||||||||||||||||
| 了翁道覚禅師が55才の時の貞享元(1684)年に江戸不忍に建てた学問所(五間×八間)。 その後講師の居室に宛てるために客院(四間×八間)を、さらには文庫(二間×三間)として2棟を建てている。 天台宗の碩学を迎えて講師とし、午前は内典を、午後は外典を講ずることになっていたという。 これら施設の維持や講師の賄い費用として白金1,980両を積み立て準備していたうえに、それまでに蒐集していた群書類三万余巻をも備え自由な閲覧に供したという。 遠近にかかわらず、学び来る者600人を超えたという。 実に現在の大学、あるいは図書館のはしりといえる。 →〔吉永卯太郎著・黄檗の了翁「黄檗の話(五)」〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| かんがくや(勧学屋) | ||||||||||||||||||||||||||
| 了翁道覚禅師が売り出した錦袋圓(きんたいえん。→)という薬を販売した店舗名。 「江戸名所図絵」巻五には店舗図(下図)が掲載されているが、独特な構造であったことが知られる。 残念ながら関東大震災で被災し、消滅した。→〔川瀬信雄著「名僧・了翁禅師伝」、「江戸賣薬志」〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| かんげしょ(貫華處) | ||||||||||||||||||||||||||
| 鉄眼禅師一切経の印房に掛けられた黄檗二代木庵禅師揮毫による額字。 「貫華」とは多くの花を糸で貫いて花輪を作るのに似て、言葉で一切の理議を貫き散逸することの無いようにすること、つまりお経のことであるが、その経典を繙くところ、印刷する大切な所との意を込めて書かれたもの。 現在は、塔頭宝蔵院本堂に懸けられている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かんざんなみ(関山浪) | ||||||||||||||||||||||||||
| 二度までも妙心寺住持を務めた龍谿性潜禅師が、袂を分かつ形で、隠元禅師の弟子となったことは、妙心寺派の僧にとって耐え耐えられないことであった。 しかも万治二(一六五九)年九月十二日には妙心寺開山である関山慧玄禅師の三百年遠忌を迎えていたが、その僅か三ヶ月前の六月には、幕府は、隠元禅師に宇治に寺地を与える旨通知していたのである。 この時妙心寺住持を務めていたのは愚堂東寔禅師であるが、彼ならずとも妙心寺派の多くの僧にとっては苦々しい事であったことは容易に推察できる。 その後も、龍谿禅師は、黄檗山萬福寺の建立に奔走し、黄檗派の中核として活躍している。 しかし禅師は妙心寺派離脱、ほぼ十年後の延宝八(一六七〇)年八月二十三日、滞在する九島院(きゆうとういん。現・大阪市西区本田三丁目四─十八)での開堂法要中、台風来襲による大津波が押し寄せ、禅師はそのまま不動端座され海水中に入寂された。 これを知った妙心寺派の多くの僧は、禅師を襲った津波に開山・関山禅師の名を付け「関山浪」と称したという。(→九条の人柱) |
||||||||||||||||||||||||||
| かんしゅうさぶく・ねんぶつずせつ(勧修作福念仏図説) | ||||||||||||||||||||||||||
| 黄檗第四代・獨湛性瑩禅師が住持をした獅子林院に於いて版行した念仏奨励のための木版刷り説明図。 中央には獨湛禅師の自筆と伝えられる阿弥陀如来図が描かれ、蓮台の上の空白欄に念仏者の声明を記載するようになっている。 また如来図の左右には趣旨説明が書かれている。 図全体のまわりには数多くの○印がつらねられていて、記載された説明文によると、念仏千唱毎に、青黄赤白黒の色をもって塗りつぶしていくのだとのこと。 全ての○印を塗りつぶすと、百万遍の念仏を声明したことになるという。 獨湛禅師が図説のなかで述べているように、多くの人たちがこの図で念仏することによって無量の御利益を得、浄土に生まれんことを願い、往生の資けとするようにとの期待に添い、相当部数が流布したという。 現存しているものの中には、柳沢吉保公の側室・定子婦人のものがあり、庶民から武家社会まで、幅広く広がっていたことをうかがい知る。 また、この版行は、大正時代まで続いていて、第六版が悦心和尚によって発行され、版によって、如来図等の図柄も多生変遷している。 なお、昭和の初期まで流布していた模様である。 こうした念仏唱導に拠って、獨湛禅師は「念仏獨湛(ねんぶつどくたん)」の名をほしいままにしたが、禅師の語録からは念仏のことは見いだせない。 つまり禅師は応病与薬の方便として念仏を奨励されたことを知るのである。 |
||||||||||||||||||||||||||
| がんせんどう(龕薦堂) | ||||||||||||||||||||||||||
| 僧侶の津葬儀において、霊龕を安置するための御堂のこと。 葬儀の際に臨時に設置される建屋で基本的には屋外、本堂の正面に設けられる。 二間間隔程度に四本の柱(または青竹)を立て、上部を白布で覆っただけの簡素なもので四門(→)ともいう。 四本柱の間にはそれぞれに「発心門」「修行門」「菩提門」「涅槃門」と記した額に見立てた紙を貼り付ける。 今日では、葬儀の一切が葬祭専門会社に委ねられたり、簡略化されることからほとんど見かけられなくなったが、10年ほど以前までは、設置されていた。 近年、復興しようと略式ながらも意識的に設けられることがある。 なお、建屋は設置しないものの、宿忌(通夜)から津送にかけて「那伽定」→「龕薦堂」→「那伽定」と記した幕を張り替えることも為されている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かんちょう(管長) | ||||||||||||||||||||||||||
| 明治17(1884)年、明治政府に於いて、各宗に宗門に於ける代表者を立てることが定められた。 黄檗宗の初代管長は黄檗山万福寺第四十代住持・観輪行乗禅師(姓・多々良氏)である。 黄檗山住職は、江戸時代および明治時代初頭は、幕府または政府の許可を得て発令されていたが、これ以降、公選制となり、同時に宗教法人・黄檗宗の管長として就任することとなっている。 任期は七年。 現在の管長は第61代。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かんてん(寒天) | ||||||||||||||||||||||||||
| 「寒天」は日本が世界に誇る発明品の一つであるが、その名付け親が隠元禅師であることは意外と知られていない。 京都伏見の美濃屋太郎左衛門は、ある日、島津公の宿泊時に出された心太(ところてん)料理の残りが捨てられているのを見つけた。 最初はゲル状であったのに厳寒のために氷り、いつの間にかへちまのような乾物に変わっていた。 美濃屋は試しにその乾物を煮溶かして見たところ、また元のゲル状態に戻ったことから、工夫を加え、今日のカンテンを発明したという。 慶安3(1650)年頃の事という。 後に隠元禅師がこれを試食されたところ、「佛家の食用として清浄これに優るものなし」と賞賛され、これを「寒天」と名付けられたという。 →〔松橋鉄治郎著・寒天「文華」第116号〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| かんとうのはい(看燈の拝) | ||||||||||||||||||||||||||
| 中元法要中、各塔頭は、寿塔前廻廊に塔頭名を大書した提灯を掲げ、ここで猊下、塔頭院主、両序は毎朝拝をする習わしになっている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| かんろすい(甘露水) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人々の苦悩を去らしめ、長寿を保ち、死者を復活させるという甘味の霊液を言い、演浄儀や施餓鬼法要の際に堂内や壇上を清める意味合いで洒水する。 清浄水を水瓶に入れておき、使用前に洒水器に移し入れる。 通常は清浄水であるが、開眼法要や地鎮祭等、時に応じ清酒を使用することもある。 |
||||||||||||||||||||||||||
| かんろどう(甘露堂) | ||||||||||||||||||||||||||
| ①〔建築〕万福寺東方丈内の一宇。 単層瓦葺。 寛文五年(一六六五)年建立。 管長の常在居室。 ②〔呼称〕宗門管長のこと。 ①が転じて管長(住持)の尊称として用いられている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| き | ||||||||||||||||||||||||||
| きくしゃ・くひ(菊舎句碑) 俳人菊舎尼は、寛政2(1790)年3月25日、京都東山雙林寺での芭蕉百回忌取越法要に参列したのち、黄檗山を詣でた際に「見聞に耳目をおどろかしつゝ、黄檗山のうちを拝しめぐり、誠に唐土の心地し侍れば」と記し 、「山門を出(で)れば日本ぞ茶摘うた」の句を詠んだという。 38才の時だったという。 〔注〕『吉野行餞吟(よしのいきせんぎん)』に収録。 のち、大正11(1922)年10月13日、黄檗山万福寺山門前にこの句碑が建立された。 |
||||||||||||||||||||||||||
| きはだ(黄蘗) 黄檗山万福寺の山号名の元となった樹木。 ミカン科の高さ20メートルに達する落葉高木樹で雌雄異種。黄蘗、黄檗、黄膚、蘗などといろいろに書かれるがいずれも「きはだ」と読む。 5~7月に黄緑色の小さな花が開き、果実は球形で直径1㎝ほど。 最初緑色であるが熟すと黒色になり、10月頃成熟して芳香を放つ。 「きはだ」には、ヒロハノキハダ、オオバノキハダ等、5種類あり、チュウゴクキハダが最も大きくなり、樹皮も厚く、材の品質もよいとされている。この木の特徴は、内皮が生薬や染料として利用されてきたことである。きはだの樹皮を剥ぐと中から真っ黄色の内皮が出てくる。この内皮をさらにはいで乾燥させたものを黄檗、黄蘗、黄柏、黄栢などとも書かれ、「おおばく」または「おうばく」と読ませている。 なお、そこから抽出される塩酸ベルベリンが、健胃薬、止瀉薬(ししややく)としての薬効があるとされ、古来、民間療法に利用されてきたという。 |
||||||||||||||||||||||||||
| きゅうこうあん(汲江庵) 塔頭の一院。もともと黄檗山が創建される以前から五ヶ庄の地には汲江庵という普化宗(臨済宗とは別の禅宗一派)の寺院が存在していた。 虚無僧姿の僧が出入りし、不穏な動勢が見られたことから、江戸幕府の規制があり、衰退の一途をたどっていったという。その跡地を僧が再興し、この寺院は幕末まで黄檗宗の一派として残っていたという。 今日、汲江派は末寺としては存在するが、塔頭としては名前のみが残されている。→〔坂本博司著「万福寺の塔頭に関する覚書」文華118号〕ほか |
||||||||||||||||||||||||||
| キンカンジャンス(金剛上師) 施餓鬼法要の際、導師(中座という)が宝冠をかぶり脱ぐまでの間、勤める役を言う。「こんごうじょうし」とも読めるが、一般的には唐韻読みしている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| きんざん(径山) 径山萬寿寺のこと。 中国浙江省杭州府杭州市余杭区径山鎮西北の径山にある。 天宝年間(742~756)に国一禅師法欽により開創された古刹で、「碧巌録」の佛果克勤、「宗門武庫」、「正法眼蔵」を著した大慧宗杲、さらには密庵咸傑、無準師範(圓爾辨圓や無学祖元が嗣法した)、虚堂智愚などが住した中国五山第一の古刹である。 宗門にとっては、宗祖の師である費隠通容が住持したところとしてもしられる。 |
||||||||||||||||||||||||||
| きんざんしゅしゅつ・こくし(径山首出国師) 明和9(1772)年、隠元禅師の師である費隠通容禅師の百回忌に際し、後花園天皇から隠元禅師に贈られた謚号(→)。 |
||||||||||||||||||||||||||
| きんたいえん(錦袋圓) 了翁道覚禅師が販売した漢方薬の名称。 了翁禅師は砕いた小指を燃やすという捨身苦行を行い、一切経の発願を起こしたが、指が腫れ苦痛が絶えず困惑していた折りに、肥前の国、興福寺開山の如定(にょじょう)禅師から、錦の袋から取り出した薬の製法を授かるという夢を見た。 早速、その製法通りに製薬し服用したところ、あれほど悩んだ痛みが治まったことから、万病に効く錦袋圓として販売したところ、大成功を修めるに到ったという。 了翁禅師は、当初、僧侶であることから売薬については相当悩まれたようであるが、全国に経蔵を建てたいとの一大発願があり、踏み切られたもので、その益金は、経蔵達成にとどまらず、鉄眼禅師の一切経製作の資金として、あるいは万福寺諸堂の整備のため等にも寄付されている。 「江戸名所図絵」には池の端あるいは浅草の店舗図(→勧学屋)が掲載されている。 錦袋圓は、万病に効いたと言うが、特に酔い覚ましに効能があったともいう。 袋にはブリキ製の観音像が入っており、あるいは袋に観音の絵が印刷されていたという。 「江戸名物初編」には、方外道人の「請フ看ヨ一貼百文の包 現シ出ス観音ハ是レ結縁ナラン」という歌が掲載されていたとの記録がある。 ところで、この錦袋圓の原料は何かと言うことが話題になる。 逍遙離俎中に所載の薬方口伝によると、阿仙薬十匁、圭支五匁、人参五匁、當帰五匁、龍脳五匁、薄荷五匁、丁子五匁、甘草五匁、沙参五匁、返脳五匁、麝香一分以上を粉末にして丸薬にしたものであったという。→〔近世風俗研究会編「江戸賣薬志」〕〔「瞎驢眼」第66号〕ほか |
||||||||||||||||||||||||||
| きんたいきょう(錦帯橋) 「日本三名橋」の一つである岩国「錦帯橋」は、黄檗僧・獨立性易(戴曼公、一五九六~一六七二)が、時の第3代岩国領主・吉川広嘉にみせた『西湖遊覧誌』の絵図からヒントを得て作られたとされている。 架橋の計画が進められていた錦川は、岩国城を守るべきお堀の役割を果たしていたが、たびたび洪水で流失していたことから、洪水に耐えられる橋の建造が求められていたのである。 『西湖遊覧誌』絵図には、小島をつなぐ橋が描かれており、川中に石塁を築き橋脚を無くすことにより、橋の流失は避けられるとのアイディアが生まれたとされ、寛文13(1673)年に完成している。 当時、獨立は、橋の付近にある山麓の浄土院(現在の「紅葉谷」付近)に住んでいたとされ、明国の進んだ文化や医療等の知識が役だった事例の一つである。〔→「獨立一勺の水」〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| きんぱいせき(禁牌石) |  |
|||||||||||||||||||||||||
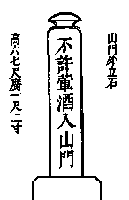 ↑ 清規に記載の禁牌石 |
「不許葷酒入山門 (くんしゅ山門にいるを許さず。 …生臭いものや酒を山内に入れることを許さない。)」と書かれ、多くは禅宗寺院の門前に建てられた石碑のこと。 今日では、禅宗以外の寺院でも見かけるが、もともとは、持戒を重要視する黄檗宗が最初に導入し、建てたものであると言われる。 「清規」には高さ六、七尺、広さ一尺二寸と規定されている。 右写真は黄檗山三門前の禁牌石 → |
|||||||||||||||||||||||||
| きんめいちく(錦明竹) | ||||||||||||||||||||||||||
| ① 〔植物〕 錦明竹は隠元禅師が伝来されたものと伝えられている。 孟宗錦明竹と真竹錦明竹とがあり、「金名竹」とも書く。 この竹には、節、小枝、葉まで金色の美しい縦縞が入っていて、盆栽等の観賞用としても珍重されている。 孟宗錦明竹は、現在、福岡県に二箇所、宮崎県に一箇所の天然記念物の指定を受けた自生竹林がある。 ② 〔芸能〕 古典落語の題名。 古道具屋に来た使い客の早口の口上に、「・・・・自在は黄檗山錦明竹、ズンドの花活には遠州宗甫の銘がございます。 利休の茶杓、織部の香合、のんこの茶碗、古池や蛙飛び込む水の音、これは風雅坊(芭蕉のこと)正筆の掛物、沢庵・木庵・隠元禅師張り混ぜの小屏風。云々・・・・・・・・」とあり、黄檗文化がいかに庶民にまで広がっていたかを物語っている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| く | ||||||||||||||||||||||||||
| くういんこじ(空印居士) | ||||||||||||||||||||||||||
| 四代将軍幕閣の中心的人物であった酒井忠勝(→)のこと。 隠元禅師滞留に積極的な役割を果たしたとされ、禅師に帰国断念を促す書状を送るなどしている。 晩年法体となり空印居士を名乗っているが、命名をしたのは隠元禅師である。 寛文8(1668)年8月、禅師は夢に「空印」の二字を見、「道交感応之験」の偈を残している。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ぐかいほうぎ(弘戒法儀) | ||||||||||||||||||||||||||
| 隠元禅師が「黄檗三壇戒法要」の法式等の実施要領についてとりまとめたもの。 「戒経」ともいう。 宗祖がもたらした授戒は、嘉靖年間以来途絶えていたものを雲棲袾宏が再興したものであり、梵網経の立場に立って法儀がとりまとめられている。〔「雲棲袾宏の研究」cfP78〕 三壇戒とは、沙弥戒、比丘戒、菩薩戒を指す。 出家には、具足戒を授け、次いで菩薩戒を授けるのを一般的とする。 |
||||||||||||||||||||||||||
| くじょう・の・ひとばしら(九条の人柱) | ||||||||||||||||||||||||||
| 龍谿性潜禅師は、弟子拙道和尚の求めに応じ九島院(きゆうとういん。現・大阪市西区本田三丁目4─18)の開堂法要に行かれていた。 折しも延宝8(1670年8月23日、入仏開眼法要中の堂内に台風来襲による大津波が押し寄せ、避難を勧め弟子たちに、禅師はそこにとどまることを告げられ遺偈を書かれるとともに、不動端座され海水中に入寂された。 世寿69歳であった。 人々は、龍谿禅師が、その地が水利が悪く危険なことを身を以て教えられたとし、人呼んで「九条の人柱」と言い伝えたという。 幕府は、このことを契機に、10年後に河村瑞賢に命じて衢壌(くじょう)島を開削し安治川を通している。 →〔中尾文雄著『龍谿禅師の生涯と思想』久島院蔵版、ほか〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| ぐぜだいし(救世大士) | ||||||||||||||||||||||||||
| 鉄眼道光(てつげんどうこう。→)禅師の尊称。 鉄眼禅師は、一切経を製作する過程で、洪水や飢饉で飢えに苦しむ難民たちの困窮に直面し、集めた募財金を二度までも放出し、難民救済活動を展開された。 世の衆生を救済する救世菩薩(観世音菩薩のこと。 救世尊、救世大慈悲父等ともいう。)は慈悲の権化として衆生にもっとも渇望される仏であり、鉄眼禅師の行為はまさに救世大士に喩えられるものとしてこう呼ばれた。 |
||||||||||||||||||||||||||
| くつもん(窟門) | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国様式の土塀に開けられた通り口。 黄檗山三門の両側に設けられた門はその様式をよく伝えている。(下絵図→印ヶ所) 正面に向かって右を通宵路(つうしょうろ)、左側を白雲関(はくうんかん)と呼ぶ。 それぞれに聯額が掛けられている。 通宵路の聯は右が「眼底に疑有らば縦(ほしいまま)に歩することを休(や)めよ」、左が「胸中に碍(げ)無ければ自ずから通宵」である。 白雲関は右が「門外已(すで)に無差別の路(みち)」、左が「雲辺(うんぺん)又一重(いちじゅう)の関有り」である。 何れも黄檗山5代高泉禅師の筆になるものである。 |
||||||||||||||||||||||||||
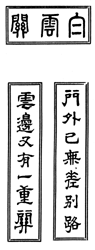 |
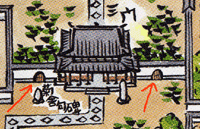 |
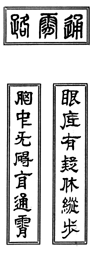 |
||||||||||||||||||||||||
| 山内に足を踏み入れた途端に中国情緒を味わえる場所。 それが三門前の景観である。 |
||||||||||||||||||||||||||
| くりあげ(繰り上げ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 宗門では法要開始時、参列者は上首先行(ジャンシュセンヒン。→)で雁行、入堂し、終了時には末位先行(マウイセンヒン。→)で退堂するのを通例とするが、黄檗山における開山忌にあっては、引き続き登丈の拝(→)があることから、この「繰り上げ」作法により、上首先行に列班し直し東方丈へ向かう。 具体的には、開山堂を退堂後、末位先行で雁行していた一団が、合山鐘(→)を行き過ぎたあたりで停止し向かい合うのである。 ここで最後尾の上位者は止まらずにそのまま雁行を続ける、次位者も順次上位者について行くと、最後尾と先頭が自然と交代出来ることになる。 実は、唐僧の中には明軍の兵隊上がりがいたことがわかってり、彼らの教練がこうした形で伝えられ残ったのかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||
| け | ||||||||||||||||||||||||||
| げいか(猊下) | ||||||||||||||||||||||||||
| 猊下の猊とは獅子の別称である。 獅子のような高僧の下に坐る、即ち「猊坐下」の略称で高僧の尊称である。 宗門では、黄檗山万福寺住持と、東堂(とうどう。→)のみに用い、万福寺住持が宗門の管長を兼務していることから、「管長猊下」あるいは「東堂猊下」と重ねて称することもある。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けいがん・もんか(桂巌門下) 即非如一法嗣・桂巌明幢門下から碩学禅者が輩出したことからこの名称がある。 法嗣には青海実東、大智実統、良逐実文、断橋実外等20人を数え、青海実東は『碧巌録無明解』を、大智実統は『碧巖集種電鈔』(→)を、断橋実外は『禅林口実混明集』を著し、それぞれ今日も使用されている。 また、良逐実文の法系下は今日の瑞光下を席巻している。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けいさく(警策) | ||||||||||||||||||||||||||
| 坐禅時の励ましに用いる棒で、清規(しんぎ)では「香版(こうはん)」と記載されているが、通常、使用している呼称は「警策(けいさく)」である。 臨済宗、曹洞宗では「きょうさく」と呼ばれている。 材料の多くは樫(かし)材で、長さは約120㎝、巾6~7㎝程度の板で、取手の部分は握りやすいように丸いが、先に行くに従って扁平に作られていて、およそ5~6㎜の厚さに作られている。 禅堂修行の最高位である「禅士(ぜんじ)」は、座の付近にこれを配置し、坐禅開始の直前に、この警策をいただいて堂内を巡視し、修行者の姿勢を正し、あるいは怠惰に陥ることのないよう、戒めて回る。 禅士の巡回中に、修行者が合掌する場合は、警策を受けたいとの合図になる。 警策を入れる場合は警策で軽く相手の肩を敲く。 この場合、合掌、低頭した修行者の肩からタスキがけに三度ずつ打ち下ろす。 板が丁度背中にぴったりと貼りつくように入れる打ち方が最適とされている。 なお受策者(警策を受ける者)は、まず左手を右脇に深く差し入れると左肩が自然と落ち、肩から背が丸くなって警策が入れやすくなり、板が骨に当たることもないので、この姿勢を薦める。 逆の場合も同様。 ついでながら、警策を入れるについては三種の区別がある。 一は「罰棒」と言い、居眠りや怠けたときに打つ文字通りの罰の棒である。 二は「賞棒」と言い、よくやっている、頑張れとの励ましの棒である。 三つ目は「無為の棒」と言い、賞罰に関係なくついでにたたいてやろうという棒である。 実はこれが一番痛かったりして…。(つまり、何にせよ、敲かれるのを逃げることは出来ないのだ。) |
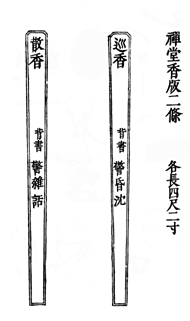 ↑ 清規記載の警策 |
|||||||||||||||||||||||||
| けいさくぶん(警策文) | ||||||||||||||||||||||||||
| 朝課時に読誦する「清晨普願偈」、晩課時に読誦する「晩課普願警衆偈」を言う。 また、巡照偈も警策文の一つである。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けいさく・を・ふむ(警策を踏む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 法式用語。 警策文(→)読経時、最後の句にさしかかり出すとき、香灯師(ヒヤンテンス。→)は、警策文の読みに合わせて一歩一歩、歩を進めながら太鼓に近づいていく。 この作法をいう。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けごんぼさつ(華厳菩薩) 惟一道実禅師のこと。 明の武将であったが、父の殉職に遭遇し脱俗、隠元禅師に就いて出家した。禅師が渡来するのに際し随行したが、いったん帰国し、寛文元(1661)年に高泉禅師と共に再び渡来し、普門寺から新黄檗に至るまで隠元禅師に仕えていたという。 その後、双鶴亭(→)で華厳経八十一巻を血書したことから、世人はこう称したという。華厳院に塔した。世寿73才。→〔人名〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| けぞうばん(華蔵版) 宗門で用いられる施餓鬼用経本の種類。 何種類かが確認されているが、その中でも「華蔵版」と「柏巌版」(→)がもっとも多用されている。 このうち、「華蔵版」は、本山塔頭の華蔵院が延宝6(1678)年に刊行したとされる。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けっしょきょう(血書経) 自身の血でもって書き上げた経典をいう。 血を採る場所としては、多くは指の先からであるが、耳や鼻からも採ったと言われている。 「黄檗血書」の名で知られるほどに多くの檗僧が取り組んでおり、有名な血書としては、惟一道実禅師の華厳経、法華経、楞厳咒、潮音禅師の法華経等がよく知られている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| げったい(月台) | ||||||||||||||||||||||||||
| 大雄宝殿正面前に設けられた砂を敷いた広場のこと。 法要を行う際の基壇で、白砂が一面に敷き詰められ、常に月光を受けるのでこの名がある。 中国寺院の明朝様式の特徴の一つとされ、仏教の戒律と月を象徴する。 その効用として月光の反射光で堂内を明るくする効果がある。 なお、黄檗山の月台中央には「罰跪香頂石(ばっきこうちょうせき)。 梵壇石ともいう。」という長方形の平らな石があり、叢林の共住規約を守らなかった者が罰として線香を立て、この石に跪き礼拝して懺悔(さんげ)することとなっている。 黄檗山伽藍の中心線上にあり、月台の核とも言うべきもので、結界の戒碑でもある。 なお、余談ながら現在の中国語では、月台とはプラットホームのことである。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けもう(羯磨) | ||||||||||||||||||||||||||
| 懺悔(さんげ)の法要を言う。 仏教で言うところの懺悔は、キリスト教等の懺悔(ざんげ)とは異なり、これまでに犯した罪を悔い改め反省するだけにとどまらず、さらには未来に向かっても同じ過ちを犯すことのないように止断する決意を持つ意味が込められていて、「懺悔(さんげ)」と濁らずに読む。 仏教行事はインドでは陰暦で執り行われ、太陽神よりも月の神を上位とする風潮があったとされているが、中国でもその影響を受け、明、清の時代には月をお祭りする行事も行われていた。 たとえば仲秋節は三大節句の一つである。 宗門では、1日(新月、塑旦ともいう)と、15(満月、望旦ともいう)には祝聖(しゅくしん→)と称される特別の法要を厳修し、その前日の14日と晦日の晩課時には半月間の罪を懺悔する法要を挙行するもの。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けんぐ(献具(供)) | ||||||||||||||||||||||||||
| 法要に先立ち導師が、本尊に供物等を供える法式をいう。 ご飯、お茶、上供(シヤンコン。→)の内、油揚、箸(「真前」と記した箸袋に入れる。)、香資(こうし)、疏(しよ。→)の順を原則とする。 なお、献具を途中で行う場合があり、これを中献具(なかけんぐ。→)という。 |
||||||||||||||||||||||||||
| げんこうようし(原稿用紙) 今日使用されている二十字×二十行というマス目つき原稿用紙の規格は、実に黄檗版(→)と称される黄檗宗独自の版木彫刻の基本型式から誕生したものである。 なお、黄檗版では縦の罫線は引かれているが、マス目にまでは発展していない。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けんとくぜんじ(建徳禅寺) | ||||||||||||||||||||||||||
| 古黄檗(→)の前身の名称。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けんぱんりょう(献飯料) 末寺が法系の宿院(→)に納入する維持費のこと。 宿院によっては献米料、献香料などと呼ぶところもある。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けんぽう(顕法) | ||||||||||||||||||||||||||
| 法を嗣ぐ師匠から付偈を受け、臨済正宗(黄檗宗)の正統な嗣法者であることが宗門で確認され、黄檗宗門下の僧侶として『黄檗宗鑑緑(通称、宗鑑緑→)』に登録されることをいう。 認められると、道号の下に法系に沿った系字(けいじ。→)をつけた諱(いみな)を受け、これを管長が証する允許証(いんきょしょう)が交付される。 また、座元位の法階が与えられ、晴れて宗門寺院の住職資格を得たことが示される。 |
||||||||||||||||||||||||||
| けんぽう・じゅんりょう(顕法巡寮) | ||||||||||||||||||||||||||
| 臨済正宗(黄檗宗)の嗣法者であることが宗門で確認されたことを公表するために、本山の各寮舎はじめ塔頭等の関係先へ挨拶回りをすることを云う。 その際、披露目として名刺代わりに手拭いやタオル、扇子等を包むが、その題荃には「菲儀(ひぎ)」と記す。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こ | ||||||||||||||||||||||||||
| こうさん(香讃) 黄檗梵唄の法式構成のうえで欠かせない節経で、法要の最初に誦まれ仏祖の慧命を敬仰する意を表す。 その種類がいくつ有るかは定かではないが、今日残され常用されているものだけで約三十種類以上ある。 香讃は、文字通り香を焚き道場を浄める意味合いをもって読誦される「爐香讃」が最も多く読誦されている。ただし、演浄儀(→)では「楊子浄水讃」が読誦され、香の代わりに水で道場を浄める。 これらの香讃は「結讃(けっさん→)」と対になって法要の荘厳さを高揚させる役割を果たし、両者は欠かせない。 前述したとおり香讃、結讃の種類は多く、法要の性質により、どれを誦むかが決められる。その代表的な「爐香讃」を以下に例示する。 ▽ 爐香讃 爐香乍爇 法界蒙薫 般若海会悉遙聞 随處結祥雲 誠意方殷 諸佛現全身 南無香雲蓋菩薩摩訶薩 ・・・・・・云々 →〔木村得玄著「黄檗経典の香讃について」春秋2004№461ほか〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| こうしかんばく(高士観瀑) 隠元禅師が帯来されたという水石(すいせき)の銘で、今日では「李白観瀑石」の名称で愛石家に知られている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こうじゃく(香尺) →定香尺(じょうこうじゃく) |
||||||||||||||||||||||||||
| こうせん・さんかん(高泉三関) 黄檗第五代・高泉禅師が参禅の徒に与えたとされる三つの公案。 一、乳を飲むこと四大海水の如く、骨を積むこと毘富羅山(びぶらせん)の如し、阿那個か是れ最初の父母。 二、人人眼有りあきらかなること秋毫を察す。 甚に因ってか自己の眉毛看不見なる。 三、日上がり月下がり春去り秋来る。 作麽生(そもさん)か是れ不動真際。 →〔中尾文雄著「高泉和尚の三関」文華12〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| こうち(小打ち) 仏殿太鼓(→)の敲き方には一定のルールがあるが、テンポが上がってくると、緩やかなテンポ時と同じ敲き方ではバチがさばけなくなってくる。 この場合に、バチを軽く扱うために小さな敲きを多用した方が打ちやすくなる。 これを称する。 ただし、この敲き方は、バチ捌きに手慣れることが必須で、望ましくない敲き方とされる。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こうはん(香版) | ||||||||||||||||||||||||||
| 警策(けいさく。→)のこと。 清規には、この名称で搭載されている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こ・おうばく(古黄檗) | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本黄檗宗の祖庭であり、日本の新・黄檗山万福寺に対して、親しみを持ち「古黄檗」、「古檗」あるいは「唐黄檗」と称している。 中華人民共和国福建省福州府福清寺魚渓鎮に位置し、黄檗山万福寺という。 唐代徳宗貞元5(789)年、沙門正幹によって創建されたという。 当初は「般若堂(般若台とも)」の名で開創され、貞元8(792)年には大伽藍が完成し、徳宗皇帝から「建徳禅寺」の名を賜ったと伝えられる。 境内を囲む山一帯が黄檗((きはだ。→)の木で覆われていたところから、黄檗山の山号がついたと伝えられている。 開創当時、地元福州出身の希運禅師はこの黄檗山で修行し、江西洪州(現・江西省高安県)の百丈山懐海禅師の門下に入り、鷲峰山に一寺を開創された。これを「黄檗山黄檗寺」と称したという。 後、黄檗希運禅師(→)の名は全国的に知られるようになり、同時に黄檗山の名も知られるようになったが、以来、福州の黄檗山と江西省の黄檗山とは、混同されることとなった。 福州の黄檗山は、一時期衰退したが、洪武年間に再建され一大叢林となったという。 しかし嘉清34(1555)年、倭寇の乱で堂宇はほとんど焼失し、僧侶は四散、境内は荒野に帰したようである。 隆慶初(1567)年、高蓋寺僧の正圓禅師は修復に尽力されたが、僧のみの力には限界があり、皇帝の威光に頼る決意をし上京されたが、不帰の人となったという。 弟子、興慈、興寿(隠元禅師得度の師匠)は、その遺志を受け継ぎ、大蔵経の下賜を懇願された。 たまたま、万暦42(1614)年、万暦帝の生母である慈聖皇太后が逝去され、大蔵経が全国6ヶ寺に下賜されることとなったことから、二人は郷土出身の葉 向高(ようこうこう。→)に協力を求め、同年、大蔵経678巻、帑金(とうきん)300両とともに、「萬福禅寺」の勅額を賜った。 その後、1630年に密雲円悟禅師が進住され、1633年には費隠通容禅師が、さらに1637年には隠元隆琦禅師が住持となり、万福寺の復興は一気に進んだ。 さて、近代の古黄檗についてであるが、大正14(1925)年、隆琦大雄禅師(当時管長職)、山田玉田禅師が訪檗(坂田金龍、安部禅梁禅師が随行)しておられるが、その頃の古黄檗は堂衆が40人近くいて建物の保存状態は良好であったようである。(→「支那祖席巡拝記」) しかし、残念ながら昭和2(1627)年2月頃に大洪水が発生し、天王殿、大雄宝殿等が流失したとのことである。(→「黄檗四十六代大雄弘法老和尚年譜」) その後、自然災害や文化大革命による紅衛兵の乱暴狼藉で荒れるに任かされ、昭和54(1979)年、黄檗宗々会議長・吉井鳩峰禅師を団長とする第一次「古黄檗拝塔訪中団(→)」(中国側は「日本古黄檗拝塔友好訪華団」と表記)が訪問拝塔した頃には、大殿ほか多くの建物が破壊されていた。 その後、日中関係者の協力で立派に復興されている。 更に昭和58(1983)年、「日中友好臨黄協会」が訪問した時に、『日本黄檗山万福寺開山隠元禅師東渡振錫之地』の記念石碑が建立された。 また同年、中華民国国務院より漢民族地区仏教全国重点寺院に指定されている。 平成元(1989)年5月には、福清市黄檗山万福寺修建委員会が組織され、修復が進められている。 →〔中国仏寺道観「黄檗山万福寺」〕、〔林田芳男著「明末における福州の仏教」〔文華〕第114号〕、〔阪田金龍著「福唐黄檗山略史」〕、ほか。 なお、この「古黄檗」、「古檗」あるいは「唐黄檗」の呼称が、いつごろから使用されるようになったのかははっきりしない。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こおうばく・じゅうにほう(古黄檗十二峰) | ||||||||||||||||||||||||||
| 古黄檗(中国黄檗山万福寺)をとりまく景勝の十二峰をいう。 ① 寶峰(ほうほう) ② 屏嶂峰(ひょうしょうほう) ③ 紫薇峰(しびほう) ④ 獅子峰(ししほう) ⑤ 香炉峰(こうろほう) ⑥ 佛座峰(ぶつざほう) ⑦ 羅漢峰(らかんほう) ⑧ 鉢盂峰(はつうほう) ⑨ 天柱峰(てんちゅうほう) ⑩ 五雲峰(ごうんぽう) ⑪報雨峰(ほううほう) ⑫吉祥峰(きっしょうほう) |
||||||||||||||||||||||||||
| ごてんはま(御殿浜) 現在の宇治市五ヶ庄の隠元橋(→)付近の宇治川東岸を言う。 当初、岡谷津(おかやのつ)と呼ばれていたところであるが、この付近は近衛家の所領するところで、岡屋御殿があり、いつしか御殿浜と称されるようになったという。 隠元禅師が登岸した場所もこの付近と言い、いつしか隠元浜と呼ばれるようになったという。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ごとうげんとう(五燈巖統) 隠元禅師の師である費隠禅師によって著わされた法灯の系譜書。 全二十五巻。順治10(1653)年6月に刊行された。 内容は従来の同類書物で一般に流布していた「五燈会元」に対し、ある系譜に所属する一派を認めていなかったことから、当該勢力の大きな反駁を受けることとなってしまった。 費隠禅師はこのため「五燈巖統解惑篇」を発刊し反論を試みたが、騒動は拡大する一方で抗しきれず、結局原版毀棄を余儀なくされてしまうこととなる。 一方、隠元禅師は「解惑篇」の出されたその年の、順治11(1654)年7月、長崎に降り立っていた。 明暦3(1657)年2月、隠元禅師は、逸然禅師の求めに応じて五燈巖統を『重刊五燈巖統』と題して刊行し、我が国に於いて日の目を見ることとなった。→〔鳥越文邦著「費隠禅師とその著・五燈巖統」〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| こはいのま(小拝の間) 東方丈内の甘露堂に最も近い一室の呼称。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ごぶつほうかん(五仏宝冠) 施餓鬼法要で中座(導師)が金剛上師(→)の役目を果たす際にかぶる宝冠。 五仏、即ち五智如来(釈迦、阿閃、阿弥陀、大日、宝生の各如来)が描かれていることから、このように称する。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ごほうさんこじ(護法三居士) 黄檗山万福寺開創時に、宗門興隆に貢献尽力した三人の民間人を尊称したもの。 青木端山居士(重兼 摂津国麻田藩主、瑞聖寺、仏日寺、方廣寺) 伊達肯山居士(綱村 陸奥国仙台藩主 大年寺、万寿寺開基) 鍋島金粟居士(元武 肥前国小城藩主 星巌寺、玉毫寺開基 潮音道海禅師嗣法 金粟元明) 別に三居士(→)あり。→〔名数〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| こぼりぎん(小堀銀) いつの頃からか本山幕府から支給される基本金は京都代官小堀氏が所管することとなっており、利息分は本山の常住費に当てられていた。 これを小堀銀と称する。 とはいえ、この利息金は滞り勝ちで、交付されることは稀であったとされる。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ごまどうふ(胡麻豆腐) ごまをすりつぶし、葛粉(または片栗粉)と酒等で練り上げ、豆腐状に固めたもの。 通称「麻腐(まふ)」と呼ばれ普茶料理に欠かせない一品である。 黄檗豆腐(→)と呼ぶ人もあるが、それはまた別物である。 なお、麻腐は会席料理の刺身に相応するものとして取り扱われ、わさびを添えることを欠かしてはならないとされている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こまのあしかげひ(駒足影碑) 宇治茶の発祥記念碑で、大正15(1926)年、万福寺門前の茶畑(現市場付近)に建てられていたもの。 その後、市街地化が進み、現在地の総門前に移設されたという。 栂尾の明恵上人(1173~1232)が茶の栽培に適したこの辺りの畠地に馬を歩かせ、その蹄の跡に茶の種を播かせたことに由来すると言われ、自然石の碑には、上人の「都賀山乃 尾上の茶の木分け植ゑし あとぞ生ふべし 駒の蹄影」の詩が刻まれている。 毎年10月初旬には碑前で茶業関係者と共に法要が厳修されている。 |
||||||||||||||||||||||||||
| ごみのしゅく(五味の粥) 成道会に備えられていた五種類の薬味を使った粥のこと。五種とは、白米、紅豆、榧子、貫柿子、栗子と記録にあるが、薬味の穀物等は時代とともに変わった様である。 なお、粥の呼称も臘月粥、果粥、七宝五味粥などと呼ばれていたようである。→〔名数〕〔田中智誠著黄檗の五大法要…「文華」119号〕 |
||||||||||||||||||||||||||
| ころもがえ(衣替え) | ||||||||||||||||||||||||||
| 衣替えは仏教各宗派まちまちであるが、宗門の衣替えは、「知客寮須知」により、5月と10月の開山忌を境として行うことが基本とされている。 即ち、5月3日の開山忌終了時から10月3日開山忌の終了時までは夏衣、10月3日の開山忌終了時から翌年5月3日の開山忌終了時までは冬衣を着用すると定められている。 ただし、地域差があるうえに、近年の温暖化で夏衣が長く着用される傾向になりつつある。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こんごうじょうし(金剛上師) 施餓鬼の中で、法要を主宰し餓鬼を救う導師のこと。 宗門では「キンカンジャンス」が通称。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こんごうぶつ(金剛佛) 潮音道海禅師のことをいう。 |
||||||||||||||||||||||||||
| こんぞくざん(金粟山) 「金粟山」もしくは「金粟」と称し、金粟山廣慧寺(こうけいじ)のことをいう。 なお、「きんぞく」と呼ぶ人もあるが、いっぱんてきには「こんぞく」で膾炙されている。 中華人民共和国浙江省嘉興府海塩県にある。 隠元禅師が33才の時、この寺院に進住した密雲円悟禅師に参見、以後参禅工夫に努め、大悟するに至った思い出深い寺院である。 |
||||||||||||||||||||||||||