![]()
下記の号をクリックするとその号の市場新聞がご覧いただけます。
| 市場新聞1月号 | 市場新聞2月号 | 市場新聞3月号 | 市場新聞4月号 | 市場新聞5月号 | 市場新聞6月号 |
| 市場新聞7月号 | 市場新聞8月号 | 市場新聞9月号 | 市場新聞10月号 | 市場新聞11月号 | 市場新聞12月号 |

滋賀県内の死亡事故多発!!

滋賀県内で2025年に発生した交通事故による死者数が54人で人口10万人当たり3.85人と全国ワーストでした。
前年比26人増となり、増加率は92・9%でこちらも全国ワーストでした。死亡した人を年代別で見ると、約半数にあたる28人が65歳以上の高齢者です。
このうち15人が歩行者で、横断歩道のない道路を横断中に車にはねられるケースが多かったそうです。
通勤時また配達時など車を運転する機会は多いと思います。横断歩道以外でも歩行者には十分注意し、安全運転を心がけましょう。
まだまだノロウイルスに要注意
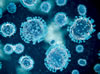
毎年11月から2月にかけての冬場は、ノロウイルスによる食中毒が多発しています。
ノロウイルスは、小さな球形をしたウイルスで、非常に強い感染力をもっています。
ノロウイルスによる食中毒は、ノロウイルスが付着した手で調理し、そのノロウイルスが付着した食品を食べたりするなどして、ノロウイルスに感染することで起こります。
食品従事者である皆様は十分注意されていると思いますが、ノロウイルス食中毒の予防4原則であるノロウイルスを「持ち込まない」「つけない」「やっつける」「ひろげない」を守り、しっかり対策しましょう。
令和7年度放射性物質検査の実施結果
滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に放射性物質の検査を実施しており、その結果を確認することができます。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
放射性セシウムの基準値や検査結果については、「滋賀県 放射性物質検査の実施結果」をご確認下さい。
滋賀県産「ホンモロコ」
素焼きや南蛮漬けに美味と評判の琵琶湖の固有

ホンモロコは、琵琶湖の固有種で、知る人ぞ知るおいしい魚です。
通年漁獲されますが、特に春先は美味とされ、琵琶湖の春の名物になっています。
素焼きにし、軽く塩を振るか酢味噌などで食べると絶品。その他、やわらか煮や南蛮漬け、佃煮などでも美味しくいただけます。
漁獲時期 10月~4月末
おすすめレシピ♪
「ホンモロコの南蛮漬け」一晩漬けておくと味がしみこみ、さらに美味しくなります
●青果部門

野菜の部2月のおすすめは、新馬鈴薯、新玉葱、新キャベツ、人参、菜の花、白菜、大根、きのこ類です。
新馬鈴薯は皮が薄く皮付きのまま食べられるため、皮ごとフライにしたり、小ぶりなのでじゃがバターや揚げ煮などの丸ごと調理する食べ方が向いています。
また、新馬鈴薯にはビタミン類が豊富に含まれており、おおよそ200gを食べると1日のビタミンCの必要量に達するほどです。

果実の部では、蔵出しミカン、デコポン、いよかん、はっさく、清見オレンジ、湖北イチゴなどがおすすめとなっております。
●水産部門

水産の部2月のおすすめは、カキ、ホタテ・ハマグリなどの貝類です。
特にハマグリの旬は一般的に2月から4月で、春先が最も美味しい時期とされていますので、ぜひお試し下さい。
他にもマダラやブリ・マハタなども魚も今が一番脂のりがよく、非常に美味しくなっております。そして2月といえば節分です。
タイ・ブリ・ホタテ・イカなど脂ののった食材を使っての手巻き寿司は絶品です。

今年は贅沢な海鮮巻きで節分を迎えてみてはいかがでしょうか。ちなみに今年の恵方巻きを食べる方角は南南東のやや南です。
| 市場新聞1月号 | 市場新聞2月号 | 市場新聞3月号 | 市場新聞4月号 | 市場新聞5月号 | 市場新聞6月号 |
| 市場新聞7月号 | 市場新聞8月号 | 市場新聞9月号 | 市場新聞10月号 | 市場新聞11月号 | 市場新聞12月号 |
上記の号をクリックするとその月号の市場新聞がご覧いただけます。